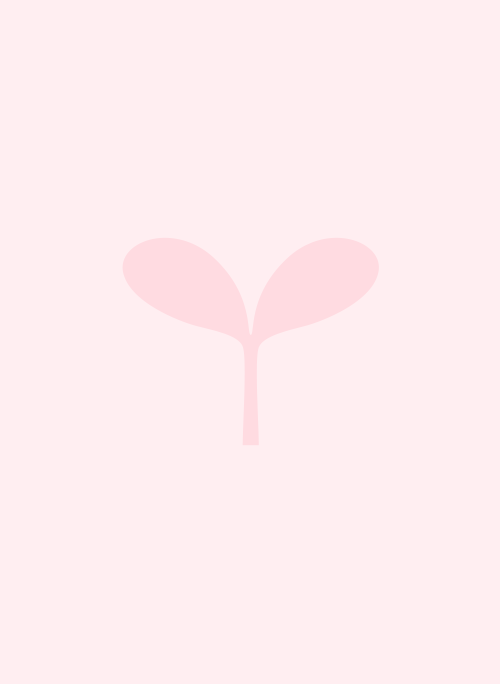天気……『雲の上の学校』では、雲は下に見える。雲海が足元に広がっていて、あたかも広い海のなかに白い波が立っているように思われる。
「『雲の上の学校』にいる子どもたちは、どうして、ここへやってきたのか、お前は知っているのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「知っています。教えてあげましょうか」
シャオパイがそう言った。ぼくはうなずいた。
「子どもたちが、いやな夢を見たからです」
シャオパイがそう答えた。ぼくには何のことだか、さっぱり分からなかった。
「つまり、こういうことです」
ぼくが、ぽかんとしているのを見て、シャオパイが説明を始めた。
「ぼくの飼い主さんは、子どもたちの夢を集めることをしています。夢には楽しい夢と、いやな夢があります。その二つの夢を分別して、それぞれ別の袋に入れています。よい夢はピンクの袋に入れて、いやな夢は黒い袋に入れています。ゴミにたとえると、燃えるゴミと、燃えないゴミを分別して、それぞれ違う色の袋に入れるようなものです」
シャオパイは分かりやすく説明したつもりでいるようだった。しかしそれでも、ぼくにはまだ、何のことだか、さっぱり見当がつかなかった。
「お前が言っていることは意味がまったく分からない」
ぼくはそう言った。
「おかしなことを話して、笑い猫のあんちゃんをびっくりさせたくないから、言わないつもりだったけど、昨日、笑い猫のあんちゃんが話してくれたタイムスリップの話を聞いて、その話はまんざら否定できないと思うようになってきました」
シャオパイが、そう言った。
「お前の飼い主さんが、唐の時代からタイムスリップしてきたのではないかという話か?」
ぼくがそう聞くと、シャオパイがうなずいた。
「初めのうちは、そんなことは絶対にありえないと思っていました。でも、よく考えてみると、もしかしたら、その可能性も1パーセントぐらいはあるかもしれないと思うようになってきました」
シャオパイが、そう言った。
「そう思うようになったわけを、話してくれないか」
ぼくが懇願すると、シャオパイが、ぽつぽつと話し始めた。
「ぼくがあの人のうちで飼われるようになってから、飼い主さんがどんな人なのか、だんだん、分かるようになってきました。大きなキャリーバッグを持って、旅行によく行く人でした。うちにいるときは、ぼくのことを、とても大切にしてくれました。夜、寝るときも、ぼくはいつも飼い主さんと同じ部屋で寝ていました。ところがある晩、飼い主さんは、こっそりと起きだして、寝室を出て、うちから出ていきました。手には、からかさと、黒い袋とピンクの袋を持っていました」
シャオパイがそう言った。
「お前もいっしょに行ったのか」
ぼくが聞くと、シャオパイは首を横に振った。
「一人で出て行きました。でも、気づかれないように、ぼくはこっそりあとをつけていきました」
シャオパイの話に、ぼくは興味しんしんだった。
「飼い主さんは、どこへ行ったのだ」
ぼくはすぐに聞き返した。
「飼い主さんは玄関の前で、からかさを開いて、からかさについているボタンを押しました。すると不思議なことに、飼い主さんの体が、ふわふわと宙に浮いていきました。ぼくはそれを見て、びっくりして、思わず息を飲みました」
シャオパイが、そう言った。
「そのあと、どうしたのだ」
ぼくはますます興味を覚えていた。
「飼い主さんは、この町の住宅地が広がっているほうへ飛んでいきました。ぼくもあとを追っていきました。するとやがて飼い主さんは、ある家の前までくると、鍵がかかっていない窓から、なかに入って、三十分近く出てきませんでした。出てきたときには、背中に黒い袋を背負っていました。飼い主さんは、それから再び、空を飛んで、町のはずれにある自分のうちへ帰り始めました。ぼくは急いで、うちへ帰って、飼い主さんが戻ってくる前に、寝室に入って、うちにずっといたふりをしていました。飼い主さんは、うちへ帰ってくると、黒い袋を洋服ダンスのなかに入れて、そのあと再びベッドに横たわって朝まで寝ていました」
シャオパイがそう言った。
「そのあと、どうなったのだ」
ぼくは間髪を入れずに聞いた。
「夜が明けると、飼い主さんは、何事もなかったかのように目を覚ましてから、顔を洗って、そのあと朝食をとっていました。トーストと、カボチャがゆと、オレンジジュースを、いつものように食べたり飲んだりしていました。それから散歩に出かけていきました。ぼくもいっしょに散歩についていきました。飼い主さんの顔の表情には何の変化も見られなかったので、ぼくには昨夜の出来事が、まるで夢のように思えました。散歩から帰ってくると、飼い主さんは、書斎にこもって出てきませんでした。飼い主さんは在宅ワークをしている人なので、朝の十時ごろからお昼の三時ごろまで、書斎にこもって仕事をしています。その間、ぼくは好きなことが自由にできるので、昨日見たことが本当だったのかどうか、確かめてみようと思いました。そのためにこっそりと寝室に入って洋服ダンスのなかを開けてみました。すると黒い袋がいくつも入っていました。袋のなかからは、いやなにおいがしていました。悪夢のなかにしか出てこない亡霊のようなものが、袋のなかに見えたので、ぼくは正視できなくなって、すぐに洋服ダンスを閉めました」
シャオパイがそう言った。
「そうか。そういうことだったのか」
ぼくにはようやく、シャオパイが言ったことが少し分かってきたような気がした。
シャオパイは、そのあと次のように話した。
「黒い袋のなかには、悪夢が閉じ込められているのではないかと思うと、怖かったけど、悪夢を取り除いてもらった人は、今は、すっきりした気持ちでいるのではないかと、ぼくは思いました。それと同時に、その人は、どんな人だろうという興味がわいてきたので、飼い主さんが書斎で仕事をしている間に、ぼくはうちを出て、昨夜、飼い主さんが入っていったうちを探しにいきました。うちはすぐに見つかりました。窓の外に張り出している板の上にあがって、なかの様子を、こっそりうかがうと、部屋のなかに十歳ぐらいの女の子がいるのが見えました。女の子は机の前に座って、作文のようなものを書いていました。でも、筆がなかなか進まないようで、女の子は鉛筆を持ったまま、ぼーっとした顔をしながら、うつろな目で窓の外を見ていることが多かったです。しばらくしてから、部屋のドアが開いて、女の子のお母さんが部屋のなかに入ってきました。お母さんは女の子の机の上をのぞきこんで、作文がまだ、ほとんど書けていないのを見ると、女の子の作文帳を机の上にばーんとたたきつけてから、怖い顔をしながら、大きな声で、がみがみと何か言っていました。ぼくには人の話が分からないから、何を言っていたのかよく分かりませんでした。でもお母さんがひどく怒っているのは分かりました。お母さんは鬼のような形相をして、怒っていたから、女の子はこらえきれなくなって泣きべそをかいていました。それを見て、あの人は本当に、あの子のお母さんだろうかと、ぼくは思いました」
シャオパイがそう言った。それを聞いて、ぼくは、ふっと杜真子のことを思い浮かべた。杜真子と、杜真子のお母さんの関係によく似ていると思ったからだ。杜真子のお母さんは、杜真子のことを、この世で一番愛しているのは分かっている。しかしちょっとしたことでよく怒るし、その怒り方は半端ではない。天が震えるほどの激しい雷を頭の上から、がーんと落として目に角を立てる。とても聞くに堪えないような言葉を機関銃のように、だだだだだだーと杜真子に浴びせて杜真子を侮辱する。杜真子は、しくしくと泣き出すし、それを見て、ぼくはとても悲しくなる。心が花のように繊細で優しい杜真子にとって、お母さんの、あの侮辱の仕方はとても我慢できるようなレベルではない。ぼくは人の言葉が分かるので、お母さんが怒るたびに、ぼくの心は、ずきずきと痛んだ。あの人は本当に杜真子のお母さんだろうかと、ぼくは疑ったことがあった。『愛の鞭』という言葉を、ぼくは知っているが、杜真子のお母さんの度を過ぎた怒り方に、ぼくはいつも閉口していた。
シャオパイはさらに話を続けた。
「あの子はずっと泣いていたので、ぼくの心は張り裂けそうになった。できることなら、部屋のなかに入っていって、慰めてあげたいと思った。でも、ぼくには人の言葉が話せないから慰めてあげる術がなかった。あの子と別れるのがつらかったから、ぼくはしばらく、窓の外に張り出している板の上で、あの子をじっと見ていた。すると、あの子がぼくに気がついて、何か話しかけてきた。でも、ぼくには人の言葉が分からないので、何を言っているのか、さっぱり分からなかった。笑い猫のあんちゃんは、人の言葉が分かるから、あのとき、あんちゃんがそばにいたらよかったのになあと、ぼくは、つくづく思った」
シャオパイがそう言った。
それを聞いて、ぼくはまた杜真子のことを思った。ぼくが杜真子のうちに住んでいたころ、杜真子はお母さんからひどく怒られるたびに、ぼくによく心のなかにある、もんもんとした思いを吐露していた。耳にたこができるくらいに、ぼくは何度も杜真子の愚痴を聞いていた。そのために、ぼくはそのときから、だんだん人の言葉が分かるようになってきた。そのことをふっと思って、杜真子のことが懐かしくなった。
シャオパイはさらに話を続けた。
「ぼくはしばらくあの女の子のうちの窓の外にいて、女の子の心を慰めていた。ぼくには、笑い猫のあんちゃんのように笑うことはできないけど、ぼくの姿を見て、あの女の子が、にっこり笑ってくれたので、ぼくはうれしくなった。ぼくはそのあと、うちへ帰っていった。飼い主さんはそのときまだ書斎に閉じこもって仕事をしていた。書斎のドアは固く閉まっていて、なかに入っていくことができなかったから、ぼくは再び寝室に入って、洋服ダンスのなかを、少しだけ開けてみた。すると黒い袋がないことに気がついた」
シャオパイがそう言った。
「ゴミとして、どこかに捨てにいったのか?」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「ぼくも初めは、そう思っていました。ところが、そうではなかったです。黒い袋が書斎のなかに置いてあるのが、ベランダからレースのカーテン越しに見えたからです」
シャオパイがそう答えた。
「飼い主さんは何をしていたのだ?」
ぼくが聞くと、シャオパイが
「黒い袋の一つを机の上に載せて、なかを開けてから、何かを分析しているような目で、じっと見ていました。普段は眼鏡をかけない人ですが、そのときは、大きな眼鏡をかけていて、何とも言えないような妖気な雰囲気が書斎のなか全体に漂っていました」
と答えた。
「その眼鏡をかけると、普通は見えないものが見えてくるのかもしれないな」
ぼくはそう言った。それを聞いてシャオパイがうなずいた。
「その眼鏡をかけると、子どもたちが見た夢の内容が、はっきりと見えてくるのかもしれないと、ぼくはそのとき思いました。黒い袋を見ていれば見ているほど、飼い主さんの顔が悲しそうな表情に変わっていくのに、気がついたからです」
シャオパイがそう答えた。
「いやな夢を見る子どもは、現実生活に適応できなくて、うつうつとしている子どもが多いと思う。その子どもたちの心を解放してあげるために、お前の飼い主さんは、子どもたちが住んでいる家に行って、いやな夢を集めていたのかもしれないな」
ぼくがそう言うと、シャオパイが
「そうかもしれません」
と言って、うなずいていた。
「『雲の上の学校』にいる子どもたちは、どうして、ここへやってきたのか、お前は知っているのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「知っています。教えてあげましょうか」
シャオパイがそう言った。ぼくはうなずいた。
「子どもたちが、いやな夢を見たからです」
シャオパイがそう答えた。ぼくには何のことだか、さっぱり分からなかった。
「つまり、こういうことです」
ぼくが、ぽかんとしているのを見て、シャオパイが説明を始めた。
「ぼくの飼い主さんは、子どもたちの夢を集めることをしています。夢には楽しい夢と、いやな夢があります。その二つの夢を分別して、それぞれ別の袋に入れています。よい夢はピンクの袋に入れて、いやな夢は黒い袋に入れています。ゴミにたとえると、燃えるゴミと、燃えないゴミを分別して、それぞれ違う色の袋に入れるようなものです」
シャオパイは分かりやすく説明したつもりでいるようだった。しかしそれでも、ぼくにはまだ、何のことだか、さっぱり見当がつかなかった。
「お前が言っていることは意味がまったく分からない」
ぼくはそう言った。
「おかしなことを話して、笑い猫のあんちゃんをびっくりさせたくないから、言わないつもりだったけど、昨日、笑い猫のあんちゃんが話してくれたタイムスリップの話を聞いて、その話はまんざら否定できないと思うようになってきました」
シャオパイが、そう言った。
「お前の飼い主さんが、唐の時代からタイムスリップしてきたのではないかという話か?」
ぼくがそう聞くと、シャオパイがうなずいた。
「初めのうちは、そんなことは絶対にありえないと思っていました。でも、よく考えてみると、もしかしたら、その可能性も1パーセントぐらいはあるかもしれないと思うようになってきました」
シャオパイが、そう言った。
「そう思うようになったわけを、話してくれないか」
ぼくが懇願すると、シャオパイが、ぽつぽつと話し始めた。
「ぼくがあの人のうちで飼われるようになってから、飼い主さんがどんな人なのか、だんだん、分かるようになってきました。大きなキャリーバッグを持って、旅行によく行く人でした。うちにいるときは、ぼくのことを、とても大切にしてくれました。夜、寝るときも、ぼくはいつも飼い主さんと同じ部屋で寝ていました。ところがある晩、飼い主さんは、こっそりと起きだして、寝室を出て、うちから出ていきました。手には、からかさと、黒い袋とピンクの袋を持っていました」
シャオパイがそう言った。
「お前もいっしょに行ったのか」
ぼくが聞くと、シャオパイは首を横に振った。
「一人で出て行きました。でも、気づかれないように、ぼくはこっそりあとをつけていきました」
シャオパイの話に、ぼくは興味しんしんだった。
「飼い主さんは、どこへ行ったのだ」
ぼくはすぐに聞き返した。
「飼い主さんは玄関の前で、からかさを開いて、からかさについているボタンを押しました。すると不思議なことに、飼い主さんの体が、ふわふわと宙に浮いていきました。ぼくはそれを見て、びっくりして、思わず息を飲みました」
シャオパイが、そう言った。
「そのあと、どうしたのだ」
ぼくはますます興味を覚えていた。
「飼い主さんは、この町の住宅地が広がっているほうへ飛んでいきました。ぼくもあとを追っていきました。するとやがて飼い主さんは、ある家の前までくると、鍵がかかっていない窓から、なかに入って、三十分近く出てきませんでした。出てきたときには、背中に黒い袋を背負っていました。飼い主さんは、それから再び、空を飛んで、町のはずれにある自分のうちへ帰り始めました。ぼくは急いで、うちへ帰って、飼い主さんが戻ってくる前に、寝室に入って、うちにずっといたふりをしていました。飼い主さんは、うちへ帰ってくると、黒い袋を洋服ダンスのなかに入れて、そのあと再びベッドに横たわって朝まで寝ていました」
シャオパイがそう言った。
「そのあと、どうなったのだ」
ぼくは間髪を入れずに聞いた。
「夜が明けると、飼い主さんは、何事もなかったかのように目を覚ましてから、顔を洗って、そのあと朝食をとっていました。トーストと、カボチャがゆと、オレンジジュースを、いつものように食べたり飲んだりしていました。それから散歩に出かけていきました。ぼくもいっしょに散歩についていきました。飼い主さんの顔の表情には何の変化も見られなかったので、ぼくには昨夜の出来事が、まるで夢のように思えました。散歩から帰ってくると、飼い主さんは、書斎にこもって出てきませんでした。飼い主さんは在宅ワークをしている人なので、朝の十時ごろからお昼の三時ごろまで、書斎にこもって仕事をしています。その間、ぼくは好きなことが自由にできるので、昨日見たことが本当だったのかどうか、確かめてみようと思いました。そのためにこっそりと寝室に入って洋服ダンスのなかを開けてみました。すると黒い袋がいくつも入っていました。袋のなかからは、いやなにおいがしていました。悪夢のなかにしか出てこない亡霊のようなものが、袋のなかに見えたので、ぼくは正視できなくなって、すぐに洋服ダンスを閉めました」
シャオパイがそう言った。
「そうか。そういうことだったのか」
ぼくにはようやく、シャオパイが言ったことが少し分かってきたような気がした。
シャオパイは、そのあと次のように話した。
「黒い袋のなかには、悪夢が閉じ込められているのではないかと思うと、怖かったけど、悪夢を取り除いてもらった人は、今は、すっきりした気持ちでいるのではないかと、ぼくは思いました。それと同時に、その人は、どんな人だろうという興味がわいてきたので、飼い主さんが書斎で仕事をしている間に、ぼくはうちを出て、昨夜、飼い主さんが入っていったうちを探しにいきました。うちはすぐに見つかりました。窓の外に張り出している板の上にあがって、なかの様子を、こっそりうかがうと、部屋のなかに十歳ぐらいの女の子がいるのが見えました。女の子は机の前に座って、作文のようなものを書いていました。でも、筆がなかなか進まないようで、女の子は鉛筆を持ったまま、ぼーっとした顔をしながら、うつろな目で窓の外を見ていることが多かったです。しばらくしてから、部屋のドアが開いて、女の子のお母さんが部屋のなかに入ってきました。お母さんは女の子の机の上をのぞきこんで、作文がまだ、ほとんど書けていないのを見ると、女の子の作文帳を机の上にばーんとたたきつけてから、怖い顔をしながら、大きな声で、がみがみと何か言っていました。ぼくには人の話が分からないから、何を言っていたのかよく分かりませんでした。でもお母さんがひどく怒っているのは分かりました。お母さんは鬼のような形相をして、怒っていたから、女の子はこらえきれなくなって泣きべそをかいていました。それを見て、あの人は本当に、あの子のお母さんだろうかと、ぼくは思いました」
シャオパイがそう言った。それを聞いて、ぼくは、ふっと杜真子のことを思い浮かべた。杜真子と、杜真子のお母さんの関係によく似ていると思ったからだ。杜真子のお母さんは、杜真子のことを、この世で一番愛しているのは分かっている。しかしちょっとしたことでよく怒るし、その怒り方は半端ではない。天が震えるほどの激しい雷を頭の上から、がーんと落として目に角を立てる。とても聞くに堪えないような言葉を機関銃のように、だだだだだだーと杜真子に浴びせて杜真子を侮辱する。杜真子は、しくしくと泣き出すし、それを見て、ぼくはとても悲しくなる。心が花のように繊細で優しい杜真子にとって、お母さんの、あの侮辱の仕方はとても我慢できるようなレベルではない。ぼくは人の言葉が分かるので、お母さんが怒るたびに、ぼくの心は、ずきずきと痛んだ。あの人は本当に杜真子のお母さんだろうかと、ぼくは疑ったことがあった。『愛の鞭』という言葉を、ぼくは知っているが、杜真子のお母さんの度を過ぎた怒り方に、ぼくはいつも閉口していた。
シャオパイはさらに話を続けた。
「あの子はずっと泣いていたので、ぼくの心は張り裂けそうになった。できることなら、部屋のなかに入っていって、慰めてあげたいと思った。でも、ぼくには人の言葉が話せないから慰めてあげる術がなかった。あの子と別れるのがつらかったから、ぼくはしばらく、窓の外に張り出している板の上で、あの子をじっと見ていた。すると、あの子がぼくに気がついて、何か話しかけてきた。でも、ぼくには人の言葉が分からないので、何を言っているのか、さっぱり分からなかった。笑い猫のあんちゃんは、人の言葉が分かるから、あのとき、あんちゃんがそばにいたらよかったのになあと、ぼくは、つくづく思った」
シャオパイがそう言った。
それを聞いて、ぼくはまた杜真子のことを思った。ぼくが杜真子のうちに住んでいたころ、杜真子はお母さんからひどく怒られるたびに、ぼくによく心のなかにある、もんもんとした思いを吐露していた。耳にたこができるくらいに、ぼくは何度も杜真子の愚痴を聞いていた。そのために、ぼくはそのときから、だんだん人の言葉が分かるようになってきた。そのことをふっと思って、杜真子のことが懐かしくなった。
シャオパイはさらに話を続けた。
「ぼくはしばらくあの女の子のうちの窓の外にいて、女の子の心を慰めていた。ぼくには、笑い猫のあんちゃんのように笑うことはできないけど、ぼくの姿を見て、あの女の子が、にっこり笑ってくれたので、ぼくはうれしくなった。ぼくはそのあと、うちへ帰っていった。飼い主さんはそのときまだ書斎に閉じこもって仕事をしていた。書斎のドアは固く閉まっていて、なかに入っていくことができなかったから、ぼくは再び寝室に入って、洋服ダンスのなかを、少しだけ開けてみた。すると黒い袋がないことに気がついた」
シャオパイがそう言った。
「ゴミとして、どこかに捨てにいったのか?」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「ぼくも初めは、そう思っていました。ところが、そうではなかったです。黒い袋が書斎のなかに置いてあるのが、ベランダからレースのカーテン越しに見えたからです」
シャオパイがそう答えた。
「飼い主さんは何をしていたのだ?」
ぼくが聞くと、シャオパイが
「黒い袋の一つを机の上に載せて、なかを開けてから、何かを分析しているような目で、じっと見ていました。普段は眼鏡をかけない人ですが、そのときは、大きな眼鏡をかけていて、何とも言えないような妖気な雰囲気が書斎のなか全体に漂っていました」
と答えた。
「その眼鏡をかけると、普通は見えないものが見えてくるのかもしれないな」
ぼくはそう言った。それを聞いてシャオパイがうなずいた。
「その眼鏡をかけると、子どもたちが見た夢の内容が、はっきりと見えてくるのかもしれないと、ぼくはそのとき思いました。黒い袋を見ていれば見ているほど、飼い主さんの顔が悲しそうな表情に変わっていくのに、気がついたからです」
シャオパイがそう答えた。
「いやな夢を見る子どもは、現実生活に適応できなくて、うつうつとしている子どもが多いと思う。その子どもたちの心を解放してあげるために、お前の飼い主さんは、子どもたちが住んでいる家に行って、いやな夢を集めていたのかもしれないな」
ぼくがそう言うと、シャオパイが
「そうかもしれません」
と言って、うなずいていた。