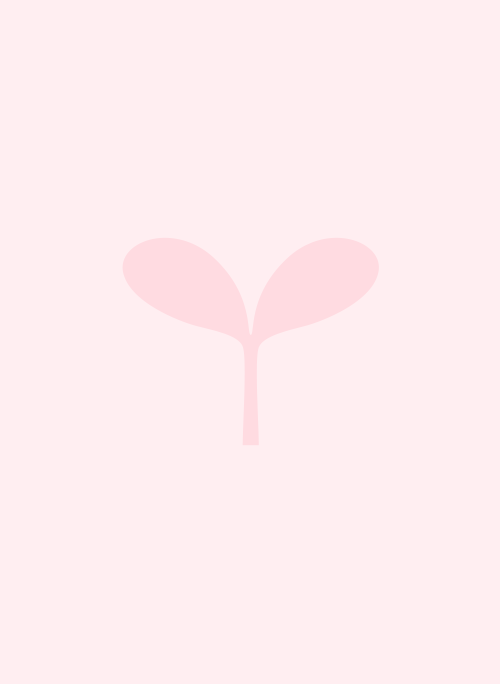天気……海抜が高くなるにつれて、空気はますます希薄になり、紫外線はますます強くなる。高山の山頂付近にある学校の近くには、コマクサ、クロユリ、チングルマ、ハイマツなどの高山植物が咲いている。
昨夜は、ここへ来て初めての夜を過ごした。感情が高ぶって、ぼくは、なかなか寝つけなかった。老いらくさんも、なかなか眠れないでいた。今朝早く、浅い眠りから覚めて、外を見ると、地面に、ピンク色のもやが、薄く立ちこめているのが分かった。顔をあげて空を見ると、東の空がピンク色の朝焼けに染まっていて、柔らかな朝日が、ほろほろと地面にこぼれているのが分かった。あたり一面がピンク色のもやに包まれていて、そのなかにキノコ形をした小さな家が、いくつか並んでいるのが、ぼんやりと見えた。小鳥のさえずりも、どこからか聞こえてきて、朝を迎えた喜びを歌っているように思えた。
それからまもなくキノコ形の小さな家のなかから、人間の子どもたちが次々と出てくるのが見えた。全部で六人いた。子どもたちはみんな、トレーニングウェアーを着ていて、元気はつらつとした顔をしていた。そのあと信じられないような出来事が起きた。子どもたちが、太陽を見ながら両手を横に伸ばして、手を鳥の翼のようにはばたかせると、子どもたちの体が宙に舞って、空中を飛び始めたからだ。
「うそだろう。こんなことがありうるのか」
ぼくは、あっけにとられて、目の前の光景を、ただ、ぼうぜんとして見ているよりほかなかった。老いらくさんも、口をぽかんと開けて放心状態にあるのが見て取れた。
「びっくりしたでしょう?」
シャオパイが、いつのまにか、ぼくと老いらくさんのすぐ後ろまで来ていて、そう言った。
「びっくりするも何も、こんなことがありうるのか。信じられない」
ぼくはそう答えた。
「あのトレーニングウェアーを着ると、空を飛ぶことができます。ライフジャケットも兼ねているので、水のなかを安全に泳ぐこともできます」
シャオパイがそう言った。
普通では絶対に考えられないような不思議な出来事を前にして、ぼくは、興奮がいつまでも冷めないでいた。
「びっくりするようなことは、これからも次々と起きるから、徐々に慣れていって」
シャオパイがそう言った。
「空を飛んでどうするのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「飛ぶことは早朝トレーニングの一環です。子どもたちは小鳥の声で目が覚めると、まず早朝トレーニングをします。小鳥たちといっしょに木々の上を楽しく飛んで、そのあと湖へ行きます。とてもきれいな湖です。そこへ案内します」
シャオパイがそう言った。
それからまもなく、ぼくと老いらくさんはシャオパイのあとについて、深い森林のなかに分け入っていった。やがて目の前に、神々しいほどに美しく輝いている湖が現れた。
「さあ、着きましたよ。鏡のように、きらきらと光っているので、『鏡湖』と呼ばれています」
シャオパイが、そう説明した。
高山の奥深くに、ひっそりと眠っている湖にふさわしく、サファイアのように青く透き通っていて、とても神秘的な湖だった。湖の美しさに魅了されながら、湖畔にしばらくたたずんでいると、やがて子どもたちが飛行訓練を終えて、湖のほとりに次々と降りてきた。
「子どもたちは、ここで何をするの?」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「見ていれば分かります」
シャオパイがそう答えた。
湖のほとりにアオガエルの群れが、一列にきちんと並んで立っているのが見えた。子どもたちが空から降りてきたのを見て、アオガエルは次々と湖のなかに飛び込んでいった。それを見て、子どもたちも次々と湖のなかに飛び込んでいった。子どもたちはアオガエルの泳ぎ方を真似しながら、アオガエルといっしょに楽しそうに泳いでいた。三十分ほど泳いでから、アオガエルは水のなかから上がってきた。それを見て、子どもたちも水のなかから上がってきた。アオガエルはそのあと再び一列にきちんと並んで、今度はカエル跳びを始めた。それを見て、子どもたちもカエル跳びを始めた。子どもたちはカエルのあとに続いて、ぴょんぴょんと跳びながら、湖の周りを楽しそうに回っていた。そのあとアオガエルはどこかへ行ってしまい、姿が見えなくなった。子どもたちは跳ぶのをやめて、今度は植物を育てるための温室のほうへ向かっていた。広くて大きな温室だった。
「子どもたちは、あそこで何をするの?」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「早朝トレーニングが終わったから、これから朝食の準備をします」
シャオパイが、そう答えた。それを聞いて、ぼくはけげんに思った。
「あそこは温室だろう?」
ぼくが聞くと、シャオパイが、うなずいた。
「そうです。温室です」
シャオパイが、そう答えた。
「温室のなかで、どうやって朝食の準備をするのか?」
ぼくには合点がいかなかった。
「行ったらすぐに分かります」
シャオパイがそう答えた。
「分かった。行ってみるよ」
ぼくはそう答えて、子どもたちのあとから、ついていった。
温室に近づけば近づくほど、温室のなかから、果物のいいにおいが漂ってきた。桃のにおいだった。温室のなかに桃の木があって、今、ちょうど桃の実が実っていて、収穫の時季を迎えているようだった。ここは高山の山頂付近だが、温室のなかは暖かくて、植物が順調に育っているようだった。ぼくは桃を食べたことがある。以前、シャオパイのうちへ遊びに行ったとき、シャオパイの飼い主さんが、ごちそうしてくれた。とてもおいしかった。そのときのことを、ぼくはふっと思い出した。
温室の前に着くと、子どもたちは、ガラスの扉を開けて、温室のなかに入っていった。ぼくと老いらくさんとシャオパイは温室の外から、なかの様子を見ていた。温室のなかには、食事をするためのテーブルがあって、テーブルの上にはトレーが六つ並べられていた。トレーのなかには皿が二つと、マグカップが一つ、セットになって置かれていた。
ぼくが思っていた通り、温室のなかに桃の木があって、実がたわわに実っていた。子どもたちは、実を一つずつ、ちぎって、皿の一つに入れていた。温室のなかにはニワトリも飼われていて、子どもたちがニワトリの背中を、ぽんとたたくと、ニワトリの体のなかから卵が、ころりと出てきた。子どもたちはニワトリが産んだばかりの新鮮な卵を、もう一つの皿に入れていた。温室のなかにはニワトリのほかに牛も飼われていた。子どもたちがマグカップを持ってきて、牛の乳房の下に置いてから乳をしぼると、温かい牛乳が、じゅるじゅると出ていた。
「わあ、すごい。どれもこれも新鮮なものばかりだ!」
ぼくは思わず感嘆の声を上げた。老いらくさんは、おなかをぐうぐう言わせていた。
「こんな朝食を食べてみたいでしょう?」
シャオパイが聞いた。
「ぼくたちも食べることができるのか」
ぼくは間髪を入れずに聞き返した。シャオパイは首を横に振った。
「今はできません。でも子どもたちが朝食を食べ終えて、温室のなかから出ていったあとに食べることができます」
シャオパイが、そう答えた。
「そうか、それなら、しばらく、ここで待つことにしよう」
ぼくはそう言った。
三十分ほどで、子どもたちは朝食を終えて、温室のなかから出てきた。子どもたちはみんな新鮮な桃や卵を食べたり、しぼりたての牛乳を飲んだりして、ますます元気そうな顔をしていた。
「さあ、これから温室のなかに入りましょう」
子どもたちの姿が見えなくなったあと、シャオパイが、そう言った。温室のなかには風通しをよくするために常に空けてあるすきまがあるので、ぼくたちは、そこから温室のなかに入っていった。ぼくたちはまず桃の木の下に行った。
「桃は、ぼくの飼い主さんが一番好きな果物だから、このなかで大切に育てています。甘くて糖度が高い『夏乙女』という品種の桃です。大きくて甘くて、乙女のように美しい果実です。さあ、早くちぎって食べてみて」
シャオパイがそう言った。
「うん、では早速、一ついただくことにするよ」
ぼくはそう答えてから、完熟しておいしそうな桃をちぎって、歯で一口かんだ。するとその瞬間、とろけるような甘い舌ざわりを感じた。高い糖度と優しい酸味のする上品な味わいが口のなかいっぱいに広がっていって、とても幸せな気持ちになった。
「何ておいしい桃だろう」
ぼくは思わず、そうつぶやいた。
そのあとぼくは、卵を食べることにした。温室のなかで飼われているニワトリの背中を手で軽くたたくと、ニワトリの体のなかから、ほかほかの卵が、ころりと出てきた。産みたての卵を割って食べると、とても新鮮でおいしかった。そのあとぼくは牛の乳しぼりをした。マグカップを牛の乳房の下に置いてから乳房をしぼると、真っ白い牛乳が出てきて、すぐにマグカップいっぱいになった。一口飲んでみると、温かくて、とてもおいしかった。
ぼくとシャオパイはテーブルに向かい合わせに座って、おしゃべりをしながら、ヘルシーな朝食を味わっていた。老いらくさんはテーブルの下にいたので、桃の果肉の一部を、わざと下に落として食べさせていた。
ぼくは以前、杜真子のうちで飼われていたとき、ゆで卵や牛乳を、朝食としてごちそうしてもらったことがある。でもここで食べたり飲んだりした卵や牛乳の味は、あのときの味とは、まったく違っていた。ここで飼われているニワトリや牛は、町のなかにある狭いゲージのなかで飼われているニワトリや牛とは違って、空気のきれいな高山のなかで、のびのぴと暮らしているから、ストレスがたまっていないのだろう。そのためにこんなにおいしい卵や牛乳を与えてくれるのだろう。ぼくはそう思った。
シャオパイが新鮮でヘルシーな朝食をごちそうしてくれたことに、ぼくは心から感謝した。するとシャオパイが
「これはまだ、ほんの序章に過ぎません。これからまだ目新しいものをたくさん見たり、珍しい体験をたくさんしたりします」
と言った。
「そうか。それは楽しみだな」
ぼくは、そう答えた。
「笑い猫のあんちゃん、ここは、ぼくの飼い主さんが作った学校で、今は六人の子どもが学んでいます。先生は、ぼくの飼い主さんが一人いるだけですが、鳥やカエルなどが先生のアシスタントとして、子どもたちの教育に一役かっています」
シャオパイがそう言った。
「そうか。ここは、そんな学校だったのか。ここに学校があることを、ぼくはつい最近まで知らなかった。いつできたのか?」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「ぼくもよく知らないけど、ずっと昔のことではないかと思います」
シャオパイがそう答えた。
「おまえは、これまで、ここへ何度も来たことがあったのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「いいえ、ぼくは最近初めてここへ来ました。飼い主さんが時々、夜中にキャリーバッグを引きながら、外に出ていくのを見たことはあったけど、これまでは、ぼくをいっしょに連れていかなかったから」
シャオパイがそう答えた。
「飼い主さんは、どうしてこの学校を作ったのか、お前は知っているか」
ぼくはシャオパイに聞いた。シャオパイが首を横に振った。
「ぼくは人間の言葉が話せないから、詳しい理由を聞くことはできません。でもここにいる子どもたちは、普通の子どもたちとは違って、普通の学校生活に適応できなくて、周りから浮いていたり、疎外感を感じたり、強制的に勉強させられることに圧迫感を感じている子どもばかりのような気がしました。そのために、その子どもたちを息苦しさから解放するために、この学校を作ったのではないかと、ぼくは思っています」
シャオパイがそう答えた。ぼくはそれを聞いて、先ほどの光景を思い浮かべた。六人の子どもたちが、鳥といっしょに空を飛んだり、アオガエルといっしょに湖のなかを泳いだりしている姿が、ぼくの脳裏によみがえってきた。みんなとても楽しそうに見えたので、明るい子どもたちばかりだと思っていた。ところが実際には、そうではなくて、心のうちに息苦しさを感じている子どもたちばかりだったのか。少しもそうは見えなかったので、ぼくはそのギャップに戸惑うばかりだった。
「子どもたちはここへ来てから、とても変わりました。もともとは、みんな明るい子どもだったようですが、その明るさがよみがえってきて、今は生気はつらつとした自分を取り戻して、毎日楽しく学んだり遊んだりしています」
シャオパイがそう言った。
「そうだったのか、それはよかったな」
ぼくはそう答えた。シャオパイがうなずいた。
「朝食をすませた子どもたちは、これから勉強をしに行きます」
シャオパイがそう言った。
「そうか。勉強することは、子どもたちにとって何よりも大切なことだからね」
ぼくはそう答えた。
「勉強すると言っても、この学校では教室のなかにじっと座って、先生の話を聞く授業はありません。この学校に教室はありません」
シャオパイがそう言ったので、ぼくはびっくりした。
「教室がなかったら、子どもたちは、どこで、どうやって勉強するのか?」
ぼくは間髪を入れずに聞き返した。
「子どもたちが勉強しているところへ連れて行きます。それを見たら分かると思います」
シャオパイは、もったいぶって、そう答えた。
昨夜は、ここへ来て初めての夜を過ごした。感情が高ぶって、ぼくは、なかなか寝つけなかった。老いらくさんも、なかなか眠れないでいた。今朝早く、浅い眠りから覚めて、外を見ると、地面に、ピンク色のもやが、薄く立ちこめているのが分かった。顔をあげて空を見ると、東の空がピンク色の朝焼けに染まっていて、柔らかな朝日が、ほろほろと地面にこぼれているのが分かった。あたり一面がピンク色のもやに包まれていて、そのなかにキノコ形をした小さな家が、いくつか並んでいるのが、ぼんやりと見えた。小鳥のさえずりも、どこからか聞こえてきて、朝を迎えた喜びを歌っているように思えた。
それからまもなくキノコ形の小さな家のなかから、人間の子どもたちが次々と出てくるのが見えた。全部で六人いた。子どもたちはみんな、トレーニングウェアーを着ていて、元気はつらつとした顔をしていた。そのあと信じられないような出来事が起きた。子どもたちが、太陽を見ながら両手を横に伸ばして、手を鳥の翼のようにはばたかせると、子どもたちの体が宙に舞って、空中を飛び始めたからだ。
「うそだろう。こんなことがありうるのか」
ぼくは、あっけにとられて、目の前の光景を、ただ、ぼうぜんとして見ているよりほかなかった。老いらくさんも、口をぽかんと開けて放心状態にあるのが見て取れた。
「びっくりしたでしょう?」
シャオパイが、いつのまにか、ぼくと老いらくさんのすぐ後ろまで来ていて、そう言った。
「びっくりするも何も、こんなことがありうるのか。信じられない」
ぼくはそう答えた。
「あのトレーニングウェアーを着ると、空を飛ぶことができます。ライフジャケットも兼ねているので、水のなかを安全に泳ぐこともできます」
シャオパイがそう言った。
普通では絶対に考えられないような不思議な出来事を前にして、ぼくは、興奮がいつまでも冷めないでいた。
「びっくりするようなことは、これからも次々と起きるから、徐々に慣れていって」
シャオパイがそう言った。
「空を飛んでどうするのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「飛ぶことは早朝トレーニングの一環です。子どもたちは小鳥の声で目が覚めると、まず早朝トレーニングをします。小鳥たちといっしょに木々の上を楽しく飛んで、そのあと湖へ行きます。とてもきれいな湖です。そこへ案内します」
シャオパイがそう言った。
それからまもなく、ぼくと老いらくさんはシャオパイのあとについて、深い森林のなかに分け入っていった。やがて目の前に、神々しいほどに美しく輝いている湖が現れた。
「さあ、着きましたよ。鏡のように、きらきらと光っているので、『鏡湖』と呼ばれています」
シャオパイが、そう説明した。
高山の奥深くに、ひっそりと眠っている湖にふさわしく、サファイアのように青く透き通っていて、とても神秘的な湖だった。湖の美しさに魅了されながら、湖畔にしばらくたたずんでいると、やがて子どもたちが飛行訓練を終えて、湖のほとりに次々と降りてきた。
「子どもたちは、ここで何をするの?」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「見ていれば分かります」
シャオパイがそう答えた。
湖のほとりにアオガエルの群れが、一列にきちんと並んで立っているのが見えた。子どもたちが空から降りてきたのを見て、アオガエルは次々と湖のなかに飛び込んでいった。それを見て、子どもたちも次々と湖のなかに飛び込んでいった。子どもたちはアオガエルの泳ぎ方を真似しながら、アオガエルといっしょに楽しそうに泳いでいた。三十分ほど泳いでから、アオガエルは水のなかから上がってきた。それを見て、子どもたちも水のなかから上がってきた。アオガエルはそのあと再び一列にきちんと並んで、今度はカエル跳びを始めた。それを見て、子どもたちもカエル跳びを始めた。子どもたちはカエルのあとに続いて、ぴょんぴょんと跳びながら、湖の周りを楽しそうに回っていた。そのあとアオガエルはどこかへ行ってしまい、姿が見えなくなった。子どもたちは跳ぶのをやめて、今度は植物を育てるための温室のほうへ向かっていた。広くて大きな温室だった。
「子どもたちは、あそこで何をするの?」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「早朝トレーニングが終わったから、これから朝食の準備をします」
シャオパイが、そう答えた。それを聞いて、ぼくはけげんに思った。
「あそこは温室だろう?」
ぼくが聞くと、シャオパイが、うなずいた。
「そうです。温室です」
シャオパイが、そう答えた。
「温室のなかで、どうやって朝食の準備をするのか?」
ぼくには合点がいかなかった。
「行ったらすぐに分かります」
シャオパイがそう答えた。
「分かった。行ってみるよ」
ぼくはそう答えて、子どもたちのあとから、ついていった。
温室に近づけば近づくほど、温室のなかから、果物のいいにおいが漂ってきた。桃のにおいだった。温室のなかに桃の木があって、今、ちょうど桃の実が実っていて、収穫の時季を迎えているようだった。ここは高山の山頂付近だが、温室のなかは暖かくて、植物が順調に育っているようだった。ぼくは桃を食べたことがある。以前、シャオパイのうちへ遊びに行ったとき、シャオパイの飼い主さんが、ごちそうしてくれた。とてもおいしかった。そのときのことを、ぼくはふっと思い出した。
温室の前に着くと、子どもたちは、ガラスの扉を開けて、温室のなかに入っていった。ぼくと老いらくさんとシャオパイは温室の外から、なかの様子を見ていた。温室のなかには、食事をするためのテーブルがあって、テーブルの上にはトレーが六つ並べられていた。トレーのなかには皿が二つと、マグカップが一つ、セットになって置かれていた。
ぼくが思っていた通り、温室のなかに桃の木があって、実がたわわに実っていた。子どもたちは、実を一つずつ、ちぎって、皿の一つに入れていた。温室のなかにはニワトリも飼われていて、子どもたちがニワトリの背中を、ぽんとたたくと、ニワトリの体のなかから卵が、ころりと出てきた。子どもたちはニワトリが産んだばかりの新鮮な卵を、もう一つの皿に入れていた。温室のなかにはニワトリのほかに牛も飼われていた。子どもたちがマグカップを持ってきて、牛の乳房の下に置いてから乳をしぼると、温かい牛乳が、じゅるじゅると出ていた。
「わあ、すごい。どれもこれも新鮮なものばかりだ!」
ぼくは思わず感嘆の声を上げた。老いらくさんは、おなかをぐうぐう言わせていた。
「こんな朝食を食べてみたいでしょう?」
シャオパイが聞いた。
「ぼくたちも食べることができるのか」
ぼくは間髪を入れずに聞き返した。シャオパイは首を横に振った。
「今はできません。でも子どもたちが朝食を食べ終えて、温室のなかから出ていったあとに食べることができます」
シャオパイが、そう答えた。
「そうか、それなら、しばらく、ここで待つことにしよう」
ぼくはそう言った。
三十分ほどで、子どもたちは朝食を終えて、温室のなかから出てきた。子どもたちはみんな新鮮な桃や卵を食べたり、しぼりたての牛乳を飲んだりして、ますます元気そうな顔をしていた。
「さあ、これから温室のなかに入りましょう」
子どもたちの姿が見えなくなったあと、シャオパイが、そう言った。温室のなかには風通しをよくするために常に空けてあるすきまがあるので、ぼくたちは、そこから温室のなかに入っていった。ぼくたちはまず桃の木の下に行った。
「桃は、ぼくの飼い主さんが一番好きな果物だから、このなかで大切に育てています。甘くて糖度が高い『夏乙女』という品種の桃です。大きくて甘くて、乙女のように美しい果実です。さあ、早くちぎって食べてみて」
シャオパイがそう言った。
「うん、では早速、一ついただくことにするよ」
ぼくはそう答えてから、完熟しておいしそうな桃をちぎって、歯で一口かんだ。するとその瞬間、とろけるような甘い舌ざわりを感じた。高い糖度と優しい酸味のする上品な味わいが口のなかいっぱいに広がっていって、とても幸せな気持ちになった。
「何ておいしい桃だろう」
ぼくは思わず、そうつぶやいた。
そのあとぼくは、卵を食べることにした。温室のなかで飼われているニワトリの背中を手で軽くたたくと、ニワトリの体のなかから、ほかほかの卵が、ころりと出てきた。産みたての卵を割って食べると、とても新鮮でおいしかった。そのあとぼくは牛の乳しぼりをした。マグカップを牛の乳房の下に置いてから乳房をしぼると、真っ白い牛乳が出てきて、すぐにマグカップいっぱいになった。一口飲んでみると、温かくて、とてもおいしかった。
ぼくとシャオパイはテーブルに向かい合わせに座って、おしゃべりをしながら、ヘルシーな朝食を味わっていた。老いらくさんはテーブルの下にいたので、桃の果肉の一部を、わざと下に落として食べさせていた。
ぼくは以前、杜真子のうちで飼われていたとき、ゆで卵や牛乳を、朝食としてごちそうしてもらったことがある。でもここで食べたり飲んだりした卵や牛乳の味は、あのときの味とは、まったく違っていた。ここで飼われているニワトリや牛は、町のなかにある狭いゲージのなかで飼われているニワトリや牛とは違って、空気のきれいな高山のなかで、のびのぴと暮らしているから、ストレスがたまっていないのだろう。そのためにこんなにおいしい卵や牛乳を与えてくれるのだろう。ぼくはそう思った。
シャオパイが新鮮でヘルシーな朝食をごちそうしてくれたことに、ぼくは心から感謝した。するとシャオパイが
「これはまだ、ほんの序章に過ぎません。これからまだ目新しいものをたくさん見たり、珍しい体験をたくさんしたりします」
と言った。
「そうか。それは楽しみだな」
ぼくは、そう答えた。
「笑い猫のあんちゃん、ここは、ぼくの飼い主さんが作った学校で、今は六人の子どもが学んでいます。先生は、ぼくの飼い主さんが一人いるだけですが、鳥やカエルなどが先生のアシスタントとして、子どもたちの教育に一役かっています」
シャオパイがそう言った。
「そうか。ここは、そんな学校だったのか。ここに学校があることを、ぼくはつい最近まで知らなかった。いつできたのか?」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「ぼくもよく知らないけど、ずっと昔のことではないかと思います」
シャオパイがそう答えた。
「おまえは、これまで、ここへ何度も来たことがあったのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「いいえ、ぼくは最近初めてここへ来ました。飼い主さんが時々、夜中にキャリーバッグを引きながら、外に出ていくのを見たことはあったけど、これまでは、ぼくをいっしょに連れていかなかったから」
シャオパイがそう答えた。
「飼い主さんは、どうしてこの学校を作ったのか、お前は知っているか」
ぼくはシャオパイに聞いた。シャオパイが首を横に振った。
「ぼくは人間の言葉が話せないから、詳しい理由を聞くことはできません。でもここにいる子どもたちは、普通の子どもたちとは違って、普通の学校生活に適応できなくて、周りから浮いていたり、疎外感を感じたり、強制的に勉強させられることに圧迫感を感じている子どもばかりのような気がしました。そのために、その子どもたちを息苦しさから解放するために、この学校を作ったのではないかと、ぼくは思っています」
シャオパイがそう答えた。ぼくはそれを聞いて、先ほどの光景を思い浮かべた。六人の子どもたちが、鳥といっしょに空を飛んだり、アオガエルといっしょに湖のなかを泳いだりしている姿が、ぼくの脳裏によみがえってきた。みんなとても楽しそうに見えたので、明るい子どもたちばかりだと思っていた。ところが実際には、そうではなくて、心のうちに息苦しさを感じている子どもたちばかりだったのか。少しもそうは見えなかったので、ぼくはそのギャップに戸惑うばかりだった。
「子どもたちはここへ来てから、とても変わりました。もともとは、みんな明るい子どもだったようですが、その明るさがよみがえってきて、今は生気はつらつとした自分を取り戻して、毎日楽しく学んだり遊んだりしています」
シャオパイがそう言った。
「そうだったのか、それはよかったな」
ぼくはそう答えた。シャオパイがうなずいた。
「朝食をすませた子どもたちは、これから勉強をしに行きます」
シャオパイがそう言った。
「そうか。勉強することは、子どもたちにとって何よりも大切なことだからね」
ぼくはそう答えた。
「勉強すると言っても、この学校では教室のなかにじっと座って、先生の話を聞く授業はありません。この学校に教室はありません」
シャオパイがそう言ったので、ぼくはびっくりした。
「教室がなかったら、子どもたちは、どこで、どうやって勉強するのか?」
ぼくは間髪を入れずに聞き返した。
「子どもたちが勉強しているところへ連れて行きます。それを見たら分かると思います」
シャオパイは、もったいぶって、そう答えた。