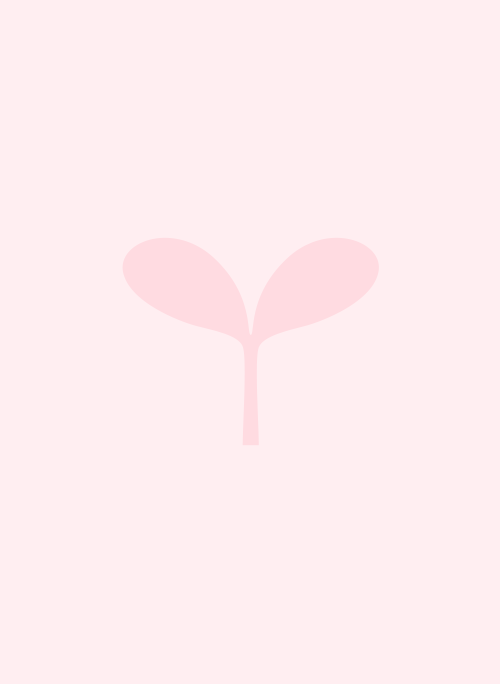天気……山岳地帯を歩いていると、朝夕は吹く風にひんやりとした冷たさを感じる。しかし、お昼近くになると太陽の光が暑く照りつけ、もうすでに季節は初夏に入っていることを実感する。
これまで三日間、ぼくと老いらくさんは、昼も夜も、ほとんど休まず、歩きに歩いて急峻な山々を幾つも越えて、西山山脈の高みを目指して登って行った。そしてついにある日のお昼過ぎに西山山脈の最高峰である『入雲峰』の五合目辺りまで到達することができた。山の頂上付近が常に雲のなかに隠れていて、ぼんやりとしか見えないことから、『入雲峰』と呼ばれている。
「もう少し上まで登って行けば、『雲の上の学校』が、もっとはっきり見えてきます。でもぼくが案内できるのはここまでです」
カヤネズミがそう言った。
「どうしてだ?」
ぼくは、けげんに思って聞き返した。
「山の上の方は空気が薄いので、これ以上、登ったら高山病にかかる危険性があるからです」
カヤネズミがそう答えた。
「高山病?」
聞きなれない言葉だったので、ぼくはカヤネズミに聞き返した。
「そう、高山病。短時間で高山に登るとおこる可能性がある病気です。気圧の低下による酸素不足が原因だと言われています」
カヤネズミが、そう説明してくれた。
「そうか、そんな病気になるのか」
ぼくは少し怖くなってきた。
「わしも怖くないことはないが、それでも、そこに学校があるということは、行けないことはないのだ。少しずつ体を慣らして、それから徐々に登っていけばいいのだ。そうしよう」
老いらくさんが、そう言った。老いらくさんの提案に、ぼくは同意した。
それからまもなくカヤネズミは、ひとりで下山していった。
高山が連なっている山岳地帯の八合目から上は常に雲と霧に深く覆われている。天気がよいときでも、何か、もやもやとしたものが立ち込めていて、頭を上げて、上を見ても、頂上付近は、ひどくかすんでしか見えなかった。
「シャオパイと、シャオパイの飼い主さんは、よくあんなところまで登っていきましたね」
ぼくは感心したような声で、老いらくさんに、そう言った。
「そうだな。わしらと同じように、一歩一歩、登っていったのだろうか」
老いらくさんが、そう答えた。
「それ以外、考えられないでしょう。高山病にはかからなかったのでしょうか」
ぼくはシャオパイや、シャオパイの飼い主さんの体調を気遣っていた。
「シャオパイはともかく、シャオパイの飼い主さんは仙女のような人だから、大丈夫だったのではないかな」
老いらくさんが、そう答えた。
ぼくと老いらくさんは高山病になるのを恐れて、しばらく五合目に留まって、低い気圧に体を徐々に慣らしてから登ることにした。高山病の症状としては、頭痛や、めまいや、意識や思考力の低下や、息切れや、動悸などがあるそうなので、もし、それらを感じたら無理をしないで、体が慣れるまで、それ以上、上に登らないことにしていた。一週間ほど、五合目にとどまって、それから、ぼくと老いらくさんは、さらに上を目指して登り始めた。食料と水の確保も大切な問題だ。ぼくと老いらくさんは高山植物の葉を食べたり、葉についているしずくを飲んだりして、命をつないでいた。
ぼくと老いらくさんは、朝早くから登り始めて、時々、休憩を取りながら、お昼まで登り続けた。しかし雲と霧が深く立ち込めていて、視界が悪かったので、山頂付近は、ひどくかすんでしか見えなかった。お昼の休憩を取ってから、夕方近くまで再び登り続けた。しかしやはり、もうろうとしたものが立ち込めていて視界がさえぎられていた。しばらくしてから上を見ると、大きな鷹が空を飛んでいるのが見えた。
「あの鷹の背中に乗ることができたら、こんなに苦労をしないで山頂まで、すぐに飛んでいけるのになあ」
と、ぼくは、たわいもないことを、老いらくさんに言った。すると老いらくさんが
「それもありうるのではないか」
と、意外なことを言った。
「どうしてですか」
ぼくはすぐに聞き返した。
「だってお前は、いろいろな動物の言葉が話せるではないか。鳥の言葉も話せるのだろう?」
老いらくさんが、聞いた。
「ええ、話せます」
ぼくはそう答えた。
「だったら鳥の言葉でお願いしてみたらどうだ。にっこりと笑みを浮かべながら、乗りたいわけを話したら、もしかしたら乗せてくれるかもしれないではないか」
老いらくさんが、そう言った。
「さすが、老いらくさん。いいことを思いつきましたね。でもそんなことをしたら危ないですから、やめておきます」
ぼくはそう答えて、老いらくさんの提案を聞き流した。
そのとき、突然、空がにわかに曇ってきて、バケツをひっくり返したような、どしゃぶりの雨が降ってきた。雨ととともに激しい風も吹いてきて、たくさんの木々が根こそぎ引き抜かれて地面に倒れた。倒れた木々の枝と葉は空に吹きあげられて、遠くへ飛ばされていった。ぼくと老いらくさんは身の危険を感じて、木にしっかりと、しがみついていた。それでもやはり、恐ろしさのあまり、生きている心地がしなかった。
それからまもなく、ぼくは木にしがみついたまま、風に巻きあげられて宙を飛び、ほどなく、気を失ってしまった。
「笑い猫のあんちゃん、しっかりして」
気を失ってから、どれくらい経ったのか分からないが、かすかに、ぼくを呼ぶ声が聞こえたような気がした。うっすらと目を開けると、目の前にシャオパイがいた。日はすでにとっぷりと暮れていて、空には満月が、こうこうと輝いていた。
「あっ、気がついた」
シャオパイが、うれしそうな顔をして、そう言った。
「シャオパイか。ここは一体、どこなのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「ぼくの飼い主さんがいる学校だよ」
シャオパイが、そう答えた。
「笑い猫のあんちゃん、どうやってここへ来たの」
シャオパイが、けげんそうな顔をしていた。
「ぼくにもよく分からない。竜巻のような強風に巻きあげられて、木にしがみついたまま宙に飛ばされたことまでは覚えているが、そのあとのことは……」
ぼくはそう答えるしかなかった。
「そうだったの。だから、木の葉がいっぱい体にくっついているのね」
シャオパイは合点がいったような顔をしていた。
「ここは強風は吹かなかったのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「吹かなかったよ。ほんの数秒だけ、何か、どさっという音がしたので、何だろうと思って、外に出てみると、ここに笑い猫のあんちゃんがいた。びっくりした」
シャオパイがそう答えた。
「ぼくのほかには、だれもいなかったか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「いや、だれも見ていないよ。だれかといっしょだったの?」
シャオパイが聞いた。
「ぼくの友だちの老いらくさんといっしょに吹き飛ばされたから」
ぼくはそう答えた。
「そうだったの。じゃあ、どこか別のところにいるかもしれない。これから手分けして探しにいってみましょう」
シャオパイがそう言った。ぼくとシャオパイはそれからまもなく、老いらくさんを探しにいった。シャオパイは老いらくさんのことを知っているので、探しに行くことに快く協力してくれた。
しばらく探していると、老いらくさんが猫よけのために体に塗っているツバキ油のにおいが、ぷーんと漂ってきた。においがしてくる方に近づいて行くと、木の枝から、老いらくさんの声がした。
「笑い猫、ここだよ」
「あー、そんなところにいたのですか。早く、下りてきてくださいよ」
ぼくは老いらくさんに呼びかけた。すると老いらくさんが困ったような顔をしながら
「下りたくても、下りることができないのだよ」
と言った。
「どうしてですか」
ぼくはけげんに思って聞き返した。
「体が木のまたに挟まって、動きが取れないのだ」
泣きそうな声で、老いらくさんが、そう言った。それを聞いて、ぼくはすぐに、その木に登って、老いらくさんのすぐ近くまで行って、下から老いらくさんの体を押しあげた。力をこめてぐいと押すと、老いらくさんの体が、ようやく木のまたから、すぽっと抜けた。
「ありがとう。お前のおかげで助かったよ」
老いらくさんが、ほっとしたような顔をしていた。
それからまもなく、ぼくは老いらくさんといっしょにシャオパイの前まで行った。
「お前や、お前の飼い主さんがこの山の頂上付近にある学校のなかにいると、お前のうちにいたカヤネズミから聞いたので、どんなところなのか興味を覚えたので、見に来ていたのだ」
ぼくはシャオパイに、ここへ来たわけを話した。
「そうだったの」
シャオパイがうなずいた。
「ここへ来るのはとても大変だった。登っても登っても、雲と霧に深く覆われていて、頂上付近が、ほとんど見えなかったからだ。それでもめげないで登っていると、強風に吹きあげられて、意識を失って、気がついたら、ここに来ていた」
ぼくはこれまでのいきさつを話した。
「そうだったの。それは大変だったね」
シャオパイがそう答えた。
「お前や、お前の飼い主さんは、ここで何をしているのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「ぼくは飼い主さんの手伝いをしている」
シャオパイがそう言った。
「何の手伝いをしているのだ?」
ぼくはすぐに聞き返した。
「教育の手伝いだよ。子どもたちに起床を呼びかけたり、夜の見回りをしている」
シャオパイが、そう答えた。ぼくにはぴんとこなかった。
「お前の飼い主さんは何をしているのか?」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「子どもたちの先生をしている」
シャオパイがそう答えた。
「そうか。あの人は、そんなこともできるのか」
ぼくは、うなずいた。
シャオパイの飼い主さんが先生をしているという話を聞いて、ぼくは老いらくさんが、先日話してくれた話を、ふと思い出した。老いらくさんが見た夢のなかに、飼い主さんそっくりの女の人が出てきて、子どもたちに愛情深く教えていたという話だ。
「老いらくさんが最近、不思議な夢を見て、そのなかに、お前の飼い主さんにそっくりの女の人が出てきたそうだ」
ぼくがそう言うと、シャオパイが興味深そうな顔をしていた。
「どんな夢ですか」
「それは言えない」
ぼくはそう答えて首を横に振った。
「どうしてですか」
「あくまでも夢に過ぎないからだ」
ぼくはそう答えた。老いらくさんが夢のなかで唐の時代にタイムスリップして、そこにシャオパイの飼い主さんにそっくりの人がいたと話しても、シャオパイには、おそらく何のことだか、さっぱり分からないだろうから、話しても意味がないと思ったからだ。
「お前や、お前の飼い主さんは、いつ、どうやって、ここへ来たのだ」
ぼくは話題を変えて、シャオパイに聞いた。
「ある夜更けに、ぼくの飼い主さんが大きなキャリーバッグの上に、ぼくを乗せて外に出ました」
シャオパイがそう答えた。
「そのキャリーバッグなら、見たことがあるよ。以前、お前のうちに遊びに行ったとき、飼い主さんが、そのキャリーバッグを引きながら、うちから出てきて、旅行に出かけようとしていたから」
ぼくはそう答えた。
「そう、あのキャリーバッグです」
シャオパイがそう答えた。
「あの、大きなキャリーバッグの上に乗って、お前はうちを出たのか」
ぼくが聞くと、シャオパイがうなずいた。
「いつもは車で出かけていくけど、あの晩は車の手配はしなくて、歩いてうちの外に出ました」
シャオパイがそう言った。
「バッグのなかに何が入っているのか知らないが、手で引いて運ぶのは、大変だったのではないのか」
ぼくが聞くと、シャオパイが首を横に振った。
「それが意外と軽いみたいでした。飼い主さんは、がらがらと音を立てながら、しばらくキャリーバッグを引きずって運んでいました。周りに誰もいないことを確認すると、飼い主さんはキャリーバッグのファスナーを開けて、なかから、からかさを取り出しました。そのあと、ぼくを抱えてキャリーバッグの上に座りました。そして、からかさを開いてから、柄についているボタンを押しました。すると不思議なことが起きました。キャリーバッグがふわふわと宙に浮かび出したからです。飼い主さんは、からかさを右手で差して、左手で、ぼくを抱えて何か言いました。するとキャリーバッグは夜空に上がり、この山の山頂まで飛んできました」
シャオパイがそう言った。
それを聞いて、ぼくは、びっくりした。
(何て不思議な出来事なんだろう。信じられない)
ぼくは、そう思った。シャオパイが言ったことを老いらくさんに話すと、老いらくさんも、仰天していた。
「まるで魔法使いではないか。あの人は、やはり、ただ者ではない」
老いらくさんが、そう言った。
「そうだね。ぼくもそう思う」
老いらくさんの意見に、ぼくは同意した。
「せっかく、ここまで来たのだから、ぼくは、そのうち、あんちゃんたちを飼い主さんのところへ連れて行ってあげるよ」
シャオパイが、そう言った。
「分かった。そのときを楽しみにしているよ」
ぼくは、そう答えた。
「じゃあ、ぼくはこれから、建物のなかに戻ります。飼い主さんが、ぼくを待っていると思うから」
シャオパイが、そう言った。それからまもなく、シャオパイの姿は、深い闇のなかに消えていった。ぼくはそのあと、シャオパイの飼い主さんのことに、思いを馳せていた。シャオパイの飼い主さんと、ぼくは以前、いっしょにお茶を飲んだことがある。ぼくのことをまだ覚えてくれているかもしれない。ぼくはそう思った。ぼくを見て、びっくりするだろうが、ぼくのことを嫌ってはいないので、喜んで迎えてくれるかもしれない。ぼくはそう思った。老いらくさんはネズミなので、歓迎されないと思うので、建物の外で、しばらく待ってもらうしかない。そう思いながら、ぼくは、老いらくさんといっしょに建物の陰に身を横たえて、眠ることにした。空に輝いている月の光が、ほろほろとこぼれていて、優しい気持ちにしてくれた。でも今夜は、ここへ来て初めての夜だから、気持ちが自然と高揚して、なかなか眠りに就けないでいた。
これまで三日間、ぼくと老いらくさんは、昼も夜も、ほとんど休まず、歩きに歩いて急峻な山々を幾つも越えて、西山山脈の高みを目指して登って行った。そしてついにある日のお昼過ぎに西山山脈の最高峰である『入雲峰』の五合目辺りまで到達することができた。山の頂上付近が常に雲のなかに隠れていて、ぼんやりとしか見えないことから、『入雲峰』と呼ばれている。
「もう少し上まで登って行けば、『雲の上の学校』が、もっとはっきり見えてきます。でもぼくが案内できるのはここまでです」
カヤネズミがそう言った。
「どうしてだ?」
ぼくは、けげんに思って聞き返した。
「山の上の方は空気が薄いので、これ以上、登ったら高山病にかかる危険性があるからです」
カヤネズミがそう答えた。
「高山病?」
聞きなれない言葉だったので、ぼくはカヤネズミに聞き返した。
「そう、高山病。短時間で高山に登るとおこる可能性がある病気です。気圧の低下による酸素不足が原因だと言われています」
カヤネズミが、そう説明してくれた。
「そうか、そんな病気になるのか」
ぼくは少し怖くなってきた。
「わしも怖くないことはないが、それでも、そこに学校があるということは、行けないことはないのだ。少しずつ体を慣らして、それから徐々に登っていけばいいのだ。そうしよう」
老いらくさんが、そう言った。老いらくさんの提案に、ぼくは同意した。
それからまもなくカヤネズミは、ひとりで下山していった。
高山が連なっている山岳地帯の八合目から上は常に雲と霧に深く覆われている。天気がよいときでも、何か、もやもやとしたものが立ち込めていて、頭を上げて、上を見ても、頂上付近は、ひどくかすんでしか見えなかった。
「シャオパイと、シャオパイの飼い主さんは、よくあんなところまで登っていきましたね」
ぼくは感心したような声で、老いらくさんに、そう言った。
「そうだな。わしらと同じように、一歩一歩、登っていったのだろうか」
老いらくさんが、そう答えた。
「それ以外、考えられないでしょう。高山病にはかからなかったのでしょうか」
ぼくはシャオパイや、シャオパイの飼い主さんの体調を気遣っていた。
「シャオパイはともかく、シャオパイの飼い主さんは仙女のような人だから、大丈夫だったのではないかな」
老いらくさんが、そう答えた。
ぼくと老いらくさんは高山病になるのを恐れて、しばらく五合目に留まって、低い気圧に体を徐々に慣らしてから登ることにした。高山病の症状としては、頭痛や、めまいや、意識や思考力の低下や、息切れや、動悸などがあるそうなので、もし、それらを感じたら無理をしないで、体が慣れるまで、それ以上、上に登らないことにしていた。一週間ほど、五合目にとどまって、それから、ぼくと老いらくさんは、さらに上を目指して登り始めた。食料と水の確保も大切な問題だ。ぼくと老いらくさんは高山植物の葉を食べたり、葉についているしずくを飲んだりして、命をつないでいた。
ぼくと老いらくさんは、朝早くから登り始めて、時々、休憩を取りながら、お昼まで登り続けた。しかし雲と霧が深く立ち込めていて、視界が悪かったので、山頂付近は、ひどくかすんでしか見えなかった。お昼の休憩を取ってから、夕方近くまで再び登り続けた。しかしやはり、もうろうとしたものが立ち込めていて視界がさえぎられていた。しばらくしてから上を見ると、大きな鷹が空を飛んでいるのが見えた。
「あの鷹の背中に乗ることができたら、こんなに苦労をしないで山頂まで、すぐに飛んでいけるのになあ」
と、ぼくは、たわいもないことを、老いらくさんに言った。すると老いらくさんが
「それもありうるのではないか」
と、意外なことを言った。
「どうしてですか」
ぼくはすぐに聞き返した。
「だってお前は、いろいろな動物の言葉が話せるではないか。鳥の言葉も話せるのだろう?」
老いらくさんが、聞いた。
「ええ、話せます」
ぼくはそう答えた。
「だったら鳥の言葉でお願いしてみたらどうだ。にっこりと笑みを浮かべながら、乗りたいわけを話したら、もしかしたら乗せてくれるかもしれないではないか」
老いらくさんが、そう言った。
「さすが、老いらくさん。いいことを思いつきましたね。でもそんなことをしたら危ないですから、やめておきます」
ぼくはそう答えて、老いらくさんの提案を聞き流した。
そのとき、突然、空がにわかに曇ってきて、バケツをひっくり返したような、どしゃぶりの雨が降ってきた。雨ととともに激しい風も吹いてきて、たくさんの木々が根こそぎ引き抜かれて地面に倒れた。倒れた木々の枝と葉は空に吹きあげられて、遠くへ飛ばされていった。ぼくと老いらくさんは身の危険を感じて、木にしっかりと、しがみついていた。それでもやはり、恐ろしさのあまり、生きている心地がしなかった。
それからまもなく、ぼくは木にしがみついたまま、風に巻きあげられて宙を飛び、ほどなく、気を失ってしまった。
「笑い猫のあんちゃん、しっかりして」
気を失ってから、どれくらい経ったのか分からないが、かすかに、ぼくを呼ぶ声が聞こえたような気がした。うっすらと目を開けると、目の前にシャオパイがいた。日はすでにとっぷりと暮れていて、空には満月が、こうこうと輝いていた。
「あっ、気がついた」
シャオパイが、うれしそうな顔をして、そう言った。
「シャオパイか。ここは一体、どこなのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「ぼくの飼い主さんがいる学校だよ」
シャオパイが、そう答えた。
「笑い猫のあんちゃん、どうやってここへ来たの」
シャオパイが、けげんそうな顔をしていた。
「ぼくにもよく分からない。竜巻のような強風に巻きあげられて、木にしがみついたまま宙に飛ばされたことまでは覚えているが、そのあとのことは……」
ぼくはそう答えるしかなかった。
「そうだったの。だから、木の葉がいっぱい体にくっついているのね」
シャオパイは合点がいったような顔をしていた。
「ここは強風は吹かなかったのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「吹かなかったよ。ほんの数秒だけ、何か、どさっという音がしたので、何だろうと思って、外に出てみると、ここに笑い猫のあんちゃんがいた。びっくりした」
シャオパイがそう答えた。
「ぼくのほかには、だれもいなかったか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「いや、だれも見ていないよ。だれかといっしょだったの?」
シャオパイが聞いた。
「ぼくの友だちの老いらくさんといっしょに吹き飛ばされたから」
ぼくはそう答えた。
「そうだったの。じゃあ、どこか別のところにいるかもしれない。これから手分けして探しにいってみましょう」
シャオパイがそう言った。ぼくとシャオパイはそれからまもなく、老いらくさんを探しにいった。シャオパイは老いらくさんのことを知っているので、探しに行くことに快く協力してくれた。
しばらく探していると、老いらくさんが猫よけのために体に塗っているツバキ油のにおいが、ぷーんと漂ってきた。においがしてくる方に近づいて行くと、木の枝から、老いらくさんの声がした。
「笑い猫、ここだよ」
「あー、そんなところにいたのですか。早く、下りてきてくださいよ」
ぼくは老いらくさんに呼びかけた。すると老いらくさんが困ったような顔をしながら
「下りたくても、下りることができないのだよ」
と言った。
「どうしてですか」
ぼくはけげんに思って聞き返した。
「体が木のまたに挟まって、動きが取れないのだ」
泣きそうな声で、老いらくさんが、そう言った。それを聞いて、ぼくはすぐに、その木に登って、老いらくさんのすぐ近くまで行って、下から老いらくさんの体を押しあげた。力をこめてぐいと押すと、老いらくさんの体が、ようやく木のまたから、すぽっと抜けた。
「ありがとう。お前のおかげで助かったよ」
老いらくさんが、ほっとしたような顔をしていた。
それからまもなく、ぼくは老いらくさんといっしょにシャオパイの前まで行った。
「お前や、お前の飼い主さんがこの山の頂上付近にある学校のなかにいると、お前のうちにいたカヤネズミから聞いたので、どんなところなのか興味を覚えたので、見に来ていたのだ」
ぼくはシャオパイに、ここへ来たわけを話した。
「そうだったの」
シャオパイがうなずいた。
「ここへ来るのはとても大変だった。登っても登っても、雲と霧に深く覆われていて、頂上付近が、ほとんど見えなかったからだ。それでもめげないで登っていると、強風に吹きあげられて、意識を失って、気がついたら、ここに来ていた」
ぼくはこれまでのいきさつを話した。
「そうだったの。それは大変だったね」
シャオパイがそう答えた。
「お前や、お前の飼い主さんは、ここで何をしているのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「ぼくは飼い主さんの手伝いをしている」
シャオパイがそう言った。
「何の手伝いをしているのだ?」
ぼくはすぐに聞き返した。
「教育の手伝いだよ。子どもたちに起床を呼びかけたり、夜の見回りをしている」
シャオパイが、そう答えた。ぼくにはぴんとこなかった。
「お前の飼い主さんは何をしているのか?」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「子どもたちの先生をしている」
シャオパイがそう答えた。
「そうか。あの人は、そんなこともできるのか」
ぼくは、うなずいた。
シャオパイの飼い主さんが先生をしているという話を聞いて、ぼくは老いらくさんが、先日話してくれた話を、ふと思い出した。老いらくさんが見た夢のなかに、飼い主さんそっくりの女の人が出てきて、子どもたちに愛情深く教えていたという話だ。
「老いらくさんが最近、不思議な夢を見て、そのなかに、お前の飼い主さんにそっくりの女の人が出てきたそうだ」
ぼくがそう言うと、シャオパイが興味深そうな顔をしていた。
「どんな夢ですか」
「それは言えない」
ぼくはそう答えて首を横に振った。
「どうしてですか」
「あくまでも夢に過ぎないからだ」
ぼくはそう答えた。老いらくさんが夢のなかで唐の時代にタイムスリップして、そこにシャオパイの飼い主さんにそっくりの人がいたと話しても、シャオパイには、おそらく何のことだか、さっぱり分からないだろうから、話しても意味がないと思ったからだ。
「お前や、お前の飼い主さんは、いつ、どうやって、ここへ来たのだ」
ぼくは話題を変えて、シャオパイに聞いた。
「ある夜更けに、ぼくの飼い主さんが大きなキャリーバッグの上に、ぼくを乗せて外に出ました」
シャオパイがそう答えた。
「そのキャリーバッグなら、見たことがあるよ。以前、お前のうちに遊びに行ったとき、飼い主さんが、そのキャリーバッグを引きながら、うちから出てきて、旅行に出かけようとしていたから」
ぼくはそう答えた。
「そう、あのキャリーバッグです」
シャオパイがそう答えた。
「あの、大きなキャリーバッグの上に乗って、お前はうちを出たのか」
ぼくが聞くと、シャオパイがうなずいた。
「いつもは車で出かけていくけど、あの晩は車の手配はしなくて、歩いてうちの外に出ました」
シャオパイがそう言った。
「バッグのなかに何が入っているのか知らないが、手で引いて運ぶのは、大変だったのではないのか」
ぼくが聞くと、シャオパイが首を横に振った。
「それが意外と軽いみたいでした。飼い主さんは、がらがらと音を立てながら、しばらくキャリーバッグを引きずって運んでいました。周りに誰もいないことを確認すると、飼い主さんはキャリーバッグのファスナーを開けて、なかから、からかさを取り出しました。そのあと、ぼくを抱えてキャリーバッグの上に座りました。そして、からかさを開いてから、柄についているボタンを押しました。すると不思議なことが起きました。キャリーバッグがふわふわと宙に浮かび出したからです。飼い主さんは、からかさを右手で差して、左手で、ぼくを抱えて何か言いました。するとキャリーバッグは夜空に上がり、この山の山頂まで飛んできました」
シャオパイがそう言った。
それを聞いて、ぼくは、びっくりした。
(何て不思議な出来事なんだろう。信じられない)
ぼくは、そう思った。シャオパイが言ったことを老いらくさんに話すと、老いらくさんも、仰天していた。
「まるで魔法使いではないか。あの人は、やはり、ただ者ではない」
老いらくさんが、そう言った。
「そうだね。ぼくもそう思う」
老いらくさんの意見に、ぼくは同意した。
「せっかく、ここまで来たのだから、ぼくは、そのうち、あんちゃんたちを飼い主さんのところへ連れて行ってあげるよ」
シャオパイが、そう言った。
「分かった。そのときを楽しみにしているよ」
ぼくは、そう答えた。
「じゃあ、ぼくはこれから、建物のなかに戻ります。飼い主さんが、ぼくを待っていると思うから」
シャオパイが、そう言った。それからまもなく、シャオパイの姿は、深い闇のなかに消えていった。ぼくはそのあと、シャオパイの飼い主さんのことに、思いを馳せていた。シャオパイの飼い主さんと、ぼくは以前、いっしょにお茶を飲んだことがある。ぼくのことをまだ覚えてくれているかもしれない。ぼくはそう思った。ぼくを見て、びっくりするだろうが、ぼくのことを嫌ってはいないので、喜んで迎えてくれるかもしれない。ぼくはそう思った。老いらくさんはネズミなので、歓迎されないと思うので、建物の外で、しばらく待ってもらうしかない。そう思いながら、ぼくは、老いらくさんといっしょに建物の陰に身を横たえて、眠ることにした。空に輝いている月の光が、ほろほろとこぼれていて、優しい気持ちにしてくれた。でも今夜は、ここへ来て初めての夜だから、気持ちが自然と高揚して、なかなか眠りに就けないでいた。