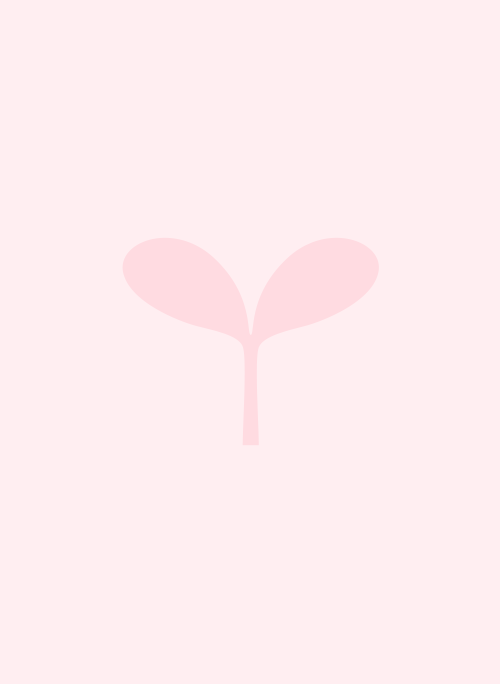天気……夏至が近づいてきた。翠湖公園のなかを歩いていると、日中はだんだん汗ばむようになってきた。それでも朝晩は、まだいくぶん涼しさが感じられる。朝早く散歩に出ると、さわやかな風がそよそよと吹いてきて気持ちがいい。
ぼくが翠湖公園に帰ってきてから、数日がたった。ぼくはまだ『雲の上の学校』のことが忘れられないでいる。『雲の上の学校』のことを妻猫に話したら、とても興味深そうな顔をしていた。
「雲の上に学校があるのですか?」
妻猫が、けげんそうな顔をしていた。
「高い山の上にある学校なので、下から見たら雲の上にある学校のように見えるから、そう呼ばれている」
ぼくは、そう答えた。
「その学校は普通の学校と、どう違っているのですか」
妻猫が聞いた。
「普通の学校では子どもたちは、教室のなかで先生から教わったり、教科書に書かれていることを覚えたりしているけど、『雲の上の学校』では違うのだ」
ぼくは、そう答えた。
「どう違うのですか」
妻猫が、さらに聞いた。
「『雲の上の学校』では、子どもたちに知識を一方的に教え込んだり、覚えさせたりするのではなくて、子どもたちに探索と発見の喜びを与えながら、自分たちの目と耳と足で実際に学ばせる教育方法を採っている。そのために学習効果がとてもあって、子どもたちがみんな生き生きとしている」
ぼくは、そう答えた。
「そうですか。それは素晴らしいですね」
妻猫が、そう答えた。
「ぼくは、これまで杜真子や馬小跳の学校に行って、授業見学をしたことがあるけど、どちらの学校でも、先生が一方的に教える教育方法を採っていた。そのために子どもたちのなかには受け入れることができなくて消極的になっている子どもがいた。けっして勉強が嫌いなのではなくて、自分が興味があることを自分で発見して学びたいと思っていた子どもだった。でもそのような考え方は自分勝手だとして認めてもらえなかったから、自信を失って、心理的な圧力を感じて、夜、いやな夢を見て、うなされていた」
ぼくは、そう言った。ぼくの話を聞いて、妻猫は、やるせない顔をした。
「その子どもは、どうなったの?」
妻猫が、心配そうな声で聞き返した。
「いやな夢を見た子どもは勉強することがだんだん嫌いになり、成績が落ちていった」
シャオパイから聞いたことを、ぼくは妻猫に伝えた。
「そうですか。その子どもは落第したのですか?」
妻猫が暗く沈んだ声で聞き返した。ぼくは首を横に振った。
「いや、落第はしていない。先生と親が、その子をしばらく休学させることにした」
ぼくは、そう答えた。
「休学した子はどうしたの?」
妻猫が聞き返した。
「先生や親の承諾が得られた子どもは『雲の上の学校』に行って、転地療養をしていた」
ぼくはそう答えた。
「転地療養って何ですか?」
妻猫がけげんそうな顔をして聞き返した。
「病気の治療や養生のために、気候のよいところに移ることだ」
ぼくがそう言うと、妻猫がうなずいていた。
「それで、その子たちの転地療養は、うまくいったのですか?」
妻猫が聞いた。
「うん、うまくいった。みんな元気になったから、みんな『雲の上の学校』から下界におりてきて、それまで通っていた学校に復学することになった」
ぼくは、そう答えた。
「『雲の上の学校』では先生が子どもたちを鼓舞して、子どもたちが興味があることを自分から主体的に探索させたり、発見させたりしていると、さっき、お父さんは言ったよね」
妻猫がそう言った。
「うん、そう言ったよ」
ぼくは、うなずいた。
「その教育方法で、子どもたちは、どのように変わっていったのですか?」
妻猫が聞いた。
「子どもたちは未知のことに対する興味や関心を積極的に抱くようになり、知りたいと思って危険や冒険をものともせずに自然のなかに飛び込んでいった。そして発見できた喜びを知り、勉強することに対して、もともと持っていた意欲を回復して、楽しさと自信を取り戻すようになった」
ぼくは、そう答えた。
「『雲の上の学校』では何人の子どもたちが学んでいたのですか?」
妻猫が聞いた。
「六人の子どもたちが学んでいた」
ぼくはそう答えた。
「教室はいくつありましたか?」
ぼくは首を横に振った。
「建物のなかに教室は一つもなかった」
ぼくがそう答えると、妻猫は、合点がいかないような顔をしていた。
「では、どこで授業をしていたのですか」
妻猫が聞き返した。
「自然のなかで授業をしていた。自然のなか全体が教室になっていた」
ぼくはそう答えた。妻猫はまだ、ぴんとこないような顔をしていた。
「天気がよくないときも、戸外で授業をしていたのですか」
妻猫が、そう聞いた。
「そうだよ。雨や雪のときも戸外で授業をしていた」
ぼくは、そう答えた。
「宿題も出されたのですか?」
妻猫が聞いた。ぼくは、うなずいた。
「もちろん出されたよ。みんなでまずテーマの中心的な問題について話し合って、そのあと宿舎に帰って一人で宿題をしていた。そのあとみんなでもう一度話し合って、分からない点や疑問に感じたことを出し合って、テーマに対する理解を深めてから、加筆修正をして、質の高いものを提出していた」
ぼくはそう答えた。
「どんな宿題が出されたのですか?」
妻猫が興味深そうな顔をして聞き返した。
「子どもたちが興味がありそうなものばかり出されていた。提出された宿題は先生が本にして、子どもたちに見せていた。『どれも珠玉の作品ばかりだ』と言って、子どもたちが書いた物語や、描いた絵を、先生が、ほめていた。それを聞いて、子どもたちは、みんな、とても喜んでいた」
ぼくは、そう答えた。
「いい先生ですね。子どもたちを励ますのが、とても上手な先生ですね。どんな先生なのか、わたしも一度、会ってみたいわ」
妻猫がそう言った。
「その先生なら、お母さんは、もうすでに会ったことがあるはずだよ」
ぼくは、そう答えた。それを聞いて、妻猫が、けげんそうな顔をしていた。
「えっ、だってわたしは、杜真子と馬小跳の学校の先生よりほかの先生は誰も知らないわ」
妻猫が、そう答えた。ぼくは、それを聞いて、思わず、くつくつと笑った。
「その先生というのは、シャオパイの飼い主さんだよ」
ぼくがそう言うと、妻猫がびっくりしたような顔をしていた。
「えっ、あの人が、その学校の先生だったのですか」
妻猫が聞き返した。ぼくはうなずいた。
「シャオパイの飼い主さんは、シャオパイを連れて、その学校に行って、子どもたちの教育に当たっていた。子どもたちは、その人のことを、ミー先生と呼んでいた。ほかに先生はいなかったから、シャオパイの飼い主さんは一人ですべての授業を受け持っていた」
ぼくはそう言った。
「シャオパイの飼い主さんのことを、わたしはよく覚えているわ。温和で上品で神秘的な雰囲気のする人ですよね」
妻猫がそう言った。ぼくは、うなずいた。
「そうです。その人だ」
「あの人はどことなく普通の人とは違っているように、わたしはずっと思っていたけど、まさか、そんなことをしている人だとは想像だにしていなかったわ」
妻猫が、そう言った。
「シャオパイの飼い主さんとシャオパイは今、郊外にあるうちへ戻ってきているから、久しぶりに、お母さんといっしょに、あそこへ行ってみようか。シャオパイや、シャオパイの飼い主さんと、もうずいぶん長い間、会っていないのだろう?」
ぼくは妻猫に、そう言った。妻猫が、うなずいた。
「いいですね。ぜひ行ってみたいわ」
妻猫が、声を弾ませていた。
それからまもなく、ぼくと妻猫は、シャオパイと、シャオパイの飼い主さんが住んでいる郊外のうちに向かった。うちに着くとすぐに前庭にある花壇のなかから、ぼくは一声鳴いた。するとシャオパイが、ぼくの声を聞いて、すぐに玄関から出てきた。
「笑い猫のあんちゃん、どうしたの?」
シャオパイが聞いた。
「妻猫が、お前や、お前の飼い主さんとしばらく会っていなかったから、連れてきた。久しぶりに会ってみたいと言っていたから」
ぼくはそう答えた。
「そうだったの。どうぞ、なかに入って」
シャオパイはそう言って、ぼくと妻猫を家のなかに入れてくれた。シャオパイは、ぼくと妻猫を台所に連れて行って、油で揚げた小魚をごちそうしてくれた。
「飼い主さんは今、どこにいるの?」
ぼくはシャオパイに聞いた。するとシャオパイは声をひそめながら
「書斎にいます」
と答えた。
「何をしているの?」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「ぼくにも、はっきりとは分かりません」
シャオパイが、そう答えた。
「そうか。飼い主さんは昨夜はずっと、うちにいたのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。するとシャオパイが首を横に振った。
それを見て、ぼくは、飼い主さんは昨日の夜も、子どもたちの夢を集めに行って、集めてきた夢を今、書斎で分析しているのではないかと思った。以前、そうしていたからだ。
ぼくと妻猫が油で揚げた小魚を食べ終わったとき、シャオパイが
「ぼくはこれから買い物に行かなければなりません」
と言った。
「何を買いに行くのだ?」
ぼくはシャオパイに聞き返した。
「桜餅を買いに行きます」
シャオパイが、そう答えた。
「そうか。桜餅は、おまえの飼い主さんの大好物で、ジャスミン茶を飲みながら、よく食べていたからな」
ぼくはそう答えた。シャオパイが、うなずいた。
「申し訳ないけど、すぐ戻ってくるから、しばらくここで待っていてくれない?」
シャオパイが、そう言った。
「分かった。車に気をつけて行ってこい」
ぼくはそう答えた。
それからしばらくしてから、シャオパイは、首に買い物袋をさげて、うちから出ていった。
「シャオパイは、ひとりで買い物に行けるの?」
妻猫が、けげんそうな顔をしていた。
「大丈夫だと思う。これまで何度も、ひとりで買い物に出かけていたから」
ぼくは、そう答えた。
「買いたいものの前に行けば、お店の人が気がついて、その商品を買い物袋に入れてくれるはずだ。シャオパイが、以前、そう話していたから」
ぼくは、そう言った。
「お金はどうやって払うの?」
妻猫がさらに聞いた。
「買い物袋のなかにクレジットカードを入れているので、そのカードで払っているそうだ」
ぼくはそう答えた。妻猫が、うなずいた。
シャオパイが買い物に出かけていったあと、ぼくは妻猫を連れて、外壁をつたって二階のベランダにのぼっていった。ベランダからは書斎のなかがよく見える。書斎のなかにシャオパイの飼い主さんがいて、大きな眼鏡をかけて机の前に座りながら、黒い袋を、じっと見ていた。やはり、ぼくが思っていたとおりだった。
「何をしているの?」
妻猫が、けげんそうな顔をしながら、ぼくに聞いた。
「夢を分析しているのだ」
ぼくは、そう答えた。
「何のことだか、わたしには、さっぱり分からないわ」
妻猫が首をかしげていた。
「あの黒い袋のなかには、飼い主さんが昨日の夜、子どもたちが住んでいる家に行って、子どもたちから集めてきたいやな夢が入っている。その夢の原因は何なのかを分析しているのだ」
ぼくは妻猫に、そう説明した。
「夢を集めるって、どうやって集めるの?」
妻猫には、まだ合点がいかないようだった。
「口で説明してもぴんと来ないだろうから、今夜まで待っていなさい。今夜も夢を集めに行くと思うから、集めているところを実際に見たら、すぐに分かるよ」
ぼくは妻猫に、そう言った。それを聞いて、妻猫が、うなずいた。
「分かったわ。どのようにして夢を集めているのかを見るのを楽しみにしているわ」
妻猫が、そう答えた。
それからしばらくしてから、シャオパイが買い物から戻ってきた。
「待たせたね」
シャオパイは、そう言って、二階のベランダにいるぼくと妻猫に声をかけた。
「大丈夫だよ。退屈しなかったよ」
ぼくは、そう答えた。
「よかった。桜餅を買ってきたから、ぼくはこれから、飼い主さんといっしょにジャスミン茶を飲みながら桜餅を食べるよ。一個、余計に買ってきたから、ふたりで半分ずつ食べて」
シャオパイが、そう言って、ぼくと妻猫に桜餅を一個くれた。
「ありがとう。お前は本当に思いやりのある優しい犬だね」
ぼくは、そう言って、シャオパイの心遣いに感謝した。妻猫も、うれしそうな顔をしていた。
「ぼくと妻猫は、これから庭木に登って、お前と、お前の飼い主さんが食べたり飲んだりしているところを見ながら、桜餅をいただくことにするよ」
ぼくは、そう答えた。
「分かったわ。落ちないように気をつけて登ってね」
シャオパイが、そう言って、ぼくと妻猫に気をつかってくれた。ぼくは、うなずいた。
それからまもなく、ぼくは桜餅をくわえながら庭木に登った。妻猫も、ぼくのあとから庭木に登ってきた。そのあとしばらくしてから、シャオパイの飼い主さんが一階に下りてきた。居間のテーブルの前に座ると、シャオパイの飼い主さんは、シャオパイといっしょに、ジャスミン茶を飲んだり、桜餅を食べたりしていた。
「あの人には、普通の人とは違った何か特別な雰囲気があふれているわ。まるで天から降りてきた仙女みたい」
妻猫が、そう言った。それを聞いて、ぼくは、びっくりした。妻猫の目に、シャオパイの飼い主さんが仙女のように映っていたとは、思ってもいなかったからだ。
「どうして、そのように思うのだ?」
ぼくは間髪を入れずに聞き返した。
「だって、あの人の容貌や一挙手一投足を見ていると、俗世間から遠く離れたところで暮らしている人のように思えるから」
妻猫が、そう言った。
それを聞いて、ぼくは妻猫に、老いらくさんが言ったことを話そうかと思った。老いらくさんは以前、ぼくに、シャオパイの飼い主さんは唐の時代からタイムスリップして、今の世の中に来ている人ではないかと、話したことがあったからだ。でも確証はないので、あえて話さないことにした。いずれにせよ、今晩暗くなるまで待って、飼い主さんがどのようなことをする人なのかを実際に目で見たら、妻猫は、この人が仙女かどうか、はっきり分かるだろうと、ぼくは思った。
シャオパイの飼い主さんはティータイムを終えると、再び二階の書斎にこもって、夢の分析を始めていた。シャオパイはその間、特に何もすることがないので、ぼくや妻猫といっしょに外に出て、いっしょに散歩をしたりしていた。
日が暮れたころ、シャオパイはうちへ帰り、ぼくと妻猫も、あとからついていった。ぼくと妻猫は、再び庭木に登って、なかの様子をじっと見ていた。シャオパイの飼い主さんは夜の十時ごろまで書斎にこもって仕事をしていた。そのあと書斎の電気が消えて、家のなかから飼い主さんが出てきた。右手には、からかさを持っていた。左手には、黒とピンクの袋を持っていた。
「ほら、見ろ。これから信じられないことが起きるぞ」
ぼくは、そう言って妻猫に喚起した。
飼い主さんは玄関の前に立つと、からかさを開いた。そして柄についているボタンのひとつを押した。するとそれからしばらくしてから、飼い主さんの体は、ふわふわと浮き上がった。それを見て、妻猫は驚きのあまり、言葉を失って、茫然として立ちすくんでいた。からかさを差した飼い主さんは、夜空に高く上がっていった。飼い主さんが着ている白いワンピースだけが点のように小さく見えていた。飼い主さんは、翠湖公園のほうへ向かっていた。ぼくと妻猫は、走りながら、あとを追っていた。
翠湖公園の近くには高層マンションがたくさん建っていて、人がたくさん住んでいる。飼い主さんは『高貴楼』というマンションの上までくると、しばらく、その上を、くるくると回っていた。
「何をしているの」
妻猫が聞いた。
「この建物のなかに子どもがいるので、どの部屋なのかを探しているのだと思う」
ぼくは、そう答えた。
そのあとしばらくしてから、飼い主さんは、『高貴楼』の五階にある家のベランダまで下りてきて、鍵のかかっていない窓をすーっと開けて、なかに入っていった。手には黒とピンクの袋を持っていた。
「何をするの?」
妻猫が聞いた。
「子どもの夢を集めると思う」
ぼくは、そう答えた。
「……」
妻猫は意味がよく分からないでいた。
「いやな夢を見てうなされている子どもがいたら、その夢は黒い袋に入れる。楽しい夢を見て安らかに寝ている子どもがいたら、その夢はピンクの袋に入れる」
ぼくは、そう説明した。妻猫は、うなずいた。
「今、入っていった家からは、どちらの袋に夢を入れて出てくるのかしら」
妻猫が、つぶやくように、そう聞いた。
「ピンクの袋に入れて出てきたらいいな」
ぼくは、そう答えた。
「わたしも、そう願っているわ」
妻猫が、そう言った。
しばらくしてから、シャオパイの飼い主さんは再び、窓から出てきた。ぼくと妻猫は、シャオパイの飼い主さんが背中に背負っている二つの袋をじっと見ていた。すると、黒い袋のほうが膨らんでいた。ぼくはそれを見て、ふっと、ためいきをついた。妻猫も期待が外れて、がっかりしたような顔をしていた。
シャオパイの飼い主さんは、それからまもなく、再び、自分のうちがある郊外のほうへ向かって飛んでいった。
(シャオパイの飼い主さんは、集めた夢を、うちに持ち帰って、夢を分析して、その子がいやな夢を見た原因を突き止めて、その子の心の健康の回復に努めるのだろう)
ぼくは、そう思った。シャオパイの飼い主さんの崇高な生き方に、ぼくは感動した。
「やはり、あの人は仙女に間違いないわ」
妻猫が、そう言った。
「ぼくも、そう思うよ」
ぼくはそう答えて、相づちを打った。
夜空にきらきらと輝いている星を見ながら、ぼくと妻猫は仙女に会えた喜びで心が満たされていた。
ぼくが翠湖公園に帰ってきてから、数日がたった。ぼくはまだ『雲の上の学校』のことが忘れられないでいる。『雲の上の学校』のことを妻猫に話したら、とても興味深そうな顔をしていた。
「雲の上に学校があるのですか?」
妻猫が、けげんそうな顔をしていた。
「高い山の上にある学校なので、下から見たら雲の上にある学校のように見えるから、そう呼ばれている」
ぼくは、そう答えた。
「その学校は普通の学校と、どう違っているのですか」
妻猫が聞いた。
「普通の学校では子どもたちは、教室のなかで先生から教わったり、教科書に書かれていることを覚えたりしているけど、『雲の上の学校』では違うのだ」
ぼくは、そう答えた。
「どう違うのですか」
妻猫が、さらに聞いた。
「『雲の上の学校』では、子どもたちに知識を一方的に教え込んだり、覚えさせたりするのではなくて、子どもたちに探索と発見の喜びを与えながら、自分たちの目と耳と足で実際に学ばせる教育方法を採っている。そのために学習効果がとてもあって、子どもたちがみんな生き生きとしている」
ぼくは、そう答えた。
「そうですか。それは素晴らしいですね」
妻猫が、そう答えた。
「ぼくは、これまで杜真子や馬小跳の学校に行って、授業見学をしたことがあるけど、どちらの学校でも、先生が一方的に教える教育方法を採っていた。そのために子どもたちのなかには受け入れることができなくて消極的になっている子どもがいた。けっして勉強が嫌いなのではなくて、自分が興味があることを自分で発見して学びたいと思っていた子どもだった。でもそのような考え方は自分勝手だとして認めてもらえなかったから、自信を失って、心理的な圧力を感じて、夜、いやな夢を見て、うなされていた」
ぼくは、そう言った。ぼくの話を聞いて、妻猫は、やるせない顔をした。
「その子どもは、どうなったの?」
妻猫が、心配そうな声で聞き返した。
「いやな夢を見た子どもは勉強することがだんだん嫌いになり、成績が落ちていった」
シャオパイから聞いたことを、ぼくは妻猫に伝えた。
「そうですか。その子どもは落第したのですか?」
妻猫が暗く沈んだ声で聞き返した。ぼくは首を横に振った。
「いや、落第はしていない。先生と親が、その子をしばらく休学させることにした」
ぼくは、そう答えた。
「休学した子はどうしたの?」
妻猫が聞き返した。
「先生や親の承諾が得られた子どもは『雲の上の学校』に行って、転地療養をしていた」
ぼくはそう答えた。
「転地療養って何ですか?」
妻猫がけげんそうな顔をして聞き返した。
「病気の治療や養生のために、気候のよいところに移ることだ」
ぼくがそう言うと、妻猫がうなずいていた。
「それで、その子たちの転地療養は、うまくいったのですか?」
妻猫が聞いた。
「うん、うまくいった。みんな元気になったから、みんな『雲の上の学校』から下界におりてきて、それまで通っていた学校に復学することになった」
ぼくは、そう答えた。
「『雲の上の学校』では先生が子どもたちを鼓舞して、子どもたちが興味があることを自分から主体的に探索させたり、発見させたりしていると、さっき、お父さんは言ったよね」
妻猫がそう言った。
「うん、そう言ったよ」
ぼくは、うなずいた。
「その教育方法で、子どもたちは、どのように変わっていったのですか?」
妻猫が聞いた。
「子どもたちは未知のことに対する興味や関心を積極的に抱くようになり、知りたいと思って危険や冒険をものともせずに自然のなかに飛び込んでいった。そして発見できた喜びを知り、勉強することに対して、もともと持っていた意欲を回復して、楽しさと自信を取り戻すようになった」
ぼくは、そう答えた。
「『雲の上の学校』では何人の子どもたちが学んでいたのですか?」
妻猫が聞いた。
「六人の子どもたちが学んでいた」
ぼくはそう答えた。
「教室はいくつありましたか?」
ぼくは首を横に振った。
「建物のなかに教室は一つもなかった」
ぼくがそう答えると、妻猫は、合点がいかないような顔をしていた。
「では、どこで授業をしていたのですか」
妻猫が聞き返した。
「自然のなかで授業をしていた。自然のなか全体が教室になっていた」
ぼくはそう答えた。妻猫はまだ、ぴんとこないような顔をしていた。
「天気がよくないときも、戸外で授業をしていたのですか」
妻猫が、そう聞いた。
「そうだよ。雨や雪のときも戸外で授業をしていた」
ぼくは、そう答えた。
「宿題も出されたのですか?」
妻猫が聞いた。ぼくは、うなずいた。
「もちろん出されたよ。みんなでまずテーマの中心的な問題について話し合って、そのあと宿舎に帰って一人で宿題をしていた。そのあとみんなでもう一度話し合って、分からない点や疑問に感じたことを出し合って、テーマに対する理解を深めてから、加筆修正をして、質の高いものを提出していた」
ぼくはそう答えた。
「どんな宿題が出されたのですか?」
妻猫が興味深そうな顔をして聞き返した。
「子どもたちが興味がありそうなものばかり出されていた。提出された宿題は先生が本にして、子どもたちに見せていた。『どれも珠玉の作品ばかりだ』と言って、子どもたちが書いた物語や、描いた絵を、先生が、ほめていた。それを聞いて、子どもたちは、みんな、とても喜んでいた」
ぼくは、そう答えた。
「いい先生ですね。子どもたちを励ますのが、とても上手な先生ですね。どんな先生なのか、わたしも一度、会ってみたいわ」
妻猫がそう言った。
「その先生なら、お母さんは、もうすでに会ったことがあるはずだよ」
ぼくは、そう答えた。それを聞いて、妻猫が、けげんそうな顔をしていた。
「えっ、だってわたしは、杜真子と馬小跳の学校の先生よりほかの先生は誰も知らないわ」
妻猫が、そう答えた。ぼくは、それを聞いて、思わず、くつくつと笑った。
「その先生というのは、シャオパイの飼い主さんだよ」
ぼくがそう言うと、妻猫がびっくりしたような顔をしていた。
「えっ、あの人が、その学校の先生だったのですか」
妻猫が聞き返した。ぼくはうなずいた。
「シャオパイの飼い主さんは、シャオパイを連れて、その学校に行って、子どもたちの教育に当たっていた。子どもたちは、その人のことを、ミー先生と呼んでいた。ほかに先生はいなかったから、シャオパイの飼い主さんは一人ですべての授業を受け持っていた」
ぼくはそう言った。
「シャオパイの飼い主さんのことを、わたしはよく覚えているわ。温和で上品で神秘的な雰囲気のする人ですよね」
妻猫がそう言った。ぼくは、うなずいた。
「そうです。その人だ」
「あの人はどことなく普通の人とは違っているように、わたしはずっと思っていたけど、まさか、そんなことをしている人だとは想像だにしていなかったわ」
妻猫が、そう言った。
「シャオパイの飼い主さんとシャオパイは今、郊外にあるうちへ戻ってきているから、久しぶりに、お母さんといっしょに、あそこへ行ってみようか。シャオパイや、シャオパイの飼い主さんと、もうずいぶん長い間、会っていないのだろう?」
ぼくは妻猫に、そう言った。妻猫が、うなずいた。
「いいですね。ぜひ行ってみたいわ」
妻猫が、声を弾ませていた。
それからまもなく、ぼくと妻猫は、シャオパイと、シャオパイの飼い主さんが住んでいる郊外のうちに向かった。うちに着くとすぐに前庭にある花壇のなかから、ぼくは一声鳴いた。するとシャオパイが、ぼくの声を聞いて、すぐに玄関から出てきた。
「笑い猫のあんちゃん、どうしたの?」
シャオパイが聞いた。
「妻猫が、お前や、お前の飼い主さんとしばらく会っていなかったから、連れてきた。久しぶりに会ってみたいと言っていたから」
ぼくはそう答えた。
「そうだったの。どうぞ、なかに入って」
シャオパイはそう言って、ぼくと妻猫を家のなかに入れてくれた。シャオパイは、ぼくと妻猫を台所に連れて行って、油で揚げた小魚をごちそうしてくれた。
「飼い主さんは今、どこにいるの?」
ぼくはシャオパイに聞いた。するとシャオパイは声をひそめながら
「書斎にいます」
と答えた。
「何をしているの?」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「ぼくにも、はっきりとは分かりません」
シャオパイが、そう答えた。
「そうか。飼い主さんは昨夜はずっと、うちにいたのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。するとシャオパイが首を横に振った。
それを見て、ぼくは、飼い主さんは昨日の夜も、子どもたちの夢を集めに行って、集めてきた夢を今、書斎で分析しているのではないかと思った。以前、そうしていたからだ。
ぼくと妻猫が油で揚げた小魚を食べ終わったとき、シャオパイが
「ぼくはこれから買い物に行かなければなりません」
と言った。
「何を買いに行くのだ?」
ぼくはシャオパイに聞き返した。
「桜餅を買いに行きます」
シャオパイが、そう答えた。
「そうか。桜餅は、おまえの飼い主さんの大好物で、ジャスミン茶を飲みながら、よく食べていたからな」
ぼくはそう答えた。シャオパイが、うなずいた。
「申し訳ないけど、すぐ戻ってくるから、しばらくここで待っていてくれない?」
シャオパイが、そう言った。
「分かった。車に気をつけて行ってこい」
ぼくはそう答えた。
それからしばらくしてから、シャオパイは、首に買い物袋をさげて、うちから出ていった。
「シャオパイは、ひとりで買い物に行けるの?」
妻猫が、けげんそうな顔をしていた。
「大丈夫だと思う。これまで何度も、ひとりで買い物に出かけていたから」
ぼくは、そう答えた。
「買いたいものの前に行けば、お店の人が気がついて、その商品を買い物袋に入れてくれるはずだ。シャオパイが、以前、そう話していたから」
ぼくは、そう言った。
「お金はどうやって払うの?」
妻猫がさらに聞いた。
「買い物袋のなかにクレジットカードを入れているので、そのカードで払っているそうだ」
ぼくはそう答えた。妻猫が、うなずいた。
シャオパイが買い物に出かけていったあと、ぼくは妻猫を連れて、外壁をつたって二階のベランダにのぼっていった。ベランダからは書斎のなかがよく見える。書斎のなかにシャオパイの飼い主さんがいて、大きな眼鏡をかけて机の前に座りながら、黒い袋を、じっと見ていた。やはり、ぼくが思っていたとおりだった。
「何をしているの?」
妻猫が、けげんそうな顔をしながら、ぼくに聞いた。
「夢を分析しているのだ」
ぼくは、そう答えた。
「何のことだか、わたしには、さっぱり分からないわ」
妻猫が首をかしげていた。
「あの黒い袋のなかには、飼い主さんが昨日の夜、子どもたちが住んでいる家に行って、子どもたちから集めてきたいやな夢が入っている。その夢の原因は何なのかを分析しているのだ」
ぼくは妻猫に、そう説明した。
「夢を集めるって、どうやって集めるの?」
妻猫には、まだ合点がいかないようだった。
「口で説明してもぴんと来ないだろうから、今夜まで待っていなさい。今夜も夢を集めに行くと思うから、集めているところを実際に見たら、すぐに分かるよ」
ぼくは妻猫に、そう言った。それを聞いて、妻猫が、うなずいた。
「分かったわ。どのようにして夢を集めているのかを見るのを楽しみにしているわ」
妻猫が、そう答えた。
それからしばらくしてから、シャオパイが買い物から戻ってきた。
「待たせたね」
シャオパイは、そう言って、二階のベランダにいるぼくと妻猫に声をかけた。
「大丈夫だよ。退屈しなかったよ」
ぼくは、そう答えた。
「よかった。桜餅を買ってきたから、ぼくはこれから、飼い主さんといっしょにジャスミン茶を飲みながら桜餅を食べるよ。一個、余計に買ってきたから、ふたりで半分ずつ食べて」
シャオパイが、そう言って、ぼくと妻猫に桜餅を一個くれた。
「ありがとう。お前は本当に思いやりのある優しい犬だね」
ぼくは、そう言って、シャオパイの心遣いに感謝した。妻猫も、うれしそうな顔をしていた。
「ぼくと妻猫は、これから庭木に登って、お前と、お前の飼い主さんが食べたり飲んだりしているところを見ながら、桜餅をいただくことにするよ」
ぼくは、そう答えた。
「分かったわ。落ちないように気をつけて登ってね」
シャオパイが、そう言って、ぼくと妻猫に気をつかってくれた。ぼくは、うなずいた。
それからまもなく、ぼくは桜餅をくわえながら庭木に登った。妻猫も、ぼくのあとから庭木に登ってきた。そのあとしばらくしてから、シャオパイの飼い主さんが一階に下りてきた。居間のテーブルの前に座ると、シャオパイの飼い主さんは、シャオパイといっしょに、ジャスミン茶を飲んだり、桜餅を食べたりしていた。
「あの人には、普通の人とは違った何か特別な雰囲気があふれているわ。まるで天から降りてきた仙女みたい」
妻猫が、そう言った。それを聞いて、ぼくは、びっくりした。妻猫の目に、シャオパイの飼い主さんが仙女のように映っていたとは、思ってもいなかったからだ。
「どうして、そのように思うのだ?」
ぼくは間髪を入れずに聞き返した。
「だって、あの人の容貌や一挙手一投足を見ていると、俗世間から遠く離れたところで暮らしている人のように思えるから」
妻猫が、そう言った。
それを聞いて、ぼくは妻猫に、老いらくさんが言ったことを話そうかと思った。老いらくさんは以前、ぼくに、シャオパイの飼い主さんは唐の時代からタイムスリップして、今の世の中に来ている人ではないかと、話したことがあったからだ。でも確証はないので、あえて話さないことにした。いずれにせよ、今晩暗くなるまで待って、飼い主さんがどのようなことをする人なのかを実際に目で見たら、妻猫は、この人が仙女かどうか、はっきり分かるだろうと、ぼくは思った。
シャオパイの飼い主さんはティータイムを終えると、再び二階の書斎にこもって、夢の分析を始めていた。シャオパイはその間、特に何もすることがないので、ぼくや妻猫といっしょに外に出て、いっしょに散歩をしたりしていた。
日が暮れたころ、シャオパイはうちへ帰り、ぼくと妻猫も、あとからついていった。ぼくと妻猫は、再び庭木に登って、なかの様子をじっと見ていた。シャオパイの飼い主さんは夜の十時ごろまで書斎にこもって仕事をしていた。そのあと書斎の電気が消えて、家のなかから飼い主さんが出てきた。右手には、からかさを持っていた。左手には、黒とピンクの袋を持っていた。
「ほら、見ろ。これから信じられないことが起きるぞ」
ぼくは、そう言って妻猫に喚起した。
飼い主さんは玄関の前に立つと、からかさを開いた。そして柄についているボタンのひとつを押した。するとそれからしばらくしてから、飼い主さんの体は、ふわふわと浮き上がった。それを見て、妻猫は驚きのあまり、言葉を失って、茫然として立ちすくんでいた。からかさを差した飼い主さんは、夜空に高く上がっていった。飼い主さんが着ている白いワンピースだけが点のように小さく見えていた。飼い主さんは、翠湖公園のほうへ向かっていた。ぼくと妻猫は、走りながら、あとを追っていた。
翠湖公園の近くには高層マンションがたくさん建っていて、人がたくさん住んでいる。飼い主さんは『高貴楼』というマンションの上までくると、しばらく、その上を、くるくると回っていた。
「何をしているの」
妻猫が聞いた。
「この建物のなかに子どもがいるので、どの部屋なのかを探しているのだと思う」
ぼくは、そう答えた。
そのあとしばらくしてから、飼い主さんは、『高貴楼』の五階にある家のベランダまで下りてきて、鍵のかかっていない窓をすーっと開けて、なかに入っていった。手には黒とピンクの袋を持っていた。
「何をするの?」
妻猫が聞いた。
「子どもの夢を集めると思う」
ぼくは、そう答えた。
「……」
妻猫は意味がよく分からないでいた。
「いやな夢を見てうなされている子どもがいたら、その夢は黒い袋に入れる。楽しい夢を見て安らかに寝ている子どもがいたら、その夢はピンクの袋に入れる」
ぼくは、そう説明した。妻猫は、うなずいた。
「今、入っていった家からは、どちらの袋に夢を入れて出てくるのかしら」
妻猫が、つぶやくように、そう聞いた。
「ピンクの袋に入れて出てきたらいいな」
ぼくは、そう答えた。
「わたしも、そう願っているわ」
妻猫が、そう言った。
しばらくしてから、シャオパイの飼い主さんは再び、窓から出てきた。ぼくと妻猫は、シャオパイの飼い主さんが背中に背負っている二つの袋をじっと見ていた。すると、黒い袋のほうが膨らんでいた。ぼくはそれを見て、ふっと、ためいきをついた。妻猫も期待が外れて、がっかりしたような顔をしていた。
シャオパイの飼い主さんは、それからまもなく、再び、自分のうちがある郊外のほうへ向かって飛んでいった。
(シャオパイの飼い主さんは、集めた夢を、うちに持ち帰って、夢を分析して、その子がいやな夢を見た原因を突き止めて、その子の心の健康の回復に努めるのだろう)
ぼくは、そう思った。シャオパイの飼い主さんの崇高な生き方に、ぼくは感動した。
「やはり、あの人は仙女に間違いないわ」
妻猫が、そう言った。
「ぼくも、そう思うよ」
ぼくはそう答えて、相づちを打った。
夜空にきらきらと輝いている星を見ながら、ぼくと妻猫は仙女に会えた喜びで心が満たされていた。