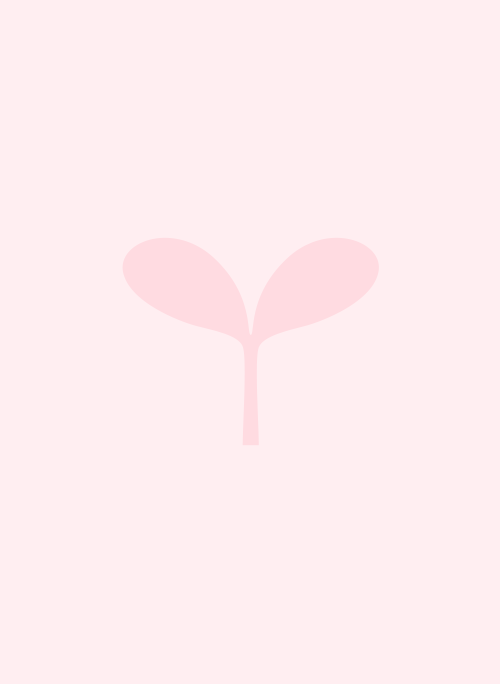天気……高山は、空気が澄んでいるので、視界が広い。昼は真っ青な空が広がっているが、日が暮れると外は真っ暗になり、星の光が、こうこうと輝くようになる。
『雲の上の学校』に戻ってきてから数日がたった。子どもたちは、以前と同じように、早朝トレーニングのときは、小鳥といっしょに空を飛んだり、池に飛び込んでカエルの泳ぎ方を真似して泳いだり、池のほとりでカエル跳びをしていた。そのあと朝ご飯を食べてからキノコ形の宿舎に戻って、ミー先生が与えた宿題に取り組んだり、外に出て野外授業に参加したりしていた。夕方になると、子どもたちは、散歩したり、宿題のことについて友だちと話し合ったりしていた。宿題をしているときも、散歩をしているときも、友だちと話をしているときも、子どもたちはみんな生き生きとして、とても楽しそうな表情をしていた。
「わしは、これまでこんなに楽しそうな表情をしながら宿題をしている子どもたちを見たことがなかったよ」
老いらくさんが、そう言った。
「ぼくも同じです。この学校に来る前、この子たちは、勉強したり宿題をすることに楽しさを感じていなかったと、シャオパイが言っていました。うちで、ぼーっとしていると、親から怒られたし、学校では先生から知識を覚えることばかり強要されていて、楽しみながら勉強や宿題をする機会がほとんどなくて、いつもうつうつとした生活をしていたそうです。そのために夜寝ているときには、いやな夢ばかり見て、うなされていたようです。ところが、今は全然、そういったイメージとは異なっています。環境によって、こうも変わるのでしょうか」
ぼくは老いらくさんに、そう言った。
「わしにも、はっきりした理由はよく分からない。ただ一つだけ言えることは、この子たちは、もともとは勉強や宿題をすることがとても好きな子どもだったと言えるのではないだろうか。そうでなかったら、ここに来ても、勉強や宿題に楽しさを見いだせなかっただろうと、わしは思っている」
老いらくさんが、そう言った。ぼくは、うなずいた。
「ミー先生が子どもたちに話をしていたときに、よく言っていた言葉は何だか知っていますか」
ぼくは老いらくさんに聞いた。老いらくさんが首を横に振った。
「わしは人の言葉を聞いても分からないから、わしが知っているわけがないではないか」
老いらくさんが、そう答えた。
「『発見』という言葉です。興味があることを自分で発見して、どうして、そうなるのかを発見してください。それが勉強ですと、よく話していました」
ぼくがそう言うと、老いらくさんが、うなずいていた。
「そうか。そんなことを話していたのか。さすがにミー先生だけのことはあるな。普通の教師や、親は、そんなことは絶対に言わないだろう」
老いらくさんがそう言った。
「『発見』という言葉の意味を、老いらくさんは、どのように考えていますか」
ぼくは老いらくさんに聞いた。
「これまで知らなかったことを知ることが『発見』だと、わしは思っている。知らなかったことを知ったら、知識が増えるだけでなくて、心も豊かになる。『発見』は楽しさのもとだと、わしは考えている」
老いらくさんが、そう答えた。
「そうですね。ぼくも、そのように思っています」
老いらくさんの考えに、ぼくは賛同した。
「ミー先生は子どもたちを体験と探索の旅に連れて行って、自分たちで発見する喜びを教えていた。そのために子どもたちの好奇心や知的欲求心が大いに満たされていた」
老いらくさんが、そう言った。
「そうですね。その通りです。ミー先生が実践した教育のやり方は理にかなっているのに、どうして、あまり普及していないのでしょうか」
ぼくは老いらくさんに疑問を投げかけた。
「今までずっとおこなってきた伝統的な教育のやり方を、一朝一夕に変えることは、そう簡単にはいかないのではないかと、わしは思っている」
老いらくさんが、そう答えた。
「そうかもしれませんね」
ぼくは老いらくさんの話に相づちを打った。
子どもたちが、キノコ形の宿舎にこもって、宿題をしているときには、ぼくと老いらくさんは、暇をもてあましていた。何もすることがないから、学校のなかを、ぶらぶらしているよりほかなかった。時々、シャオパイがやってきて、首からさげたビニール袋をおろして、なかに入っている食べ物をぼくにくれた。シャオパイの心遣いが、とてもうれしかった。でもぼくはシャオパイと、ぺちゃくちゃ話す時間はあまりなかった。ぼくに食べ物をくれると、シャオパイは、いつも、そそくさとした足取りで、ミー先生のもとへ帰っていったからだ。シャオパイが帰っていったあと、ぼくは食べ物を老いらくさんにおすそわけした。老いらくさんは、「ありがとう」と言って、ぼくに感謝しながら、ぽりぽりと、かじっていた。
今日の午後、シャオパイがやってきたときに、ニュースを持ってきてくれた。
「笑い猫のあんちゃん、今夜、この学校を離れて、下界に戻ることになりました。日が暮れたら、この山の頂上にある八角亭に来てください。いっしょに下界に戻りましょう」
シャオパイが、そう言った。寝耳に水のような話だったが、シャオパイはけっして冗談を言うような犬ではないので、ぼくはシャオパイの話を信じることにした。老いらくさんにも、シャオパイが言ったことを伝えた。
「そうか、いよいよ今日で、この学校ともお別れか。楽しいこともたくさんあったし、怖いことも、いろいろあったなあ」
老いらくさんが、そう言って、感慨ぶかそうな顔をしていた。
「子どもたちは今、どんな気持ちでいるのでしょうか」
ぼくは老いらくさんに聞いた。
「親やきょうだいや、先生や友人に久しぶりに会える喜びを感じている子どももいるかもしれない。しかしそれとは逆に下界での生活にまた不安を感じている子どもがいるかもしれない」
老いらくさんが、そう言った。
「ぼくもそう思います。でもいつまでも、この学校で暮らしていくわけにはいかないですからね」
ぼくは、そう答えた。
「ここは隔離された別世界だから、子どもたちはいずれは現実の世界に戻っていかなければならない。ここで学んだことを糧にして、現実の世界でも楽しく生活してほしい。わしはそう願っている」
老いらくさんが、そう言った。ぼくは、うなずいた。
ぼくと老いらくさんは、この日は、日が暮れる前にもう、山頂にある八角亭に行って、ミー先生と子どもたちとシャオパイがやってくるのを待っていた。八角亭には、ベンチも水飲み場もあるので、ぼくと老いらくさんは、ベンチに座って、水を飲みながら、ここでの思い出に花を咲かせていた。
しばらくしてからミー先生がやってきた。大きなキャリーバッグを、がらがらと音を立てて引きずりながら、歩いてきた。あのキャリーバッグのなかには、不思議なからかさが入っているはずだと、ぼくは思った。ミー先生が来てから、まもなく、子どもたちとシャオパイがやってきた。子どもたちはミー先生の周りに集まった。ミー先生は、手に本を二冊、持っていた。
「みなさん、この本を見てください。本のタイトルは『水の物語』です。童話の本です」
ミー先生が、まず一冊の本を手に取って、そう言った。
「作者は誰ですか」
唐さんが聞いていた。
「作者はみなさんです。みなさんが提出してくれた作文をまとめて一冊の本にしました」
ミー先生が晴れやかな顔をしながら、そう言った。
「わあ、本当ですか。うれしい」
王さんが、嬉々とした声で、そう言った。
「わたしは、この本が大好きです。メルヘンのような美しいストーリーで、雨や雪が、どのようにしてできたのかや、雨や雪は、どこへどうやって流れていくのかについて、とても楽しく書かれています。絵もきれいに描かれていて、ストーリーの美しさをいちだんと引き立てています」
ミー先生が、そう言った。子どもたちはそれを聞いて、先を争うようにして、その本を手にとって、自分たちが書いた物語や絵を見ながら、とてもうれしそうな顔をしていた。
「わたしたちが書いた水の話が本になるなんて思ってもいなかったわ」
蒋さんが、そう言った。
「そうだね。一生の思い出になる」
李くんが、そう答えていた。
「この学校に来て、ミー先生に出会えてよかった」
柳くんが、そう答えていた。
「ミー先生は女神のような人です」
陳くんが、そう言った。
本の表紙絵を描いた唐さんは、格別、うれしそうな顔をしていた。
「わたしは将来、デザイナーになって、こんな仕事をしてみたいと、ずっと思っていたけど、まさかこんなに早く夢が実現できるなんて思ってもいなかったわ」
唐さんが、そう言った。
「唐さんの表紙絵は、本当に素晴らしいです。雪の結晶のなかから生まれた水の妖精が、しなやかに空を飛びながら、虹のかなたに向かって旅をしていく絵です。とても夢があって楽しいです」
ミー先生が、そう言って、唐さんが描いた絵を、ほめていた。本の装丁もよくできていて、本の内容と、よく合っていた。
「みなさんは本当に素晴らしいです。知識が広くて感性も豊かだし、文才や画才に優れた人がたくさんいます。こんな素晴らしいみなさんたちに巡りあえて、わたしは、とてもうれしいです。みなさんに心から『ありがとう』と、お礼を言います」
ミー先生が、そう言っていた。
ミー先生は、そのあと、手に持っていた、もう一冊の本を、子どもたちに見せていた。
「この本のタイトルは『蝶谷』です。この本も、みなさんたちが書いた作文や物語や絵をもとにして作りました。この本も、とても素晴らしい本です。たくさんの種類の蝶たちが花の上を楽しそうに飛び交っている様子が目に見えるように生き生きと描かれています。ここに来なかった子どもたちにも深い感動を与える本だと思います」
ミー先生が、そう言っていた。
「わたしにも見せてください」
子どもたちは、そう言って、この本もまた、先を争うようにして手に取って見ていた。子どもたちはみんな、とても楽しそうな顔をしながら、文を読んだり、絵を見たりしていた。この本の表紙絵は蒋さんが描いてくれたものだった。たくさんの種類の蝶たちの羽の色や模様を細かに観察しながら、蒋さんが丁寧に描いてくれた表紙絵は芸術性にあふれていて、大人顔負けの素晴らしい絵だった。装丁も蝶の物語にふさわしく、とても華やかで美しく仕上げられていた。
「みなさんは協力して、このような素晴らしい本を二冊も作り上げることができました。みなさんは、これから下界の学校に戻りますが、普通の子どもにはできないことができたことで、自信を持って生活してください。そうすることによって、下界でも、生き生きとした楽しい生活を送ることができるようになりますから」
ミー先生が、子どもたちに、そう言っていた。それを聞いて、子どもたちはみんな、にっこりと、うなずいていた。
「ここに来る前は、わたしは、毎日、うつうつとした生活を送っていたけど、普通の学校に戻ってからも、明るい生活が送れそうです」
王さんが、そう言っていた。
「ぼくも同じです。クラスのなかで、ぼくは浮いていて、友だちもいなかったけど、みんなで協力したら、楽しいことが分かりました」
李くんが、そう答えていた。
「そうですか。よかったですね。わたしも、みなさんと出会えて、発見した喜びがたくさんありました。一番の喜びは何だと思いますか」
ミー先生が、子どもたちに聞いていた。
「……」
子どもたちは、しばらく考えていたけど、分からないでいた。
「わたしが発見した一番の喜びは、だめな子どもは、ひとりもいないということです。みなさんは、下界では、みんなから、つまはじきにされて、自分でも、だめな子どもだと思って、自信を失っていました。そのために、いやな夢をよく見て、うなされていました。でも実際には違っていました。だめな子どもどころか、性格も才能も普通の子ども以上に優れた子どもでした。タンチョウの背中に乗って空を飛んでいく勇気もあったし、文才にも画才にもたけていました。わたしは、このことを発見して、とてもうれしく思っています」
ミー先生が感動に震えるような顔をしながら、そう言っていた。ミー先生は、そのあと
子どもたち、一人ひとりと熱いハグをしていた。
それからまもなく、いよいよ『雲の上の学校』を離れるときがやってきた。ミー先生はキャリーバッグを開いて、子どもたちが書いた二冊の本を、なかに入れた。そのあと、本と入れ替わるように、からかさを取り出して、かさを開いた。
「みなさん、これから、このかさを一人ひとりに持たせますから、かさの柄についている三つのボタンのうちの真ん中のボタンを押してください。するとみなさんの体が軽くなります」
ミー先生が、そう言った。それからまもなく、からかさが子どもたちに回された。子どもたちはミー先生に言われたとおりに、真ん中のボタンを押していた。子どもたちが押し終わったあと、ぼくと老いらくさんとシャオパイも、真ん中のボタンを押した。みんなが押し終わったからかさは再び、ミー先生のもとに戻された。
「さあ、いよいよ、これから出発します。体がふわふわと宙に浮いていきますが、怖くはないから大丈夫です。落ちることはありません」
ミー先生がそう言った。ボタンを押した効果は五分後にあらわれて、ミー先生と子どもたちの体は、宙にふわふわと上がっていった。ぼくと老いらくさんとシャオパイの体も宙に浮いていった。
「ここへ来るときも、子どもたちは、このようにして来たのだろうなあ」
老いらくさんが、そう言った。
「たぶん、そうだと思います」
ぼくは、そう答えた。
日はすでにとっぷりと暮れていて、空には星がきらきらと輝いていた。星が間近に見えたので、宇宙のロマンを、よりいっそう強く感じながら、ぼくたちは下界へ戻っていくための旅を始めた。体に翼をつけなくても、遠くまで空を飛んでいけることに、子どもたちは無限の喜びを見いだしているように思えた。ぼくと老いらくさんも、浮き浮きしながら、まるで宇宙飛行士のような気分になって空の旅を楽しんでいた。少しも怖くはなかった。
やがて、町のあかりが見えてきた。旅を始めてから三十分ほどで、ぼくたちは住み慣れた町に戻ってきた。降り立ったのは、ぼくと老いらくさんが住んでいる翠湖公園のなかだった。夜が明けるまで、ミー先生と子どもたちは翠湖公園のなかを散歩したり、ベンチに座っておしゃべりをしたりして過ごしていた。そして夜が明けると、それぞれのうちへ帰っていった。シャオパイもミー先生といっしょに郊外にあるうちへ帰っていった。
『雲の上の学校』に戻ってきてから数日がたった。子どもたちは、以前と同じように、早朝トレーニングのときは、小鳥といっしょに空を飛んだり、池に飛び込んでカエルの泳ぎ方を真似して泳いだり、池のほとりでカエル跳びをしていた。そのあと朝ご飯を食べてからキノコ形の宿舎に戻って、ミー先生が与えた宿題に取り組んだり、外に出て野外授業に参加したりしていた。夕方になると、子どもたちは、散歩したり、宿題のことについて友だちと話し合ったりしていた。宿題をしているときも、散歩をしているときも、友だちと話をしているときも、子どもたちはみんな生き生きとして、とても楽しそうな表情をしていた。
「わしは、これまでこんなに楽しそうな表情をしながら宿題をしている子どもたちを見たことがなかったよ」
老いらくさんが、そう言った。
「ぼくも同じです。この学校に来る前、この子たちは、勉強したり宿題をすることに楽しさを感じていなかったと、シャオパイが言っていました。うちで、ぼーっとしていると、親から怒られたし、学校では先生から知識を覚えることばかり強要されていて、楽しみながら勉強や宿題をする機会がほとんどなくて、いつもうつうつとした生活をしていたそうです。そのために夜寝ているときには、いやな夢ばかり見て、うなされていたようです。ところが、今は全然、そういったイメージとは異なっています。環境によって、こうも変わるのでしょうか」
ぼくは老いらくさんに、そう言った。
「わしにも、はっきりした理由はよく分からない。ただ一つだけ言えることは、この子たちは、もともとは勉強や宿題をすることがとても好きな子どもだったと言えるのではないだろうか。そうでなかったら、ここに来ても、勉強や宿題に楽しさを見いだせなかっただろうと、わしは思っている」
老いらくさんが、そう言った。ぼくは、うなずいた。
「ミー先生が子どもたちに話をしていたときに、よく言っていた言葉は何だか知っていますか」
ぼくは老いらくさんに聞いた。老いらくさんが首を横に振った。
「わしは人の言葉を聞いても分からないから、わしが知っているわけがないではないか」
老いらくさんが、そう答えた。
「『発見』という言葉です。興味があることを自分で発見して、どうして、そうなるのかを発見してください。それが勉強ですと、よく話していました」
ぼくがそう言うと、老いらくさんが、うなずいていた。
「そうか。そんなことを話していたのか。さすがにミー先生だけのことはあるな。普通の教師や、親は、そんなことは絶対に言わないだろう」
老いらくさんがそう言った。
「『発見』という言葉の意味を、老いらくさんは、どのように考えていますか」
ぼくは老いらくさんに聞いた。
「これまで知らなかったことを知ることが『発見』だと、わしは思っている。知らなかったことを知ったら、知識が増えるだけでなくて、心も豊かになる。『発見』は楽しさのもとだと、わしは考えている」
老いらくさんが、そう答えた。
「そうですね。ぼくも、そのように思っています」
老いらくさんの考えに、ぼくは賛同した。
「ミー先生は子どもたちを体験と探索の旅に連れて行って、自分たちで発見する喜びを教えていた。そのために子どもたちの好奇心や知的欲求心が大いに満たされていた」
老いらくさんが、そう言った。
「そうですね。その通りです。ミー先生が実践した教育のやり方は理にかなっているのに、どうして、あまり普及していないのでしょうか」
ぼくは老いらくさんに疑問を投げかけた。
「今までずっとおこなってきた伝統的な教育のやり方を、一朝一夕に変えることは、そう簡単にはいかないのではないかと、わしは思っている」
老いらくさんが、そう答えた。
「そうかもしれませんね」
ぼくは老いらくさんの話に相づちを打った。
子どもたちが、キノコ形の宿舎にこもって、宿題をしているときには、ぼくと老いらくさんは、暇をもてあましていた。何もすることがないから、学校のなかを、ぶらぶらしているよりほかなかった。時々、シャオパイがやってきて、首からさげたビニール袋をおろして、なかに入っている食べ物をぼくにくれた。シャオパイの心遣いが、とてもうれしかった。でもぼくはシャオパイと、ぺちゃくちゃ話す時間はあまりなかった。ぼくに食べ物をくれると、シャオパイは、いつも、そそくさとした足取りで、ミー先生のもとへ帰っていったからだ。シャオパイが帰っていったあと、ぼくは食べ物を老いらくさんにおすそわけした。老いらくさんは、「ありがとう」と言って、ぼくに感謝しながら、ぽりぽりと、かじっていた。
今日の午後、シャオパイがやってきたときに、ニュースを持ってきてくれた。
「笑い猫のあんちゃん、今夜、この学校を離れて、下界に戻ることになりました。日が暮れたら、この山の頂上にある八角亭に来てください。いっしょに下界に戻りましょう」
シャオパイが、そう言った。寝耳に水のような話だったが、シャオパイはけっして冗談を言うような犬ではないので、ぼくはシャオパイの話を信じることにした。老いらくさんにも、シャオパイが言ったことを伝えた。
「そうか、いよいよ今日で、この学校ともお別れか。楽しいこともたくさんあったし、怖いことも、いろいろあったなあ」
老いらくさんが、そう言って、感慨ぶかそうな顔をしていた。
「子どもたちは今、どんな気持ちでいるのでしょうか」
ぼくは老いらくさんに聞いた。
「親やきょうだいや、先生や友人に久しぶりに会える喜びを感じている子どももいるかもしれない。しかしそれとは逆に下界での生活にまた不安を感じている子どもがいるかもしれない」
老いらくさんが、そう言った。
「ぼくもそう思います。でもいつまでも、この学校で暮らしていくわけにはいかないですからね」
ぼくは、そう答えた。
「ここは隔離された別世界だから、子どもたちはいずれは現実の世界に戻っていかなければならない。ここで学んだことを糧にして、現実の世界でも楽しく生活してほしい。わしはそう願っている」
老いらくさんが、そう言った。ぼくは、うなずいた。
ぼくと老いらくさんは、この日は、日が暮れる前にもう、山頂にある八角亭に行って、ミー先生と子どもたちとシャオパイがやってくるのを待っていた。八角亭には、ベンチも水飲み場もあるので、ぼくと老いらくさんは、ベンチに座って、水を飲みながら、ここでの思い出に花を咲かせていた。
しばらくしてからミー先生がやってきた。大きなキャリーバッグを、がらがらと音を立てて引きずりながら、歩いてきた。あのキャリーバッグのなかには、不思議なからかさが入っているはずだと、ぼくは思った。ミー先生が来てから、まもなく、子どもたちとシャオパイがやってきた。子どもたちはミー先生の周りに集まった。ミー先生は、手に本を二冊、持っていた。
「みなさん、この本を見てください。本のタイトルは『水の物語』です。童話の本です」
ミー先生が、まず一冊の本を手に取って、そう言った。
「作者は誰ですか」
唐さんが聞いていた。
「作者はみなさんです。みなさんが提出してくれた作文をまとめて一冊の本にしました」
ミー先生が晴れやかな顔をしながら、そう言った。
「わあ、本当ですか。うれしい」
王さんが、嬉々とした声で、そう言った。
「わたしは、この本が大好きです。メルヘンのような美しいストーリーで、雨や雪が、どのようにしてできたのかや、雨や雪は、どこへどうやって流れていくのかについて、とても楽しく書かれています。絵もきれいに描かれていて、ストーリーの美しさをいちだんと引き立てています」
ミー先生が、そう言った。子どもたちはそれを聞いて、先を争うようにして、その本を手にとって、自分たちが書いた物語や絵を見ながら、とてもうれしそうな顔をしていた。
「わたしたちが書いた水の話が本になるなんて思ってもいなかったわ」
蒋さんが、そう言った。
「そうだね。一生の思い出になる」
李くんが、そう答えていた。
「この学校に来て、ミー先生に出会えてよかった」
柳くんが、そう答えていた。
「ミー先生は女神のような人です」
陳くんが、そう言った。
本の表紙絵を描いた唐さんは、格別、うれしそうな顔をしていた。
「わたしは将来、デザイナーになって、こんな仕事をしてみたいと、ずっと思っていたけど、まさかこんなに早く夢が実現できるなんて思ってもいなかったわ」
唐さんが、そう言った。
「唐さんの表紙絵は、本当に素晴らしいです。雪の結晶のなかから生まれた水の妖精が、しなやかに空を飛びながら、虹のかなたに向かって旅をしていく絵です。とても夢があって楽しいです」
ミー先生が、そう言って、唐さんが描いた絵を、ほめていた。本の装丁もよくできていて、本の内容と、よく合っていた。
「みなさんは本当に素晴らしいです。知識が広くて感性も豊かだし、文才や画才に優れた人がたくさんいます。こんな素晴らしいみなさんたちに巡りあえて、わたしは、とてもうれしいです。みなさんに心から『ありがとう』と、お礼を言います」
ミー先生が、そう言っていた。
ミー先生は、そのあと、手に持っていた、もう一冊の本を、子どもたちに見せていた。
「この本のタイトルは『蝶谷』です。この本も、みなさんたちが書いた作文や物語や絵をもとにして作りました。この本も、とても素晴らしい本です。たくさんの種類の蝶たちが花の上を楽しそうに飛び交っている様子が目に見えるように生き生きと描かれています。ここに来なかった子どもたちにも深い感動を与える本だと思います」
ミー先生が、そう言っていた。
「わたしにも見せてください」
子どもたちは、そう言って、この本もまた、先を争うようにして手に取って見ていた。子どもたちはみんな、とても楽しそうな顔をしながら、文を読んだり、絵を見たりしていた。この本の表紙絵は蒋さんが描いてくれたものだった。たくさんの種類の蝶たちの羽の色や模様を細かに観察しながら、蒋さんが丁寧に描いてくれた表紙絵は芸術性にあふれていて、大人顔負けの素晴らしい絵だった。装丁も蝶の物語にふさわしく、とても華やかで美しく仕上げられていた。
「みなさんは協力して、このような素晴らしい本を二冊も作り上げることができました。みなさんは、これから下界の学校に戻りますが、普通の子どもにはできないことができたことで、自信を持って生活してください。そうすることによって、下界でも、生き生きとした楽しい生活を送ることができるようになりますから」
ミー先生が、子どもたちに、そう言っていた。それを聞いて、子どもたちはみんな、にっこりと、うなずいていた。
「ここに来る前は、わたしは、毎日、うつうつとした生活を送っていたけど、普通の学校に戻ってからも、明るい生活が送れそうです」
王さんが、そう言っていた。
「ぼくも同じです。クラスのなかで、ぼくは浮いていて、友だちもいなかったけど、みんなで協力したら、楽しいことが分かりました」
李くんが、そう答えていた。
「そうですか。よかったですね。わたしも、みなさんと出会えて、発見した喜びがたくさんありました。一番の喜びは何だと思いますか」
ミー先生が、子どもたちに聞いていた。
「……」
子どもたちは、しばらく考えていたけど、分からないでいた。
「わたしが発見した一番の喜びは、だめな子どもは、ひとりもいないということです。みなさんは、下界では、みんなから、つまはじきにされて、自分でも、だめな子どもだと思って、自信を失っていました。そのために、いやな夢をよく見て、うなされていました。でも実際には違っていました。だめな子どもどころか、性格も才能も普通の子ども以上に優れた子どもでした。タンチョウの背中に乗って空を飛んでいく勇気もあったし、文才にも画才にもたけていました。わたしは、このことを発見して、とてもうれしく思っています」
ミー先生が感動に震えるような顔をしながら、そう言っていた。ミー先生は、そのあと
子どもたち、一人ひとりと熱いハグをしていた。
それからまもなく、いよいよ『雲の上の学校』を離れるときがやってきた。ミー先生はキャリーバッグを開いて、子どもたちが書いた二冊の本を、なかに入れた。そのあと、本と入れ替わるように、からかさを取り出して、かさを開いた。
「みなさん、これから、このかさを一人ひとりに持たせますから、かさの柄についている三つのボタンのうちの真ん中のボタンを押してください。するとみなさんの体が軽くなります」
ミー先生が、そう言った。それからまもなく、からかさが子どもたちに回された。子どもたちはミー先生に言われたとおりに、真ん中のボタンを押していた。子どもたちが押し終わったあと、ぼくと老いらくさんとシャオパイも、真ん中のボタンを押した。みんなが押し終わったからかさは再び、ミー先生のもとに戻された。
「さあ、いよいよ、これから出発します。体がふわふわと宙に浮いていきますが、怖くはないから大丈夫です。落ちることはありません」
ミー先生がそう言った。ボタンを押した効果は五分後にあらわれて、ミー先生と子どもたちの体は、宙にふわふわと上がっていった。ぼくと老いらくさんとシャオパイの体も宙に浮いていった。
「ここへ来るときも、子どもたちは、このようにして来たのだろうなあ」
老いらくさんが、そう言った。
「たぶん、そうだと思います」
ぼくは、そう答えた。
日はすでにとっぷりと暮れていて、空には星がきらきらと輝いていた。星が間近に見えたので、宇宙のロマンを、よりいっそう強く感じながら、ぼくたちは下界へ戻っていくための旅を始めた。体に翼をつけなくても、遠くまで空を飛んでいけることに、子どもたちは無限の喜びを見いだしているように思えた。ぼくと老いらくさんも、浮き浮きしながら、まるで宇宙飛行士のような気分になって空の旅を楽しんでいた。少しも怖くはなかった。
やがて、町のあかりが見えてきた。旅を始めてから三十分ほどで、ぼくたちは住み慣れた町に戻ってきた。降り立ったのは、ぼくと老いらくさんが住んでいる翠湖公園のなかだった。夜が明けるまで、ミー先生と子どもたちは翠湖公園のなかを散歩したり、ベンチに座っておしゃべりをしたりして過ごしていた。そして夜が明けると、それぞれのうちへ帰っていった。シャオパイもミー先生といっしょに郊外にあるうちへ帰っていった。