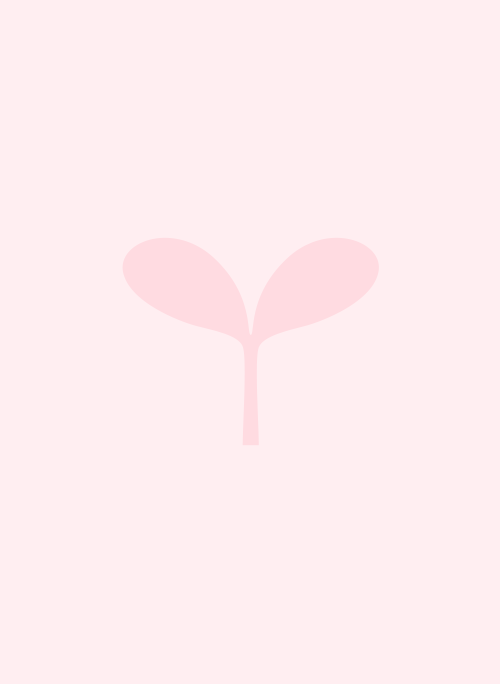天気……昨夜は一晩中、雨が降っていた。夜が明けたころ、家の玄関から外を見たら雨はやんでいて、空全体に、かすみがかかっていた。雨に洗われて大気中の不純物は消えてなくなり、どこからかカーネーションのにおいが漂ってきた。カーネーションは普通は、においのしない花だが、芳香性のあるナデシコと交配した新しい品種のカーネーションは、ほのかなにおいがすることで知られている。
(それにしてもカーネーションのにおいがするのは、どうしてだろう)
ぼくは、そう思った。朝ご飯を食べたあと、散歩のついでに町に出たとき、ようやくそのわけが分かった。今日は『母の日』だったからだ。町を歩いている人たちのなかには、カーネーションの花束を持っている人が何人もいて、その花束のなかから、花のにおいが、大気中にふわふわと発散していた。男の人も女の人も大人も子どももみんな手にカーネーションの花束を大事そうに抱えながら楽しそうに歩いていた。毎年、『母の日』には、こういった光景がよく見られるので、ぼくはとてもうらやましく思っている。ぼくも本当は今日、お母さんにカーネーションを贈りたいと思っている。でもぼくのお母さんは今どこにいるか分からないので、贈ることができないでいる。ぼくは生まれてから三日目に、ある人にもらわれてお母さんのもとから離れていったからだ。お母さんのことは、ほとんど覚えていない。その後、飼い主が何度か代わって、最後には杜真子のうちに行って、そこでしばらく暮らしていた。でも杜真子のお母さんに嫌われたので、うちを出ていくよりほかなかった。そのあとぼくは翠湖公園に行って、築山のなかに洞窟を見つけて、そこで暮らすようになった。その後、ぼくは結婚して、妻猫が子どもを三匹生んでくれた。子どもたちは今はみんな成長して、うちを出ていった。ぼくは今、妻猫とふたりで暮らしている。
カーネーションのにおいがする通りを歩いているときに、不意に後ろから背中を軽くたたかれた。びっくりして振り返ると、そこに、アーヤーがいた。アーヤーは、ぼくと妻猫の二番目の子どもだ。成長して今は老人ホームで、お年寄りに歌を歌って聞かせる仕事をしている。アーヤーは人の声真似ができる。九官鳥に教わって声真似の技術を習得していたからだ。歌い方も九官鳥から習ったので、アーヤーはその特技を生かして、老人ホームで歌を歌って、お年寄りたちを楽しませている。
「誰かと思ったら、お前だったのか」
久しぶりにアーヤーの顔を見て、ぼくはとてもうれしくなった。アーヤーはピンクのカーネーションを口にくわえていた。カーネーションを地面に置いてから、アーヤーが
「今日は『母の日』だから、お母さんにカーネーションをあげようと思って、今、うちへ帰っているところだったの。お父さんに、まさか、こんなところで会うとは思ってもいなかったわ」
と言った。
「父さんも、まさか、こんなところで、お前に会うとは思ってもいなかったよ。元気に頑張っているか?」
「ええ、もちろん頑張っているわ。お年寄りはみんな、わたしの歌を聞くのを楽しみにしているわ。スタッフの人たちからも、とても大切にされていて、毎日おいしいものをたくさん食べさせてもらえるので、毎日とても楽しいわ」
アーヤーの顔が生き生きと輝いていた。
「そうか。それはよかったな。父さんもうれしいよ。これからも頑張れよ」
ぼくはそう言って、アーヤーを励ました。
「ありがとう。これからも頑張るわ」
アーヤーが、そう答えた。
「お父さんも元気?」
アーヤーが、ぼくのことを気遣ってくれた。
「うん、元気だよ」
ぼくは、そう答えた。
「よかった。お母さんも元気?」
アーヤーが聞いた。
「うん、とても元気だよ。お前の顔を見たら、もっと元気になるだろう」
ぼくはそう言って、笑みを浮かべた。
それからまもなく、アーヤーは再び口にカーネーションをくわえた。明るい陽ざしがさんさんと降り注ぐなか、ぼくとアーヤーは並んで歩きながら、翠湖公園のなかにあるうちへ帰っていった。
うちへ着くと、妻猫が久しぶりにアーヤーの顔を見て、うれしくてたまらないような顔をしていた。
「はい、これはお母さんへのプレゼント。今日は『母の日』だからね。わたしを生んでくれて、お母さん、ありがとう」
アーヤーはそう言ってから、口にくわえて持ってきたカーネーションを、妻猫にあげていた。
「ありがとう。わざわざ、わたしのためにプレゼントを持って帰ってきてくれたのね」
妻猫は感激のあまり、目がうるうるしていた。
「大好きなお母さんに喜んでもらって、わたしもとてもうれしいわ。お母さん、これからもお元気でいてね」
アーヤーは心をこめて、そう言った。
「ありがとう。お前も元気そうだね」
妻猫がアーヤーの顔色を見ながら、そう言った。
「ええ、元気よ。人から必要とされている喜びを感じているので、毎日心が満たされていて、とても楽しいわ」
アーヤーがそう答えた。
「そうですか。それを聞いて、母さんもうれしいわ。今はどんな歌を歌っているの?」
妻猫が興味深そうな顔をしながら、アーヤーに聞いていた。
「今は『月亮代表我的心』(月はわたしの心を表す)」という歌をよく歌っているわ。この歌はみんながよく知っている歌なので、わたしが歌い出すと、みんないっしょに歌い出して、とても盛り上がって楽しい雰囲気になるの」
アーヤーが弾んだ声で、そう答えていた。
「そうかい。よかったら、母さんにも、その歌を聞かせてくれない?」
妻猫がそう言うと、アーヤーは二つ返事で
「ええ、いいわ」
と答えて、呼吸を整えてから、歌い始めた。
♪ 你问我爱你有多深
我爱你有几分
你去想一想
你去看一看
月亮代表我的心
……
アーヤーが情感をたっぷりこめて歌ってくれたので、妻猫は思わず、うっとりとした顔をして酔いしれていた。ぼくもアーヤーの歌い方のうまさに感心していた。ぼくは歌詞の意味が分かるので、妻猫以上に、この歌にこめられている思いを、よく捉えながら歌っているなあと感じた。
「お前は本当にたいしたものだ」
ぼくがそう言うと、アーヤーは、嬉々とした顔をしながら
「ありがとう」
と、照れくさそうに言った。
「お前の歌を聞いていたら、お年寄りたちも元気で、長生きできるのではないのか」
ぼくがそう言うと、アーヤーが
「そうあってほしいわ」
と、明るい顔で答えていた。
アーヤーが歌を歌っている、ちょうどそのとき、パントーが、うちへ帰ってきた。パントーは、ぼくと妻猫の一番上の子どもだ。パオパオという自閉症の子どもといっしょに生活している。パオパオは卓越した指揮者としての素質がある子どもなので、楽団の指揮者として指揮棒を振っている。パントーはパオパオにとって大切な友だちなので、いつも付き添っていて、あちこちいっしょに公演に出かけている。パントーはピアノの弾き方を習ったことがあるので、ピアノの腕前を披露して観客から拍手喝采を受けることもある。
パントーも口にピンクのカーネーションをくわえていた。
「お母さん、『母の日』おめでとうございます。これからもお元気で」
パントーはカーネーションを妻猫に手渡すと、そう言った。
「ありがとう。うれしいわ。あなたも元気で頑張っていますか?」
「うん、元気で頑張っているよ」
パントーが明るい声で、そう答えていた。
「それにしてもアーヤーは歌が上手ですね。ぼくはこれまで、いろいろな人の歌を聞いてきたけど、アーヤーの歌はプロの歌手にも匹敵するぐらい上手です。たいしたものです」
パントーはそう言って、アーヤーに感心しきりだった。パントーにほめられて、アーヤーはまんざらでもないような顔をしていた。
「パオパオはどうしていますか?」
妻猫がパントーに聞いていた。
「うん、元気にしていますよ。今はここから遠い所で公演しているから、ぼくとパオパオは今日は飛行機に乗って、この町へ帰ってきました。パオパオもお母さんといっしょに『母の日』を過ごそうと思って、ずっと前から楽しみにしていました」
パントーがそう答えた。
「そうですか。パオパオのお母さんも、とても喜んでおられると思います」
妻猫がにこやかな顔でそう答えていた。
「飛行機に乗って帰ってくるなんて、いいなあ。わたしはまだ一度も飛行機に乗ったことがないから」
アーヤーがうらやましそうな顔をしていた。
「空から下を見下ろすのは気持ちがいいですが、飛行機が離陸してから三十分も経たないうちに、この町の空港に着いたので、感慨に浸っている間もなかったです」
パントーがそう答えていた。
それからしばらくしてから、サンパオがうちへ帰ってきた。サンパオは、ぼくと妻猫の一番下の子どもだ。今は盲目のピアノ調律師の盲導猫となって働いている。ピアノ調律師が住んでいる家には黒騎士という盲導犬もいるので、サンパオは黒騎士のアシスタントとして、ふたりでピアノ調律師をサポートしている。
サンパオも口にカーネーションをくわえていた。
「お母さん、『母の日』おめでとうございます。ぼくはお母さんが大好きです」
サンパオはカーネーションを妻猫に手渡しながら、そう言った。
「ありがとう。母さんも、サンパオが大好きです」
妻猫が幸福感に満たされたような顔で、そう答えていた。
「黒騎士とはうまくやっているかい?」
ぼくはサンパオに聞いた。
「うん、うまくやっているよ。犬の言葉は、ぼくにはまだ理解できないけど、黒騎士が手取り足取りしながら、親切丁寧にサポートの仕方を教えてくれるので、ぼくは黒騎士が大好きだ」
サンパオがそう答えた。
子どもたちがみんな『母の日』に帰ってきてくれたので、妻猫は、ふわふわとした恍惚感に浸りながら
「わたしは何てしあわせなのでしょう」
とつぶやいて、悦に入っていた。
ぼくと妻猫は、帰ってきた子どもたちに、おいしいごちそうをふるまって、もてなした。家族みんなが集まるのは久しぶりだったので、話が弾んで、楽しいひとときが、あっという間に過ぎていった。
それからまもなく、子どもたちは帰り支度を始めた。うちを出ていく前に、妻猫はひとりひとりハグして、強く抱きしめながら
「今日は、忙しいなか、わざわざ帰ってきてくれてありがとう。今日のことは一生忘れないわ」
と言った。子どもたちと、またしばらく会えなくなるかと思うと、妻猫は名残惜しそうな顔をしていた。しかしそれでも妻猫はけっして情に流される猫ではない。子どもたちがみんな社会に貢献しているので、長く引き留めないで、今必要とされている場所へ早く帰って行かせることが親としてすべきことだと認識していたからだ。
「アーヤー、お年寄りたちが、あなたの帰りを待っていると思うので、早く帰って、歌で心を癒やしてあげなさい」
妻猫はアーヤーに、そう言った。
「ありがとう。今度またうちへ帰ってきたときに、お母さんにも歌を歌って聞かせるわ」
アーヤーが、そう言った。
「ありがとう、楽しみにしているわ」
妻猫が、アーヤーに、そう答えていた。アーヤーは、それからまもまく、後ろ髪を引かれるような思いで、妻猫とぼくのほうを何度も振り返りながら、うちを出ていった。
「パントーも早く、パオパオのもとへ帰っていきなさい。待っていると思うわ。帰りの飛行機の時間があるのでしょう。遅れないようにね」
妻猫は、パントーに、そう言った。
「うん、分かった。今度、この町でコンサートをするときは、お母さんとお父さんを招待するから、ぜひ見に来てね」
パントーが妻猫に、そう言った。
「ありがとう、楽しみにしているわ」
妻猫が、パントーに、そう答えていた。パントーは、それからまもまく、妻猫と、ぼくに「またいつか会いましょう」と言って、うちを出ていった。
「サンパオも、早く、帰りなさい。ピアノ調律師と黒騎士が、あなたの帰りを待っていると思うわ。ピアノ調律師は目が見えない人だから、あなたがいないと、生活に支障をきたしているかもしれないから」
妻猫が、心配そうな顔をしながら、サンパオに、そう言っていた。
「うん、分かった。黒騎士だけに仕事を任せるわけにはいかないからね。黒騎士の右腕となって、ぼくはこれからも頑張るよ」
サンパオが、力強い声で、そう答えていた。サンパオは、それからまもなく、妻猫とぼくのほおに軽くキスをしてから、うちを出ていった。
子どもたちがみんな帰っていったあと、ぼくは心のなかに、ぽっかりと穴が空いたように感じた。でも不思議と寂しくはなかった。子どもたちが立派な猫になって社会に貢献していることが、あらためて分かっただけではなくて、ぼくと妻猫にたいする感謝の念も深く抱いていることが分かったからだ。妻猫も、ぼくと同じように幸福感に満たされているように思えた。
(ぼくと妻猫ほど幸せな猫の親がこの世にいるだろうか)
ぼくはそう思うと、何だか誇らしく思えてきて、この幸せを誰かと分かち合いたいと思った。そう思ったとき、ぼくは親友の老いらくさんのことを、真っ先に思い浮かべた。老いらくさんには、これまで、いろいろなことで親身になって相談に乗ってもらった。貴重なアドバイスをたくさんしてもらったので、とても感謝している。でも老いらくさんに言わせれば、何か困った事や悩みがあるときにだけ、ぼくが相談に行くので、ぼくと話していてもあまり楽しくないそうだ。たまには楽しい話を聞かせてくれよと、言われたことを思い出した。そこで、ぼくは今日、これから老いらくさんを久しぶりに訪ねていって、老いらくさんと幸せや喜びを分かち合いたいと思った。子どもたちがみんな立派な猫になって親孝行も忘れない猫になったのは、老いらくさんから受けたアドバイスによるところも大きかったからだ。
老いらくさんは住んでいるところが決まっていないし、神出鬼没なところがあるので、なかなか探しに行きにくい。でも老いらくさんは、ぼくのにおいを知っているので、適当にぶらぶら歩きながら探していたら、向こうから近づいてくることがよくある。
ところが今日はどれほど探しても、老いらくさんと出会えなかった。思い起こせば、もうずいぶん長く、老いらくさんと会っていなかった。最後に会ってから、二週間以上にもなる。先月の末に、パントーの様子を見るためにいっしょにパオパオのうちへ行って以来、会っていなかった。自閉症のパオパオは、ちょろちょろ動くものを極端に怖がるところがあるのでネズミの老いらくさんを部屋のなかに入れるわけにはいかなかった。そのためにアパートの階下で待たせていた。すると、ぼくがパオパオのうちから出てきたときには、老いらくさんの姿はなかった。翠湖公園に一足先に、ひとりで帰っていったのかなと、ぼくはそのとき思った。それ以来、ぼくは老いらくさんと会っていない。
ぼくの推測では、老いらくさんは、翠湖公園に今はいないのではないかと思っている。そうでなかったら、二週間以上も会わないことは考えにくいからだ。
(老いらくさんは、どこに行ったのだろうか)
ぼくはそう思いながら、老いらくさんとよく行った築山に登って、斜面に寝そべりながら空を仰いでいた。雲がゆっくりと流れていくのが見えた。雲の流れを追いながら、ぼくは老いらくさんが話してくれた機知に富んだ面白い話や、ユーモラスな話のことを思い出していた。老いらくさんは今、どこにいるのか分からないが、今までと同じように、どこからか神出鬼没に、ひょっこりと姿を現わして
「やあ、元気か」
と、声をかけてくれたら、どんなにうれしいだろうと、ぼくは心からそう思っていた。
(それにしてもカーネーションのにおいがするのは、どうしてだろう)
ぼくは、そう思った。朝ご飯を食べたあと、散歩のついでに町に出たとき、ようやくそのわけが分かった。今日は『母の日』だったからだ。町を歩いている人たちのなかには、カーネーションの花束を持っている人が何人もいて、その花束のなかから、花のにおいが、大気中にふわふわと発散していた。男の人も女の人も大人も子どももみんな手にカーネーションの花束を大事そうに抱えながら楽しそうに歩いていた。毎年、『母の日』には、こういった光景がよく見られるので、ぼくはとてもうらやましく思っている。ぼくも本当は今日、お母さんにカーネーションを贈りたいと思っている。でもぼくのお母さんは今どこにいるか分からないので、贈ることができないでいる。ぼくは生まれてから三日目に、ある人にもらわれてお母さんのもとから離れていったからだ。お母さんのことは、ほとんど覚えていない。その後、飼い主が何度か代わって、最後には杜真子のうちに行って、そこでしばらく暮らしていた。でも杜真子のお母さんに嫌われたので、うちを出ていくよりほかなかった。そのあとぼくは翠湖公園に行って、築山のなかに洞窟を見つけて、そこで暮らすようになった。その後、ぼくは結婚して、妻猫が子どもを三匹生んでくれた。子どもたちは今はみんな成長して、うちを出ていった。ぼくは今、妻猫とふたりで暮らしている。
カーネーションのにおいがする通りを歩いているときに、不意に後ろから背中を軽くたたかれた。びっくりして振り返ると、そこに、アーヤーがいた。アーヤーは、ぼくと妻猫の二番目の子どもだ。成長して今は老人ホームで、お年寄りに歌を歌って聞かせる仕事をしている。アーヤーは人の声真似ができる。九官鳥に教わって声真似の技術を習得していたからだ。歌い方も九官鳥から習ったので、アーヤーはその特技を生かして、老人ホームで歌を歌って、お年寄りたちを楽しませている。
「誰かと思ったら、お前だったのか」
久しぶりにアーヤーの顔を見て、ぼくはとてもうれしくなった。アーヤーはピンクのカーネーションを口にくわえていた。カーネーションを地面に置いてから、アーヤーが
「今日は『母の日』だから、お母さんにカーネーションをあげようと思って、今、うちへ帰っているところだったの。お父さんに、まさか、こんなところで会うとは思ってもいなかったわ」
と言った。
「父さんも、まさか、こんなところで、お前に会うとは思ってもいなかったよ。元気に頑張っているか?」
「ええ、もちろん頑張っているわ。お年寄りはみんな、わたしの歌を聞くのを楽しみにしているわ。スタッフの人たちからも、とても大切にされていて、毎日おいしいものをたくさん食べさせてもらえるので、毎日とても楽しいわ」
アーヤーの顔が生き生きと輝いていた。
「そうか。それはよかったな。父さんもうれしいよ。これからも頑張れよ」
ぼくはそう言って、アーヤーを励ました。
「ありがとう。これからも頑張るわ」
アーヤーが、そう答えた。
「お父さんも元気?」
アーヤーが、ぼくのことを気遣ってくれた。
「うん、元気だよ」
ぼくは、そう答えた。
「よかった。お母さんも元気?」
アーヤーが聞いた。
「うん、とても元気だよ。お前の顔を見たら、もっと元気になるだろう」
ぼくはそう言って、笑みを浮かべた。
それからまもなく、アーヤーは再び口にカーネーションをくわえた。明るい陽ざしがさんさんと降り注ぐなか、ぼくとアーヤーは並んで歩きながら、翠湖公園のなかにあるうちへ帰っていった。
うちへ着くと、妻猫が久しぶりにアーヤーの顔を見て、うれしくてたまらないような顔をしていた。
「はい、これはお母さんへのプレゼント。今日は『母の日』だからね。わたしを生んでくれて、お母さん、ありがとう」
アーヤーはそう言ってから、口にくわえて持ってきたカーネーションを、妻猫にあげていた。
「ありがとう。わざわざ、わたしのためにプレゼントを持って帰ってきてくれたのね」
妻猫は感激のあまり、目がうるうるしていた。
「大好きなお母さんに喜んでもらって、わたしもとてもうれしいわ。お母さん、これからもお元気でいてね」
アーヤーは心をこめて、そう言った。
「ありがとう。お前も元気そうだね」
妻猫がアーヤーの顔色を見ながら、そう言った。
「ええ、元気よ。人から必要とされている喜びを感じているので、毎日心が満たされていて、とても楽しいわ」
アーヤーがそう答えた。
「そうですか。それを聞いて、母さんもうれしいわ。今はどんな歌を歌っているの?」
妻猫が興味深そうな顔をしながら、アーヤーに聞いていた。
「今は『月亮代表我的心』(月はわたしの心を表す)」という歌をよく歌っているわ。この歌はみんながよく知っている歌なので、わたしが歌い出すと、みんないっしょに歌い出して、とても盛り上がって楽しい雰囲気になるの」
アーヤーが弾んだ声で、そう答えていた。
「そうかい。よかったら、母さんにも、その歌を聞かせてくれない?」
妻猫がそう言うと、アーヤーは二つ返事で
「ええ、いいわ」
と答えて、呼吸を整えてから、歌い始めた。
♪ 你问我爱你有多深
我爱你有几分
你去想一想
你去看一看
月亮代表我的心
……
アーヤーが情感をたっぷりこめて歌ってくれたので、妻猫は思わず、うっとりとした顔をして酔いしれていた。ぼくもアーヤーの歌い方のうまさに感心していた。ぼくは歌詞の意味が分かるので、妻猫以上に、この歌にこめられている思いを、よく捉えながら歌っているなあと感じた。
「お前は本当にたいしたものだ」
ぼくがそう言うと、アーヤーは、嬉々とした顔をしながら
「ありがとう」
と、照れくさそうに言った。
「お前の歌を聞いていたら、お年寄りたちも元気で、長生きできるのではないのか」
ぼくがそう言うと、アーヤーが
「そうあってほしいわ」
と、明るい顔で答えていた。
アーヤーが歌を歌っている、ちょうどそのとき、パントーが、うちへ帰ってきた。パントーは、ぼくと妻猫の一番上の子どもだ。パオパオという自閉症の子どもといっしょに生活している。パオパオは卓越した指揮者としての素質がある子どもなので、楽団の指揮者として指揮棒を振っている。パントーはパオパオにとって大切な友だちなので、いつも付き添っていて、あちこちいっしょに公演に出かけている。パントーはピアノの弾き方を習ったことがあるので、ピアノの腕前を披露して観客から拍手喝采を受けることもある。
パントーも口にピンクのカーネーションをくわえていた。
「お母さん、『母の日』おめでとうございます。これからもお元気で」
パントーはカーネーションを妻猫に手渡すと、そう言った。
「ありがとう。うれしいわ。あなたも元気で頑張っていますか?」
「うん、元気で頑張っているよ」
パントーが明るい声で、そう答えていた。
「それにしてもアーヤーは歌が上手ですね。ぼくはこれまで、いろいろな人の歌を聞いてきたけど、アーヤーの歌はプロの歌手にも匹敵するぐらい上手です。たいしたものです」
パントーはそう言って、アーヤーに感心しきりだった。パントーにほめられて、アーヤーはまんざらでもないような顔をしていた。
「パオパオはどうしていますか?」
妻猫がパントーに聞いていた。
「うん、元気にしていますよ。今はここから遠い所で公演しているから、ぼくとパオパオは今日は飛行機に乗って、この町へ帰ってきました。パオパオもお母さんといっしょに『母の日』を過ごそうと思って、ずっと前から楽しみにしていました」
パントーがそう答えた。
「そうですか。パオパオのお母さんも、とても喜んでおられると思います」
妻猫がにこやかな顔でそう答えていた。
「飛行機に乗って帰ってくるなんて、いいなあ。わたしはまだ一度も飛行機に乗ったことがないから」
アーヤーがうらやましそうな顔をしていた。
「空から下を見下ろすのは気持ちがいいですが、飛行機が離陸してから三十分も経たないうちに、この町の空港に着いたので、感慨に浸っている間もなかったです」
パントーがそう答えていた。
それからしばらくしてから、サンパオがうちへ帰ってきた。サンパオは、ぼくと妻猫の一番下の子どもだ。今は盲目のピアノ調律師の盲導猫となって働いている。ピアノ調律師が住んでいる家には黒騎士という盲導犬もいるので、サンパオは黒騎士のアシスタントとして、ふたりでピアノ調律師をサポートしている。
サンパオも口にカーネーションをくわえていた。
「お母さん、『母の日』おめでとうございます。ぼくはお母さんが大好きです」
サンパオはカーネーションを妻猫に手渡しながら、そう言った。
「ありがとう。母さんも、サンパオが大好きです」
妻猫が幸福感に満たされたような顔で、そう答えていた。
「黒騎士とはうまくやっているかい?」
ぼくはサンパオに聞いた。
「うん、うまくやっているよ。犬の言葉は、ぼくにはまだ理解できないけど、黒騎士が手取り足取りしながら、親切丁寧にサポートの仕方を教えてくれるので、ぼくは黒騎士が大好きだ」
サンパオがそう答えた。
子どもたちがみんな『母の日』に帰ってきてくれたので、妻猫は、ふわふわとした恍惚感に浸りながら
「わたしは何てしあわせなのでしょう」
とつぶやいて、悦に入っていた。
ぼくと妻猫は、帰ってきた子どもたちに、おいしいごちそうをふるまって、もてなした。家族みんなが集まるのは久しぶりだったので、話が弾んで、楽しいひとときが、あっという間に過ぎていった。
それからまもなく、子どもたちは帰り支度を始めた。うちを出ていく前に、妻猫はひとりひとりハグして、強く抱きしめながら
「今日は、忙しいなか、わざわざ帰ってきてくれてありがとう。今日のことは一生忘れないわ」
と言った。子どもたちと、またしばらく会えなくなるかと思うと、妻猫は名残惜しそうな顔をしていた。しかしそれでも妻猫はけっして情に流される猫ではない。子どもたちがみんな社会に貢献しているので、長く引き留めないで、今必要とされている場所へ早く帰って行かせることが親としてすべきことだと認識していたからだ。
「アーヤー、お年寄りたちが、あなたの帰りを待っていると思うので、早く帰って、歌で心を癒やしてあげなさい」
妻猫はアーヤーに、そう言った。
「ありがとう。今度またうちへ帰ってきたときに、お母さんにも歌を歌って聞かせるわ」
アーヤーが、そう言った。
「ありがとう、楽しみにしているわ」
妻猫が、アーヤーに、そう答えていた。アーヤーは、それからまもまく、後ろ髪を引かれるような思いで、妻猫とぼくのほうを何度も振り返りながら、うちを出ていった。
「パントーも早く、パオパオのもとへ帰っていきなさい。待っていると思うわ。帰りの飛行機の時間があるのでしょう。遅れないようにね」
妻猫は、パントーに、そう言った。
「うん、分かった。今度、この町でコンサートをするときは、お母さんとお父さんを招待するから、ぜひ見に来てね」
パントーが妻猫に、そう言った。
「ありがとう、楽しみにしているわ」
妻猫が、パントーに、そう答えていた。パントーは、それからまもまく、妻猫と、ぼくに「またいつか会いましょう」と言って、うちを出ていった。
「サンパオも、早く、帰りなさい。ピアノ調律師と黒騎士が、あなたの帰りを待っていると思うわ。ピアノ調律師は目が見えない人だから、あなたがいないと、生活に支障をきたしているかもしれないから」
妻猫が、心配そうな顔をしながら、サンパオに、そう言っていた。
「うん、分かった。黒騎士だけに仕事を任せるわけにはいかないからね。黒騎士の右腕となって、ぼくはこれからも頑張るよ」
サンパオが、力強い声で、そう答えていた。サンパオは、それからまもなく、妻猫とぼくのほおに軽くキスをしてから、うちを出ていった。
子どもたちがみんな帰っていったあと、ぼくは心のなかに、ぽっかりと穴が空いたように感じた。でも不思議と寂しくはなかった。子どもたちが立派な猫になって社会に貢献していることが、あらためて分かっただけではなくて、ぼくと妻猫にたいする感謝の念も深く抱いていることが分かったからだ。妻猫も、ぼくと同じように幸福感に満たされているように思えた。
(ぼくと妻猫ほど幸せな猫の親がこの世にいるだろうか)
ぼくはそう思うと、何だか誇らしく思えてきて、この幸せを誰かと分かち合いたいと思った。そう思ったとき、ぼくは親友の老いらくさんのことを、真っ先に思い浮かべた。老いらくさんには、これまで、いろいろなことで親身になって相談に乗ってもらった。貴重なアドバイスをたくさんしてもらったので、とても感謝している。でも老いらくさんに言わせれば、何か困った事や悩みがあるときにだけ、ぼくが相談に行くので、ぼくと話していてもあまり楽しくないそうだ。たまには楽しい話を聞かせてくれよと、言われたことを思い出した。そこで、ぼくは今日、これから老いらくさんを久しぶりに訪ねていって、老いらくさんと幸せや喜びを分かち合いたいと思った。子どもたちがみんな立派な猫になって親孝行も忘れない猫になったのは、老いらくさんから受けたアドバイスによるところも大きかったからだ。
老いらくさんは住んでいるところが決まっていないし、神出鬼没なところがあるので、なかなか探しに行きにくい。でも老いらくさんは、ぼくのにおいを知っているので、適当にぶらぶら歩きながら探していたら、向こうから近づいてくることがよくある。
ところが今日はどれほど探しても、老いらくさんと出会えなかった。思い起こせば、もうずいぶん長く、老いらくさんと会っていなかった。最後に会ってから、二週間以上にもなる。先月の末に、パントーの様子を見るためにいっしょにパオパオのうちへ行って以来、会っていなかった。自閉症のパオパオは、ちょろちょろ動くものを極端に怖がるところがあるのでネズミの老いらくさんを部屋のなかに入れるわけにはいかなかった。そのためにアパートの階下で待たせていた。すると、ぼくがパオパオのうちから出てきたときには、老いらくさんの姿はなかった。翠湖公園に一足先に、ひとりで帰っていったのかなと、ぼくはそのとき思った。それ以来、ぼくは老いらくさんと会っていない。
ぼくの推測では、老いらくさんは、翠湖公園に今はいないのではないかと思っている。そうでなかったら、二週間以上も会わないことは考えにくいからだ。
(老いらくさんは、どこに行ったのだろうか)
ぼくはそう思いながら、老いらくさんとよく行った築山に登って、斜面に寝そべりながら空を仰いでいた。雲がゆっくりと流れていくのが見えた。雲の流れを追いながら、ぼくは老いらくさんが話してくれた機知に富んだ面白い話や、ユーモラスな話のことを思い出していた。老いらくさんは今、どこにいるのか分からないが、今までと同じように、どこからか神出鬼没に、ひょっこりと姿を現わして
「やあ、元気か」
と、声をかけてくれたら、どんなにうれしいだろうと、ぼくは心からそう思っていた。