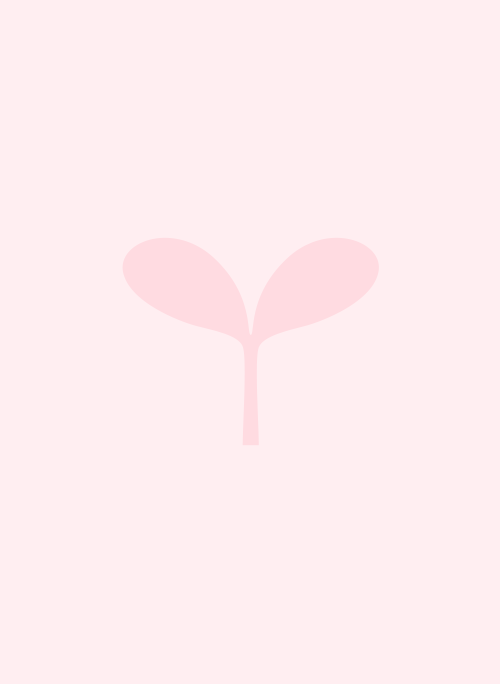天気……同じ山でも、海抜によって、気温と植生が、大きく違っている。タンチョウがぼくたちを乗せて、暴風雪が吹き荒れる山の上から、山のふもとに下りてきたときには、まるで別世界に来たかのような感じさえした。気温も比較的暖かかったし、雪の量も少なくて、植物が雪のなかから顔をのぞかせていたからだ。
山の中腹付近から流れてきた雪解け水は、山のふもとで、いくつかの流れが合流して、川となり、水の量を増しながら、さらに下流へ向かって流れていた。木の上に積もっている雪は、地面にばさっと落ちて、だんだん、融けはじめていた。山の山頂付近を見ると、太陽の光を浴びて、雪がきらきらと輝いていて、まぶしくて、目を開けてはいられないほどだった。
「山頂は太陽から近いのに、どうして雪は融けないのかなあ」
王さんが、山頂を見ながら、素朴な疑問を投げかけていた。
「ずっと昔、この山の山頂付近は氷河になっていて、地面が、かちかちに凍っていました。雪線より上に降った雪は融けないのです」
ミー先生が、そう答えていた。
「氷河って何ですか。雪線って何ですか」
蒋さんが、聞いていた。
「氷河というのは高山や極地の高いところに積もった雪が、一年中融けないで、氷のかたまりとなって、川のように流れくだるものを言います。雪線というのは、降った雪が一年を通して融けないところと、融けるところの境界線を言います。雪線より上に降った雪は万年雪となって、太陽の光がどんなに強くても融けることはありません」
ミー先生が、そう説明していた。
蒋さんが、うなずいていた。
「高山の山頂付近は、一年を通して厚い雪に覆われています。そして雪は圧力によって氷になり、氷は重力の作用によって、地面に沿って移動していきます。この移動していく大きな氷が氷河と呼ばれています」
ミー先生がさらに、そう説明すると、子どもたちが、みんな、うなずいていた。
「川や池の源流は、雪線より下の雪が融けて作られていたのですね」
李くんが、ミー先生に聞いていた。
「そうです。そのとおりです」
ミー先生が、そう答えていた。
王さんはポケットのなかから望遠鏡を取り出して、山の頂上付近を見ながら
「昔、あそこに氷河があって、氷のかたまりが流れていたのですね」
と、聞いていた。
「そうです。そのとおりです。昔は今よりも、ずっと寒い時代でした」
ミー先生が、そう答えていた。
「雪線は海抜何メートルあたりにあるのですか」
蒋さんが聞いていた。
「雪線は山の地形や、風が吹いてくる方向によって異なっています。この山では五千メートル前後のところを雪線が不規則に走っています」
ミー先生が、そう答えていた。
ミー先生の説明を聞いて、ぼくは氷河や雪線が、どのようなものなのか想像していた。そのとき、望遠鏡で山の頂上付近を見ていた王さんが、びっくりしたような顔をしていた。
「あれっ、あそこにいるのは花顔鹿ではないの」
王さんが、そう言った。
「えっ、本当に?」
蒋さんも、びっくりしたような顔をしていた。蒋さんは王さんから望遠鏡を借りると、山頂付近をじっと見ていた。
「あ、本当だ。まちがいなく、あれは花顔鹿だ。いつのまに、あんなところに行っていたのだろう」
蒋さんは、けげんそうな顔をしていた。
「花顔鹿が何をしているか、分かるか」
李くんが聞いていた。
「ここからは遠すぎて、はっきりとは分からないわ。地面に顔をくっつけているように見えるので、雪を食べているのではないかしら」
蒋さんが、そう答えていた。
「花顔鹿は花を食べる動物だろう。どうして雪を食べるのだ」
李くんが反論していた。
「花がないから、雪を食べているのではないの」
唐さんが、そう言った。それを聞いて、ミー先生が
「暴風雪もやんだようだから、もう一度、タンチョウに乗って、山の頂上付近に戻ってみませんか。近くから見れば、花顔鹿が何を食べているのか分かりますから」
と言った。
「いいですね。タンチョウに乗って、空を飛ぶのは楽しいですから」
陳くんがそう言った。
それからまもなく、ミー先生と子どもたちは再び、タンチョウの背中に乗って、山の上のほうへ向かって飛び始めた。ぼくと老いらくさんとシャオパイも、ミー先生や子どもたちのあとに続いた。しばらくしてから、ぼくたちは花顔鹿がいるところに着いた。花顔鹿が食べていたのは雪ではなくて、花だった。黄色い花が雪の下から顔を出していた。
「この花の名前を知っていますか」
ミー先生が聞いていた。
「……」
返事は返ってこなかった。
「福寿草と言います」
ミー先生がそう答えていた。
「福寿草ですか?」
王さんが聞き返していた。
「そうです。福寿草です。福寿とは、幸福で長命なことを言います。元日草とも言います。名前にふさわしく、とてもおめでたい花です」
ミー先生がそう説明していた。
「人も、この花を食べることができますか」
李くんが聞いていた。
「人は、この花を食べることはできません。でも根をせんじて薬として使ったり、お正月の飾りものとして、玄関に飾る人がいます」
ミー先生がそう説明していた。
「ここはまだ寒くて雪が積もっているのに、雪のなかから顔を出して、屈強な花ですね」
唐さんが、感心したような声で、そう言った。それを聞いて、ミー先生が
「いつもは、もう少し暖かくなってから顔を出します。でも花顔鹿がやってきたので、歓迎するために、いつもより早く顔を出しているのかもしれません」
と、答えていた。それを聞いて、子どもたちは、顔を見合わせながら、にっこりと笑みを浮かべていた。
それからまもなく、陳くんが
「あれっ、花の上に蝶がいる。雪が積もっている時季に蝶が飛んでいるなんて思ってもいなかったよ」
と言った。それを聞いて、ほかの子どもたちが、うなずいていた。
「この蝶の名前を知っていますか」
ミー先生が聞いていた。
「……」
返事は返ってこなかった。
「絹蝶といいます。高山でしか見られない珍しい蝶です。絹のように透き通った羽をしていて、雪線の付近に生息している蝶です。雪が融けてからよく見られます。今はまだ雪は融けていませんが、福寿草が雪のなかから顔を出したから、福寿草を歓迎するために、一足はやく、成虫になって、ここへやってきたのかもしれません」
ミー先生が、そう言っていた。それを聞いて、子どもたちは、くつくつと笑っていた。
絹蝶は、透き通った羽を、ひらひらと動かしながら、福寿草の上を優雅に飛びまわっていた。花の上におりてきて、蜜を吸っている蝶もいた。太陽の光が絹蝶の透き通った羽に当たって、きらきらと輝いていて、とても美しかった。絹蝶という名前に、ふさわしい蝶だと、ぼくは思った。
唐さんが、ほっこりした顔をしながら
「福寿草が屈強な花なら、絹蝶は屈強な蝶だわ。こんなに厳しい自然環境のなかでも、めげないで頑張っているのを見ると、何だか勇気をもらって励まされているように感じるわ」
と言って、福寿草や絹蝶を、いとおしそうに見ていた。
しばらくしてから、ミー先生が子どもたちに
「みなさんたちを、これから『蝶谷』へ連れていきます」
と言った。
「『蝶谷』?」
子どもたちは、みんな、きょとんとした顔をしていた。
「『蝶谷』というのは、蝶がたくさん生息している谷のことです。たくさんの種類の蝶たちが、そこにいます。これから再びタンチョウに乗って、深い谷へおりていきます」
ミー先生が、そう言った。
それからまもなく、ミー先生と子どもたちはタンチョウに乗って空を飛び始めた。ぼくと老いらくさんとシャオパイもタンチョウに乗って、あとを追った。ミー先生が乗ったタンチョウが先導して、「人」の形に隊列を組みながら、タンチョウたちは一団となって『蝶谷』をめざして、山をくだっていった。上空から下を見ると、雪原のあちこちに、黄色い点のようなものが、ぽつぽつと見えた。点の上には、きらきらと光るものが動いているのも見えた。福寿草と絹蝶が互いに仲睦まじく親しみ合っているのだと思うと、ぼくには、とても微笑ましく思えた。
タンチョウが谷までくだってくると、山の上の景色とは違って、春の息吹のようなものが、ここかしこにあふれていた。木々の若葉が、すでに芽吹きはじめていた。ビオラやパンジーやジュリアンなど、いろいろな花も咲きはじめていた。赤やピンクや紫の花びらが柔らかな光をいっぱいに浴びながら、きらきらと輝いていた。花の上には、たくさんの蝶がいて、ひらひらと飛び交っていた。
「蝶は今、花の受粉を手伝っているのです」
ミー先生がそう言った。
蝶といっしょに、枯葉が、ひらひらと舞っているのが見えた。でもよく見ると枯葉は下に落ちないで、ずっと、舞い続けていた。
「あれっ、どうしてだろう?」
ぼくは不思議に思ったから、老いらくさんに聞いた。
「あれは枯葉ではないよ。蝶だよ」
老いらくさんが、そう答えた。
蝶のなかにカレハチョウという蝶がいるのを聞いたことがあったが、実際に目で見るのは初めてだった。ぼくは、てっきり枯葉だとばかり思っていた。
「笑い猫、ここには、いろんな蝶がいる。お前は蝶の名前を、どれくらい知っているか」
老いらくさんが聞いた。
「モンシロチョウ、モンキチョウ、アゲハチョウ、カレハチョウ、それから……」
ぼくには、それ以上、蝶の名前が出てこなかった。
「そのほか、オオムラサキ、カラスアゲハ、テングチョウ、ウラギンシジミ、カバマダラ、アオバセセリなどもいる」
老いらくさんが、そう言った。老いらくさんは博学多才なので、知識が豊富だ。
ぼくは感心した。
「あれっ、あの蝶は目玉が二つあって、きょろきょろ動かしている」
ぼくが、そう言うと、
「あれは目玉ではないよ。まだら模様だよ」
と、老いらくさんが教えてくれた。よく見ると、確かにそうだった。
「あっ、本当だ。目玉にそっくりだったから、ぼくは、てっきり目玉だとばかり思っていた」
ぼくは、そう答えた。
「敵の目をごまかして、びっくりさせるために、あのような模様をつけているのだよ」
老いらくさんが、そう答えた。それを聞いて、ぼくはうなずいた。
「ぼくが一番好きなのは、アゲハチョウです」
ぼくがそう言うと、老いらくさんが
「わしが一番好きな蝶はオオムラサキだ」
と、答えた。
ミー先生が言ったように、『蝶谷』には、たくさんの種類の蝶がいた。
「まるで蝶の世界に迷い込んだようですね」
ぼくがそう言うと、老いらくさんが、うなずいていた。
蝶から受粉を手伝ってもらっている花たちは、自分たちにも劣らないほど美しい蝶たちに口づけをしてもらって、喜びで浮き浮きしているように思えた。蝶と花が繰り広げるメルヘンの世界に浸りながら、ミー先生も子どもたちも、うっとりとした顔をしながら、受粉の様子をじっと見ていた。
しばらくしてから、ミー先生が
「今回の旅は、そろそろ、これくらいにして、『雲の上の学校』に戻りましょう。旅を通して、いろいろなことを発見したり、珍しい体験をすることができたと思います」
と言った。子どもたちは、みんなうなずいていた。
それからまもなく、ミー先生と子どもたちは再び、タンチョウの背中に乗った。ぼくと老いらくさんとシャオパイも、タンチョウの背中に乗った。ミー先生が乗ったタンチョウが先陣をきって、空を飛び始めた。子どもたちが乗ったタンチョウが、そのあとに続き、ぼくと老いらくさんとシャオパイが乗ったタンチョウも、子どもたちのあとに続いた。
山の中腹付近から流れてきた雪解け水は、山のふもとで、いくつかの流れが合流して、川となり、水の量を増しながら、さらに下流へ向かって流れていた。木の上に積もっている雪は、地面にばさっと落ちて、だんだん、融けはじめていた。山の山頂付近を見ると、太陽の光を浴びて、雪がきらきらと輝いていて、まぶしくて、目を開けてはいられないほどだった。
「山頂は太陽から近いのに、どうして雪は融けないのかなあ」
王さんが、山頂を見ながら、素朴な疑問を投げかけていた。
「ずっと昔、この山の山頂付近は氷河になっていて、地面が、かちかちに凍っていました。雪線より上に降った雪は融けないのです」
ミー先生が、そう答えていた。
「氷河って何ですか。雪線って何ですか」
蒋さんが、聞いていた。
「氷河というのは高山や極地の高いところに積もった雪が、一年中融けないで、氷のかたまりとなって、川のように流れくだるものを言います。雪線というのは、降った雪が一年を通して融けないところと、融けるところの境界線を言います。雪線より上に降った雪は万年雪となって、太陽の光がどんなに強くても融けることはありません」
ミー先生が、そう説明していた。
蒋さんが、うなずいていた。
「高山の山頂付近は、一年を通して厚い雪に覆われています。そして雪は圧力によって氷になり、氷は重力の作用によって、地面に沿って移動していきます。この移動していく大きな氷が氷河と呼ばれています」
ミー先生がさらに、そう説明すると、子どもたちが、みんな、うなずいていた。
「川や池の源流は、雪線より下の雪が融けて作られていたのですね」
李くんが、ミー先生に聞いていた。
「そうです。そのとおりです」
ミー先生が、そう答えていた。
王さんはポケットのなかから望遠鏡を取り出して、山の頂上付近を見ながら
「昔、あそこに氷河があって、氷のかたまりが流れていたのですね」
と、聞いていた。
「そうです。そのとおりです。昔は今よりも、ずっと寒い時代でした」
ミー先生が、そう答えていた。
「雪線は海抜何メートルあたりにあるのですか」
蒋さんが聞いていた。
「雪線は山の地形や、風が吹いてくる方向によって異なっています。この山では五千メートル前後のところを雪線が不規則に走っています」
ミー先生が、そう答えていた。
ミー先生の説明を聞いて、ぼくは氷河や雪線が、どのようなものなのか想像していた。そのとき、望遠鏡で山の頂上付近を見ていた王さんが、びっくりしたような顔をしていた。
「あれっ、あそこにいるのは花顔鹿ではないの」
王さんが、そう言った。
「えっ、本当に?」
蒋さんも、びっくりしたような顔をしていた。蒋さんは王さんから望遠鏡を借りると、山頂付近をじっと見ていた。
「あ、本当だ。まちがいなく、あれは花顔鹿だ。いつのまに、あんなところに行っていたのだろう」
蒋さんは、けげんそうな顔をしていた。
「花顔鹿が何をしているか、分かるか」
李くんが聞いていた。
「ここからは遠すぎて、はっきりとは分からないわ。地面に顔をくっつけているように見えるので、雪を食べているのではないかしら」
蒋さんが、そう答えていた。
「花顔鹿は花を食べる動物だろう。どうして雪を食べるのだ」
李くんが反論していた。
「花がないから、雪を食べているのではないの」
唐さんが、そう言った。それを聞いて、ミー先生が
「暴風雪もやんだようだから、もう一度、タンチョウに乗って、山の頂上付近に戻ってみませんか。近くから見れば、花顔鹿が何を食べているのか分かりますから」
と言った。
「いいですね。タンチョウに乗って、空を飛ぶのは楽しいですから」
陳くんがそう言った。
それからまもなく、ミー先生と子どもたちは再び、タンチョウの背中に乗って、山の上のほうへ向かって飛び始めた。ぼくと老いらくさんとシャオパイも、ミー先生や子どもたちのあとに続いた。しばらくしてから、ぼくたちは花顔鹿がいるところに着いた。花顔鹿が食べていたのは雪ではなくて、花だった。黄色い花が雪の下から顔を出していた。
「この花の名前を知っていますか」
ミー先生が聞いていた。
「……」
返事は返ってこなかった。
「福寿草と言います」
ミー先生がそう答えていた。
「福寿草ですか?」
王さんが聞き返していた。
「そうです。福寿草です。福寿とは、幸福で長命なことを言います。元日草とも言います。名前にふさわしく、とてもおめでたい花です」
ミー先生がそう説明していた。
「人も、この花を食べることができますか」
李くんが聞いていた。
「人は、この花を食べることはできません。でも根をせんじて薬として使ったり、お正月の飾りものとして、玄関に飾る人がいます」
ミー先生がそう説明していた。
「ここはまだ寒くて雪が積もっているのに、雪のなかから顔を出して、屈強な花ですね」
唐さんが、感心したような声で、そう言った。それを聞いて、ミー先生が
「いつもは、もう少し暖かくなってから顔を出します。でも花顔鹿がやってきたので、歓迎するために、いつもより早く顔を出しているのかもしれません」
と、答えていた。それを聞いて、子どもたちは、顔を見合わせながら、にっこりと笑みを浮かべていた。
それからまもなく、陳くんが
「あれっ、花の上に蝶がいる。雪が積もっている時季に蝶が飛んでいるなんて思ってもいなかったよ」
と言った。それを聞いて、ほかの子どもたちが、うなずいていた。
「この蝶の名前を知っていますか」
ミー先生が聞いていた。
「……」
返事は返ってこなかった。
「絹蝶といいます。高山でしか見られない珍しい蝶です。絹のように透き通った羽をしていて、雪線の付近に生息している蝶です。雪が融けてからよく見られます。今はまだ雪は融けていませんが、福寿草が雪のなかから顔を出したから、福寿草を歓迎するために、一足はやく、成虫になって、ここへやってきたのかもしれません」
ミー先生が、そう言っていた。それを聞いて、子どもたちは、くつくつと笑っていた。
絹蝶は、透き通った羽を、ひらひらと動かしながら、福寿草の上を優雅に飛びまわっていた。花の上におりてきて、蜜を吸っている蝶もいた。太陽の光が絹蝶の透き通った羽に当たって、きらきらと輝いていて、とても美しかった。絹蝶という名前に、ふさわしい蝶だと、ぼくは思った。
唐さんが、ほっこりした顔をしながら
「福寿草が屈強な花なら、絹蝶は屈強な蝶だわ。こんなに厳しい自然環境のなかでも、めげないで頑張っているのを見ると、何だか勇気をもらって励まされているように感じるわ」
と言って、福寿草や絹蝶を、いとおしそうに見ていた。
しばらくしてから、ミー先生が子どもたちに
「みなさんたちを、これから『蝶谷』へ連れていきます」
と言った。
「『蝶谷』?」
子どもたちは、みんな、きょとんとした顔をしていた。
「『蝶谷』というのは、蝶がたくさん生息している谷のことです。たくさんの種類の蝶たちが、そこにいます。これから再びタンチョウに乗って、深い谷へおりていきます」
ミー先生が、そう言った。
それからまもなく、ミー先生と子どもたちはタンチョウに乗って空を飛び始めた。ぼくと老いらくさんとシャオパイもタンチョウに乗って、あとを追った。ミー先生が乗ったタンチョウが先導して、「人」の形に隊列を組みながら、タンチョウたちは一団となって『蝶谷』をめざして、山をくだっていった。上空から下を見ると、雪原のあちこちに、黄色い点のようなものが、ぽつぽつと見えた。点の上には、きらきらと光るものが動いているのも見えた。福寿草と絹蝶が互いに仲睦まじく親しみ合っているのだと思うと、ぼくには、とても微笑ましく思えた。
タンチョウが谷までくだってくると、山の上の景色とは違って、春の息吹のようなものが、ここかしこにあふれていた。木々の若葉が、すでに芽吹きはじめていた。ビオラやパンジーやジュリアンなど、いろいろな花も咲きはじめていた。赤やピンクや紫の花びらが柔らかな光をいっぱいに浴びながら、きらきらと輝いていた。花の上には、たくさんの蝶がいて、ひらひらと飛び交っていた。
「蝶は今、花の受粉を手伝っているのです」
ミー先生がそう言った。
蝶といっしょに、枯葉が、ひらひらと舞っているのが見えた。でもよく見ると枯葉は下に落ちないで、ずっと、舞い続けていた。
「あれっ、どうしてだろう?」
ぼくは不思議に思ったから、老いらくさんに聞いた。
「あれは枯葉ではないよ。蝶だよ」
老いらくさんが、そう答えた。
蝶のなかにカレハチョウという蝶がいるのを聞いたことがあったが、実際に目で見るのは初めてだった。ぼくは、てっきり枯葉だとばかり思っていた。
「笑い猫、ここには、いろんな蝶がいる。お前は蝶の名前を、どれくらい知っているか」
老いらくさんが聞いた。
「モンシロチョウ、モンキチョウ、アゲハチョウ、カレハチョウ、それから……」
ぼくには、それ以上、蝶の名前が出てこなかった。
「そのほか、オオムラサキ、カラスアゲハ、テングチョウ、ウラギンシジミ、カバマダラ、アオバセセリなどもいる」
老いらくさんが、そう言った。老いらくさんは博学多才なので、知識が豊富だ。
ぼくは感心した。
「あれっ、あの蝶は目玉が二つあって、きょろきょろ動かしている」
ぼくが、そう言うと、
「あれは目玉ではないよ。まだら模様だよ」
と、老いらくさんが教えてくれた。よく見ると、確かにそうだった。
「あっ、本当だ。目玉にそっくりだったから、ぼくは、てっきり目玉だとばかり思っていた」
ぼくは、そう答えた。
「敵の目をごまかして、びっくりさせるために、あのような模様をつけているのだよ」
老いらくさんが、そう答えた。それを聞いて、ぼくはうなずいた。
「ぼくが一番好きなのは、アゲハチョウです」
ぼくがそう言うと、老いらくさんが
「わしが一番好きな蝶はオオムラサキだ」
と、答えた。
ミー先生が言ったように、『蝶谷』には、たくさんの種類の蝶がいた。
「まるで蝶の世界に迷い込んだようですね」
ぼくがそう言うと、老いらくさんが、うなずいていた。
蝶から受粉を手伝ってもらっている花たちは、自分たちにも劣らないほど美しい蝶たちに口づけをしてもらって、喜びで浮き浮きしているように思えた。蝶と花が繰り広げるメルヘンの世界に浸りながら、ミー先生も子どもたちも、うっとりとした顔をしながら、受粉の様子をじっと見ていた。
しばらくしてから、ミー先生が
「今回の旅は、そろそろ、これくらいにして、『雲の上の学校』に戻りましょう。旅を通して、いろいろなことを発見したり、珍しい体験をすることができたと思います」
と言った。子どもたちは、みんなうなずいていた。
それからまもなく、ミー先生と子どもたちは再び、タンチョウの背中に乗った。ぼくと老いらくさんとシャオパイも、タンチョウの背中に乗った。ミー先生が乗ったタンチョウが先陣をきって、空を飛び始めた。子どもたちが乗ったタンチョウが、そのあとに続き、ぼくと老いらくさんとシャオパイが乗ったタンチョウも、子どもたちのあとに続いた。