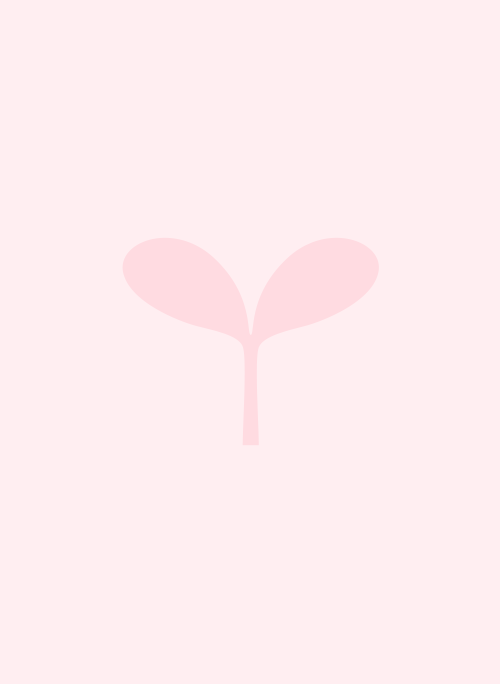天気……西の空が茜色に染まっているころ、東の空には月がもう出ていた。今夜の月は三日月だった。完全な日没まではまだ少し時間があったが、時間がたつととともに、三日月は明るさを増してくるように思えた。
真っ暗い洞窟のなかから、ようやく抜け出すことができたので、ぼくは、胸をほっと、なでおろした。外はすでに日が暮れかけていたが、空に浮かんでいる三日月から、ほろほろと、こぼれている明かりを見ると、地上にいることを実感して、うれしさが、こみあげてきた。外の景色は、これまでとは一変して、いろいろな木が、たくさん茂っていて、生命が息づいていることを、ひしひしと感じた。川の水が、ざあざあと流れている音も聞こえていた。
それからまもなく、ミー先生の声が聞こえた。
「みなさん、これから夕ご飯の準備をしましょう」
それを聞いて、柳くんが、けげんそうな顔をしていた。
「ここには何もないのに、どうやって、夕ご飯の準備をするのですか」
「大丈夫です。花顔鹿が、これから、みなさんたちを実がなっている木の下に連れていきます。その実を食べましょう」
ミー先生がそう答えた。
「分かりました」
柳くんが、そう言って、うなずいていた。
「どんな実を食べるのですか」
蒋さんが聞いていた。
「動物が食べる実を、わたしたちが食べても大丈夫ですか」
王さんが不安そうな顔をしながら、そう聞いていた。
「毒のあるもの以外なら何でもいいから、早く食べたいな」
李くんが、そう答えていた。
「わたしも早く食べたい」
唐さんが、そう言った。
子どもたちは、みんな、おなかを空かしているように見えた。
それからまもなく、ミー先生と子どもたちは、花顔鹿のあとについていった。花顔鹿は木がジャングルのように茂っているところに、分け入っていった。しばらくしてから花顔鹿は足をとめて、木の上を見上げた。木の枝に楕円形の実が、なっているのが見えた。
「みなさん、この木の名前を知っていますか」
ミー先生が子どもたちに聞いていた。
「……」
返事は、返ってこなかった。
「パンノキと言います。実がなっているのが見えますか」
ミー先生がそう言うと
「見えます」
蒋さんが、そう答えていた。
「あの実をちぎって、食べましょう」
ミー先生がそう言った。
「でも、どうやって、ちぎるのですか」
王さんが、けげんそうな顔をしていた。
「木登りが得意な人が、誰かいませんか」
ミー先生がそう聞くと、李くんが手を挙げた。
「では李くにお願いしましょう。落ちないように気をつけて登ってください」
ミー先生が李くんにお願いしていた。
「分かりました」
李くんは、そう答えると、それからまもなく、注意深く、木に登りはじめた。地上から三メートルほど登ったところに、実がなっていたので、李くんは慎重に、その実を木の枝からもぎとって、下に落としていた。下で待ち受けていた子どもたちが、実が落ちてくるたびに歓声をあげながら、手で受け取っていた。李くんは全部で七個のパンノキの実をちぎってから、下におりてきた。
「ありがとう。助かったわ」
ミー先生が李くんにお礼を言っていた。
「これから木の枝や枯葉を集めて、火をおこします。火がついたら、パンノキの実を、火であぶります。そのあと実を、手でちぎって食べます。ジャムをつけて食べたら、もっとおいしくなります」
ミー先生が食べ方の説明をしていた。それを聞いて、陳くんが
「ジャムは、ここにはないじゃありませんか」
と言って、口をとがらせていた。するとミー先生が首を横に振った。
「そんなことはありません。この近くにキイチゴの木があります。今、ちょうど、実がなっていますから、その実をすりつぶして、ジャムを作ることができます」
ミー先生がそう言うと、蒋さんが、うなずいていた。
「分かりました。では、これから、みんなでキイチゴの木を探しにいきましょう。案内してください」
蒋さんがそう答えていた。
「分かりました。ではわたしのあとについてきてください」
ミー先生は、そう答えてから、率先して、灌木のなかに分け入っていった。子どもたちも
あとに続いていた。ぼくと老いらくさんも、子どもたちのあとから、ついていった。花顔鹿は、このとき、どこかにふっと消えて姿が見えなくなっていた。
しばらくしてから、ミー先生が
「あっ、ありました。これがキイチゴの木です。バラ科の植物です。今、ちょうど実がなっています」
と言った。それを聞いて、子どもたちは、顔をキイチゴの木に近づけて、明るいだいだい色の実を、珍しそうに、じっと見ていた。
「いちごジャムや、いちご酒の原料として、キイチゴが使われていることは知っていたけども、キイチゴの実を実際に見るのは、わたしは初めてです」
王さんが、そう言っていた。
「そうですか。キイチゴは山野に自生していて、初夏に白い花が咲きます。茎と葉には、バラのようなとげがありますから、刺さらないように注意してください」
ミー先生がキイチゴの説明をしていた。
子どもたちは、そのあとさっそく、キイチゴの実を摘みはじめた。たちまちのうちに、子どもたちは、ポケットいっぱいにキイチゴの実を摘んで、満たされたような顔をしていた。キイチゴの実を、その場で、なまのまま、食べる子どももいて、おいしそうな顔をしていた。ポケットに入れて持ち帰ったキイチゴの実は、ミー先生が教えてくれたジャムの作り方にしたがって、いちごジャムにしていた。そのあとパンノキの実を火であぶって、焦げ目が軽くついたらジャムを塗って食べることにしていた。自分たちの手で、自然のなかから採ってきたばかりのパンノキの実と、キイチゴの実を、その場で食べるという、野趣にあふれた体験をしているので、子どもたちは喜びと感動で、目がきらきらと輝いていた。
そのとき、花顔鹿が、花をくわえて戻ってきた。それを見て、ミー先生が嬉々とした顔をしながら
「花顔鹿が、わたしたちにサラダの材料を持ってきてくれたわ」
と言った。それを聞いて、蔣さんが
「花を食べることができるのですか」
と、けげんそうな顔をしながら聞き返していた。
「もちろんですよ。この花は食べることができます。おいしいし、栄養価も高いです」
ミー先生がそう答えていた。
「これからわたしが、サラダの作り方を説明します。わたしの言うとおりにしてください」
ミー先生がそう言うと
「はーい」
という声が、あちこちから、あがった。
「まず、この花を手で細かく、ちぎってください。それからパンノキの葉の上に、ちぎったものを載せてください。そのあと、いちごジャムをつけて、パンノキの葉ごと食べてください。葉も栄養価が高いです。植物繊維が豊富で、健康によいサラダができあがります。たくさん食べてください」
ミー先生がそう言うと、子どもたちはみんな楽しそうな顔をしながら、ミー先生の指示にしたがって、サラダを作り始めた。しばらくすると、彩り豊かで、芳ばしいにおいが、ぷんぷんする新鮮なサラダがたくさんできあがった。
「主食と副食の準備は、これでできました。でもまだ、何か足りないものがあるとは思いませんか」
ミー先生がそう言うと、李くんが
「飲み物がありません」
と、答えていた。
「そうですね。食べ物だけあっても、食事がのどを通りませんよね」
ミー先生がそう答えていた。
「でも、ここには飲み物は何もないじゃありませんか」
陳くんが、そう答えていた。
「大丈夫です。樹液を飲むことができます」
ミー先生がそう言った。
「樹液?」
陳くんが、けげんそうな顔をしていた。
「そう、樹液です。樹木の皮からにじみ出た液体が樹液です。樹液は飲むことができます。栄養価が高いです」
ミー先生がそう言うと、子どもたちは、口をぽかんと開けて、あっけにとられたような顔をしていた。樹液を昆虫が吸うことは、ぼくも知っていたが、人が飲むことができるとは、ぼくは、まったく思ってもいなかった。老いらくさんに聞いたら、老いらくさんも、ぼくと同じように、樹液はセミやカブトムシのような昆虫が吸う飲み物だと思っているようだった。
「樹液は、木から出るお乳のようなものですか」
王さんが面白いことを言った。
「そうですね。そのようなものと考えてもいいです」
ミー先生が、くすっと笑いながら、そう答えていた。
「牛乳や、羊乳や、赤ちゃんが飲むお乳は知っているけども、木乳があるとは思ってもいなかったわ」
蒋さんが、あぜんとした顔をしていた。
「飲んでみたいですか」
ミー先生がそう言うと、子どもたちは、みんな、うなずいていた。
「分かりました。ではみなさん、これからわたしのあとに、ついてきてください」
ミー先生はそう言うと、子どもたちを再び、灌木のなかに連れていった。しばらくしてからミー先生は、幹が白い木の前で足をとめた。
「みなさん、この木はミルクの木です。普通の木と違って、木の幹が白いです。幹のなかにミルクがいっぱい入っているから、このような色をしています」
ミー先生がそう説明していた。
「幹の上にキノコが生えていますね」
蔣さんがそう言った。
「シロキクラゲです。純白色で、半透明のゼリー質をしていて、食べることができるキノコです」
ミー先生の説明に、子どもたちはみんな真剣な顔をして聞き入っていた。
「シロキクラゲは、樹液を栄養分として吸い込んで、体のなかにたくさん蓄えています。シロキクラゲを採って、しぼったら、ミルクのような白い汁がたくさん出てきます」
ミー先生がそう言ったので、李くんが
「へえー、そうなのか」
と、感心したような声で、うなずいていた。
「試しに一つ、採ってみてもいいですか」
王さんが聞いていた。
「いいですよ」
ミー先生がそう言ったので、王さんはさっそく、シロキクラゲを一つ、採って、手で、キノコのかさの部分を、しぼっていた。するとミー先生が言ったとおりに、ミルクのような白い汁が、じゅるじゅると出てきた。王さんが、指先に汁をちょっとつけて、なめていた。
「おいしい。まるで、牛乳のような味がするわ」
王さんが歓喜の声をあげていた。それを聞いて、ほかの子どもたちも、次々とシロキクラゲを採ってから、かさの部分を口にくわえて、歯で軽くかんでから、舌でぺろぺろなめていた。
「どうですか。おいしいですか」
ミー先生が聞いていた。
「ええ、とてもおいしいです。採り立てのキノコを、なまでかじるのは初めてだけど、かさも汁もこんなにおいしいとは思ってもいなかったです」
唐さんが、そう言った。
「キノコは健康によい食べ物だし、採り立てのキノコは味もいいし、最高だね」
李くんが、そう言った。
「キノコから出た汁をお茶の代わりに飲むと、食も進みそうだわ」
蒋さんが、そう言った。
子どもたちは、みんな幸福感に満たされたような顔をしながら、キノコから出た汁を吸っていた。
「さあ、これで主食も副食も飲み物も全部そろったから、これから、みんなで夕食をいただくことにしましょう」
ミー先生がそう言ったので、子どもたちは、うれしそうな顔をしていた。
ミー先生と子どもたちは、それからまもなく、大きな木の周りに車座に座って、ジャムを塗ったパンノキの実や、サラダを食べたり、シロキクラゲをしぼった汁を飲んだりして、夕食を取り始めた。辺りはもうすでにとっぷりと日が暮れていて、空には三日月が、こうこうと輝いていた。
「月あかりのもとで夕食をいただくのはロマンティックですね」
月を見あげながら、蒋さんがそう言っていた。
ぼくと老いらくさんは、ミー先生と子どもたちが楽しそうに食事をしているところを、木の陰から、こっそり見ていた。ぼくの心は、それだけでも十分、満たされていた。幸せのおすそわけをしてもらっているように思えたからだ。でも老いらくさんは、ぼくとは違って、じりじりしていた。子どもたちが食べ残したものを、おすそわけとして、おなかのなかに入れないと満たされたようには思えないようだった。そのために子どもたちの食が進んで、食べ物がだんだん少なくなっていくのを見ながら
「子どもたちが全部食べてしまったら、わしや,お前が、食べるものがなくなってしまう」
と言って、心配していた。
「大丈夫ですよ。子どもたちやミー先生が食べたり、飲んだりしているものは、みんな、この山のなかから採ってきたものばかりだから、残り物がなかったら、あとで、採りにいきましょうよ」
ぼくは老いらくさんに、そう言った。
「夜がだいぶ更けてきたから、これから山のなかに分け入って探しに行くのは大変だぞ」
老いらくさんは渋い顔をしながら、そう答えた。
子どもたちは夕ご飯を食べたあと、寝る準備を始めた。子どもたちはみんな、折り畳み式のハンモックを、リュックに入れて持ってきていたので、つり方をミー先生から教わって、木の間にしっかりとかけていた。夜風が吹いてハンモックが心地よく揺れるなか、子どもたちはハンモックのなかに入って、眠り始めた。月の光が、こうこうと輝いていて、子どもたちを楽しい夢にいざなっているように思えた。
老いらくさんが心配していたとおり、子どもたちは食べ物を全部平らげてしまっていたので、ぼくと老いらくさんは、月明りに照らされながら、山のなかに分け入って、食べ物を探しに出かけた。まずパンノキの下まで行った。木の上を見あげなから、ぼくは老いらくさんに
「これから、いっしょに登りましょう」
と、さそった。すると老いらくさんは気乗りがしないような顔をしながら
「わしは年寄りだから、あんなに高いところまで実を採りに行くことはできないよ」
と答えた。
「分かりました。では、ぼくが登って、上から実を落としますから、あとでいっしょに食べましょう」
ぼくがそう言うと、老いらくさんがうなずいた。
それからまもなく、ぼくは落ちないように気をつけながら、木の上に登っていって、大きくて、よく熟したパンノキの実を二つちぎって下に落とした。そのあと下におりてきて、老いらくさんといっしょに食べた。実は柔らかくて、とてもおいしかった。ライチのような味がした。
「あっ、あそこを見ろ」
パンノキの実を食べているときに、老いらくさんが、不意に食べるのをやめて、声を低く抑えながら、そう言った。
(何だろう?)
ぼくはそう思って、老いらくさんが指さしたところを見た。すると、そこには昨日の夜現れた、あの人影がまた現れていた。謎に包まれた神秘的な人影がピンクと黒の袋を手に持って、木々のあいだを、ひらひらと揺れながら、行ったり来たりしていた。人影はやがて子どもたちが寝ているハンモックのなかに入っていった。しばらくしてから人影はハンモックのなかから出てきて、次のハンモックへ移っていた。ハンモックから出てくるたびに、ピンクの袋だけが、だんだん膨れてきていることに、ぼくも老いらくさんも気がついた。人影は全部のハンモックを回ると、そのあと、どこかへ消えていって、姿が見えなくなった。
真っ暗い洞窟のなかから、ようやく抜け出すことができたので、ぼくは、胸をほっと、なでおろした。外はすでに日が暮れかけていたが、空に浮かんでいる三日月から、ほろほろと、こぼれている明かりを見ると、地上にいることを実感して、うれしさが、こみあげてきた。外の景色は、これまでとは一変して、いろいろな木が、たくさん茂っていて、生命が息づいていることを、ひしひしと感じた。川の水が、ざあざあと流れている音も聞こえていた。
それからまもなく、ミー先生の声が聞こえた。
「みなさん、これから夕ご飯の準備をしましょう」
それを聞いて、柳くんが、けげんそうな顔をしていた。
「ここには何もないのに、どうやって、夕ご飯の準備をするのですか」
「大丈夫です。花顔鹿が、これから、みなさんたちを実がなっている木の下に連れていきます。その実を食べましょう」
ミー先生がそう答えた。
「分かりました」
柳くんが、そう言って、うなずいていた。
「どんな実を食べるのですか」
蒋さんが聞いていた。
「動物が食べる実を、わたしたちが食べても大丈夫ですか」
王さんが不安そうな顔をしながら、そう聞いていた。
「毒のあるもの以外なら何でもいいから、早く食べたいな」
李くんが、そう答えていた。
「わたしも早く食べたい」
唐さんが、そう言った。
子どもたちは、みんな、おなかを空かしているように見えた。
それからまもなく、ミー先生と子どもたちは、花顔鹿のあとについていった。花顔鹿は木がジャングルのように茂っているところに、分け入っていった。しばらくしてから花顔鹿は足をとめて、木の上を見上げた。木の枝に楕円形の実が、なっているのが見えた。
「みなさん、この木の名前を知っていますか」
ミー先生が子どもたちに聞いていた。
「……」
返事は、返ってこなかった。
「パンノキと言います。実がなっているのが見えますか」
ミー先生がそう言うと
「見えます」
蒋さんが、そう答えていた。
「あの実をちぎって、食べましょう」
ミー先生がそう言った。
「でも、どうやって、ちぎるのですか」
王さんが、けげんそうな顔をしていた。
「木登りが得意な人が、誰かいませんか」
ミー先生がそう聞くと、李くんが手を挙げた。
「では李くにお願いしましょう。落ちないように気をつけて登ってください」
ミー先生が李くんにお願いしていた。
「分かりました」
李くんは、そう答えると、それからまもなく、注意深く、木に登りはじめた。地上から三メートルほど登ったところに、実がなっていたので、李くんは慎重に、その実を木の枝からもぎとって、下に落としていた。下で待ち受けていた子どもたちが、実が落ちてくるたびに歓声をあげながら、手で受け取っていた。李くんは全部で七個のパンノキの実をちぎってから、下におりてきた。
「ありがとう。助かったわ」
ミー先生が李くんにお礼を言っていた。
「これから木の枝や枯葉を集めて、火をおこします。火がついたら、パンノキの実を、火であぶります。そのあと実を、手でちぎって食べます。ジャムをつけて食べたら、もっとおいしくなります」
ミー先生が食べ方の説明をしていた。それを聞いて、陳くんが
「ジャムは、ここにはないじゃありませんか」
と言って、口をとがらせていた。するとミー先生が首を横に振った。
「そんなことはありません。この近くにキイチゴの木があります。今、ちょうど、実がなっていますから、その実をすりつぶして、ジャムを作ることができます」
ミー先生がそう言うと、蒋さんが、うなずいていた。
「分かりました。では、これから、みんなでキイチゴの木を探しにいきましょう。案内してください」
蒋さんがそう答えていた。
「分かりました。ではわたしのあとについてきてください」
ミー先生は、そう答えてから、率先して、灌木のなかに分け入っていった。子どもたちも
あとに続いていた。ぼくと老いらくさんも、子どもたちのあとから、ついていった。花顔鹿は、このとき、どこかにふっと消えて姿が見えなくなっていた。
しばらくしてから、ミー先生が
「あっ、ありました。これがキイチゴの木です。バラ科の植物です。今、ちょうど実がなっています」
と言った。それを聞いて、子どもたちは、顔をキイチゴの木に近づけて、明るいだいだい色の実を、珍しそうに、じっと見ていた。
「いちごジャムや、いちご酒の原料として、キイチゴが使われていることは知っていたけども、キイチゴの実を実際に見るのは、わたしは初めてです」
王さんが、そう言っていた。
「そうですか。キイチゴは山野に自生していて、初夏に白い花が咲きます。茎と葉には、バラのようなとげがありますから、刺さらないように注意してください」
ミー先生がキイチゴの説明をしていた。
子どもたちは、そのあとさっそく、キイチゴの実を摘みはじめた。たちまちのうちに、子どもたちは、ポケットいっぱいにキイチゴの実を摘んで、満たされたような顔をしていた。キイチゴの実を、その場で、なまのまま、食べる子どももいて、おいしそうな顔をしていた。ポケットに入れて持ち帰ったキイチゴの実は、ミー先生が教えてくれたジャムの作り方にしたがって、いちごジャムにしていた。そのあとパンノキの実を火であぶって、焦げ目が軽くついたらジャムを塗って食べることにしていた。自分たちの手で、自然のなかから採ってきたばかりのパンノキの実と、キイチゴの実を、その場で食べるという、野趣にあふれた体験をしているので、子どもたちは喜びと感動で、目がきらきらと輝いていた。
そのとき、花顔鹿が、花をくわえて戻ってきた。それを見て、ミー先生が嬉々とした顔をしながら
「花顔鹿が、わたしたちにサラダの材料を持ってきてくれたわ」
と言った。それを聞いて、蔣さんが
「花を食べることができるのですか」
と、けげんそうな顔をしながら聞き返していた。
「もちろんですよ。この花は食べることができます。おいしいし、栄養価も高いです」
ミー先生がそう答えていた。
「これからわたしが、サラダの作り方を説明します。わたしの言うとおりにしてください」
ミー先生がそう言うと
「はーい」
という声が、あちこちから、あがった。
「まず、この花を手で細かく、ちぎってください。それからパンノキの葉の上に、ちぎったものを載せてください。そのあと、いちごジャムをつけて、パンノキの葉ごと食べてください。葉も栄養価が高いです。植物繊維が豊富で、健康によいサラダができあがります。たくさん食べてください」
ミー先生がそう言うと、子どもたちはみんな楽しそうな顔をしながら、ミー先生の指示にしたがって、サラダを作り始めた。しばらくすると、彩り豊かで、芳ばしいにおいが、ぷんぷんする新鮮なサラダがたくさんできあがった。
「主食と副食の準備は、これでできました。でもまだ、何か足りないものがあるとは思いませんか」
ミー先生がそう言うと、李くんが
「飲み物がありません」
と、答えていた。
「そうですね。食べ物だけあっても、食事がのどを通りませんよね」
ミー先生がそう答えていた。
「でも、ここには飲み物は何もないじゃありませんか」
陳くんが、そう答えていた。
「大丈夫です。樹液を飲むことができます」
ミー先生がそう言った。
「樹液?」
陳くんが、けげんそうな顔をしていた。
「そう、樹液です。樹木の皮からにじみ出た液体が樹液です。樹液は飲むことができます。栄養価が高いです」
ミー先生がそう言うと、子どもたちは、口をぽかんと開けて、あっけにとられたような顔をしていた。樹液を昆虫が吸うことは、ぼくも知っていたが、人が飲むことができるとは、ぼくは、まったく思ってもいなかった。老いらくさんに聞いたら、老いらくさんも、ぼくと同じように、樹液はセミやカブトムシのような昆虫が吸う飲み物だと思っているようだった。
「樹液は、木から出るお乳のようなものですか」
王さんが面白いことを言った。
「そうですね。そのようなものと考えてもいいです」
ミー先生が、くすっと笑いながら、そう答えていた。
「牛乳や、羊乳や、赤ちゃんが飲むお乳は知っているけども、木乳があるとは思ってもいなかったわ」
蒋さんが、あぜんとした顔をしていた。
「飲んでみたいですか」
ミー先生がそう言うと、子どもたちは、みんな、うなずいていた。
「分かりました。ではみなさん、これからわたしのあとに、ついてきてください」
ミー先生はそう言うと、子どもたちを再び、灌木のなかに連れていった。しばらくしてからミー先生は、幹が白い木の前で足をとめた。
「みなさん、この木はミルクの木です。普通の木と違って、木の幹が白いです。幹のなかにミルクがいっぱい入っているから、このような色をしています」
ミー先生がそう説明していた。
「幹の上にキノコが生えていますね」
蔣さんがそう言った。
「シロキクラゲです。純白色で、半透明のゼリー質をしていて、食べることができるキノコです」
ミー先生の説明に、子どもたちはみんな真剣な顔をして聞き入っていた。
「シロキクラゲは、樹液を栄養分として吸い込んで、体のなかにたくさん蓄えています。シロキクラゲを採って、しぼったら、ミルクのような白い汁がたくさん出てきます」
ミー先生がそう言ったので、李くんが
「へえー、そうなのか」
と、感心したような声で、うなずいていた。
「試しに一つ、採ってみてもいいですか」
王さんが聞いていた。
「いいですよ」
ミー先生がそう言ったので、王さんはさっそく、シロキクラゲを一つ、採って、手で、キノコのかさの部分を、しぼっていた。するとミー先生が言ったとおりに、ミルクのような白い汁が、じゅるじゅると出てきた。王さんが、指先に汁をちょっとつけて、なめていた。
「おいしい。まるで、牛乳のような味がするわ」
王さんが歓喜の声をあげていた。それを聞いて、ほかの子どもたちも、次々とシロキクラゲを採ってから、かさの部分を口にくわえて、歯で軽くかんでから、舌でぺろぺろなめていた。
「どうですか。おいしいですか」
ミー先生が聞いていた。
「ええ、とてもおいしいです。採り立てのキノコを、なまでかじるのは初めてだけど、かさも汁もこんなにおいしいとは思ってもいなかったです」
唐さんが、そう言った。
「キノコは健康によい食べ物だし、採り立てのキノコは味もいいし、最高だね」
李くんが、そう言った。
「キノコから出た汁をお茶の代わりに飲むと、食も進みそうだわ」
蒋さんが、そう言った。
子どもたちは、みんな幸福感に満たされたような顔をしながら、キノコから出た汁を吸っていた。
「さあ、これで主食も副食も飲み物も全部そろったから、これから、みんなで夕食をいただくことにしましょう」
ミー先生がそう言ったので、子どもたちは、うれしそうな顔をしていた。
ミー先生と子どもたちは、それからまもなく、大きな木の周りに車座に座って、ジャムを塗ったパンノキの実や、サラダを食べたり、シロキクラゲをしぼった汁を飲んだりして、夕食を取り始めた。辺りはもうすでにとっぷりと日が暮れていて、空には三日月が、こうこうと輝いていた。
「月あかりのもとで夕食をいただくのはロマンティックですね」
月を見あげながら、蒋さんがそう言っていた。
ぼくと老いらくさんは、ミー先生と子どもたちが楽しそうに食事をしているところを、木の陰から、こっそり見ていた。ぼくの心は、それだけでも十分、満たされていた。幸せのおすそわけをしてもらっているように思えたからだ。でも老いらくさんは、ぼくとは違って、じりじりしていた。子どもたちが食べ残したものを、おすそわけとして、おなかのなかに入れないと満たされたようには思えないようだった。そのために子どもたちの食が進んで、食べ物がだんだん少なくなっていくのを見ながら
「子どもたちが全部食べてしまったら、わしや,お前が、食べるものがなくなってしまう」
と言って、心配していた。
「大丈夫ですよ。子どもたちやミー先生が食べたり、飲んだりしているものは、みんな、この山のなかから採ってきたものばかりだから、残り物がなかったら、あとで、採りにいきましょうよ」
ぼくは老いらくさんに、そう言った。
「夜がだいぶ更けてきたから、これから山のなかに分け入って探しに行くのは大変だぞ」
老いらくさんは渋い顔をしながら、そう答えた。
子どもたちは夕ご飯を食べたあと、寝る準備を始めた。子どもたちはみんな、折り畳み式のハンモックを、リュックに入れて持ってきていたので、つり方をミー先生から教わって、木の間にしっかりとかけていた。夜風が吹いてハンモックが心地よく揺れるなか、子どもたちはハンモックのなかに入って、眠り始めた。月の光が、こうこうと輝いていて、子どもたちを楽しい夢にいざなっているように思えた。
老いらくさんが心配していたとおり、子どもたちは食べ物を全部平らげてしまっていたので、ぼくと老いらくさんは、月明りに照らされながら、山のなかに分け入って、食べ物を探しに出かけた。まずパンノキの下まで行った。木の上を見あげなから、ぼくは老いらくさんに
「これから、いっしょに登りましょう」
と、さそった。すると老いらくさんは気乗りがしないような顔をしながら
「わしは年寄りだから、あんなに高いところまで実を採りに行くことはできないよ」
と答えた。
「分かりました。では、ぼくが登って、上から実を落としますから、あとでいっしょに食べましょう」
ぼくがそう言うと、老いらくさんがうなずいた。
それからまもなく、ぼくは落ちないように気をつけながら、木の上に登っていって、大きくて、よく熟したパンノキの実を二つちぎって下に落とした。そのあと下におりてきて、老いらくさんといっしょに食べた。実は柔らかくて、とてもおいしかった。ライチのような味がした。
「あっ、あそこを見ろ」
パンノキの実を食べているときに、老いらくさんが、不意に食べるのをやめて、声を低く抑えながら、そう言った。
(何だろう?)
ぼくはそう思って、老いらくさんが指さしたところを見た。すると、そこには昨日の夜現れた、あの人影がまた現れていた。謎に包まれた神秘的な人影がピンクと黒の袋を手に持って、木々のあいだを、ひらひらと揺れながら、行ったり来たりしていた。人影はやがて子どもたちが寝ているハンモックのなかに入っていった。しばらくしてから人影はハンモックのなかから出てきて、次のハンモックへ移っていた。ハンモックから出てくるたびに、ピンクの袋だけが、だんだん膨れてきていることに、ぼくも老いらくさんも気がついた。人影は全部のハンモックを回ると、そのあと、どこかへ消えていって、姿が見えなくなった。