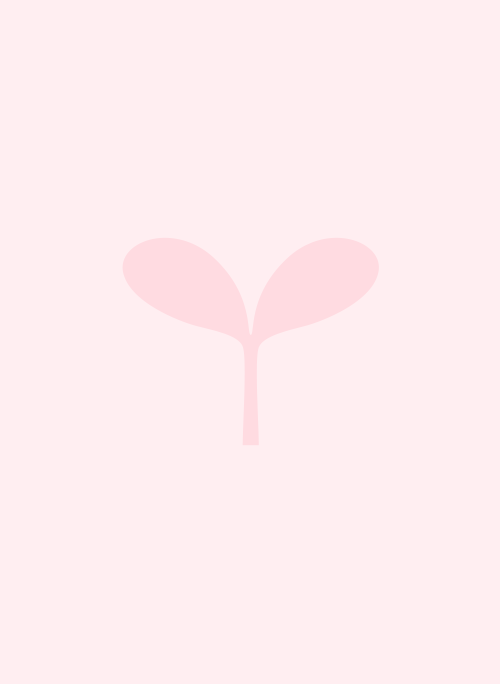天気……高山の天気は変化が激しくて予測しづらい。晴れているかと思えば、にわかに空が曇ってきて、激しい雨がざあざあ降ってくることもある。ついさっきまで、太陽の光が明るく降り注いでいたので、今日はよい天気だと思っていたら、たちまちのうちに、空全体が黒い雲に覆われて不穏な空模様に変わった。
夜が明けてからしばらく、うとうとしていたら、かすかにシャオパイの声が聞こえたような気がした。ぼくは、はっとして目を覚ました。(何だろう)と思って、声がしているほうを見ると、子どもたちに、起床を呼び掛けている声だった。
「老いらくさん、早く起きて。子どもたちがこれから、どこかへ出かけていくよ。あとをついていきましょう」
ぼくは老いらくさんに、そう言った。
「どこへ行くのかなあ」
老いらくさんが眠そうな目をこすりながら、そうつぶやいた。
「ぼくにもよく分かりません。でもたぶん、どこかでミー先生が待っていると思います」ぼくはそう答えた。
「分かった。では、わしも子どもたちのあとからついていくことにしよう」
老いらくさんが、あくびをしながら起き上がった。
ぼくと老いらくさんは、子どもたちに気づかれないように、少し距離を置きながら、あとをついていった。子どもたちは川辺に向かっていた。川辺にミー先生が、からかさを持って立っているのが見えた。さわやかな朝風が、そよそよと吹いていて、ミー先生のしなやかな長い髪が風に揺れていた。ミー先生はグリーンのセーターに、洒脱な花柄のロングスカートをはいていた。昨日の夜、見た、あの人影も同じような服装をしていたので、あれは間違いなくミー先生だったと、ぼくは確信した。
シャオパイが、ぼくたちに気がついて、やってきた。
「ミー先生はもうすぐ一時間目の授業を始めます。見学するのはいいですが、くれぐれも気づかれないようにしてください」
シャオパイがそう言った。
「分かった。こちらからは見えるけれども、向こうからは見えないところに隠れながら、こっそり見学するよ」
ぼくはそう答えた。
子どもたちはミー先生のすぐ近くまで来ると、「おはようございます」と言って、あいさつをしていた。そのあと子どもたちは川辺で軽く体を動かして、ミー先生といっしょに太極拳をしていた。ぼくと老いらくさんとシャオパイも、見様見真似で太極拳をした。太極拳が終わると、ミー先生は、からかさを開いて、柄についているボタンの一つを押した。すると、それからまもなく、風が急に強くなってきて、狂ったように、びゅんびゅん吹きはじめた。
(空へまた吹き飛ばされるかもしれない)
そう思うと、ぼくは怖くなった。飛ばされる前に老いらくさんの体をしっかり抱いて、離れ離れにならないようにした。ぼくは目をつむって、嵐に備えていた。ところが、今回はなぜかこれまでとは違って、空へ吹き飛ばされなかった。意識を失うこともなかった。しばらくしてからぼくは再び、目を開けて、周りをみた。すると狂ったような強風はやんでいて、穏やかな風に戻っていた。ミー先生も、子どもたちも、シャオパイもすぐ近くにいた。
でも強風がやんだあと、びっくりしたことがあった。これまで見たこともない不思議な動物が近くにいるのに気がついたからだ。体は鹿のような形をしていて、頭の上には角が二本生えていた。でも普通の鹿とは違っていた。顔全体を取り囲むように、長い毛が生えていて、まるで花びらのなかから顔が出ているように見えたからだ。
(ぼくが目をつむっている間に、ミー先生が、からかさを使って連れてきたのだろうか)
ぼくはそう思った。
「老いらくさん、これは何という動物ですか」
ぼくは老いらくさんに聞いた。老いらくさんは博学多才のネズミだから、もしかしたら名前を知っているかもしれないと思った。ところが老いらくさんも首をかしげていた。
「わしも、こんな動物は初めて見たよ」
老いらくさんは、そう言って口をぽかんと開けながら、不思議な動物を見ていた。
「ミー先生が、からかさを使って連れてきたのではないかと、ぼくは思っているのですが」
ぼくがそう言うと、老いらくさんがうなずいた。
「そうかもしれないな。ミー先生は唐の時代からタイムスリップしてきた人ではないかと、わしは思っているから、あの動物も、いっしょに連れてきたのではないだろうか」
老いらくさんがそう言った。
「そうかもしれませんね」
ぼくは相づちを打った。
「わしはあの動物を実際に見たことはないが、絶滅した昔の動物のなかに、確か、あのような動物がいたという話を聞いたことがある。名前は確か、えーと……えーと……、確か……、確か……」
老いらくさんは、動物の名前を、なかなか思い出せないでいた。
子どもたちも、これまで見たことがない動物が目の前にいたので、びっくりしていた。
ミー先生が、子どもたちに
「これは花顔鹿という動物です。これから、この花顔鹿が、みなさんたちを川の源流に案内してくれます」
と、言った。それを聞いて、子どもたちの間から、うれしそうな歓声があがった。
花顔鹿は、それからまもなく、川の上流のほうへ向かって、登り始めた。ミー先生と子どもたちも、そのあとに続いて、川の流れとは逆方向に登っていった。川のせせらぎの音が心地よく響いていて、とても気持ちがよかった。ぼくと老いらくさんも、ミー先生や子どもたちに気づかれないように注意しながら、あとに続いた。登るにしたがって、地勢がだんだん険しくなってきて、息があがってきた。しかしそれにもめげないで、ぼくと老いらくさんは、ミー先生や子どもたちのあとに続いて登っていった。
川の流れは比較的緩やかで、ゆったりと流れていた。川のそばにある坂が登りにくいところは遠回りをしながら慎重に登っていった。道がでこぼこしていて歩きにくかったが、(川の源流はどんなところだろう)という期待感のほうが大きかったので、みんな、頑張って歩いていた。老いらくさんは年を取っているので、さすがに少々、きつさや疲れを感じているようだった。ぼくは気を利かせて、老いらくさんを背中に乗せてあげた。
小一時間ほど歩いたとき、これまで登り続けてきた川沿いの山道の両側に広がっていた森林が途切れて、視界がぱっと開けた。そこから先には、川も道もなくて、目の前には滝が見えるだけ。その滝の上から水が勢いよく流れ落ちていた。
「みなさん、やっと着きましたよ。ここから先には道も川もありません。滝の上から水が流れてきています」
ミー先生がそう言った。それを聞いて、柳くんが
「滝の上から水が流れているとは思ってもいなかったな」
と言った。
「わたしもよ。山の深いところの地下から水が湧き出ていて、そこから水が流れていると思っていたわ」
蒋さんが、そう答えていた。
それからまもなく、花顔鹿が滝のすぐ真下まで歩いていった。それを見て、ミー先生が「わたしたちも行ってみましょう」
と言って、子どもたちに、うながしていた。ミー先生の呼びかけに応じて、子どもたちは水しぶきが飛び散って、辺り一面の岩肌を濡らしているところまで行って、雄大な自然の景観を体感していた。ぼくと老いらくさんは、体が濡れるのはあまり好きではなかったから、少し離れたところから、その様子を見ていた。
するとそれからまもなく、思わぬことが起きた。花顔鹿とミー先生と子どもたちの姿が急に見えなくなったからだ。
(まさか、滝つぼのなかに落ちたのではないだろうか)
ぼくは、そう思って、目の前が一瞬、真っ暗になった。もし本当にそうだとしたら、大変な事故が起きたことになる。ぼくはそう思って、おろおろしていた。暗鬱な顔をしながら、ぼくは老いらくさんを見た。すると老いらくさんは意外と落ち着いた顔をしていた。
「笑い猫、何をそんなに暗い顔をしているのだ。大丈夫だよ。滝つぼに落ちたのではないよ」
老いらくさんがそう言った。
「でも姿が急に見えなくなったではありませんか」
ぼくは泣きそうな顔をしながら老いらくさんに問いかけた。
「ミー先生や子どもたちが、滝つぼのなかに落ちる音や悲鳴はしなかったではないか。ミー先生が、子どもたちを、入水自殺させるわけがないよ」
老いらくさんが、そう答えた。
「だったら、どこへ行ったのですか」
ぼくは老いらくさんに問いただした。
「わしはこれまで、滝を何度か見たことがある。滝の後ろに洞窟があることがよくあった。水がぽたぽたと、したたり落ちていて、薄暗くて、神秘的な空間が、洞窟のなかに広がっていた。もしかしたら、ここにも、そのような洞窟があることに気がついて、ミー先生や花顔鹿が子どもたちを連れて、見学に行ったのかもしれない」
老いらくさんが、そう言った。
それを聞いて、ぼくは、そうであってほしいと、心から願った。居ても立ってもいられなくなったので、ぼくはすぐに、老いらくさんといっしょに滝の後ろに回っていった。すると何と、老いらくさんが言ったとおりに、滝の後ろに洞窟があって、洞窟のなかから、子どもたちの声が聞こえてきた。それを聞いて、ミー先生や子どもたちが滝つぼに落ちたのではないことが分かって、ぼくは、ほっとした。洞窟の入口の前まで来て、なかをのぞくと真っ暗で、何も見えなかった。子どもたちの声が、暗やみのなかから伝わってきたので、それだけが救いだった。
「なんだか怖いわ。真っ暗で、しーとしていて、まるで死の世界に来たようだわ」
王さんの声が聞こえてきた。李くんがそのあと
「この洞窟は、どこまでも続いていて、もう出られなくなるのではないかな」
と言って、案じていた。
子どもたちは、みんな不安におびえているようだった。
「大丈夫です。心配は要りません。花顔鹿は、けっして、みなさんを危ない目に遭わせることはしません。信頼してください」
ミー先生が子どもたちを励ましていた。
「分かりました」
唐さんがそう答えていた。それからまもなく、子どもたちの声は聞こえなくなった。遠ざかっていく足音だけが聞こえてきた。ミー先生も子どもたちも、花顔鹿のあとに続いて、さらに奥のほうに黙々と進んでいるように思えた。ぼくと老いらくさんも、洞窟のなかに入り、ミー先生や子どもたちのあとを黙々と追っていた。真っ暗いなかを、どれくらい歩いたか分からないが、不意に
「あっ、光だ。あそこに出口が見える」
という、李くんのうれしそうな声が聞こえてきた。ぼくが遠くのほうを見ると、確かに、ずっと先に、星のような小さな光が見えていた。老いらくさんに、そのことを話すと、老いらくさんも、安堵の胸をなでおろしていた。希望のあかりを見いだしたことで、子どもたちも、ミー先生も、ぼくたちもみんな元気をもらい、足を速めながら、あかりのほうを目指して歩いていった。前に行けば行くほど、光がだんだん強く差し込んできて、辺りが少しずつ明るくなってきた。そしてついに洞窟の出口に到達することができた。洞窟の外に出たとたん、まばゆくて目を開けていられないほどの強い光が差し込んできた。夕日だった。夕日がきらきらと輝いていて、西の空が茜色に染まっているのが見えた。
夜が明けてからしばらく、うとうとしていたら、かすかにシャオパイの声が聞こえたような気がした。ぼくは、はっとして目を覚ました。(何だろう)と思って、声がしているほうを見ると、子どもたちに、起床を呼び掛けている声だった。
「老いらくさん、早く起きて。子どもたちがこれから、どこかへ出かけていくよ。あとをついていきましょう」
ぼくは老いらくさんに、そう言った。
「どこへ行くのかなあ」
老いらくさんが眠そうな目をこすりながら、そうつぶやいた。
「ぼくにもよく分かりません。でもたぶん、どこかでミー先生が待っていると思います」ぼくはそう答えた。
「分かった。では、わしも子どもたちのあとからついていくことにしよう」
老いらくさんが、あくびをしながら起き上がった。
ぼくと老いらくさんは、子どもたちに気づかれないように、少し距離を置きながら、あとをついていった。子どもたちは川辺に向かっていた。川辺にミー先生が、からかさを持って立っているのが見えた。さわやかな朝風が、そよそよと吹いていて、ミー先生のしなやかな長い髪が風に揺れていた。ミー先生はグリーンのセーターに、洒脱な花柄のロングスカートをはいていた。昨日の夜、見た、あの人影も同じような服装をしていたので、あれは間違いなくミー先生だったと、ぼくは確信した。
シャオパイが、ぼくたちに気がついて、やってきた。
「ミー先生はもうすぐ一時間目の授業を始めます。見学するのはいいですが、くれぐれも気づかれないようにしてください」
シャオパイがそう言った。
「分かった。こちらからは見えるけれども、向こうからは見えないところに隠れながら、こっそり見学するよ」
ぼくはそう答えた。
子どもたちはミー先生のすぐ近くまで来ると、「おはようございます」と言って、あいさつをしていた。そのあと子どもたちは川辺で軽く体を動かして、ミー先生といっしょに太極拳をしていた。ぼくと老いらくさんとシャオパイも、見様見真似で太極拳をした。太極拳が終わると、ミー先生は、からかさを開いて、柄についているボタンの一つを押した。すると、それからまもなく、風が急に強くなってきて、狂ったように、びゅんびゅん吹きはじめた。
(空へまた吹き飛ばされるかもしれない)
そう思うと、ぼくは怖くなった。飛ばされる前に老いらくさんの体をしっかり抱いて、離れ離れにならないようにした。ぼくは目をつむって、嵐に備えていた。ところが、今回はなぜかこれまでとは違って、空へ吹き飛ばされなかった。意識を失うこともなかった。しばらくしてからぼくは再び、目を開けて、周りをみた。すると狂ったような強風はやんでいて、穏やかな風に戻っていた。ミー先生も、子どもたちも、シャオパイもすぐ近くにいた。
でも強風がやんだあと、びっくりしたことがあった。これまで見たこともない不思議な動物が近くにいるのに気がついたからだ。体は鹿のような形をしていて、頭の上には角が二本生えていた。でも普通の鹿とは違っていた。顔全体を取り囲むように、長い毛が生えていて、まるで花びらのなかから顔が出ているように見えたからだ。
(ぼくが目をつむっている間に、ミー先生が、からかさを使って連れてきたのだろうか)
ぼくはそう思った。
「老いらくさん、これは何という動物ですか」
ぼくは老いらくさんに聞いた。老いらくさんは博学多才のネズミだから、もしかしたら名前を知っているかもしれないと思った。ところが老いらくさんも首をかしげていた。
「わしも、こんな動物は初めて見たよ」
老いらくさんは、そう言って口をぽかんと開けながら、不思議な動物を見ていた。
「ミー先生が、からかさを使って連れてきたのではないかと、ぼくは思っているのですが」
ぼくがそう言うと、老いらくさんがうなずいた。
「そうかもしれないな。ミー先生は唐の時代からタイムスリップしてきた人ではないかと、わしは思っているから、あの動物も、いっしょに連れてきたのではないだろうか」
老いらくさんがそう言った。
「そうかもしれませんね」
ぼくは相づちを打った。
「わしはあの動物を実際に見たことはないが、絶滅した昔の動物のなかに、確か、あのような動物がいたという話を聞いたことがある。名前は確か、えーと……えーと……、確か……、確か……」
老いらくさんは、動物の名前を、なかなか思い出せないでいた。
子どもたちも、これまで見たことがない動物が目の前にいたので、びっくりしていた。
ミー先生が、子どもたちに
「これは花顔鹿という動物です。これから、この花顔鹿が、みなさんたちを川の源流に案内してくれます」
と、言った。それを聞いて、子どもたちの間から、うれしそうな歓声があがった。
花顔鹿は、それからまもなく、川の上流のほうへ向かって、登り始めた。ミー先生と子どもたちも、そのあとに続いて、川の流れとは逆方向に登っていった。川のせせらぎの音が心地よく響いていて、とても気持ちがよかった。ぼくと老いらくさんも、ミー先生や子どもたちに気づかれないように注意しながら、あとに続いた。登るにしたがって、地勢がだんだん険しくなってきて、息があがってきた。しかしそれにもめげないで、ぼくと老いらくさんは、ミー先生や子どもたちのあとに続いて登っていった。
川の流れは比較的緩やかで、ゆったりと流れていた。川のそばにある坂が登りにくいところは遠回りをしながら慎重に登っていった。道がでこぼこしていて歩きにくかったが、(川の源流はどんなところだろう)という期待感のほうが大きかったので、みんな、頑張って歩いていた。老いらくさんは年を取っているので、さすがに少々、きつさや疲れを感じているようだった。ぼくは気を利かせて、老いらくさんを背中に乗せてあげた。
小一時間ほど歩いたとき、これまで登り続けてきた川沿いの山道の両側に広がっていた森林が途切れて、視界がぱっと開けた。そこから先には、川も道もなくて、目の前には滝が見えるだけ。その滝の上から水が勢いよく流れ落ちていた。
「みなさん、やっと着きましたよ。ここから先には道も川もありません。滝の上から水が流れてきています」
ミー先生がそう言った。それを聞いて、柳くんが
「滝の上から水が流れているとは思ってもいなかったな」
と言った。
「わたしもよ。山の深いところの地下から水が湧き出ていて、そこから水が流れていると思っていたわ」
蒋さんが、そう答えていた。
それからまもなく、花顔鹿が滝のすぐ真下まで歩いていった。それを見て、ミー先生が「わたしたちも行ってみましょう」
と言って、子どもたちに、うながしていた。ミー先生の呼びかけに応じて、子どもたちは水しぶきが飛び散って、辺り一面の岩肌を濡らしているところまで行って、雄大な自然の景観を体感していた。ぼくと老いらくさんは、体が濡れるのはあまり好きではなかったから、少し離れたところから、その様子を見ていた。
するとそれからまもなく、思わぬことが起きた。花顔鹿とミー先生と子どもたちの姿が急に見えなくなったからだ。
(まさか、滝つぼのなかに落ちたのではないだろうか)
ぼくは、そう思って、目の前が一瞬、真っ暗になった。もし本当にそうだとしたら、大変な事故が起きたことになる。ぼくはそう思って、おろおろしていた。暗鬱な顔をしながら、ぼくは老いらくさんを見た。すると老いらくさんは意外と落ち着いた顔をしていた。
「笑い猫、何をそんなに暗い顔をしているのだ。大丈夫だよ。滝つぼに落ちたのではないよ」
老いらくさんがそう言った。
「でも姿が急に見えなくなったではありませんか」
ぼくは泣きそうな顔をしながら老いらくさんに問いかけた。
「ミー先生や子どもたちが、滝つぼのなかに落ちる音や悲鳴はしなかったではないか。ミー先生が、子どもたちを、入水自殺させるわけがないよ」
老いらくさんが、そう答えた。
「だったら、どこへ行ったのですか」
ぼくは老いらくさんに問いただした。
「わしはこれまで、滝を何度か見たことがある。滝の後ろに洞窟があることがよくあった。水がぽたぽたと、したたり落ちていて、薄暗くて、神秘的な空間が、洞窟のなかに広がっていた。もしかしたら、ここにも、そのような洞窟があることに気がついて、ミー先生や花顔鹿が子どもたちを連れて、見学に行ったのかもしれない」
老いらくさんが、そう言った。
それを聞いて、ぼくは、そうであってほしいと、心から願った。居ても立ってもいられなくなったので、ぼくはすぐに、老いらくさんといっしょに滝の後ろに回っていった。すると何と、老いらくさんが言ったとおりに、滝の後ろに洞窟があって、洞窟のなかから、子どもたちの声が聞こえてきた。それを聞いて、ミー先生や子どもたちが滝つぼに落ちたのではないことが分かって、ぼくは、ほっとした。洞窟の入口の前まで来て、なかをのぞくと真っ暗で、何も見えなかった。子どもたちの声が、暗やみのなかから伝わってきたので、それだけが救いだった。
「なんだか怖いわ。真っ暗で、しーとしていて、まるで死の世界に来たようだわ」
王さんの声が聞こえてきた。李くんがそのあと
「この洞窟は、どこまでも続いていて、もう出られなくなるのではないかな」
と言って、案じていた。
子どもたちは、みんな不安におびえているようだった。
「大丈夫です。心配は要りません。花顔鹿は、けっして、みなさんを危ない目に遭わせることはしません。信頼してください」
ミー先生が子どもたちを励ましていた。
「分かりました」
唐さんがそう答えていた。それからまもなく、子どもたちの声は聞こえなくなった。遠ざかっていく足音だけが聞こえてきた。ミー先生も子どもたちも、花顔鹿のあとに続いて、さらに奥のほうに黙々と進んでいるように思えた。ぼくと老いらくさんも、洞窟のなかに入り、ミー先生や子どもたちのあとを黙々と追っていた。真っ暗いなかを、どれくらい歩いたか分からないが、不意に
「あっ、光だ。あそこに出口が見える」
という、李くんのうれしそうな声が聞こえてきた。ぼくが遠くのほうを見ると、確かに、ずっと先に、星のような小さな光が見えていた。老いらくさんに、そのことを話すと、老いらくさんも、安堵の胸をなでおろしていた。希望のあかりを見いだしたことで、子どもたちも、ミー先生も、ぼくたちもみんな元気をもらい、足を速めながら、あかりのほうを目指して歩いていった。前に行けば行くほど、光がだんだん強く差し込んできて、辺りが少しずつ明るくなってきた。そしてついに洞窟の出口に到達することができた。洞窟の外に出たとたん、まばゆくて目を開けていられないほどの強い光が差し込んできた。夕日だった。夕日がきらきらと輝いていて、西の空が茜色に染まっているのが見えた。