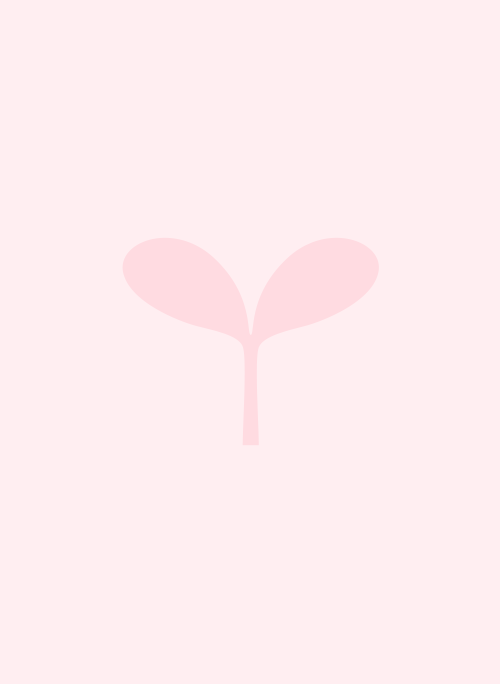天気……昼間は天気がよかったが、日が暮れたあと、空がにわかに曇ってきた。夜空に星が出ていたが、星の数はそれほど多くはなかった。でもどの星も、きらきらと輝いていて、暗い夜空に厳かな彩りを添えていた。このような夜には、何か不思議な出来事が起こるような予感がした。
しばらくしてから、ぼくは意識を取り戻した。いつのまにか、野の花が咲き誇っている河川敷にいるのが分かった。強い狂風に吹きあげられて、河川敷まで飛ばされていたのだった。老いらくさんも、ぼくの体にしっかりつかまったまま、ぼくのそばにいたのでよかった。シャオパイも、子どもたちも、ミー先生も、近くにいた。
「みなさん、大丈夫でしたか。ここでは突然、狂風が吹いてきて、びっくりさせられることがよくあります。怖くて目をつむっていたかもしれませんが、わたしたちは、河川敷の上まで吹き飛ばされてきました」
ミー先生がそう言うのが聞こえた。
「周りを見てください。野の花がたくさん咲いています。花の名前を知っていますか」
ミー先生が子どもたちに聞いていた。
子どもたちは野の花をじっと見ていた。
「レンゲソウ、タンポポ、シロツメクサ、ハハコグサ、ホトケノザ、……」
眼鏡をかけた陳くんが、目の前に咲いている野の花を見ながら、そう答えた。
「陳くん、よく知っていたわね」
ミー先生がほめていた。
「陳くんが言ってくれたほかにも、今、ここに咲いている野の花があります」
ミー先生は、そう言ってから、野の花の名前を説明しはじめた。
「これはカラスノエンドウ、あれはオオイヌノフグリ、あそこにスミレも咲いています」
ミー先生の説明に、子どもたちは耳を傾けながら、真剣なまなざしで野の花を観察していた。子どもたちは、みんな町のなかで生まれて育ったので、こんなにたくさんの野の花が群生しているところを、これまで一度も見たことがなかったようだ。そのために、子どもたちは、みんな珍しそうな顔をしながら見ていた。
「みなさん、野の花を摘んで、冠やネックレスを作りましょう」
ミー先生がそう言うと
「わあー、楽しそう」
という声が、あちこちからあがった。
ミー先生が作り方の説明をすると、子どもたちは河川敷のあちこちを歩きまわって、自分が好きな野の花を摘んでから、冠やネックレスを作り始めた。三十分ほどで、できあがったので、子どもたちは、頭に載せたり、首にかけたりして、楽しそうに、はしゃいでいた。ミー先生も自分で作った冠やネックレスを体につけていたが、まるで古代の人のような雰囲気が、体全体にあふれていた。子どもたちは河川敷には花だけでなくて、野生のマクワウリが実っているのに気がついたので、実を摘み取ってきて、ミー先生に見せていた。マクワウリはサッカーボールぐらいの大きさで、実のなかから、いいにおいが、ぷんぷんしていた。
「野生のマクワウリを、ぼくは初めてみたよ」
柳くんが、そう言って、目を輝かせていた。
「普通のマクワウリよりも、ひとまわり大きいね」
陳くんが、両手で抱えながら、そう言った。
「まるでカボチャみたい」
唐さんは、そう言って、笑みを浮かべていた。
「味はどうなのかしら」
蒋さんは、そう言って、鼻でにおいをかいでいた。
「ミー先生、食べてみてもいいですか?」
李くんが聞いていた。
「いいですよ。食べてみてください」
ミー先生がそう言ったので、子どもたちは、手に持ったマクワウリをかじり始めた。
「わあ、おいしい。こんなにおいしい食べ物が、こんなところにあるなんて思ってもいなかったわ」
王さんが、笑顔を浮かべながら、そう言った。
「みなさん、このマクワウリを使って、川のなかにいる魚をつかまえることができることを知っていますか?」
ミー先生が、子どもたちに聞いていた。
「えっ、そんなことができるのですか?」
蒋さんが、けげんそうな顔をしていた。
「どうやって、つかまえるのですか?」
李くんが聞き返していた。
「このようにしてつかまえるのです」
ミー先生は、そう言うと、マクワウリに穴をあけて、穴のなかから、中身を、ほじくり出して、川に浮かべた。すると何と、マクワウリが川に、ぷかぷかと浮いた。川に住んでいる魚たちが、それを見て、興味深そうに、マクワウリの近くに集まってきて、あいている穴のなかに顔を突っ込んで、においをかいだり、果肉を食べたりしていた。ところがそのあと顔が抜けなくなって、尾びれをばたばた動かして、もがいていた。それを見て、李くんが
「そうか。こうやってつかまえるのか」
と言って、納得していた。ミー先生の知恵に、子どもたちは、みんな感心していた。
「さすが、ミー先生。よくこんな奇抜な方法を思いつきましたね」
唐さんが、そう言った。ミー先生は、それを聞いて、くつくつと笑っていた。
それからまもなく、子どもたちは、ミー先生の真似をして、マクワウリに穴をあけて、川に浮かべていた。全部で七個のマクワウリが川に浮かべられた。どのマクワウリにも魚たちが、先を争うように寄ってきて、顔を穴に突っ込んで、においをかいだり、果肉をかじったりしていた。そしてそのあと、顔が抜けなくなって、ばたばたと、もがいていた。魚がはさまっているマクワウリを、子どもたちは岸に引き上げた。
「今夜の料理は、これにしましょう。魚を蒸してから、だしでスープを作ってマクワウリといっしょに煮ましょう」
ミー先生がそう言うと、子どもたちはみんな、うれしそうな顔をしていた。
それからまもなく、夕暮れが近づいてきて、西に傾いた太陽の光が川面に照り映えて、川の水が赤く染まり始めた。夕風も吹いてきて、川岸に咲いている野の花が、そよそよと風に揺れていた。
「今夜は宿舎には帰らないで、ここでキャンプをします」
ミー先生がそう言った。ミー先生はそのあと川岸から少し離れたところにある、二つのテントの前に、子どもたちを連れて行った。
「女の子たちは赤いテントのなかで寝ます。男の子たちは青いテントのなかで寝ます」
ミー先生がそう言った。それを聞いて、ぼくは、(ミー先生とシャオパイは、どこで寝るのだろう)と思った。ほかにテントは見当たらなかったので、ぼくは、けげんに思った。シャオパイが、ぼくの近くにやってきたので、ぼくはシャオパイに聞いた。するとシャオパイが
「ぼくは夜間は、寝ないで巡回パトロールをしているので、寝るひまはありません」
と答えた。
「ミー先生はどこで寝るのか?」
ぼくはシャオパイに聞いた。するとシャオパイが首を横に振りながら
「分かりません」
と答えた。
やがて日がどっぷりと暮れて、辺りが真っ暗になった。星はあまり多くは出ていなかったが、出ている星はどれも明るく輝いていた。このような夜には、何か不思議なことが起こりそうな予感がした。
ミー先生と子どもたちは、先ほど川辺で採ってきたマクワウリと魚を煮込んだ料理を作って、おなかいっぱいに食べてから、男女別々に分かれて、テントのなかに入っていった。そしてしばらく楽しそうに話したり、歌ったり、ゲームをしたりしていた。九時になったとき、ミー先生が巡回にやってきて
「みなさん、そろそろ寝る時間になりました」
と言って、子どもたちに寝るように、うながしていた。それからまもなく子どもたちは、テントのなかで白河夜船をこぎ始めた。川の水が静かに流れる音が心地よく響いて、子どもたちを深い眠りへと、優しくいざなっていた。静寂な夜のしじまのなか、シャオパイは子どもたちが休んでいるテントの周りを回って、パトロールにあたっていた。
ぼくと老いらくさんは、子どもたちが休んでいるテントの近くに体を横たえながら、夜を過ごすことにした。今晩何か不思議な出来事が起きるような予感が、ぼくにはどうしてもしてしかたがなかった。もし本当に、そのようなことが起きたときにはすぐに起きられるように、ぼくは浅くまどろんでいた。老いらくさんは時々、いびきをかいて深く眠ろうとしていた。老いらくさんのいびきが聞こえるたびに、ぼくは老いらくさんの体をゆすって「寝ないでください」と言って、注意をうながしていた。
「せっかく気持ちよく寝ていたのに、どうして、じゃまをするのだ」
老いらくさんが不快そうな目で、ぼくを見ていた。
「だって、今晩、きっと何かが起きるような予感がしますから」
ぼくはそう言って、弁解した。
「どうして、そう思うのだ。何か根拠でもあるのか?」
ぼくは、どう答えてよいか分からなかった。
「根拠はありません。ぼくの勘です」
ぼくはそう答えるよりほかなかった。
「そうか。わしは年を取っているから、夜はぐっすり寝たいのだ」
老いらくさんが仏頂面をしながら、そう言った。
子どもたちが寝ているテントの近くには、奇妙な形をした大きな石が、ごろごろころがっていた。暗闇のなかで見ると、不気味な怪獣がじっと伏せているように見えた。川の水音は夜が更けるとともに大きくなり、怪獣がその音を聞きながら、出番を待っているようにさえ、ぼくには思えた。怖くて、たまらなかったが、おじけることはなかった。好奇心のほうが恐怖心よりもまさっていたからだ。ぼくと老いらくさんは、子どもたちが寝ているテントをじっと見ていた。すると草木も眠る、うしみつどきに、テントの上に不思議な人影のようなものが現れた。
「来た、来た。老いらくさん、ほら、見て、あそこ」
ぼくはそう言って、声をひそめながら、老いらくさんに話しかけた。
不思議な人影は、二つのテントの上をしばらく行ったり来たりしていたが、そのあと男の子たちが寝ているテントのなかに、そっと忍び込んでいった。それを見て、老いらくさんが、あっけにとられたような顔をしていた。
「あれは一体、何なのだ。何をしに行ったのだ」
老いらくさんは、魂を奪われたような顔をしながら、ぼうぜんとしていた。
ぼくは以前、シャオパイが言ったことを思い出した。ミー先生はいつも夜更けに子どもたちの夢を集めに行っていると言っていたから、あの不思議な人影の正体はミー先生で、子どもたちの夢を集めに行ったのかもしれないと思った。
「もうしばらくしたら、あの不思議な人影がテントのなかから出てくると思います。そのとき、きっと背中に黒い袋かピンクの袋を背負っていると思います」
ぼくはそう答えた。
「それは何の袋なのだ」
老いらくさんが聞き返した。
「夢を入れる袋です」
ぼくはそう答えた。
「夢を入れる袋?」
老いらくさんは合点がいかないような顔をしていた。
「そうです。夢を入れる袋です。いやな夢は黒い袋に入れます。楽しい夢はピンクの袋に入れます」
ぼくはそう答えた。
「そうか。それなら、きっとその人影は、ピンクの袋を膨らませながら、背中に背負って出てくるにきまっているよ」
老いらくさんがそう言った。
「どうして、そう思うのですか」
ぼくは間髪を入れずに聞き返した。
「だって、今日、男の子たちは、とても楽しそうに過ごしていたではないか。マクワウリで魚を取る方法を教えてもらったから、みんな、はしゃいでいたではないか」
老いらくさんがそう答えた。
それからまもなく、不思議な人影が男の子たちが寝ているテントのなかから、すーっと出てきた。背中には老いらくさんが予想したとおり、ピンクの袋を背負っていた。袋は、ぱんぱんに膨らんでいた。
「ほら、わしが言ったとおりだろう」
予想が当たったことに、老いらくさんは満足していた。
そのあと、不思議な人影は、女の子たちが寝ているテントのなかに入っていった。
「今度もまたピンクの袋を持って出てくるよ」
老いらくさんがそう言った。
「どうして、そう思うのですか」
ぼくは今度も間髪を入れずに聞き返した。
「だって、今日、女の子たちは、とても楽しそうに過ごしていたではないか。花を摘んで冠やネックレスを作ったり、マクワウリや魚を使って料理を作ったりして、みんな、楽しそうだったではないか」
老いらくさんがそう答えた。それを聞いて、ぼくは、うなずいた。
それからまもなく、不思議な人影が女の子たちが寝ているテントのなかから、すーっと出てきた。背中には老いらくさんが予想したとおり、ピンクの袋を持っていた。袋は、はちきれんばかりに膨らんでいた。
「ほら、わしが言ったとおりだろう」
今度もまた予想が当たったので、老いらくさんは、ますます悦に入っていた。
空から現れた不思議な人影は、二つのピンクの袋を背中に背負うと、再び、空へふわふわと浮かびあがって、夜のとばりのなかに静かに消えていった。
「あの人影はミー先生に間違いないと、わしは思っている。やはり、あの人は常軌を逸した不思議な人だ」
老いらくさんが、そう言った。ぼくはうなずいた。
「あのピンクの袋を持って、これからどこへ行くのだろう?」
老いらくさんが、小首をかしげながら、つぶやいていた。
そのことについては、シャオパイが以前、ぼくに話してくれたことを、ぼくは覚えている。ミー先生は子どもたちの夢を集めたあと、自分の部屋に持ち帰って、夢の分析をして、いやな夢を見た子どもがいたら、心理療法をほどこして改善に努めていると、話していた。楽しい夢を見た子どもの場合は、その夢を見るに至ったいきさつを分析して、その夢が現実でもかなうようにするためにはどうすればよいかを研究して、子どもたちにアドバイスしていると話していた。
「袋を持って、どこかへ行って、夜が明けてから夢の分析をすると思います」
ぼくは老いらくさんに、そう答えた。
しばらくしてから、ぼくは意識を取り戻した。いつのまにか、野の花が咲き誇っている河川敷にいるのが分かった。強い狂風に吹きあげられて、河川敷まで飛ばされていたのだった。老いらくさんも、ぼくの体にしっかりつかまったまま、ぼくのそばにいたのでよかった。シャオパイも、子どもたちも、ミー先生も、近くにいた。
「みなさん、大丈夫でしたか。ここでは突然、狂風が吹いてきて、びっくりさせられることがよくあります。怖くて目をつむっていたかもしれませんが、わたしたちは、河川敷の上まで吹き飛ばされてきました」
ミー先生がそう言うのが聞こえた。
「周りを見てください。野の花がたくさん咲いています。花の名前を知っていますか」
ミー先生が子どもたちに聞いていた。
子どもたちは野の花をじっと見ていた。
「レンゲソウ、タンポポ、シロツメクサ、ハハコグサ、ホトケノザ、……」
眼鏡をかけた陳くんが、目の前に咲いている野の花を見ながら、そう答えた。
「陳くん、よく知っていたわね」
ミー先生がほめていた。
「陳くんが言ってくれたほかにも、今、ここに咲いている野の花があります」
ミー先生は、そう言ってから、野の花の名前を説明しはじめた。
「これはカラスノエンドウ、あれはオオイヌノフグリ、あそこにスミレも咲いています」
ミー先生の説明に、子どもたちは耳を傾けながら、真剣なまなざしで野の花を観察していた。子どもたちは、みんな町のなかで生まれて育ったので、こんなにたくさんの野の花が群生しているところを、これまで一度も見たことがなかったようだ。そのために、子どもたちは、みんな珍しそうな顔をしながら見ていた。
「みなさん、野の花を摘んで、冠やネックレスを作りましょう」
ミー先生がそう言うと
「わあー、楽しそう」
という声が、あちこちからあがった。
ミー先生が作り方の説明をすると、子どもたちは河川敷のあちこちを歩きまわって、自分が好きな野の花を摘んでから、冠やネックレスを作り始めた。三十分ほどで、できあがったので、子どもたちは、頭に載せたり、首にかけたりして、楽しそうに、はしゃいでいた。ミー先生も自分で作った冠やネックレスを体につけていたが、まるで古代の人のような雰囲気が、体全体にあふれていた。子どもたちは河川敷には花だけでなくて、野生のマクワウリが実っているのに気がついたので、実を摘み取ってきて、ミー先生に見せていた。マクワウリはサッカーボールぐらいの大きさで、実のなかから、いいにおいが、ぷんぷんしていた。
「野生のマクワウリを、ぼくは初めてみたよ」
柳くんが、そう言って、目を輝かせていた。
「普通のマクワウリよりも、ひとまわり大きいね」
陳くんが、両手で抱えながら、そう言った。
「まるでカボチャみたい」
唐さんは、そう言って、笑みを浮かべていた。
「味はどうなのかしら」
蒋さんは、そう言って、鼻でにおいをかいでいた。
「ミー先生、食べてみてもいいですか?」
李くんが聞いていた。
「いいですよ。食べてみてください」
ミー先生がそう言ったので、子どもたちは、手に持ったマクワウリをかじり始めた。
「わあ、おいしい。こんなにおいしい食べ物が、こんなところにあるなんて思ってもいなかったわ」
王さんが、笑顔を浮かべながら、そう言った。
「みなさん、このマクワウリを使って、川のなかにいる魚をつかまえることができることを知っていますか?」
ミー先生が、子どもたちに聞いていた。
「えっ、そんなことができるのですか?」
蒋さんが、けげんそうな顔をしていた。
「どうやって、つかまえるのですか?」
李くんが聞き返していた。
「このようにしてつかまえるのです」
ミー先生は、そう言うと、マクワウリに穴をあけて、穴のなかから、中身を、ほじくり出して、川に浮かべた。すると何と、マクワウリが川に、ぷかぷかと浮いた。川に住んでいる魚たちが、それを見て、興味深そうに、マクワウリの近くに集まってきて、あいている穴のなかに顔を突っ込んで、においをかいだり、果肉を食べたりしていた。ところがそのあと顔が抜けなくなって、尾びれをばたばた動かして、もがいていた。それを見て、李くんが
「そうか。こうやってつかまえるのか」
と言って、納得していた。ミー先生の知恵に、子どもたちは、みんな感心していた。
「さすが、ミー先生。よくこんな奇抜な方法を思いつきましたね」
唐さんが、そう言った。ミー先生は、それを聞いて、くつくつと笑っていた。
それからまもなく、子どもたちは、ミー先生の真似をして、マクワウリに穴をあけて、川に浮かべていた。全部で七個のマクワウリが川に浮かべられた。どのマクワウリにも魚たちが、先を争うように寄ってきて、顔を穴に突っ込んで、においをかいだり、果肉をかじったりしていた。そしてそのあと、顔が抜けなくなって、ばたばたと、もがいていた。魚がはさまっているマクワウリを、子どもたちは岸に引き上げた。
「今夜の料理は、これにしましょう。魚を蒸してから、だしでスープを作ってマクワウリといっしょに煮ましょう」
ミー先生がそう言うと、子どもたちはみんな、うれしそうな顔をしていた。
それからまもなく、夕暮れが近づいてきて、西に傾いた太陽の光が川面に照り映えて、川の水が赤く染まり始めた。夕風も吹いてきて、川岸に咲いている野の花が、そよそよと風に揺れていた。
「今夜は宿舎には帰らないで、ここでキャンプをします」
ミー先生がそう言った。ミー先生はそのあと川岸から少し離れたところにある、二つのテントの前に、子どもたちを連れて行った。
「女の子たちは赤いテントのなかで寝ます。男の子たちは青いテントのなかで寝ます」
ミー先生がそう言った。それを聞いて、ぼくは、(ミー先生とシャオパイは、どこで寝るのだろう)と思った。ほかにテントは見当たらなかったので、ぼくは、けげんに思った。シャオパイが、ぼくの近くにやってきたので、ぼくはシャオパイに聞いた。するとシャオパイが
「ぼくは夜間は、寝ないで巡回パトロールをしているので、寝るひまはありません」
と答えた。
「ミー先生はどこで寝るのか?」
ぼくはシャオパイに聞いた。するとシャオパイが首を横に振りながら
「分かりません」
と答えた。
やがて日がどっぷりと暮れて、辺りが真っ暗になった。星はあまり多くは出ていなかったが、出ている星はどれも明るく輝いていた。このような夜には、何か不思議なことが起こりそうな予感がした。
ミー先生と子どもたちは、先ほど川辺で採ってきたマクワウリと魚を煮込んだ料理を作って、おなかいっぱいに食べてから、男女別々に分かれて、テントのなかに入っていった。そしてしばらく楽しそうに話したり、歌ったり、ゲームをしたりしていた。九時になったとき、ミー先生が巡回にやってきて
「みなさん、そろそろ寝る時間になりました」
と言って、子どもたちに寝るように、うながしていた。それからまもなく子どもたちは、テントのなかで白河夜船をこぎ始めた。川の水が静かに流れる音が心地よく響いて、子どもたちを深い眠りへと、優しくいざなっていた。静寂な夜のしじまのなか、シャオパイは子どもたちが休んでいるテントの周りを回って、パトロールにあたっていた。
ぼくと老いらくさんは、子どもたちが休んでいるテントの近くに体を横たえながら、夜を過ごすことにした。今晩何か不思議な出来事が起きるような予感が、ぼくにはどうしてもしてしかたがなかった。もし本当に、そのようなことが起きたときにはすぐに起きられるように、ぼくは浅くまどろんでいた。老いらくさんは時々、いびきをかいて深く眠ろうとしていた。老いらくさんのいびきが聞こえるたびに、ぼくは老いらくさんの体をゆすって「寝ないでください」と言って、注意をうながしていた。
「せっかく気持ちよく寝ていたのに、どうして、じゃまをするのだ」
老いらくさんが不快そうな目で、ぼくを見ていた。
「だって、今晩、きっと何かが起きるような予感がしますから」
ぼくはそう言って、弁解した。
「どうして、そう思うのだ。何か根拠でもあるのか?」
ぼくは、どう答えてよいか分からなかった。
「根拠はありません。ぼくの勘です」
ぼくはそう答えるよりほかなかった。
「そうか。わしは年を取っているから、夜はぐっすり寝たいのだ」
老いらくさんが仏頂面をしながら、そう言った。
子どもたちが寝ているテントの近くには、奇妙な形をした大きな石が、ごろごろころがっていた。暗闇のなかで見ると、不気味な怪獣がじっと伏せているように見えた。川の水音は夜が更けるとともに大きくなり、怪獣がその音を聞きながら、出番を待っているようにさえ、ぼくには思えた。怖くて、たまらなかったが、おじけることはなかった。好奇心のほうが恐怖心よりもまさっていたからだ。ぼくと老いらくさんは、子どもたちが寝ているテントをじっと見ていた。すると草木も眠る、うしみつどきに、テントの上に不思議な人影のようなものが現れた。
「来た、来た。老いらくさん、ほら、見て、あそこ」
ぼくはそう言って、声をひそめながら、老いらくさんに話しかけた。
不思議な人影は、二つのテントの上をしばらく行ったり来たりしていたが、そのあと男の子たちが寝ているテントのなかに、そっと忍び込んでいった。それを見て、老いらくさんが、あっけにとられたような顔をしていた。
「あれは一体、何なのだ。何をしに行ったのだ」
老いらくさんは、魂を奪われたような顔をしながら、ぼうぜんとしていた。
ぼくは以前、シャオパイが言ったことを思い出した。ミー先生はいつも夜更けに子どもたちの夢を集めに行っていると言っていたから、あの不思議な人影の正体はミー先生で、子どもたちの夢を集めに行ったのかもしれないと思った。
「もうしばらくしたら、あの不思議な人影がテントのなかから出てくると思います。そのとき、きっと背中に黒い袋かピンクの袋を背負っていると思います」
ぼくはそう答えた。
「それは何の袋なのだ」
老いらくさんが聞き返した。
「夢を入れる袋です」
ぼくはそう答えた。
「夢を入れる袋?」
老いらくさんは合点がいかないような顔をしていた。
「そうです。夢を入れる袋です。いやな夢は黒い袋に入れます。楽しい夢はピンクの袋に入れます」
ぼくはそう答えた。
「そうか。それなら、きっとその人影は、ピンクの袋を膨らませながら、背中に背負って出てくるにきまっているよ」
老いらくさんがそう言った。
「どうして、そう思うのですか」
ぼくは間髪を入れずに聞き返した。
「だって、今日、男の子たちは、とても楽しそうに過ごしていたではないか。マクワウリで魚を取る方法を教えてもらったから、みんな、はしゃいでいたではないか」
老いらくさんがそう答えた。
それからまもなく、不思議な人影が男の子たちが寝ているテントのなかから、すーっと出てきた。背中には老いらくさんが予想したとおり、ピンクの袋を背負っていた。袋は、ぱんぱんに膨らんでいた。
「ほら、わしが言ったとおりだろう」
予想が当たったことに、老いらくさんは満足していた。
そのあと、不思議な人影は、女の子たちが寝ているテントのなかに入っていった。
「今度もまたピンクの袋を持って出てくるよ」
老いらくさんがそう言った。
「どうして、そう思うのですか」
ぼくは今度も間髪を入れずに聞き返した。
「だって、今日、女の子たちは、とても楽しそうに過ごしていたではないか。花を摘んで冠やネックレスを作ったり、マクワウリや魚を使って料理を作ったりして、みんな、楽しそうだったではないか」
老いらくさんがそう答えた。それを聞いて、ぼくは、うなずいた。
それからまもなく、不思議な人影が女の子たちが寝ているテントのなかから、すーっと出てきた。背中には老いらくさんが予想したとおり、ピンクの袋を持っていた。袋は、はちきれんばかりに膨らんでいた。
「ほら、わしが言ったとおりだろう」
今度もまた予想が当たったので、老いらくさんは、ますます悦に入っていた。
空から現れた不思議な人影は、二つのピンクの袋を背中に背負うと、再び、空へふわふわと浮かびあがって、夜のとばりのなかに静かに消えていった。
「あの人影はミー先生に間違いないと、わしは思っている。やはり、あの人は常軌を逸した不思議な人だ」
老いらくさんが、そう言った。ぼくはうなずいた。
「あのピンクの袋を持って、これからどこへ行くのだろう?」
老いらくさんが、小首をかしげながら、つぶやいていた。
そのことについては、シャオパイが以前、ぼくに話してくれたことを、ぼくは覚えている。ミー先生は子どもたちの夢を集めたあと、自分の部屋に持ち帰って、夢の分析をして、いやな夢を見た子どもがいたら、心理療法をほどこして改善に努めていると、話していた。楽しい夢を見た子どもの場合は、その夢を見るに至ったいきさつを分析して、その夢が現実でもかなうようにするためにはどうすればよいかを研究して、子どもたちにアドバイスしていると話していた。
「袋を持って、どこかへ行って、夜が明けてから夢の分析をすると思います」
ぼくは老いらくさんに、そう答えた。