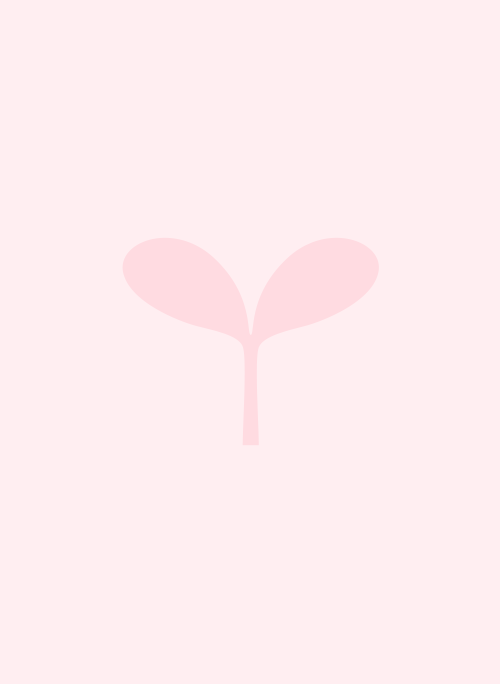天気……山の天気は目まぐるしく変化する。短時間のうちに、晴れたり曇ったり雨が降ったりして、一寸先の予測もつかない。風は気象の変化にかかわらず、いつも吹いている。比較的穏やかに吹いているが、時折、激しく吹き荒れることもある。『風雲急を告げる』という言葉があるが、山の上で、にわかに強風が吹いてきたら、何か予期せぬ出来事が起きる可能性があると、シャオパイが言った。
ぼくが『雲の上の学校』に来てから、もう何日にもなる。シャオパイが、以前、「この学校には教室がありません」と言っていたが、確かに、ぼくはこれまでまだ一度も、教室のなかで授業を受けている子どもたちの姿を見たことがない。ぼくは以前、杜真子や馬小跳が通っている学校へ行ったことがある。その学校には教室がたくさんあって、体育の授業以外は、子どもたちはみんな、教室のなかで授業を受けていた。それを思うと、教室がない学校など想像もできなかったので、ぼくは、シャオパイに、教室がない理由を聞いた。するとシャオパイが
「授業はいつも教室の外でおこなわれているからです」
と答えた。
「この前、ミー先生は草の上で授業をしていたじゃないですか。子どもたちに靴を脱がせて、素足でお日様の暖かさを、じかに感じさせたり、大地のにおいを鼻でかがせたりしていたじゃないですか。あのときは草の上が教室だったのです」
シャオパイが、そう説明した。
「雨が降ったときには、ミー先生は子どもたちを原っぱに呼び出して、いっしょに踊ったり、走り回ったりしていたじゃないですか。雨が降ったらいやだなあと思わないで、雨に打たれることは刺激的で楽しいことでもあるという感覚を子どもたちに教えていたのです。あのときは原っぱが教室だったのです」
シャオパイが、そう言った。
「そうか、そういうことだったのか」
ぼくには、ようやく合点がいった。
「雨はすぐにやんで、そのあときれいな虹が出ました。ミー先生はそのとき、子どもたちを八角亭と呼ばれている展望台に呼んで、虹の色を聞いたり、パレットの上に絵の具を出させて三原色を使って、いろいろな色が出せることを話していました。あのときは八角亭が教室だったのです」
シャオパイが、さらにそう言った。ぼくは、うなずいた。
この学校では、宿題の仕方も、普通の学校とは違っていることに、ぼくは気がついた。以前、ぼくは杜真子や馬小跳が宿題をしているのを見たことがある。杜真子も馬小跳も最初から一人で、黙々と宿題に取り組んでいた。そのために、なかなか、まとまらなくて進まないときもあった。
それに対して、この学校では、テーマに関することについてまず体験させて、そのあと、みんなで話し合って、疑問に思ったことを友だちに聞いたり、知らなかった知識や考え方を知って、テーマに対する認識を深めて、そのあと、宿舎に帰って構想を練ってから提出していた。そのために質の高いものに仕上がっていた。宿題のテーマも子どもたちが意欲をもって取り組めるようなものばかり出されていた。そのために子どもたちはみんな興味をもって、一生懸命に宿題に取り組んでいた。提出された宿題も〇×をつけて返すだけでなくて、子どもたちが喜ぶような形にして子どもたちに還元されていた。
「みなさん、これから、わたしが本を読んであげます」
天気がいい日の午後、ミー先生は子どもたちを原っぱに集めると、そう言った。原っぱには人が座れるほどの大きなキノコがたくさん自生していたので、ミー先生も、子どもたちも、ふかふかして柔らかいキノコの上に座って、楽しそうにしていた。
それからまもなく、ミー先生が
「この本は世界に一つしかない本です。本のタイトルは『私の太陽』です」
と言った。するとそれを聞いて、眼鏡をかけた男の子が
「作者は誰ですか」
と、聞いていた。
「作者はみなさんです。本の表紙に、みなさんの名前が書いてあります」
ミー先生が、そう言うと、子どもたちはみんな、びっくりしたような顔をしていた。
「わたしたちが提出した作文を本にしてくれたのですか」
ポニーテールに髪の毛を束ねた女の子が聞き返していた。ミー先生がにっこり、うなずいていた。
「どれも素晴らしい作品ばかりで、本にするだけの価値があると思ったから、本にしました」
ミー先生が、そう言った。
「感激!」
髪に赤いリボンをつけた女の子が、そう言った。
「本は大人の人が書くものとばかり思っていたから、まさか、ぼくたちの書いたものが本になるとは思ってもいなかったよ」
背が高くて体が大きい男の子が、そう言っていた。
「わたしは将来、作家になりたいので、いつか本が出せたらいなと思っていたけど、こんなに早く本が出せるとは思ってもいなかったわ」
ポニーテールに髪の毛を束ねた女の子が、そう言っていた。
ほかの子どもたちも、みんな、歓喜に満ちた表情をしていた。
「みなさんが喜んでくれてうれしいです」
ミー先生は、そう言ってから、さっそく、ページをめくって、子どもたちが書いた文を読み始めた。
「内容は多岐にわたっています。エッセイ、童話、詩、歌詞……と、どれも素晴らしい作品ばかりです。歌詞を書いてくれた子どもには、わたしが曲をつけましたから、あとで歌います」
ミー先生がそう言って、本を全部読み終わったあと、歌ったり、草笛でメロディーを演奏したりしていた。歌や演奏が終わったあと、子どもたちはみんな拍手をしていた。
「みなさん、すごいです。どれもこれも、きらきらした才能があふれた作品ばかりです。みなさんが書いてくれた、これらの作品を読んで、わたしは今、感動で胸が震えています」
ミー先生がそう言った。それを聞いて、子どもたちはみんな、とてもうれしそうな顔をしていた。目に涙を浮かべている子どももいた。
シャオパイの話によると、ここにいる子どもたちは、下界では、周りから認められなくて浮いている子どもたちばかりのようだった。でもここに来て、自分たちの感性や文才を認めてくれる先生と初めて出会えて、喜びが胸いっぱいに広がって、涙が自然と出てきたのではないかと、ぼくは思った。下界にいたころ、この子どもたちはいつも、うつうつとしていて、学ぶことに身が入らなかったり、いやな夢ばかり見て、うなされていた。しかし今はみんな生き生きとしていて、目が星のように、きらきらと輝いていた。環境の変化によって、こうも違ってくるのかと、ぼくは今、つくづくと思っていた。
「みなさんが、とても満足しているようで、わたしも、とてもうれしいです。でも学ぶことに終わりはありません。みなさん、もっと、いろいろなことを学びたいと思いませんか」
ミー先生がそう言うと
「思いまーす」
という声が、異口同音にあがった。
「分かりました。では、これからも、自然のなかのいろいろな事象をたくさん見て、たくさん学んでいきましょう」
ミー先生が、笑みを浮かべながら、そう言った。
「先生、よろしくお願いします」
ポニーテールに髪の毛を束ねた女の子が、そう言った。
「今度の宿題は何ですか」
眼鏡をかけた男の子が聞いていた。
「わたしは今までは宿題が嫌いでしたが、この学校に来てから、宿題をすることが、とても楽しくなりました。先生のおかげです。ありがとうございます」
髪に赤いリボンをつけた女の子が、そう答えていた。
「これからも宿題をたくさん出してください。早く宿題をしたくて、うずうずしています」
背が高くて体が大きい男の子が、そう答えていた。
それを聞いて、ミー先生が、にっこり、うなずいていた。そのあとミー先生が
「今度の新しい宿題は水について考えることです」
と言った。
「水ですか?」
「そうです。水です。水は、わたしたちの生活に欠かせないものだということを、みなさんは知っていると思います」
ミー先生がそう言うと、子どもたちは、みんな、うなずいていた。
「では、みなさんに聞きます。もし水がなかったら、どうなると思いますか?」
ミー先生がそう聞くと、われ先にとばかりに、子どもたちが手をあげた。
「では、李くん、答えてください」
ミー先生は、背が高くて、青いシャツを着た男の子に聞いていた。
「水がなかったら、人間は、のどが渇いて死んでしまいます。動物も同じです。植物も枯れてしまいます」
李くんが、そう答えていた。
「ほかに何か意見がありますか?」
ポニーテールに髪の毛を束ねた女の子が手を挙げた。
「蒋さん、答えてください」
「水がなかったら、地球にうるおいがなくて、生命がない星になっていたと思います」
蒋さんがそう答えていた。
「そうですね。その通りですね。この地球は水の惑星と呼ばれていて、地球のあちこちに水がたくさんあります」
ミー先生がそう言うと、子どもたちは、うなずいていた。
「では、みなさんに聞きます。水には、どんな種類の水がありますか?」
ミー先生がそう言うと、緑色のスカートをはいた背の高い女の子が手を挙げた。
「王さん、答えてください」
ミー先生がそう言った。
「海水、湖水、池の水、井戸の水、川の水、それから……」
王さんが頭のなかで、いろいろな水を思い浮かべていた。
「そうですね。ほかには、どんな水がありますか?」
ミー先生がそう言うと、今度は眼鏡をかけたやせた男の子が手を挙げた。
「陳くん、答えてください」
ミー先生がそう聞いた。
「雨水、露、雪、氷、霜、霧、ひょう、それから……」
陳くんは王さんとは違った視点から、地球上に存在する水のことを考えようとしていた。それを聞いて、帽子をかぶった柳くんが、首をかしげながら
「ちょっと待って。雪や霜や霧やひょうは、水と言えるのか?」
と異を唱えていた。
「言えるさ。雪や霜やひょうは、水が固まってできたものだし、霧は地面近くの空中にふわふわ浮いているたくさんの水滴からできているではないか」
陳くんが反問して、自説の正しさを主張していた。ほかの子どもたちも議論に加わって、言える派と、言えない派に分かれて、それぞれの意見を述べていた。
ミー先生は、どちらが正しいとは言わないで、どちらの意見にも、うんうんと、うなずきながら、静かに聞いているだけだった。考え方は人によって様々だから、子どもたちの判断にゆだねようとしているように見えた。
それからしばらくしてから、ミー先生が
「言えるか、言えないかに分かれて、考え方を深めることができたのは、とても有意義なことだったと思います。どちらの意見が正しいかについては、もう少し考えてから結論を出すことにしましょう。では今日の新しい宿題のことについて、もう少し具体的に話します。水はどこから流れてきているかについて調べることです。それが今日の宿題です。すぐれた宿題が提出されたら、今度もまた本にします。本のタイトルは『水の物語』です。これから水の源流を探しに行きます。その前にまず水の源流に対する自分たちのイメージを述べてください」
と言った。
「はーい、分かりました」
子どもたちは異口同音に、そう答えてから、さっそく述べ始めた。いろいろな考えが述べられた。
「雨は空から降ってくるから、水のもとは空にあるよ」
李くんが、そう言った。
「海や川の水はどうなの。空から降ってきたの」
蒋さんが疑問を投げかけていた。
「海の水は川から流れてきたものだし、川の水は奥山に源があって、そこから流れてきている」
帽子をかぶった柳くんが、そう答えていた。
「大きな川の水は小さな川の水がいくつも流れ込んで、できたものだ」
眼鏡をかけた陳くんが、そう言った。
「寒い地方では氷河が融けて川の水になることもあるわ」
王さんが、そう答えていた。
「わたしには、よく分からない……」
髪に赤いリボンをつけた唐さんは、そう答えていた。
子どもたちの意見を、ミー先生は耳を傾けながら熱心に聞いていた。子どもたちの意見が、ひととおり出たあと、ミー先生が
「ではこれから、みなさんたちをこの山の山頂に連れていきます。西山山脈のなかでも最高峰の山だから、この山の山頂からは、周りにあるすべての山がよく見えます」
と言った。
それからまもなく、子どもたちはミー先生に導かれながら、山頂に着いた。ぼくと老いらくさんとシャオパイも、ミー先生や子どもたちのあとからついて山頂に登った。
「みなさん、あそこを見てください」
山頂に立って、遠くの山を見ながら、ミー先生がそう言った。
「白い帯のようなものが、あの山の山頂付近にあるのが見えますか」
「見えます。あれは何ですか」
蒋さんが聞いていた。
「あれは万年雪です」
ミー先生が、そう答えていた。
「万年雪?」
蒋さんが、けげんそうな顔をしていた。
「そう、万年雪です。夏でも消えないで残っている雪のことを万年雪と言います。万年雪が積もっているあの山の谷には雪渓があります。雪や氷が一年中解けないで残っている谷が雪渓と呼ばれています。その雪渓の下に小さな川が流れていて、その川の底から水が、ぼこぼこと湧き出ています。そこが皆さんたちが住んでいる町を流れている川の源流です」
ミー先生がそう言った。
「へえー、そうなのだ。あんな遠い所から流れてきているのだ」
蒋さんが胸の思いを源流に馳せていた。
「あそこから始まって、わたしたちの町を通って流れていって、やがて広い海に流れていくのよね」
唐さんが、そう言った。
「そう思うと、何だかロマンティックな気分になるわ」
王さんが、目を輝かせながら、そう答えていた。
「あそこが、どんなところなのか行ってみたいなあ」
陳くんが、そう言った。
「雪渓や源流がどんなものか見てみたいな」
柳くんは心をときめかせていた。
「でも、ここからはとても遠そうに見える。山道も険しそう」
李くんが顔の表情を曇らせていた。
遠くにかすかに見える山を見ながら、子どもたちは、それぞれの思いを述べたり、遠すぎて行けそうもないことに、ため息をついたりしていた。
確かにその通りだった。遠くに見える山の山頂付近にかすかに見える万年雪に心を惹かれるものの、この山と、あの山の間には、いくつもの山々が高い壁のように立ちはだかっていて、とても行けそうには思えなかった。ぼーっとしながら、万年雪を見ていると、シャオパイが慌てて近づいてきて
「もうすぐ、強い狂風が吹き荒れそうだから気をつけて」
と言った。ぼくは、それを聞いて、びっくりした。以前も狂風に吹き飛ばされて気を失ったことがあったからだ。シャオパイが言ったことを、ぼくは老いらくさんにも告げた。老いらくさんも、びっくりしていた。ぼくは老いらくさんを、ぼくの体に、しっかりと、つかまえさせた。シャオパイは狂風のことをぼくに伝えると、すぐにミー先生のところに帰っていった。ミー先生は愛用のからかさを開いて、かさの柄についているボタンのなかの一つを押した。すると、からかさを持ったミー先生の体が宙に、ふわふわと浮き出した。
その光景を口をあんぐりと開けたまま、ぼくは、しばらく見ていた。それからまもなく、シャオパイが言ったように、強い狂風が吹いてきて、ぼくの体も宙に吹きあげられた。あっという間のできごとで、地に伏せて踏ん張ることさえできなかった。空中で何度も、くるくると、とんぼ返りをしたのは覚えているが、そのあと意識を失ってしまった。
ぼくが『雲の上の学校』に来てから、もう何日にもなる。シャオパイが、以前、「この学校には教室がありません」と言っていたが、確かに、ぼくはこれまでまだ一度も、教室のなかで授業を受けている子どもたちの姿を見たことがない。ぼくは以前、杜真子や馬小跳が通っている学校へ行ったことがある。その学校には教室がたくさんあって、体育の授業以外は、子どもたちはみんな、教室のなかで授業を受けていた。それを思うと、教室がない学校など想像もできなかったので、ぼくは、シャオパイに、教室がない理由を聞いた。するとシャオパイが
「授業はいつも教室の外でおこなわれているからです」
と答えた。
「この前、ミー先生は草の上で授業をしていたじゃないですか。子どもたちに靴を脱がせて、素足でお日様の暖かさを、じかに感じさせたり、大地のにおいを鼻でかがせたりしていたじゃないですか。あのときは草の上が教室だったのです」
シャオパイが、そう説明した。
「雨が降ったときには、ミー先生は子どもたちを原っぱに呼び出して、いっしょに踊ったり、走り回ったりしていたじゃないですか。雨が降ったらいやだなあと思わないで、雨に打たれることは刺激的で楽しいことでもあるという感覚を子どもたちに教えていたのです。あのときは原っぱが教室だったのです」
シャオパイが、そう言った。
「そうか、そういうことだったのか」
ぼくには、ようやく合点がいった。
「雨はすぐにやんで、そのあときれいな虹が出ました。ミー先生はそのとき、子どもたちを八角亭と呼ばれている展望台に呼んで、虹の色を聞いたり、パレットの上に絵の具を出させて三原色を使って、いろいろな色が出せることを話していました。あのときは八角亭が教室だったのです」
シャオパイが、さらにそう言った。ぼくは、うなずいた。
この学校では、宿題の仕方も、普通の学校とは違っていることに、ぼくは気がついた。以前、ぼくは杜真子や馬小跳が宿題をしているのを見たことがある。杜真子も馬小跳も最初から一人で、黙々と宿題に取り組んでいた。そのために、なかなか、まとまらなくて進まないときもあった。
それに対して、この学校では、テーマに関することについてまず体験させて、そのあと、みんなで話し合って、疑問に思ったことを友だちに聞いたり、知らなかった知識や考え方を知って、テーマに対する認識を深めて、そのあと、宿舎に帰って構想を練ってから提出していた。そのために質の高いものに仕上がっていた。宿題のテーマも子どもたちが意欲をもって取り組めるようなものばかり出されていた。そのために子どもたちはみんな興味をもって、一生懸命に宿題に取り組んでいた。提出された宿題も〇×をつけて返すだけでなくて、子どもたちが喜ぶような形にして子どもたちに還元されていた。
「みなさん、これから、わたしが本を読んであげます」
天気がいい日の午後、ミー先生は子どもたちを原っぱに集めると、そう言った。原っぱには人が座れるほどの大きなキノコがたくさん自生していたので、ミー先生も、子どもたちも、ふかふかして柔らかいキノコの上に座って、楽しそうにしていた。
それからまもなく、ミー先生が
「この本は世界に一つしかない本です。本のタイトルは『私の太陽』です」
と言った。するとそれを聞いて、眼鏡をかけた男の子が
「作者は誰ですか」
と、聞いていた。
「作者はみなさんです。本の表紙に、みなさんの名前が書いてあります」
ミー先生が、そう言うと、子どもたちはみんな、びっくりしたような顔をしていた。
「わたしたちが提出した作文を本にしてくれたのですか」
ポニーテールに髪の毛を束ねた女の子が聞き返していた。ミー先生がにっこり、うなずいていた。
「どれも素晴らしい作品ばかりで、本にするだけの価値があると思ったから、本にしました」
ミー先生が、そう言った。
「感激!」
髪に赤いリボンをつけた女の子が、そう言った。
「本は大人の人が書くものとばかり思っていたから、まさか、ぼくたちの書いたものが本になるとは思ってもいなかったよ」
背が高くて体が大きい男の子が、そう言っていた。
「わたしは将来、作家になりたいので、いつか本が出せたらいなと思っていたけど、こんなに早く本が出せるとは思ってもいなかったわ」
ポニーテールに髪の毛を束ねた女の子が、そう言っていた。
ほかの子どもたちも、みんな、歓喜に満ちた表情をしていた。
「みなさんが喜んでくれてうれしいです」
ミー先生は、そう言ってから、さっそく、ページをめくって、子どもたちが書いた文を読み始めた。
「内容は多岐にわたっています。エッセイ、童話、詩、歌詞……と、どれも素晴らしい作品ばかりです。歌詞を書いてくれた子どもには、わたしが曲をつけましたから、あとで歌います」
ミー先生がそう言って、本を全部読み終わったあと、歌ったり、草笛でメロディーを演奏したりしていた。歌や演奏が終わったあと、子どもたちはみんな拍手をしていた。
「みなさん、すごいです。どれもこれも、きらきらした才能があふれた作品ばかりです。みなさんが書いてくれた、これらの作品を読んで、わたしは今、感動で胸が震えています」
ミー先生がそう言った。それを聞いて、子どもたちはみんな、とてもうれしそうな顔をしていた。目に涙を浮かべている子どももいた。
シャオパイの話によると、ここにいる子どもたちは、下界では、周りから認められなくて浮いている子どもたちばかりのようだった。でもここに来て、自分たちの感性や文才を認めてくれる先生と初めて出会えて、喜びが胸いっぱいに広がって、涙が自然と出てきたのではないかと、ぼくは思った。下界にいたころ、この子どもたちはいつも、うつうつとしていて、学ぶことに身が入らなかったり、いやな夢ばかり見て、うなされていた。しかし今はみんな生き生きとしていて、目が星のように、きらきらと輝いていた。環境の変化によって、こうも違ってくるのかと、ぼくは今、つくづくと思っていた。
「みなさんが、とても満足しているようで、わたしも、とてもうれしいです。でも学ぶことに終わりはありません。みなさん、もっと、いろいろなことを学びたいと思いませんか」
ミー先生がそう言うと
「思いまーす」
という声が、異口同音にあがった。
「分かりました。では、これからも、自然のなかのいろいろな事象をたくさん見て、たくさん学んでいきましょう」
ミー先生が、笑みを浮かべながら、そう言った。
「先生、よろしくお願いします」
ポニーテールに髪の毛を束ねた女の子が、そう言った。
「今度の宿題は何ですか」
眼鏡をかけた男の子が聞いていた。
「わたしは今までは宿題が嫌いでしたが、この学校に来てから、宿題をすることが、とても楽しくなりました。先生のおかげです。ありがとうございます」
髪に赤いリボンをつけた女の子が、そう答えていた。
「これからも宿題をたくさん出してください。早く宿題をしたくて、うずうずしています」
背が高くて体が大きい男の子が、そう答えていた。
それを聞いて、ミー先生が、にっこり、うなずいていた。そのあとミー先生が
「今度の新しい宿題は水について考えることです」
と言った。
「水ですか?」
「そうです。水です。水は、わたしたちの生活に欠かせないものだということを、みなさんは知っていると思います」
ミー先生がそう言うと、子どもたちは、みんな、うなずいていた。
「では、みなさんに聞きます。もし水がなかったら、どうなると思いますか?」
ミー先生がそう聞くと、われ先にとばかりに、子どもたちが手をあげた。
「では、李くん、答えてください」
ミー先生は、背が高くて、青いシャツを着た男の子に聞いていた。
「水がなかったら、人間は、のどが渇いて死んでしまいます。動物も同じです。植物も枯れてしまいます」
李くんが、そう答えていた。
「ほかに何か意見がありますか?」
ポニーテールに髪の毛を束ねた女の子が手を挙げた。
「蒋さん、答えてください」
「水がなかったら、地球にうるおいがなくて、生命がない星になっていたと思います」
蒋さんがそう答えていた。
「そうですね。その通りですね。この地球は水の惑星と呼ばれていて、地球のあちこちに水がたくさんあります」
ミー先生がそう言うと、子どもたちは、うなずいていた。
「では、みなさんに聞きます。水には、どんな種類の水がありますか?」
ミー先生がそう言うと、緑色のスカートをはいた背の高い女の子が手を挙げた。
「王さん、答えてください」
ミー先生がそう言った。
「海水、湖水、池の水、井戸の水、川の水、それから……」
王さんが頭のなかで、いろいろな水を思い浮かべていた。
「そうですね。ほかには、どんな水がありますか?」
ミー先生がそう言うと、今度は眼鏡をかけたやせた男の子が手を挙げた。
「陳くん、答えてください」
ミー先生がそう聞いた。
「雨水、露、雪、氷、霜、霧、ひょう、それから……」
陳くんは王さんとは違った視点から、地球上に存在する水のことを考えようとしていた。それを聞いて、帽子をかぶった柳くんが、首をかしげながら
「ちょっと待って。雪や霜や霧やひょうは、水と言えるのか?」
と異を唱えていた。
「言えるさ。雪や霜やひょうは、水が固まってできたものだし、霧は地面近くの空中にふわふわ浮いているたくさんの水滴からできているではないか」
陳くんが反問して、自説の正しさを主張していた。ほかの子どもたちも議論に加わって、言える派と、言えない派に分かれて、それぞれの意見を述べていた。
ミー先生は、どちらが正しいとは言わないで、どちらの意見にも、うんうんと、うなずきながら、静かに聞いているだけだった。考え方は人によって様々だから、子どもたちの判断にゆだねようとしているように見えた。
それからしばらくしてから、ミー先生が
「言えるか、言えないかに分かれて、考え方を深めることができたのは、とても有意義なことだったと思います。どちらの意見が正しいかについては、もう少し考えてから結論を出すことにしましょう。では今日の新しい宿題のことについて、もう少し具体的に話します。水はどこから流れてきているかについて調べることです。それが今日の宿題です。すぐれた宿題が提出されたら、今度もまた本にします。本のタイトルは『水の物語』です。これから水の源流を探しに行きます。その前にまず水の源流に対する自分たちのイメージを述べてください」
と言った。
「はーい、分かりました」
子どもたちは異口同音に、そう答えてから、さっそく述べ始めた。いろいろな考えが述べられた。
「雨は空から降ってくるから、水のもとは空にあるよ」
李くんが、そう言った。
「海や川の水はどうなの。空から降ってきたの」
蒋さんが疑問を投げかけていた。
「海の水は川から流れてきたものだし、川の水は奥山に源があって、そこから流れてきている」
帽子をかぶった柳くんが、そう答えていた。
「大きな川の水は小さな川の水がいくつも流れ込んで、できたものだ」
眼鏡をかけた陳くんが、そう言った。
「寒い地方では氷河が融けて川の水になることもあるわ」
王さんが、そう答えていた。
「わたしには、よく分からない……」
髪に赤いリボンをつけた唐さんは、そう答えていた。
子どもたちの意見を、ミー先生は耳を傾けながら熱心に聞いていた。子どもたちの意見が、ひととおり出たあと、ミー先生が
「ではこれから、みなさんたちをこの山の山頂に連れていきます。西山山脈のなかでも最高峰の山だから、この山の山頂からは、周りにあるすべての山がよく見えます」
と言った。
それからまもなく、子どもたちはミー先生に導かれながら、山頂に着いた。ぼくと老いらくさんとシャオパイも、ミー先生や子どもたちのあとからついて山頂に登った。
「みなさん、あそこを見てください」
山頂に立って、遠くの山を見ながら、ミー先生がそう言った。
「白い帯のようなものが、あの山の山頂付近にあるのが見えますか」
「見えます。あれは何ですか」
蒋さんが聞いていた。
「あれは万年雪です」
ミー先生が、そう答えていた。
「万年雪?」
蒋さんが、けげんそうな顔をしていた。
「そう、万年雪です。夏でも消えないで残っている雪のことを万年雪と言います。万年雪が積もっているあの山の谷には雪渓があります。雪や氷が一年中解けないで残っている谷が雪渓と呼ばれています。その雪渓の下に小さな川が流れていて、その川の底から水が、ぼこぼこと湧き出ています。そこが皆さんたちが住んでいる町を流れている川の源流です」
ミー先生がそう言った。
「へえー、そうなのだ。あんな遠い所から流れてきているのだ」
蒋さんが胸の思いを源流に馳せていた。
「あそこから始まって、わたしたちの町を通って流れていって、やがて広い海に流れていくのよね」
唐さんが、そう言った。
「そう思うと、何だかロマンティックな気分になるわ」
王さんが、目を輝かせながら、そう答えていた。
「あそこが、どんなところなのか行ってみたいなあ」
陳くんが、そう言った。
「雪渓や源流がどんなものか見てみたいな」
柳くんは心をときめかせていた。
「でも、ここからはとても遠そうに見える。山道も険しそう」
李くんが顔の表情を曇らせていた。
遠くにかすかに見える山を見ながら、子どもたちは、それぞれの思いを述べたり、遠すぎて行けそうもないことに、ため息をついたりしていた。
確かにその通りだった。遠くに見える山の山頂付近にかすかに見える万年雪に心を惹かれるものの、この山と、あの山の間には、いくつもの山々が高い壁のように立ちはだかっていて、とても行けそうには思えなかった。ぼーっとしながら、万年雪を見ていると、シャオパイが慌てて近づいてきて
「もうすぐ、強い狂風が吹き荒れそうだから気をつけて」
と言った。ぼくは、それを聞いて、びっくりした。以前も狂風に吹き飛ばされて気を失ったことがあったからだ。シャオパイが言ったことを、ぼくは老いらくさんにも告げた。老いらくさんも、びっくりしていた。ぼくは老いらくさんを、ぼくの体に、しっかりと、つかまえさせた。シャオパイは狂風のことをぼくに伝えると、すぐにミー先生のところに帰っていった。ミー先生は愛用のからかさを開いて、かさの柄についているボタンのなかの一つを押した。すると、からかさを持ったミー先生の体が宙に、ふわふわと浮き出した。
その光景を口をあんぐりと開けたまま、ぼくは、しばらく見ていた。それからまもなく、シャオパイが言ったように、強い狂風が吹いてきて、ぼくの体も宙に吹きあげられた。あっという間のできごとで、地に伏せて踏ん張ることさえできなかった。空中で何度も、くるくると、とんぼ返りをしたのは覚えているが、そのあと意識を失ってしまった。