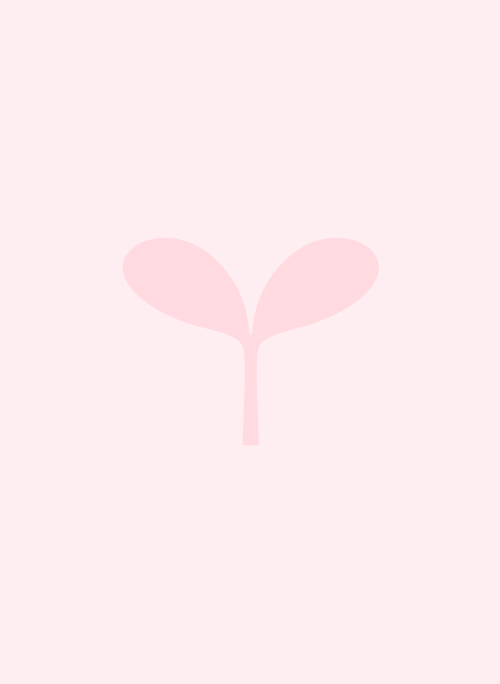天気……中秋節がやってきた。金木犀のかおりが漂うなか、人々はこの日を祝うために、うちの玄関や店の軒先に飾りをつけたり、月餅を買い求めたりしていた。中秋節の日の満月は一年のうちで、一番大きくて一番きれいな満月なので、家族そろって中秋の名月を眺めながら至福のひとときを過ごすことが、この国の人たちにとって大きな喜びとなっている。
今日は中秋節だ。家族みんなが集まって、きれいな月を眺めながら、満月のように欠けているところのない円満な家庭を祈ることが、この国の伝統的な習慣となっている。
ぼくたちが翠湖公園を離れてから、もう何日にもなるので、ぼくは今、妻猫やアーヤーやパントーのことを、とても懐かしく思っていた。中秋の名月が昇ってくる前に、サンパオを連れて翠湖公園へ帰り、家族みんなで美しい満月を眺めながら、秋の一夜を楽しく過ごしたいと、ぼくは心から思っていた。
「子どもたちは日ごとに大きくなっていくし、いつかは必ず、ぼくと妻猫のもとから離れていきます。家族みんながそろって過ごせる日がだんだん少なくなってくるので、中秋節のように家族みんなが集まる日を大切にしたいと思っています」
サンパオが木の実拾いに出かけていったあと、ぼくは老いらくさんに、そう言った。
「お前の気持ちが、わしにはよく分かるよ。わしにはもう家族はいないが、これまで長く生きてきたので、愛別離苦の悲しみをいくつも体験しているから」
老いらくさんがそう答えた。
「家族と別れてから初めて、家族と一緒にいることは何としあわせなことだろうと、ぼくは今、痛切に感じています」
ぼくがそう言うと、老いらくさんが
「愛別離苦の悲しみを知ることによって、再び会えた時に、いっそういとおしく思えてくる」
と、言った。ぼくはうなずいた。
「サンパオはまだ子どもなので、ぼく以上に、妻猫や、きょうだいに会えない寂しさを感じているかもしれません」
ぼくがそう言うと
「そうかもしれないが、サンパオは今度の旅を通して、いろいろな猫や犬と出会ったし、出会いを通して、いろいろなことを知ることができた。『かわいい子には旅をさせよ』というではないか」
と、老いらくさんが言った。
「そうですね。ぼくもそう思います」
ぼくはそう答えた。
「笑い猫、今日は中秋節だから、わしは月餅を食べたいよ」
老いらくさんがそう言った。
「そうですね。ぼくも月餅を食べたいです。サンパオも同じだと思います」
ぼくはそう答えた。
毎年、中秋節になると杜真子が気を利かせて、月餅を持ってきてくれるので、今年も持ってきてくれているかもしれない。妻猫やパントーやアーヤーが、月餅をほおばっている姿が目に浮かぶような気がした。
「ここには月餅はありませんが、何かそれに代わるものをサンパオにあげて、中秋節のプレゼントにすることはできないでしょうか」
ぼくは老いらくさんに聞いた。
「そうだなあ、何がいいかなあ……」
老いらくさんが考え込んでいた。ぼくも考えていた。
しばらくしてから、ぼくの頭に、ひらめいたものがあった。
「ぼくたちは黒騎士を探すために、今度の旅に出ましたよね。黒騎士らしい犬と出会って期待を膨らませたこともありました。しかし結局、ぬか喜びに終わってしまいました。でもついに、これまでで一番可能性が高い犬と出会いました。あの盲導犬が間違いなく黒騎士だということを確かめて、サンパオと友だちにすることができたら、サンパオにとって何よりのプレゼントになるのではないでしょうか」
ぼくはそう言った。
「それはいいかもしれないな。でもわしは、あの盲導犬が絶対に黒騎士だと、まだ決めつけているわけではない。サンパオを安易にあの盲導犬と友だちにすることには、もう少し慎重になったほうがいい」
老いらくさんがそう言った。ぼくは首を横に振った。
「老いらくさんがどう思おうと、サンパオは、あの盲導犬は間違いなく黒騎士だと思い込んでいます」
ぼくはそう答えた。
それからまもなく、サンパオが木の実拾いから戻ってきたので、ぼくは老いらくさんとの会話をやめた。老いらくさんはスイカボールの中で、じっとしていた。
「森の中にどんぐりがたくさん落ちていたので拾って食べてきたよ」
サンパオがそう言った。
「そうか。どんぐりは健康にいいそうだよ」
ぼくはそう答えた。
「今日は中秋節だから、うちでは月餅を食べているかもしれないね」
サンパオが家族のことに思いを馳せていた。
「そうだね、杜真子が持ってきてくれているかもしれないね」
ぼくはそう言った。
「いいなあ、ぼくも食べたいなあ」
サンパオが、うらやましそうな顔をしていた。
「月餅よりも、もっといいものを、父さんは今日、お前にプレゼントしようと思っている」
ぼくがそう言うと、サンパオが目を輝かせていた。
「何をくれるの」
「あの盲導犬が黒騎士に間違いないことを確かめてから、友だちにしてあげるよ。それが父さんからのプレゼントだ」
ぼくがそう言うと、サンパオが嬉しそうな顔をした。
「わあ、本当。でも、どうやって確かめるの」
サンパオが聞いた。
「機会を見て、話しかけてみることにするよ」
ぼくはそう答えた。
「あの盲導犬は、もうすでに、ぼくやお父さんのことに気がついているよね」
サンパオがそう言った。ぼくはうなずいた。
「父さんもそう思う。しかしあの盲導犬はピアノ調律師を導くことに集中していたので、ぼくたちを見ても見ぬふりをしてきた。ぼくたちのことに気をとられて、注意が疎かになって、ピアノ調律師が事故に巻き込まれたらいけないと思っていたからだろう。だからぼくもこれまで声をかけなかった。犬の言葉が話せる猫がいて、あとをずっと、つけてきたら、心中、穏やかではいられないだろうから。でも今日は機会を見て、思い切って声をかけて、黒騎士がどうか聞いてみることにするよ」
ぼくはそう言った。
「今日は中秋節だから、この日に黒騎士と友だちになれたら、一生、忘れられない大切な思い出になるね。月が、ぼくやお父さんの思いをくんでくれたらいいなあ」
サンパオがそう言った。
「杜真子が好きな歌に『月亮代表我的心(月はわたしの心を表す)』という歌がある。中秋節の時にはよく歌っていた。父さんは今、あの歌のことを思っている。月は何も言わなくても、ぼくたちの思いをきっと、くんでくれるよ」
ぼくはそう答えた。
「そうだね。ぼくもそう思う」
サンパオが確信に満ちた声で、そう言った。
ぼくとサンパオは、強い思いを持って、今日という日を迎えたので、朝早くからずっと、ピアノ調律師と盲導犬が、うちから出てくるのを、外でじっと待っていた。ところが、なかなか家の中から出てこなかった。家の中はひっそりしていて、歌を歌っている声や、ピアノを弾いている音もまったく聞こえてこなかった。
(どうしたのだろう)
ぼくは、けげんに思いながら、家の中の様子を、うかがっていた。サンパオも、小首をかしげながら、玄関の方を見ていた。
昼になっても、昼の三時を過ぎても、ピアノ調律師と盲導犬は外に出て来なかった。歌を歌っている声や、ピアノを弾いている音も、まったく聞こえてこなかった。
「どうしたのだろう。今日は中秋節なのに、楽しくないのかなあ。月餅を買いに行かないのかなあ」
サンパオがそう言った。
ぼくも一瞬、そう思ったが、ピアノ調律師の今の気持ちを推し量りながら
「今日は、家族みんなが集まって名月を観賞する日だから、家族がいなくて、一人ぼっちのピアノ調律師は、家族がいない寂しさを、家の中でじっと、かみしめているのではないのかな」
ぼくはそう言った。
「満月や月餅は丸い形をしていて、円満の象徴だから、家族もいなければ障害も負っているピアノ調律師は円満とは、ほど遠い境遇だから、中秋の日が来ても浮かれないし、月餅も食べないのだと思う」
ぼくがそう言うと、サンパオがうなずいた。
日が暮れ始めたころ、小鳥たちが森の中に帰ってくるのが見えた。たくさんの小鳥たちが群れをなしながら、ねぐらに帰っていた。それを見ていた時、山道を車が上ってくる音が聞こえた。びっくりして、音がするほうに目を向けると、ワゴン車が一台、近づいてきているのが見えた。ワゴン車はピアノ調律師が住んでいる家のすぐ前にある草地の中で止まった。中から全部で七人の人が降りてきた。その中の一人に、ぼくは見覚えがあった。ピアノ調律師が先日、仕事に出かけていった時に、部屋の中にいた、あの車いすの少女だった。
それからまもなく、ピアノ調律師の家の玄関のドアが今日、初めて開いた。車いすの少女を除く六人の若い男女がそのドアから家の中に入り、応接室に置かれていたピアノを外に運び出していた。ピアノは草地の真ん中に置かれた。そのあと六人はワゴン車の中に積まれていた折り畳みのいすを七脚下ろして、そのいすをピアノの前に半円形に並べた。半円形の真ん中に車いすの少女を座らせて、その左右に三人ずつ座った。これからここでコンサートが開かれることを、ぼくは知った。
空を見上げると、もうすでにきれいな満月が出ていて、満月からこぼれ出た清らかな光が辺り全体に柔らかく降り注いでいた。静寂な夜の森の中で、七人の若い人たちは、それぞれの思いを胸に秘めながら、夜空を静かに見上げていた。月を見ながら月餅を口にしている人もいた。
それからまもなく、ピアノ調律師が盲導犬に導かれながら、玄関の外に出てきた。七人の若い人たちは拍手で迎えた。ピアノ調律師は会釈をして拍手に応えてから、ピアノの前まで進み、いすに座ると、呼吸を整えてから、演奏を始めた。最初に弾いたのは、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第十四番の『月光』だった。静かにささやきかけてくるような、曲の始まりに、聞いている人たちはみんな心を奪われて、恍惚とした表情で見とれていた。そのあとピアノ調律師はドビュッシーの『月の光』を弾いた。ほろほろと降り注ぐ月の光を連想させるような甘美な旋律が、たゆたうように流れて、曲の美しさに誰もが酔いしれていた。ピアノ調律師は心の目と、研ぎ澄まされた感性で、作曲家が月に託して表現した音のイメージを的確にとらえて、聞く人の琴線に触れるような豊かな演奏をしていた。演奏の美しさに、夜鳴く鳥も声を出さず、森に住んでいる動物も聞き入って動き回らず、大地も、ぶるぶると揺れているように思えた。
人も鳥も動物も大地も、うっとりとして酔いしれているなか、盲導犬が、ピアノ調律師の足元からそっと離れて、ぼくたちのすぐ近くまでやってきた。チャンス到来とばかりに、ぼくは盲導犬に
「あなたは黒騎士ですよね」
と聞いた。盲導犬は、どきりとしたような表情をした。ぼくが犬の言葉を話せるとは思ってもいなかったからだろう。
「ぼくは猫ですが、犬の言葉も話せます。あなたは黒騎士ですよね」
ぼくは、もう一度聞いた。
「そうです。ぼくは黒騎士です」
盲導犬がそう答えた。
「よかった。会えて嬉しいです。ぼくと、ぼくの子どものサンパオは、あなたを探して、ここまでずっと旅をしてきました」
ぼくはそう言った。サンパオにも、この盲導犬は間違いなく黒騎士であることを伝えた。それを知って、サンパオもとても嬉しそうな顔をしていた。
月の光が、ほろほろと降り注ぎ、ピアノの美しい音が響くなか、サンパオと黒騎士はお互いに、瞳のなかを、しばらくじっと見つめ合っていた。そのあとサンパオは黒騎士の胸の中に飛び込んでいった。
「あなたたちが、ぼくに好意を抱いているのは知っていました」
黒騎士がサンパオを抱きかかえたまま、ぼくにそう言った。
「そうですか。うちのサンパオは、あなたを探して、あなたと友だちになりたいと、ずっと思っていました。サンパオと友だちになっていだけますか」
ぼくは黒騎士に聞いた。
「もちろんですよ」
黒騎士がそう答えた。ぼくはサンパオに黒騎士の言葉を伝えた。サンパオは喜びにあふれた顔をしていた。黒騎士はとても立派な犬なので、サンパオが、これから一生付き合っていけたら、得るものが多くて、サンパオも立派になる可能性にあふれている。そう思うとぼくも嬉しくなってきた。妻猫もたぶん喜んでいるだろう。ケータイ電話を持っていたら、今すぐにでも妻猫に電話して、ようやく黒騎士に会うことができた喜びを伝えたいくらいだった。ぼくがいつまでもサンパオのそばについているわけにはいかないから、サンパオが親離れして、うちを出ていく前に、通訳なしでも黒騎士と話せるように、ぼくはサンパオに折を見て、犬の言葉を教えたいと思っている。サンパオと黒騎士は、ぼくの前で一生変わらぬ友情の誓いを立てた。その場面を中秋の名月が空から見ていたので、間違いなく証人(?)となってくれることだろう。ぼくはそう思った。いずれにせよ、サンパオが無二の親友を得ることができたことは、ぼくにとっても大きな喜びだった。一緒に旅をしてきた老いらくさんはどう思っているのだろうか。ぼくはちょっと聞いてみたくなった。サンパオは黒騎士と出会った喜びで胸の中がいっぱいになり、ほかのことにはまったく注意がいっていなかったので、そのすきに、ぼくはスイカボールの中にいる老いらくさんに、小声で話しかけた。
「老いらくさん、ぼくやサンパオが思っていたとおり、ここにいる盲導犬は黒騎士でした。黒騎士はサンパオと永遠の友だちになることを誓ってくれました。老いらくさんは、これまでずっとサンパオの友だち選びには慎重になったほうがいいと言ってきましたが、もう何も、つべこべ言わないでしょう」
ぼくはそう聞いた。
「もちろんだよ。黒騎士はとても立派な犬だから、わしも一目置いている。サンパオが黒騎士と出会えて友だちになれたことを、わしもとても嬉しく思っている。サンパオがこれから生きていく上において、黒騎士はよい影響をたくさん与えてくれるだろう。よかった、よかった」
老いらくさんがそう答えた。
「ありがとうございます」
ぼくはお礼を言った。
「サンパオが黒騎士と友だちになれたことで、お前は完全に満足しているようだな。しかし、わしは少し違う。九十パーセントは満足しているがな」
老いらくさんがそう言った。
「あと十パーセントは何ですか」
ぼくは聞き返した。
「どんなにいい友だちであっても非の打ちどころがないほど完全無欠な友だちはいないからだ。それを補う意味で、別のよさを持っているものを、もうひとり友だちにしたほうがいいと、わしは思っている」
老いらくさんがそう言った。
「それはそうかもしれませんが、これからまた新しい友だちを探すのは大変ですよ」
ぼくはそう答えた。
「大変じゃないよ。お前の目の前にいるじゃないか。このわしだよ」
老いらくさんがそう言った。
「何を言っているのですか。ぼくは老いらくさんと友だちになれましたが、サンパオが老いらくさんと友だちになれるかどうか分かりません。サンパオにとって、老いらくさんはスイカボールの中に入っている虫としか思っていませんから。虫ではなくてネズミが入っていると分かったら、友だちになるどころか、食べてしまうかもしれません」
ぼくはそう答えた。
「そうか。それは残念だな。わしは黒騎士以上に長く生きてきたから、いろいろな経験をたくさん伝えることができる。わしの経験から学んだ知恵や教訓をお前がサンパオに伝えたらサンパオは立派な猫になることができるのだがなあ」
老いらくさんがそう言った。
「それはそうかもしれませんが、猫とネズミは天敵関係にあるので、老いらくさんの正体がネズミだと分かったらサンパオは本能的に飛びかかるかもしれません」
ぼくは、きっぱりとそう言った。
「分かったよ。わしはお前と友だちになれたが、あくまでもこれは特殊なケースであって、わしとお前は隠れ友にすぎないのか。何と悲しいことよ」
老いらくさんの声が沈んでいた。ぼくには返す言葉がなかった。
それからまもなく、ぼくは老いらくさんとの会話をやめて、夜空をふっと見上げた。きれいな満月が空の天頂付近まで移動していて、真上から明るい光が降り注いでいた。盲導犬はいつのまにかサンパオのもとを離れて、ピアノ調律師のすぐ横まで戻っていた。ピアノ調律師は、今はドヴォルザークの『月に寄せる歌』を弾いていた。ぼくが以前、杜真子のうちで飼われていた時に、杜真子がCDでよく聞いていた曲だ。この曲を聞くたびに、あの頃の懐かしい思い出が、ぼくの心の中に走馬灯のようによみがえってくる。月の光が、ほろほろとこぼれてくるような美しい音楽に、ぼくは身も心も酔いしれていた。聴衆もみんな陶酔に浸ったような表情で静かに聞き入っていた。曲が終わると、聴衆はピアノ調律師に暖かい拍手を送っていた。ピアノ調律師はそれに応えて深々と礼をしていた。盲導犬もピアノ調律師にならって、前足を立てて深々と礼をしていた。
車いすの少女が、ぼくとサンパオに気がついて、手に持っていた月餅を二つ、ぼくたちに持ってきてくれた。
ぼくはにっこりと笑みを浮かべながら、ありがとうの気持ちを伝えた。サンパオも、笑うことができるので、嬉々とした顔をしながら、感謝の気持ちを伝えていた。
月餅を食べながら、サンパオが
「うちでも今ごろは、妻猫とアーヤーとパントーは杜真子からもらった月餅を食べながら、中秋の名月を眺めているかなあ」
と言った。
「たぶん、そうだと思うよ」
ぼくはそう答えた。
「お父さん、これから急いでうちへ帰りませんか。お母さんやアーヤーやパントーと一緒に今夜の月を眺めたくなったから」
サンパオがそう言った。
「父さんもそう思っている。でも、ここからうちまでは少し遠いよ。ぼくたちが翠湖公園に帰り着いた時には、夜が明けていて、月はもう見えないかもしれないよ」
ぼくは心配そうな声で、そう言った。するとサンパオが
「大丈夫だよ。月はぼくたちの心をくんでくれるから、走って帰れば間に合うと思うよ」
と言った。
「そうだね。月は、ぼくたちの家族がみんな一緒に集まって眺めてくれるのをきっと待っているよ」
ぼくはそう答えた。
それからまもなく、ぼくは黒騎士のところまで行って
「これから、サンパオのことをよろしくお願いします」
と言った。黒騎士がうなずいた。
ぼくとサンパオは、そのあとすぐに森を出て、うちへ飛ぶように早く、帰っていった。老いらくさんも、スイカボールの中で体を丸くしながら、ころころと転がりながらついてきた。月明りに照らされながら、帰り道を急いでいると、木犀のかおりが、夜風に乗って、どこからか漂ってきた。
(ああ、今宵は何と美しいのだろう。清らかに輝く名月に、かぐわしい木犀のかおり……)
ぼくは走りながら、そう思った。黒騎士に会えた喜びに、ぼくもサンパオも心の中が満たされていて、自然のすべてが、とても美しく思えた。
「お父さん、ぼくは今日の日を一生、忘れない。中秋の名月のもとで黒騎士と永遠の友だちになる誓いを立てることができたから」
サンパオがそう言った。
「そうだね。父さんも今日の日を絶対に忘れない。これから黒騎士に師事して、立派な盲導猫になれるように頑張るのだよ。父さんもできるだけの援助をするから」
ぼくがそう言うと、サンパオがうなずいた。
月の光が、こうこうと輝くなかを、ぼくとサンパオと老いらくさんは、翠湖公園を目指して、わき目もふらずに、一目散に走っていった。
今日は中秋節だ。家族みんなが集まって、きれいな月を眺めながら、満月のように欠けているところのない円満な家庭を祈ることが、この国の伝統的な習慣となっている。
ぼくたちが翠湖公園を離れてから、もう何日にもなるので、ぼくは今、妻猫やアーヤーやパントーのことを、とても懐かしく思っていた。中秋の名月が昇ってくる前に、サンパオを連れて翠湖公園へ帰り、家族みんなで美しい満月を眺めながら、秋の一夜を楽しく過ごしたいと、ぼくは心から思っていた。
「子どもたちは日ごとに大きくなっていくし、いつかは必ず、ぼくと妻猫のもとから離れていきます。家族みんながそろって過ごせる日がだんだん少なくなってくるので、中秋節のように家族みんなが集まる日を大切にしたいと思っています」
サンパオが木の実拾いに出かけていったあと、ぼくは老いらくさんに、そう言った。
「お前の気持ちが、わしにはよく分かるよ。わしにはもう家族はいないが、これまで長く生きてきたので、愛別離苦の悲しみをいくつも体験しているから」
老いらくさんがそう答えた。
「家族と別れてから初めて、家族と一緒にいることは何としあわせなことだろうと、ぼくは今、痛切に感じています」
ぼくがそう言うと、老いらくさんが
「愛別離苦の悲しみを知ることによって、再び会えた時に、いっそういとおしく思えてくる」
と、言った。ぼくはうなずいた。
「サンパオはまだ子どもなので、ぼく以上に、妻猫や、きょうだいに会えない寂しさを感じているかもしれません」
ぼくがそう言うと
「そうかもしれないが、サンパオは今度の旅を通して、いろいろな猫や犬と出会ったし、出会いを通して、いろいろなことを知ることができた。『かわいい子には旅をさせよ』というではないか」
と、老いらくさんが言った。
「そうですね。ぼくもそう思います」
ぼくはそう答えた。
「笑い猫、今日は中秋節だから、わしは月餅を食べたいよ」
老いらくさんがそう言った。
「そうですね。ぼくも月餅を食べたいです。サンパオも同じだと思います」
ぼくはそう答えた。
毎年、中秋節になると杜真子が気を利かせて、月餅を持ってきてくれるので、今年も持ってきてくれているかもしれない。妻猫やパントーやアーヤーが、月餅をほおばっている姿が目に浮かぶような気がした。
「ここには月餅はありませんが、何かそれに代わるものをサンパオにあげて、中秋節のプレゼントにすることはできないでしょうか」
ぼくは老いらくさんに聞いた。
「そうだなあ、何がいいかなあ……」
老いらくさんが考え込んでいた。ぼくも考えていた。
しばらくしてから、ぼくの頭に、ひらめいたものがあった。
「ぼくたちは黒騎士を探すために、今度の旅に出ましたよね。黒騎士らしい犬と出会って期待を膨らませたこともありました。しかし結局、ぬか喜びに終わってしまいました。でもついに、これまでで一番可能性が高い犬と出会いました。あの盲導犬が間違いなく黒騎士だということを確かめて、サンパオと友だちにすることができたら、サンパオにとって何よりのプレゼントになるのではないでしょうか」
ぼくはそう言った。
「それはいいかもしれないな。でもわしは、あの盲導犬が絶対に黒騎士だと、まだ決めつけているわけではない。サンパオを安易にあの盲導犬と友だちにすることには、もう少し慎重になったほうがいい」
老いらくさんがそう言った。ぼくは首を横に振った。
「老いらくさんがどう思おうと、サンパオは、あの盲導犬は間違いなく黒騎士だと思い込んでいます」
ぼくはそう答えた。
それからまもなく、サンパオが木の実拾いから戻ってきたので、ぼくは老いらくさんとの会話をやめた。老いらくさんはスイカボールの中で、じっとしていた。
「森の中にどんぐりがたくさん落ちていたので拾って食べてきたよ」
サンパオがそう言った。
「そうか。どんぐりは健康にいいそうだよ」
ぼくはそう答えた。
「今日は中秋節だから、うちでは月餅を食べているかもしれないね」
サンパオが家族のことに思いを馳せていた。
「そうだね、杜真子が持ってきてくれているかもしれないね」
ぼくはそう言った。
「いいなあ、ぼくも食べたいなあ」
サンパオが、うらやましそうな顔をしていた。
「月餅よりも、もっといいものを、父さんは今日、お前にプレゼントしようと思っている」
ぼくがそう言うと、サンパオが目を輝かせていた。
「何をくれるの」
「あの盲導犬が黒騎士に間違いないことを確かめてから、友だちにしてあげるよ。それが父さんからのプレゼントだ」
ぼくがそう言うと、サンパオが嬉しそうな顔をした。
「わあ、本当。でも、どうやって確かめるの」
サンパオが聞いた。
「機会を見て、話しかけてみることにするよ」
ぼくはそう答えた。
「あの盲導犬は、もうすでに、ぼくやお父さんのことに気がついているよね」
サンパオがそう言った。ぼくはうなずいた。
「父さんもそう思う。しかしあの盲導犬はピアノ調律師を導くことに集中していたので、ぼくたちを見ても見ぬふりをしてきた。ぼくたちのことに気をとられて、注意が疎かになって、ピアノ調律師が事故に巻き込まれたらいけないと思っていたからだろう。だからぼくもこれまで声をかけなかった。犬の言葉が話せる猫がいて、あとをずっと、つけてきたら、心中、穏やかではいられないだろうから。でも今日は機会を見て、思い切って声をかけて、黒騎士がどうか聞いてみることにするよ」
ぼくはそう言った。
「今日は中秋節だから、この日に黒騎士と友だちになれたら、一生、忘れられない大切な思い出になるね。月が、ぼくやお父さんの思いをくんでくれたらいいなあ」
サンパオがそう言った。
「杜真子が好きな歌に『月亮代表我的心(月はわたしの心を表す)』という歌がある。中秋節の時にはよく歌っていた。父さんは今、あの歌のことを思っている。月は何も言わなくても、ぼくたちの思いをきっと、くんでくれるよ」
ぼくはそう答えた。
「そうだね。ぼくもそう思う」
サンパオが確信に満ちた声で、そう言った。
ぼくとサンパオは、強い思いを持って、今日という日を迎えたので、朝早くからずっと、ピアノ調律師と盲導犬が、うちから出てくるのを、外でじっと待っていた。ところが、なかなか家の中から出てこなかった。家の中はひっそりしていて、歌を歌っている声や、ピアノを弾いている音もまったく聞こえてこなかった。
(どうしたのだろう)
ぼくは、けげんに思いながら、家の中の様子を、うかがっていた。サンパオも、小首をかしげながら、玄関の方を見ていた。
昼になっても、昼の三時を過ぎても、ピアノ調律師と盲導犬は外に出て来なかった。歌を歌っている声や、ピアノを弾いている音も、まったく聞こえてこなかった。
「どうしたのだろう。今日は中秋節なのに、楽しくないのかなあ。月餅を買いに行かないのかなあ」
サンパオがそう言った。
ぼくも一瞬、そう思ったが、ピアノ調律師の今の気持ちを推し量りながら
「今日は、家族みんなが集まって名月を観賞する日だから、家族がいなくて、一人ぼっちのピアノ調律師は、家族がいない寂しさを、家の中でじっと、かみしめているのではないのかな」
ぼくはそう言った。
「満月や月餅は丸い形をしていて、円満の象徴だから、家族もいなければ障害も負っているピアノ調律師は円満とは、ほど遠い境遇だから、中秋の日が来ても浮かれないし、月餅も食べないのだと思う」
ぼくがそう言うと、サンパオがうなずいた。
日が暮れ始めたころ、小鳥たちが森の中に帰ってくるのが見えた。たくさんの小鳥たちが群れをなしながら、ねぐらに帰っていた。それを見ていた時、山道を車が上ってくる音が聞こえた。びっくりして、音がするほうに目を向けると、ワゴン車が一台、近づいてきているのが見えた。ワゴン車はピアノ調律師が住んでいる家のすぐ前にある草地の中で止まった。中から全部で七人の人が降りてきた。その中の一人に、ぼくは見覚えがあった。ピアノ調律師が先日、仕事に出かけていった時に、部屋の中にいた、あの車いすの少女だった。
それからまもなく、ピアノ調律師の家の玄関のドアが今日、初めて開いた。車いすの少女を除く六人の若い男女がそのドアから家の中に入り、応接室に置かれていたピアノを外に運び出していた。ピアノは草地の真ん中に置かれた。そのあと六人はワゴン車の中に積まれていた折り畳みのいすを七脚下ろして、そのいすをピアノの前に半円形に並べた。半円形の真ん中に車いすの少女を座らせて、その左右に三人ずつ座った。これからここでコンサートが開かれることを、ぼくは知った。
空を見上げると、もうすでにきれいな満月が出ていて、満月からこぼれ出た清らかな光が辺り全体に柔らかく降り注いでいた。静寂な夜の森の中で、七人の若い人たちは、それぞれの思いを胸に秘めながら、夜空を静かに見上げていた。月を見ながら月餅を口にしている人もいた。
それからまもなく、ピアノ調律師が盲導犬に導かれながら、玄関の外に出てきた。七人の若い人たちは拍手で迎えた。ピアノ調律師は会釈をして拍手に応えてから、ピアノの前まで進み、いすに座ると、呼吸を整えてから、演奏を始めた。最初に弾いたのは、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第十四番の『月光』だった。静かにささやきかけてくるような、曲の始まりに、聞いている人たちはみんな心を奪われて、恍惚とした表情で見とれていた。そのあとピアノ調律師はドビュッシーの『月の光』を弾いた。ほろほろと降り注ぐ月の光を連想させるような甘美な旋律が、たゆたうように流れて、曲の美しさに誰もが酔いしれていた。ピアノ調律師は心の目と、研ぎ澄まされた感性で、作曲家が月に託して表現した音のイメージを的確にとらえて、聞く人の琴線に触れるような豊かな演奏をしていた。演奏の美しさに、夜鳴く鳥も声を出さず、森に住んでいる動物も聞き入って動き回らず、大地も、ぶるぶると揺れているように思えた。
人も鳥も動物も大地も、うっとりとして酔いしれているなか、盲導犬が、ピアノ調律師の足元からそっと離れて、ぼくたちのすぐ近くまでやってきた。チャンス到来とばかりに、ぼくは盲導犬に
「あなたは黒騎士ですよね」
と聞いた。盲導犬は、どきりとしたような表情をした。ぼくが犬の言葉を話せるとは思ってもいなかったからだろう。
「ぼくは猫ですが、犬の言葉も話せます。あなたは黒騎士ですよね」
ぼくは、もう一度聞いた。
「そうです。ぼくは黒騎士です」
盲導犬がそう答えた。
「よかった。会えて嬉しいです。ぼくと、ぼくの子どものサンパオは、あなたを探して、ここまでずっと旅をしてきました」
ぼくはそう言った。サンパオにも、この盲導犬は間違いなく黒騎士であることを伝えた。それを知って、サンパオもとても嬉しそうな顔をしていた。
月の光が、ほろほろと降り注ぎ、ピアノの美しい音が響くなか、サンパオと黒騎士はお互いに、瞳のなかを、しばらくじっと見つめ合っていた。そのあとサンパオは黒騎士の胸の中に飛び込んでいった。
「あなたたちが、ぼくに好意を抱いているのは知っていました」
黒騎士がサンパオを抱きかかえたまま、ぼくにそう言った。
「そうですか。うちのサンパオは、あなたを探して、あなたと友だちになりたいと、ずっと思っていました。サンパオと友だちになっていだけますか」
ぼくは黒騎士に聞いた。
「もちろんですよ」
黒騎士がそう答えた。ぼくはサンパオに黒騎士の言葉を伝えた。サンパオは喜びにあふれた顔をしていた。黒騎士はとても立派な犬なので、サンパオが、これから一生付き合っていけたら、得るものが多くて、サンパオも立派になる可能性にあふれている。そう思うとぼくも嬉しくなってきた。妻猫もたぶん喜んでいるだろう。ケータイ電話を持っていたら、今すぐにでも妻猫に電話して、ようやく黒騎士に会うことができた喜びを伝えたいくらいだった。ぼくがいつまでもサンパオのそばについているわけにはいかないから、サンパオが親離れして、うちを出ていく前に、通訳なしでも黒騎士と話せるように、ぼくはサンパオに折を見て、犬の言葉を教えたいと思っている。サンパオと黒騎士は、ぼくの前で一生変わらぬ友情の誓いを立てた。その場面を中秋の名月が空から見ていたので、間違いなく証人(?)となってくれることだろう。ぼくはそう思った。いずれにせよ、サンパオが無二の親友を得ることができたことは、ぼくにとっても大きな喜びだった。一緒に旅をしてきた老いらくさんはどう思っているのだろうか。ぼくはちょっと聞いてみたくなった。サンパオは黒騎士と出会った喜びで胸の中がいっぱいになり、ほかのことにはまったく注意がいっていなかったので、そのすきに、ぼくはスイカボールの中にいる老いらくさんに、小声で話しかけた。
「老いらくさん、ぼくやサンパオが思っていたとおり、ここにいる盲導犬は黒騎士でした。黒騎士はサンパオと永遠の友だちになることを誓ってくれました。老いらくさんは、これまでずっとサンパオの友だち選びには慎重になったほうがいいと言ってきましたが、もう何も、つべこべ言わないでしょう」
ぼくはそう聞いた。
「もちろんだよ。黒騎士はとても立派な犬だから、わしも一目置いている。サンパオが黒騎士と出会えて友だちになれたことを、わしもとても嬉しく思っている。サンパオがこれから生きていく上において、黒騎士はよい影響をたくさん与えてくれるだろう。よかった、よかった」
老いらくさんがそう答えた。
「ありがとうございます」
ぼくはお礼を言った。
「サンパオが黒騎士と友だちになれたことで、お前は完全に満足しているようだな。しかし、わしは少し違う。九十パーセントは満足しているがな」
老いらくさんがそう言った。
「あと十パーセントは何ですか」
ぼくは聞き返した。
「どんなにいい友だちであっても非の打ちどころがないほど完全無欠な友だちはいないからだ。それを補う意味で、別のよさを持っているものを、もうひとり友だちにしたほうがいいと、わしは思っている」
老いらくさんがそう言った。
「それはそうかもしれませんが、これからまた新しい友だちを探すのは大変ですよ」
ぼくはそう答えた。
「大変じゃないよ。お前の目の前にいるじゃないか。このわしだよ」
老いらくさんがそう言った。
「何を言っているのですか。ぼくは老いらくさんと友だちになれましたが、サンパオが老いらくさんと友だちになれるかどうか分かりません。サンパオにとって、老いらくさんはスイカボールの中に入っている虫としか思っていませんから。虫ではなくてネズミが入っていると分かったら、友だちになるどころか、食べてしまうかもしれません」
ぼくはそう答えた。
「そうか。それは残念だな。わしは黒騎士以上に長く生きてきたから、いろいろな経験をたくさん伝えることができる。わしの経験から学んだ知恵や教訓をお前がサンパオに伝えたらサンパオは立派な猫になることができるのだがなあ」
老いらくさんがそう言った。
「それはそうかもしれませんが、猫とネズミは天敵関係にあるので、老いらくさんの正体がネズミだと分かったらサンパオは本能的に飛びかかるかもしれません」
ぼくは、きっぱりとそう言った。
「分かったよ。わしはお前と友だちになれたが、あくまでもこれは特殊なケースであって、わしとお前は隠れ友にすぎないのか。何と悲しいことよ」
老いらくさんの声が沈んでいた。ぼくには返す言葉がなかった。
それからまもなく、ぼくは老いらくさんとの会話をやめて、夜空をふっと見上げた。きれいな満月が空の天頂付近まで移動していて、真上から明るい光が降り注いでいた。盲導犬はいつのまにかサンパオのもとを離れて、ピアノ調律師のすぐ横まで戻っていた。ピアノ調律師は、今はドヴォルザークの『月に寄せる歌』を弾いていた。ぼくが以前、杜真子のうちで飼われていた時に、杜真子がCDでよく聞いていた曲だ。この曲を聞くたびに、あの頃の懐かしい思い出が、ぼくの心の中に走馬灯のようによみがえってくる。月の光が、ほろほろとこぼれてくるような美しい音楽に、ぼくは身も心も酔いしれていた。聴衆もみんな陶酔に浸ったような表情で静かに聞き入っていた。曲が終わると、聴衆はピアノ調律師に暖かい拍手を送っていた。ピアノ調律師はそれに応えて深々と礼をしていた。盲導犬もピアノ調律師にならって、前足を立てて深々と礼をしていた。
車いすの少女が、ぼくとサンパオに気がついて、手に持っていた月餅を二つ、ぼくたちに持ってきてくれた。
ぼくはにっこりと笑みを浮かべながら、ありがとうの気持ちを伝えた。サンパオも、笑うことができるので、嬉々とした顔をしながら、感謝の気持ちを伝えていた。
月餅を食べながら、サンパオが
「うちでも今ごろは、妻猫とアーヤーとパントーは杜真子からもらった月餅を食べながら、中秋の名月を眺めているかなあ」
と言った。
「たぶん、そうだと思うよ」
ぼくはそう答えた。
「お父さん、これから急いでうちへ帰りませんか。お母さんやアーヤーやパントーと一緒に今夜の月を眺めたくなったから」
サンパオがそう言った。
「父さんもそう思っている。でも、ここからうちまでは少し遠いよ。ぼくたちが翠湖公園に帰り着いた時には、夜が明けていて、月はもう見えないかもしれないよ」
ぼくは心配そうな声で、そう言った。するとサンパオが
「大丈夫だよ。月はぼくたちの心をくんでくれるから、走って帰れば間に合うと思うよ」
と言った。
「そうだね。月は、ぼくたちの家族がみんな一緒に集まって眺めてくれるのをきっと待っているよ」
ぼくはそう答えた。
それからまもなく、ぼくは黒騎士のところまで行って
「これから、サンパオのことをよろしくお願いします」
と言った。黒騎士がうなずいた。
ぼくとサンパオは、そのあとすぐに森を出て、うちへ飛ぶように早く、帰っていった。老いらくさんも、スイカボールの中で体を丸くしながら、ころころと転がりながらついてきた。月明りに照らされながら、帰り道を急いでいると、木犀のかおりが、夜風に乗って、どこからか漂ってきた。
(ああ、今宵は何と美しいのだろう。清らかに輝く名月に、かぐわしい木犀のかおり……)
ぼくは走りながら、そう思った。黒騎士に会えた喜びに、ぼくもサンパオも心の中が満たされていて、自然のすべてが、とても美しく思えた。
「お父さん、ぼくは今日の日を一生、忘れない。中秋の名月のもとで黒騎士と永遠の友だちになる誓いを立てることができたから」
サンパオがそう言った。
「そうだね。父さんも今日の日を絶対に忘れない。これから黒騎士に師事して、立派な盲導猫になれるように頑張るのだよ。父さんもできるだけの援助をするから」
ぼくがそう言うと、サンパオがうなずいた。
月の光が、こうこうと輝くなかを、ぼくとサンパオと老いらくさんは、翠湖公園を目指して、わき目もふらずに、一目散に走っていった。