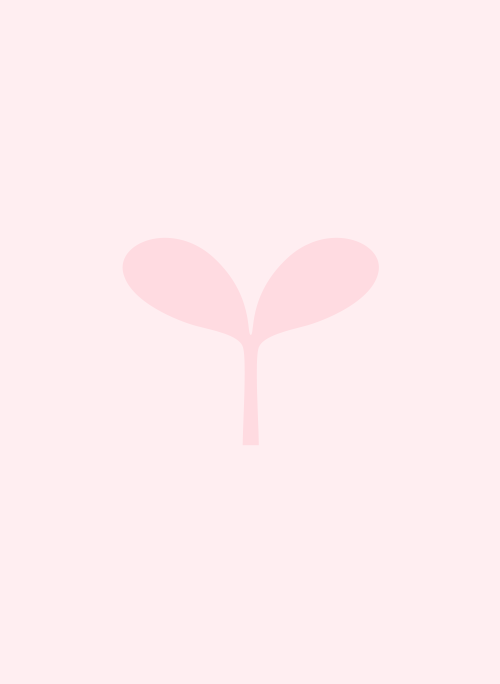天気……冬にはめったに見られないほど暖かくて、太陽の光が、きらきらと輝いている。ここちよい日差しを浴びて、冬枯れしていた木々の枝が、ほっと一息しているように感じられる。無機質なコンクリートのビルさえも冷たさが幾分、緩んで温かくなっているように見える。
昨夜は一晩中、ずっと馬小跳のことを思っていた。そして今朝早く、馬小跳のうちへ急いで出かけていった。
しばらく馬小跳のうちへ行っていなかったから、通い慣れている道も、見慣れているビルも、馬小跳のうちの近くにある花屋も、とてもなつかしく、そしてこれまで以上に親しみを感じた。
馬小跳が住んでいるマンション棟の出入口には警備員がいる。ぼくが棟のなかに入ろうとすると、けげんそうな目でじっと見たので、ぼくは軽く笑みを浮かべた。すると警備員も軽く笑みを浮かべて、ぼくをなかに通してくれた。それからまもなく、ぼくは窓伝いにのぼっていって、馬小跳のうちのバルコニーのところまで行った。
今は冬なので、馬小跳のうちの窓は全部ぴったり閉めてあった。カーテンも引かれていた。ぼくは馬小跳のうちのバルコニーで爪を出して、ガラス窓を軽くたたいた。数回たたいたとき、カーテンが開いて、カーテンの向こうから、馬小跳が眠そうな顔を出した。
「おー、誰かと思ったら、笑い猫か。おれに何か急用があって、こんなに朝早く、うちへ来たのか」
馬小跳は窓を開けて、そう言うと、ぼくを部屋のなかに入れてくれた。ぼくは、うなずいた。
(馬小跳をぼくのうちに連れていって、アーヤーを見たら、すぐに事の次第が飲みこめるはずだ)
ぼくはそう思った。
(馬小跳は何かが起きたことに気がついてくれたから、ぼくが慌てて、このうちをすぐに飛び出せば、きっと後を追ってついてくるだろう)
ぼくはそう思ったので、馬小跳の部屋をすぐに飛び出して階下に降りた。馬小跳がついてきているのが分かったので、ぼくはマンション棟の出入り口を出て、勢いよく走り始めた。馬小跳もあとから追いかけてきた。
(よかった。これでアーヤーに会わせることができる)
ぼくはそう思った。
ぼくは、うちをめざしてひたすら走った。馬小跳も息を弾ませながら、走ってついてきた。馬小跳は、ぼくのうちを知っているから、途中で、はぐれる心配はない。
ぼくが翠湖公園のなかにあるうちに着いてから、まもなく、馬小跳も、ぼくのうちにやってきた。ぼくはアーヤーを馬小跳の前に連れてきた。馬小跳はアーヤーをじっと見ていた。アーヤーも馬小跳をじっと見ていた。アーヤーののどはかれていたが、外から見たところ、普通の猫と少しも変わりがなかった。馬小跳はアーヤーの体全体を、念入りに見回しながら、けがをしているところがあるかないかを調べていた。でも特に何も見い出せなかったので、馬小跳は、小首をかしげていた。
「笑い猫、一体、何があったのだ。特に何も変わったところはないではないか」
馬小跳が、けげんそうな目で、ぼくを見た。
人の言葉が話せたら説明できるのに、話せないので、ぼくは今、もどかしてたまらなかった。ぼくはアーヤーに
「必死になって声を出そうとしているところを見せなさい」
と言った。アーヤーはうなずいた。
それからまもなく、アーヤーは口を大きく開けて、一生懸命、声を出そうとしていた。ところが声が全然出ていなかった。それを見て、馬小跳がようやくアーヤーの声が出なくなっていることに気がついた。
「分かった」
馬小跳はそう言うと、アーヤーを抱えて、ぼくのうちから急いで出ていった。ぼくも馬小跳のあとについて、うちを出た。翠湖公園の外にある歩道橋を渡り、路地を曲がり、通りを抜けて、町角を曲がったところにある動物病院の前まで来た。朝早い時間だったので、病院はまだ開いていなかったので、しばらく病院の外で待ってから、開くと同時に、病院のなかに駆け込んでいった。受付のところで、馬小跳がアーヤーの病状について、話していた。それからまもなく、馬小跳はアーヤーを抱えたまま、診察室のなかに入っていった。ぼくは待合室で待つことにした。診察室のなかにはドクターの裴帆先生がいらっしゃって、馬小跳に、いろいろと質問をしておられた。
「この子猫は、うちで飼っている猫ではないので、何が原因で、いつ声が出なくなったのか。ぼくにはよく分かりません。でも、かわいそうに思ったので、連れてきました」
馬小跳は、裴帆先生に、心配そうな声で、そう話していた。
「分かった。これから精密検査をするから、しばらく待合室で待っていてくれ」
裴帆先生が、そうおっしゃったので、馬小跳は診察室から出てきて、ぼくと並んで、診察結果を待っていた。
裴帆先生は、経験豊かなドクターなので、裴帆先生のおかげで助かった動物たちは数え切れないほどいる。裴帆先生はアーヤーの精密検査を終えると、馬小跳に診察室のなかに入るように、おっしゃった。馬小跳に診断書を見せながら
「この子猫は点滴をしなければならない。点滴室に連れて行きなさい」
と、おっしゃった。
「はい、分かりました」
馬小跳はそう答えてから、アーヤーを抱いて点滴室に行った。点滴室のなかには、ペルシャ猫が一匹と、ハスキー犬とシュナウザー犬が一匹ずついて、点滴を受けていた。
アーヤーが点滴を受けているときに、馬小跳は親友の唐飛、張達、毛超に電話をして、病院に来させた。三人のほかに、ぼくが一番好きな杜真子も急いでやってきた。杜真子を見て、馬小跳はとても不快そうな顔をした。
「お前を呼んでいないのに、どうして来たのだ」
それを聞いて、杜真子が口をとがらせていた。
「わたしが来たらいけなかったの」
「……」
馬小跳は返事が返せないでいた。
「馬小跳が笑い猫や、笑い猫の家族のことを大切に思っているように、わたしだって、大切に思っているわ」
杜真子が語気を強めて、そう言い返した。
「そうだ、そうだ。杜真子の言う通りだよ」
唐飛がすぐ援護射撃を放った。それを聞いて馬小跳が不機嫌そうな声で
「唐飛、おまえはいつも杜真子の味方ばかりしている」
と言った。
「そうじゃないよ。おれは事実を言っているだけだ。おまえこそ、いつも杜真子を目のかたきにしている。よくないよ。男子たるもの、女子とささいなことで争うものじゃないよ」
唐飛が自分のほうに理があると言わんばかりの顔をしていた。
「唐飛、おまえってやつは……」
馬小跳は頭にかちんと来て、唐飛に向かっていった。唐飛の胸ぐらをぐいとつかんで、こわい顔をして、げんこつを振り上げた。それを見て、張達が慌てて、すっ飛んできて、二人を引き離した。
「やめろよ。ここをどこだと思っているのだ。病院のなかで、ケンカなんかするものではない。みっともない」
張達がそう言った。
張達は四人のなかで、背が一番高いし、力も一番強い。ケンカも一番強い。テコンドーをいつも練習しているので、張達とケンカをしたら致命傷を受けかねない。みんなそのことを知っているので、張達を怒らせるようなことは誰もしない。そのために張達はこれまで一度もケンカをしたことがない。いつもケンカの仲裁役をしている。
張達が唐飛と馬小跳を離れさせたあと、二人の間に毛超が割って入った。
「みんな、何か言いたいことがあったら、落ち着いて話しなさい」
毛超がそう言った。毛超も四人のなかで仲裁役をしている。張達が体力にものを言わせて仲裁するのに対して、毛超は言葉の力で仲裁する。
「けなげな子猫が、どうして声が出なくなったのか、そのことについて話し合おう」
毛超が話題をさっと提起して、不穏な雰囲気を転じようとしていた。
「たぶん風邪だよ。うちのお母さんもこのあいだ風邪をひいて声が出なくなったから」
唐飛がそう言った。
「いや、おれはそうじゃないと思う。猫は魚が好きだから、魚の骨がのどに刺さったのではないかな」
毛超はそう言った。
「いや、おれはそうは思わない。毒のある草を食べたのが原因ではないかと思う。張達、おまえはどう思う」
馬小跳は自分の意見を述べてから、張達に聞いた。
「おれは……おれは……、よく分からない。笑い猫、おまえは分かるか」
張達がぼくに聞いた。
もちろん、ぼくには理由がよく分かっている。かわいそうな人を助けたいという願いを実現するために練習をし過ぎて、のどを痛めたのだ。そう話してあげたかった。でもぼくには人の言葉が話せないので、どうしようもなかった。
馬小跳がぼくの顔色をうかがっていた。ぼくは含み笑いを浮かべた。
「笑い猫がおれを見て笑った。おれの推測が正しかったのだ」
馬小跳がそう言った。
唐飛がそのあとぼくを見たので、ぼくは唐飛を見て、ふふふと笑った。唐飛はぼくの笑い顔を見て、自分の推測が正しかったと、思ったようだった。毛超もぼくのほうを見たので、くくくっと笑った。毛超もぼくの笑い顔を見て、自分の推測が正しかったと、思ったようだった。超達もぼくのほうを見たので、ひひひっと笑った。超達は何も推測できなかったので、きまり悪そうな顔をしていた。
「ごめん。おれには何も推測できなかった」
超達が小さな声で、つぶやくように言った。
そのとき杜真子が、きりっとした顔をして
「みんなの当てずっぽうな推測は、どれもみな、まちがっているわ」
と言った。
「じゃあ、おまえはどう思っているのだ」
馬小跳が聞いた。
「分からないわ。でもわたしは笑い猫といっしょに過ごしてきた時間が一番長いので、笑い猫が笑った意味が一番よく分かるわ」
杜真子がそう言った。
「笑い猫が笑いで表現する様々な思いを、みんなはあまりにも単純化し過ぎて見ているわ」
杜真子が仏頂面をしていた。
アーヤーは長い時間をかけて点滴をした。点滴が終わると、馬小跳たちは、代わる代わりにアーヤーと、ぼくを抱えながら、ぼくたちをうちまで連れて帰ってくれた。
昨夜は一晩中、ずっと馬小跳のことを思っていた。そして今朝早く、馬小跳のうちへ急いで出かけていった。
しばらく馬小跳のうちへ行っていなかったから、通い慣れている道も、見慣れているビルも、馬小跳のうちの近くにある花屋も、とてもなつかしく、そしてこれまで以上に親しみを感じた。
馬小跳が住んでいるマンション棟の出入口には警備員がいる。ぼくが棟のなかに入ろうとすると、けげんそうな目でじっと見たので、ぼくは軽く笑みを浮かべた。すると警備員も軽く笑みを浮かべて、ぼくをなかに通してくれた。それからまもなく、ぼくは窓伝いにのぼっていって、馬小跳のうちのバルコニーのところまで行った。
今は冬なので、馬小跳のうちの窓は全部ぴったり閉めてあった。カーテンも引かれていた。ぼくは馬小跳のうちのバルコニーで爪を出して、ガラス窓を軽くたたいた。数回たたいたとき、カーテンが開いて、カーテンの向こうから、馬小跳が眠そうな顔を出した。
「おー、誰かと思ったら、笑い猫か。おれに何か急用があって、こんなに朝早く、うちへ来たのか」
馬小跳は窓を開けて、そう言うと、ぼくを部屋のなかに入れてくれた。ぼくは、うなずいた。
(馬小跳をぼくのうちに連れていって、アーヤーを見たら、すぐに事の次第が飲みこめるはずだ)
ぼくはそう思った。
(馬小跳は何かが起きたことに気がついてくれたから、ぼくが慌てて、このうちをすぐに飛び出せば、きっと後を追ってついてくるだろう)
ぼくはそう思ったので、馬小跳の部屋をすぐに飛び出して階下に降りた。馬小跳がついてきているのが分かったので、ぼくはマンション棟の出入り口を出て、勢いよく走り始めた。馬小跳もあとから追いかけてきた。
(よかった。これでアーヤーに会わせることができる)
ぼくはそう思った。
ぼくは、うちをめざしてひたすら走った。馬小跳も息を弾ませながら、走ってついてきた。馬小跳は、ぼくのうちを知っているから、途中で、はぐれる心配はない。
ぼくが翠湖公園のなかにあるうちに着いてから、まもなく、馬小跳も、ぼくのうちにやってきた。ぼくはアーヤーを馬小跳の前に連れてきた。馬小跳はアーヤーをじっと見ていた。アーヤーも馬小跳をじっと見ていた。アーヤーののどはかれていたが、外から見たところ、普通の猫と少しも変わりがなかった。馬小跳はアーヤーの体全体を、念入りに見回しながら、けがをしているところがあるかないかを調べていた。でも特に何も見い出せなかったので、馬小跳は、小首をかしげていた。
「笑い猫、一体、何があったのだ。特に何も変わったところはないではないか」
馬小跳が、けげんそうな目で、ぼくを見た。
人の言葉が話せたら説明できるのに、話せないので、ぼくは今、もどかしてたまらなかった。ぼくはアーヤーに
「必死になって声を出そうとしているところを見せなさい」
と言った。アーヤーはうなずいた。
それからまもなく、アーヤーは口を大きく開けて、一生懸命、声を出そうとしていた。ところが声が全然出ていなかった。それを見て、馬小跳がようやくアーヤーの声が出なくなっていることに気がついた。
「分かった」
馬小跳はそう言うと、アーヤーを抱えて、ぼくのうちから急いで出ていった。ぼくも馬小跳のあとについて、うちを出た。翠湖公園の外にある歩道橋を渡り、路地を曲がり、通りを抜けて、町角を曲がったところにある動物病院の前まで来た。朝早い時間だったので、病院はまだ開いていなかったので、しばらく病院の外で待ってから、開くと同時に、病院のなかに駆け込んでいった。受付のところで、馬小跳がアーヤーの病状について、話していた。それからまもなく、馬小跳はアーヤーを抱えたまま、診察室のなかに入っていった。ぼくは待合室で待つことにした。診察室のなかにはドクターの裴帆先生がいらっしゃって、馬小跳に、いろいろと質問をしておられた。
「この子猫は、うちで飼っている猫ではないので、何が原因で、いつ声が出なくなったのか。ぼくにはよく分かりません。でも、かわいそうに思ったので、連れてきました」
馬小跳は、裴帆先生に、心配そうな声で、そう話していた。
「分かった。これから精密検査をするから、しばらく待合室で待っていてくれ」
裴帆先生が、そうおっしゃったので、馬小跳は診察室から出てきて、ぼくと並んで、診察結果を待っていた。
裴帆先生は、経験豊かなドクターなので、裴帆先生のおかげで助かった動物たちは数え切れないほどいる。裴帆先生はアーヤーの精密検査を終えると、馬小跳に診察室のなかに入るように、おっしゃった。馬小跳に診断書を見せながら
「この子猫は点滴をしなければならない。点滴室に連れて行きなさい」
と、おっしゃった。
「はい、分かりました」
馬小跳はそう答えてから、アーヤーを抱いて点滴室に行った。点滴室のなかには、ペルシャ猫が一匹と、ハスキー犬とシュナウザー犬が一匹ずついて、点滴を受けていた。
アーヤーが点滴を受けているときに、馬小跳は親友の唐飛、張達、毛超に電話をして、病院に来させた。三人のほかに、ぼくが一番好きな杜真子も急いでやってきた。杜真子を見て、馬小跳はとても不快そうな顔をした。
「お前を呼んでいないのに、どうして来たのだ」
それを聞いて、杜真子が口をとがらせていた。
「わたしが来たらいけなかったの」
「……」
馬小跳は返事が返せないでいた。
「馬小跳が笑い猫や、笑い猫の家族のことを大切に思っているように、わたしだって、大切に思っているわ」
杜真子が語気を強めて、そう言い返した。
「そうだ、そうだ。杜真子の言う通りだよ」
唐飛がすぐ援護射撃を放った。それを聞いて馬小跳が不機嫌そうな声で
「唐飛、おまえはいつも杜真子の味方ばかりしている」
と言った。
「そうじゃないよ。おれは事実を言っているだけだ。おまえこそ、いつも杜真子を目のかたきにしている。よくないよ。男子たるもの、女子とささいなことで争うものじゃないよ」
唐飛が自分のほうに理があると言わんばかりの顔をしていた。
「唐飛、おまえってやつは……」
馬小跳は頭にかちんと来て、唐飛に向かっていった。唐飛の胸ぐらをぐいとつかんで、こわい顔をして、げんこつを振り上げた。それを見て、張達が慌てて、すっ飛んできて、二人を引き離した。
「やめろよ。ここをどこだと思っているのだ。病院のなかで、ケンカなんかするものではない。みっともない」
張達がそう言った。
張達は四人のなかで、背が一番高いし、力も一番強い。ケンカも一番強い。テコンドーをいつも練習しているので、張達とケンカをしたら致命傷を受けかねない。みんなそのことを知っているので、張達を怒らせるようなことは誰もしない。そのために張達はこれまで一度もケンカをしたことがない。いつもケンカの仲裁役をしている。
張達が唐飛と馬小跳を離れさせたあと、二人の間に毛超が割って入った。
「みんな、何か言いたいことがあったら、落ち着いて話しなさい」
毛超がそう言った。毛超も四人のなかで仲裁役をしている。張達が体力にものを言わせて仲裁するのに対して、毛超は言葉の力で仲裁する。
「けなげな子猫が、どうして声が出なくなったのか、そのことについて話し合おう」
毛超が話題をさっと提起して、不穏な雰囲気を転じようとしていた。
「たぶん風邪だよ。うちのお母さんもこのあいだ風邪をひいて声が出なくなったから」
唐飛がそう言った。
「いや、おれはそうじゃないと思う。猫は魚が好きだから、魚の骨がのどに刺さったのではないかな」
毛超はそう言った。
「いや、おれはそうは思わない。毒のある草を食べたのが原因ではないかと思う。張達、おまえはどう思う」
馬小跳は自分の意見を述べてから、張達に聞いた。
「おれは……おれは……、よく分からない。笑い猫、おまえは分かるか」
張達がぼくに聞いた。
もちろん、ぼくには理由がよく分かっている。かわいそうな人を助けたいという願いを実現するために練習をし過ぎて、のどを痛めたのだ。そう話してあげたかった。でもぼくには人の言葉が話せないので、どうしようもなかった。
馬小跳がぼくの顔色をうかがっていた。ぼくは含み笑いを浮かべた。
「笑い猫がおれを見て笑った。おれの推測が正しかったのだ」
馬小跳がそう言った。
唐飛がそのあとぼくを見たので、ぼくは唐飛を見て、ふふふと笑った。唐飛はぼくの笑い顔を見て、自分の推測が正しかったと、思ったようだった。毛超もぼくのほうを見たので、くくくっと笑った。毛超もぼくの笑い顔を見て、自分の推測が正しかったと、思ったようだった。超達もぼくのほうを見たので、ひひひっと笑った。超達は何も推測できなかったので、きまり悪そうな顔をしていた。
「ごめん。おれには何も推測できなかった」
超達が小さな声で、つぶやくように言った。
そのとき杜真子が、きりっとした顔をして
「みんなの当てずっぽうな推測は、どれもみな、まちがっているわ」
と言った。
「じゃあ、おまえはどう思っているのだ」
馬小跳が聞いた。
「分からないわ。でもわたしは笑い猫といっしょに過ごしてきた時間が一番長いので、笑い猫が笑った意味が一番よく分かるわ」
杜真子がそう言った。
「笑い猫が笑いで表現する様々な思いを、みんなはあまりにも単純化し過ぎて見ているわ」
杜真子が仏頂面をしていた。
アーヤーは長い時間をかけて点滴をした。点滴が終わると、馬小跳たちは、代わる代わりにアーヤーと、ぼくを抱えながら、ぼくたちをうちまで連れて帰ってくれた。