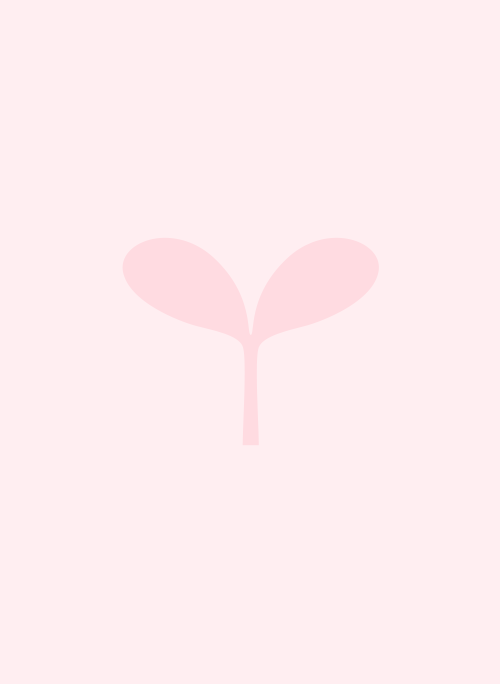天気……明け方、白い霧がうっすらと立ち込めていた。霧はレースのように柔らかく大地にまとわりついていて、木々や建物は霧にすっぽりと覆われていた。昼になると霧は晴れて、太陽の光が、さんさんと降り注いでいた。
アーヤーがのどを痛めて、声が出なくなった。練習のし過ぎによるものだ。シャオパイがびっくりして、アーヤーをすぐにうちへ連れ戻してきた。妻猫は心配で居ても立ってもいられなくなって、おろおろしていた。
「大丈夫でしょうか。もしかしたら、このままずっと声が出ないままなのでしょうか」
「そんなことはないと思うよ」
ぼくは妻猫の心配を払拭するために、そう言った。でも正直言って、ぼくも心中、穏やかではなかった。不安な気持ちがいっぱいで、胸のなかが、張り裂けそうで、がくがく揺れていたからだ。でも、ぼくはあえて、本当の気持ちは吐露しなかった。ぼくはアーヤーの父親だし、妻猫の夫だから、大黒柱のぼくが動揺している素振りを見せたら、アーヤーも妻猫も、今以上に不安な気持ちになるに違いないと思ったからだ。
アーヤーは練習のし過ぎで、とても疲れていたから、とりあえず、ぐっすり休ませることにした。そのあと徐々に体力を回復させることにした。
アーヤーが寝たのを見て、ぼくはうちを出て、翠湖の湖畔にそって散歩しながら、これからどうしたらよいのか、考えをめぐらせていた。
そのとき、向こうから老いらくさんがやってきた。
「やあ、笑い猫。元気か」
老いらくさんが声をかけてくれた。
老いらくさんは不思議なネズミだ。ぼくが翠湖公園のどのあたりを歩いていても、すぐ近くに現れることがよくあるからだ。
「ありがとう。ぼくは元気だけども……」
くぐもった声で、ぼくはあいさつを返した。
「どうしたのだ。何か心配事でもあるのか」
老いらくさんが聞き返した。
「実を言うと、アーヤーの声が出なくなったのです」
ぼくがそう答えると、老いらくさんの顔色が変わった。
「えっ、そうなのか。練習のし過ぎか」
ぼくはうなずいた。
「練習ができなくなったので、今は、うちに帰ってきています」
「そうか。心配だな」
老いらくさんの声が沈んでいた。
「でもアーヤーが夢を実現させるためには、避けては通れない関門だ。この関門をうまく抜けることができたら、その先に道が開けていく。アーヤーも、おまえも、お母さんも今はとても辛いだろうが、声は治療すればまた出るようになると思う。杞憂しないことだ」
老いらくさんがそう言った。
ぼくはうなずいた。
「『ウリを植えればウリがとれ、マメを植えればマメがとれる』という、ことわざを、おまえは知っているか」
老いらくさんが聞いた。
ぼくは首を横に振った。
「したことには、それに相応した結果が得られるということだよ」
老いらくさんが、そう説明してくれた。
「要するに、どんなに辛くても頑張って努力すれば、必ずそれに見合うだけの成果が得られるということですね」
ぼくがそう言うと、
「そうだよ、そのとおりだよ」
と、老いらくさんが答えた。
「分かりました。うちへ帰ったら、必ずアーヤーに伝えます」
ぼくは、そう答えた。
「人の言葉が話せるようになるためには、のどを痛めて声が出なくなるのは致し方ない。リスクは大きいが、それの見返りとして得られる喜びも大きい」
老いらくさんがそう言った。
老いらくさんの話を聞いて、ぼくの心のなかに少し明かりが灯ったように感じた。
しかしそうは言っても、ぼくが今一番気がかりなのは、やはり何と言っても、アーヤーの声の状態だった。夢の実現よりも何よりも、体が健康であることがまず第一だからだ。どうやったら一日も早く、アーヤーの声がまたもとのように出るようになるだろうか。ぼくの頭のなかは、今、そのことでいっぱいだった。老いらくさんは博学多才なので、もしかしたら、何かよい方法を知っているかもしれない。ぼくはそう思ったので、聞いてみることにした。すると老いらくさんは、しばらく考えてから
「のどの痛みを治療する薬を、わしは知っている。よく効くみたいだ」
と、答えた。
「どうして知っているのですか」
ぼくは、けげんに思って聞き返した。
「ゴミ箱のなかに、捨ててあるのを見たことがあるから」
老いらくさんがそう答えた。
「飲んだことはあるのですか」
「いいや、飲んだことはない。でも何度も見かけたから、よく効くのだ思う。
それでわしも少し拾ってきて、うちのなかにしまっている。取りに行ってくるから、ここでちょっと待っていてくれないか」
老いらくさんがそう言った。
「行かなくていいですよ」
ぼくは老いらくさんを引き留めた。
「どうしてだい。せっかく、わしがあげようと言っているのに」
老いらくさんが不快そうな顔をしていた。
「ご厚意はありがたいですが、人がゴミ箱に捨てた薬の大部分は期限切れだと思います。そういう薬は飲まないほうがいいです。悪いけど、ぼくは別の方法を考えます」
ぼくはそう言った。
それからまもなく、ぼくは老いらくさんと別れて、うちへ帰っていった。
「笑い猫、笑い猫」
帰る途中、ぼくは不意に声をかけられたので、びっくりした。九官鳥だった。
「誰かと思ったら、あなたでしたか」
ぼくは上を見ながら、九官鳥にあいさつをした。
「おまえの子どもの様子はどうだい。気になったので、様子を見に来たのだ」
九官鳥がそう言った。
「気遣ってくださってありがとうございます。今、うちで休んでいます」
ぼくはそう答えた。
「そうか。早く元気を取り戻してくれることを、おれは願っている」
「ありがとうございます」
九官鳥の思いやりが、ぼくはうれしかった。
「おれは今、西門から来たところだ」
九官鳥がそう言った。
「言葉が話せない障害者のお年寄りを手伝ってきたのですね」
「うん、そうだ」
九官鳥がうなずいた。
「早く、おまえの子どもの様子を見に行かなければと思ったので、何度も何度も売り声をあげた。それでたくさんの人たちが先を争うようにして新聞を買い求めていった。新聞はあっというまに全部売り切れてしまった」
九官鳥がそう言った。
「そうですか。それはよかったですね。お年寄りは、あなたのことに気がつきましたか」
ぼくが聞くと、九官鳥は首を横に振った。
「売るのに忙しくて、それ以外のことを考える余裕などなかったように見えた。それにぼくの声は全然耳に入っていないようだった」
九官鳥がそう答えた。
「そうですね。お年寄りは耳も聞こえない人だから、あなたの声は聞こえていなかったと思います。にもかかわらず、今まで全然売れなかった新聞が急に売れ出したので、あのお年寄りは、夢でも見ているのではないかと思っていたかもしれないです」
ぼくがそう言うと、九官鳥がうなずいた。
ぼくはそれからまもなく九官鳥を誘導しながら、うちの前まで帰ってきた。アーヤーはもう目を覚ましていた。
「アーヤーの気分はどうですか。声はまだ出ませんか」
ぼくは心配そうな声で妻猫に聞いた。妻猫は首を横に振った。
「焦らなくていいよ。おれも以前、この子と同じように声が出なくなったことがあったから」
九官鳥がそう言った。九官鳥が言ったことを、ぼくは妻猫に話した。すると妻猫は
「どうやって声がまた出るようになったのか、はやく聞いて」
と、ぼくにせいた。妻猫は救い主にすがるような目で九官鳥を見ていた。
ぼくは九官鳥に、妻猫の言葉を伝えた。
「いいよ。では話そう」
九官鳥がそう言った。それからまもなく九官鳥が話を始めた。
「あのころ、おれはまだ人の言葉が全然話せなかったから、毎日、懸命に練習していた。練習のし過ぎで、のどをやられて、のどから血が出た。こらえきれないような激痛に襲われたが、それでもめげないで、練習を続けていた。するとしまいには声が全然出なくなってしまった。それを見て飼い主さんが、おれを動物病院に連れて行ってくれた。病院で治療をしてもらって、それからまた声が出るようになった」
九官鳥がそう言った。九官鳥が言ったことを、ぼくは妻猫に話して聞かせた。すると妻猫の顔が急に明るくなった。
「お父さん、アーヤーに希望の光が見えてきたわ」
妻猫の声が弾んでいた。
「えっ、どういうことだい」
ぼくは妻猫に聞き返した。
「私たちもアーヤーを動物病院に連れて行って、お医者さんに診てもらいましょうよ」
妻猫がそう言った。
「なるほど、それはいいかもしれないな」
ぼくは、そう答えた。
「でも、どうやって連れていったらいいのだろう」
ぼくには、連れていく方法がさっぱり分からなかった。
「お父さん、覚えていますか」
妻猫がそう言った。何のことだろうと、ぼくは思った。
「ずっと昔、わたしをねたんだ野良猫が、ひそかに矢を放って、体にささって、生命が危険にさらされたときがあったではないですか。あのとき、お父さんがわたしを動物病院に連れていってくれたから、奇跡的に一命を取り留めることができた」
妻猫がそう言った。
「ああ、そう言えば、そういうことがあったなあ」
ぼくは昔のことを思い出した。でもあのとき、妻猫は意識を失って昏睡状態にあったから、動物病院に連れていってくれたのは、ぼくではなくて馬小跳だったことを全然覚えていなかった。ぼくが馬小跳を妻猫が倒れているところまでうまく誘導して連れていくことができたので、矢がささっている妻猫を見てびっくりした馬小跳が妻猫を抱えて、動物病院に連れて行ってくれた。病院に着くとドクターの裴帆先生が心をこめて診てくださったので、妻猫は助かったのだった。
日が暮れて、空がだんだん暗くなってきた。明日は、幸い、週末だから、馬小跳は学校に行かなくてもいい。ぼくは明日の朝早く、馬小跳のうちに行くことにした。
一晩中ずっと、ぼくは馬小跳のことを思っていた。馬小跳といっしょにいたころの楽しかった思い出について、なつかしく振り返っていた。たくさんの思い出が、今も鮮やかに心のなかによみがえってくる。今夜のぼくは、ぽかぽかとした温かい気持ちに包まれていた。
アーヤーがのどを痛めて、声が出なくなった。練習のし過ぎによるものだ。シャオパイがびっくりして、アーヤーをすぐにうちへ連れ戻してきた。妻猫は心配で居ても立ってもいられなくなって、おろおろしていた。
「大丈夫でしょうか。もしかしたら、このままずっと声が出ないままなのでしょうか」
「そんなことはないと思うよ」
ぼくは妻猫の心配を払拭するために、そう言った。でも正直言って、ぼくも心中、穏やかではなかった。不安な気持ちがいっぱいで、胸のなかが、張り裂けそうで、がくがく揺れていたからだ。でも、ぼくはあえて、本当の気持ちは吐露しなかった。ぼくはアーヤーの父親だし、妻猫の夫だから、大黒柱のぼくが動揺している素振りを見せたら、アーヤーも妻猫も、今以上に不安な気持ちになるに違いないと思ったからだ。
アーヤーは練習のし過ぎで、とても疲れていたから、とりあえず、ぐっすり休ませることにした。そのあと徐々に体力を回復させることにした。
アーヤーが寝たのを見て、ぼくはうちを出て、翠湖の湖畔にそって散歩しながら、これからどうしたらよいのか、考えをめぐらせていた。
そのとき、向こうから老いらくさんがやってきた。
「やあ、笑い猫。元気か」
老いらくさんが声をかけてくれた。
老いらくさんは不思議なネズミだ。ぼくが翠湖公園のどのあたりを歩いていても、すぐ近くに現れることがよくあるからだ。
「ありがとう。ぼくは元気だけども……」
くぐもった声で、ぼくはあいさつを返した。
「どうしたのだ。何か心配事でもあるのか」
老いらくさんが聞き返した。
「実を言うと、アーヤーの声が出なくなったのです」
ぼくがそう答えると、老いらくさんの顔色が変わった。
「えっ、そうなのか。練習のし過ぎか」
ぼくはうなずいた。
「練習ができなくなったので、今は、うちに帰ってきています」
「そうか。心配だな」
老いらくさんの声が沈んでいた。
「でもアーヤーが夢を実現させるためには、避けては通れない関門だ。この関門をうまく抜けることができたら、その先に道が開けていく。アーヤーも、おまえも、お母さんも今はとても辛いだろうが、声は治療すればまた出るようになると思う。杞憂しないことだ」
老いらくさんがそう言った。
ぼくはうなずいた。
「『ウリを植えればウリがとれ、マメを植えればマメがとれる』という、ことわざを、おまえは知っているか」
老いらくさんが聞いた。
ぼくは首を横に振った。
「したことには、それに相応した結果が得られるということだよ」
老いらくさんが、そう説明してくれた。
「要するに、どんなに辛くても頑張って努力すれば、必ずそれに見合うだけの成果が得られるということですね」
ぼくがそう言うと、
「そうだよ、そのとおりだよ」
と、老いらくさんが答えた。
「分かりました。うちへ帰ったら、必ずアーヤーに伝えます」
ぼくは、そう答えた。
「人の言葉が話せるようになるためには、のどを痛めて声が出なくなるのは致し方ない。リスクは大きいが、それの見返りとして得られる喜びも大きい」
老いらくさんがそう言った。
老いらくさんの話を聞いて、ぼくの心のなかに少し明かりが灯ったように感じた。
しかしそうは言っても、ぼくが今一番気がかりなのは、やはり何と言っても、アーヤーの声の状態だった。夢の実現よりも何よりも、体が健康であることがまず第一だからだ。どうやったら一日も早く、アーヤーの声がまたもとのように出るようになるだろうか。ぼくの頭のなかは、今、そのことでいっぱいだった。老いらくさんは博学多才なので、もしかしたら、何かよい方法を知っているかもしれない。ぼくはそう思ったので、聞いてみることにした。すると老いらくさんは、しばらく考えてから
「のどの痛みを治療する薬を、わしは知っている。よく効くみたいだ」
と、答えた。
「どうして知っているのですか」
ぼくは、けげんに思って聞き返した。
「ゴミ箱のなかに、捨ててあるのを見たことがあるから」
老いらくさんがそう答えた。
「飲んだことはあるのですか」
「いいや、飲んだことはない。でも何度も見かけたから、よく効くのだ思う。
それでわしも少し拾ってきて、うちのなかにしまっている。取りに行ってくるから、ここでちょっと待っていてくれないか」
老いらくさんがそう言った。
「行かなくていいですよ」
ぼくは老いらくさんを引き留めた。
「どうしてだい。せっかく、わしがあげようと言っているのに」
老いらくさんが不快そうな顔をしていた。
「ご厚意はありがたいですが、人がゴミ箱に捨てた薬の大部分は期限切れだと思います。そういう薬は飲まないほうがいいです。悪いけど、ぼくは別の方法を考えます」
ぼくはそう言った。
それからまもなく、ぼくは老いらくさんと別れて、うちへ帰っていった。
「笑い猫、笑い猫」
帰る途中、ぼくは不意に声をかけられたので、びっくりした。九官鳥だった。
「誰かと思ったら、あなたでしたか」
ぼくは上を見ながら、九官鳥にあいさつをした。
「おまえの子どもの様子はどうだい。気になったので、様子を見に来たのだ」
九官鳥がそう言った。
「気遣ってくださってありがとうございます。今、うちで休んでいます」
ぼくはそう答えた。
「そうか。早く元気を取り戻してくれることを、おれは願っている」
「ありがとうございます」
九官鳥の思いやりが、ぼくはうれしかった。
「おれは今、西門から来たところだ」
九官鳥がそう言った。
「言葉が話せない障害者のお年寄りを手伝ってきたのですね」
「うん、そうだ」
九官鳥がうなずいた。
「早く、おまえの子どもの様子を見に行かなければと思ったので、何度も何度も売り声をあげた。それでたくさんの人たちが先を争うようにして新聞を買い求めていった。新聞はあっというまに全部売り切れてしまった」
九官鳥がそう言った。
「そうですか。それはよかったですね。お年寄りは、あなたのことに気がつきましたか」
ぼくが聞くと、九官鳥は首を横に振った。
「売るのに忙しくて、それ以外のことを考える余裕などなかったように見えた。それにぼくの声は全然耳に入っていないようだった」
九官鳥がそう答えた。
「そうですね。お年寄りは耳も聞こえない人だから、あなたの声は聞こえていなかったと思います。にもかかわらず、今まで全然売れなかった新聞が急に売れ出したので、あのお年寄りは、夢でも見ているのではないかと思っていたかもしれないです」
ぼくがそう言うと、九官鳥がうなずいた。
ぼくはそれからまもなく九官鳥を誘導しながら、うちの前まで帰ってきた。アーヤーはもう目を覚ましていた。
「アーヤーの気分はどうですか。声はまだ出ませんか」
ぼくは心配そうな声で妻猫に聞いた。妻猫は首を横に振った。
「焦らなくていいよ。おれも以前、この子と同じように声が出なくなったことがあったから」
九官鳥がそう言った。九官鳥が言ったことを、ぼくは妻猫に話した。すると妻猫は
「どうやって声がまた出るようになったのか、はやく聞いて」
と、ぼくにせいた。妻猫は救い主にすがるような目で九官鳥を見ていた。
ぼくは九官鳥に、妻猫の言葉を伝えた。
「いいよ。では話そう」
九官鳥がそう言った。それからまもなく九官鳥が話を始めた。
「あのころ、おれはまだ人の言葉が全然話せなかったから、毎日、懸命に練習していた。練習のし過ぎで、のどをやられて、のどから血が出た。こらえきれないような激痛に襲われたが、それでもめげないで、練習を続けていた。するとしまいには声が全然出なくなってしまった。それを見て飼い主さんが、おれを動物病院に連れて行ってくれた。病院で治療をしてもらって、それからまた声が出るようになった」
九官鳥がそう言った。九官鳥が言ったことを、ぼくは妻猫に話して聞かせた。すると妻猫の顔が急に明るくなった。
「お父さん、アーヤーに希望の光が見えてきたわ」
妻猫の声が弾んでいた。
「えっ、どういうことだい」
ぼくは妻猫に聞き返した。
「私たちもアーヤーを動物病院に連れて行って、お医者さんに診てもらいましょうよ」
妻猫がそう言った。
「なるほど、それはいいかもしれないな」
ぼくは、そう答えた。
「でも、どうやって連れていったらいいのだろう」
ぼくには、連れていく方法がさっぱり分からなかった。
「お父さん、覚えていますか」
妻猫がそう言った。何のことだろうと、ぼくは思った。
「ずっと昔、わたしをねたんだ野良猫が、ひそかに矢を放って、体にささって、生命が危険にさらされたときがあったではないですか。あのとき、お父さんがわたしを動物病院に連れていってくれたから、奇跡的に一命を取り留めることができた」
妻猫がそう言った。
「ああ、そう言えば、そういうことがあったなあ」
ぼくは昔のことを思い出した。でもあのとき、妻猫は意識を失って昏睡状態にあったから、動物病院に連れていってくれたのは、ぼくではなくて馬小跳だったことを全然覚えていなかった。ぼくが馬小跳を妻猫が倒れているところまでうまく誘導して連れていくことができたので、矢がささっている妻猫を見てびっくりした馬小跳が妻猫を抱えて、動物病院に連れて行ってくれた。病院に着くとドクターの裴帆先生が心をこめて診てくださったので、妻猫は助かったのだった。
日が暮れて、空がだんだん暗くなってきた。明日は、幸い、週末だから、馬小跳は学校に行かなくてもいい。ぼくは明日の朝早く、馬小跳のうちに行くことにした。
一晩中ずっと、ぼくは馬小跳のことを思っていた。馬小跳といっしょにいたころの楽しかった思い出について、なつかしく振り返っていた。たくさんの思い出が、今も鮮やかに心のなかによみがえってくる。今夜のぼくは、ぽかぽかとした温かい気持ちに包まれていた。