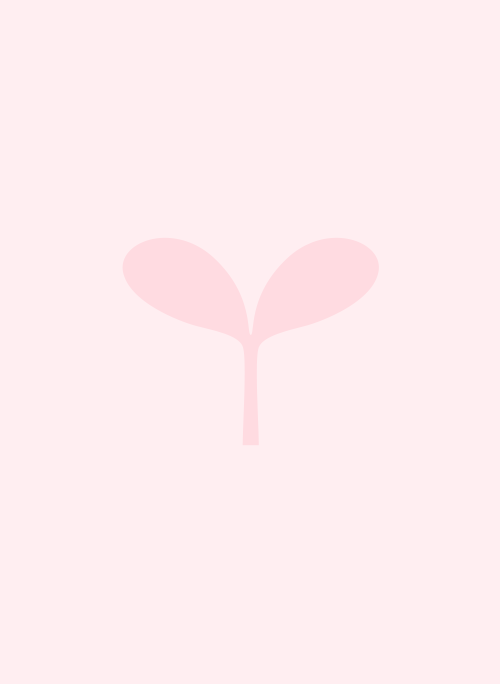天気……気温が昨日よりもさらに低くなった。風も昨日よりも強くなって、落ち葉がかさかさ舞っている。
朝早く、ぼくとアーヤーは予定より早く、シャオパイが住んでいる別荘に出かけていった。今日からアーヤーは正式に九官鳥に弟子入りをして、人の声の出し方を学ぶことにしたからだ。九官鳥にはアーヤーの気持ちをまだ伝えていなかった。伝えたら、たぶん馬鹿にされて、取り合ってもらえないと思ったからだ。
シャオパイが住んでいる別荘に着いて、ドアをノックすると、シャオパイが出てきた。
アーヤーが青い野菊の花を口にくわえているのを見て、シャオパイが
「アーヤー、おまえはどうして、ぼくが青い花が好きなのを知っていたの」
と、聞いていた。シャオパイは、てっきり、アーヤーが自分へのプレゼントを持ってきてくれたのだと思ったようだった。
「違う、違う、これはおまえへのプレゼントではない。九官鳥にあげるために持ってきたのだ」
ぼくはアーヤーに代わって、そう言った。するとシャオパイが不満そうな顔をした。「どうしてぼくではなくて、九官鳥にあげるの」
「アーヤーが今日から九官鳥に弟子入りして、人の声を学ぶことになったからだ」
ぼくはそう答えた。
「ああ、そうだったね。うまく学ぶことができたらいいね」
シャオパイがそう言った。
「ありがとう」
ぼくはシャオパイにそう言うと、応接室に行った。アーヤーもついてきた。
応接室の上にある止まり木に九官鳥が留まっていた。九官鳥は、ぼくとアーヤーを見ると
「やあ、おまえたちか」
と、止まり木の上から、ぼくたちに声をかけた。
九官鳥は、それからまもなく、ぼくたちの前に降りてきた。
アーヤーは九官鳥に青い野菊をあげた。そして九官鳥に大きく一礼をした。
「これは……どういうことなのだ」
九官鳥がぼくに聞いた。
「うちのアーヤーは、あなたのことをとても崇拝しています。あなたに弟子入りをして、人の声が話せるようになりたいと思っています」
ぼくが、わけを話した。
「ばかな」
九官鳥が高慢ちきな声でそう言った。
「この世の中に人の声が話せる猫がいるわけがない。おまえ、見たことがあるのか」
猫を見下したような言いぐさに、ぼくはかちんときた。でも、ここは気持ちをぐっと抑えた。
「ではお聞きしますが、ぼくと会う前に、笑える猫を見たことがありますか」
「……」
返事はなかった。答えに窮している九官鳥を見て、ぼくはさらに問い詰めた。
「ではもう一つ、お聞きしますが、ぼくと会う前に、動物の言葉をいろいろ話せたり、人の言葉が分る猫を見たことがありますか」
「……」
今度も答は返ってこなかった。
「多分、どちらもないだろうと思います」
九官鳥の心を読んで、ぼくはそう言った。
「そうだ、そのとおりだ」
九官鳥が、つぶやくように言った。
「世の中に不可能なことはないのです。どんなに不可能に思えることであっても、実際にやってみないと分からないのです」
ぼくの話を、九官鳥はうなずきながら聞いていた。
「見たところ、あなたも普通の鳥とはちがって、大きなことをやってやろうという気概にあふれていて、異彩を放っているように見えます」
ぼくはそう言って、九官鳥の歓心を買おうとした。
「そうか。そう見えるか。お前の目は節穴ではないな」
九官鳥は、まんざらでもないような顔をしていた。
「あなたの大きな志が何なのか、ぼくには分かります」
ぼくがそう言うと、
「そうか。何だと思うか」
と、九官鳥が聞いた。
「この世に奇跡を起こすことです」
ぼくは、そう答えた。
九官鳥は、それを聞いて
「よく分かったな。まあ、そういうところだ」
と、答えた。
「でしたら、今、あなたにチャンスが訪れているのです。アーヤーに人の言葉が話せるように指導できたら、奇跡を起こすことができるではないですか」
ぼくはそう言った。九官鳥が首をかしげた。
「確かに、そうかもしれないが、猫に人の言葉を習得させるのは奇跡のレベルをはるかに超えている。万に一つの可能性もない」
九官鳥がそう言った。
「おっしゃることはよく分かります。でも、それでもぼくはアーヤーの純粋な願いの実現に向けて、できるだけのことをしてあげたいのです。だめで、もともとだと、ぼくもアーヤーも思っていますから」
ぼくはそう言って、九官鳥にこびた。
「そうか。無駄だと百パーセント分かっていることをするのは、おれはあまり気乗りがしないのだがな」
九官鳥が渋い顔をしていた。
「人の言葉を習得するためには、大変な労力と時間を要する。物真似が得意なおれでも、毎日、血のにじむような練習を、何十回も何百回も繰り返しおこなってきた。あげくの果てには、飼い主さんが、うるさがって、おれを家から追い出してしまった。飼い主さんが、おれに何と言ったか分かるか」
九官鳥がそう言った。
「もう、おまえとは話したくない」
ぼくは、とっさにそう答えた。以前、九官鳥がそう言うのを何度も聞いたことがあったからだ。九官鳥が、けげんそうな顔をしていた。
「えっ、どうして分かるのだ」
「だって、あなたが一番よく話している人の言葉が、これだから」
ぼくは、そう答えて、くすくすっと笑った。
九官鳥は合点がいったような顔をしていた。
「物真似の習得は本当に大変だ。練習、練習の繰り返しで、のどを痛めて、口のなかが燃えるように熱くなるし、のどから血が出てくる」
九官鳥が苦渋の色を浮かべながら、そう言った。
九官鳥が言ったことを、ぼくはアーヤーに伝えた。
「お父さん、心配しないで。どんなに大変でもめげないわ。のどから血が出てもこわくないわ」
アーヤーは、けなげに、そう答えた。
ぼくはそれを聞いて、九官鳥に太鼓判を押した。
「どんなに大変でもめげないとアーヤーは言っています。アーヤーの一番よいところは、苦しさを恐れないところです。いったんやると自分で決めたことは、たとえ雨が降ろうが槍が降ろうが、けっして最後まであきらめない子どもです」
ぼくは誇らしげに、アーヤーのことを推賞した。
「そうか。それなら教えがいのある猫かもしれないな。しかし、おれはこれまで猫に教えたことはないし、猫にどうやって教えたらいいのかも分からない」
九官鳥は困惑げな顔をしていた。
「大丈夫です。あなたが今、教えることができる言葉を、何度も何度も繰り返して言って聞かせるだけでいいのです」
ぼくは九官鳥に助言した。
「そうか。それだったら、おれにもできないことがないかもしれないな」
九官鳥がそう答えた。
「でも、おまえはいったい、この子にどんな言葉を学ばせたいと思っているのだ」
九官鳥が聞いた。
「新聞の売り声です」
ぼくはそう答えた。
「新聞の売り声か。おれにはそんな言葉は話せないよ」
九官鳥が首を横に振った。
「大丈夫です。ぼくはこれから、あなたを連れて翠湖公園に行きます。公園の東門の前に新聞売りのお年寄りがいて、毎日、威勢のいい声で新聞を売っています。その売り声を覚えて、うちのアーヤーに教えてほしいのです」
ぼくはそう言った。
「分かった。新聞の売り声がどんなものか分からないが、新しい言葉を覚えるのも面白そうだな」
九官鳥がそう答えた。
九官鳥を外に連れ出すためには、シャオパイの許可を得なければならない。飼い主さんが留守の間、シャオパイがこの家の管理を任されているからだ。九官鳥の世話もシャオパイが任されている。
「シャオパイ、九官鳥を公園に連れていきたいと思っているが、いいかな」
ぼくがそう聞くと、シャオパイは顔の色を変えた。
「だめだよ。九官鳥が逃げていったら、ぼくはとても困るわ」
シャオパイの言っていることが、分からないでもなかった。シャオパイは九官鳥のことがあまり好きではなかったから、逃げたら逃げたで、それも悪くはないと思っているはずである。しかし飼い主さんが九官鳥をとても好きなことをシャオパイは知っていたので、逃げたら困ると思っていたのだ。シャオパイにとって、飼い主さんがすべてなので、飼い主さんに嫌われたら、ここにいられなくなる。シャオパイはそのことを心配していたのだ。
ぼくはシャオパイの気持ちを九官鳥に伝えた。
「そうか。おれはぜったい逃げないけどな」
九官鳥がそう言った。
「おれは、このうちが大好きだし、飼い主さんも優しい人だから、ぜったい逃げないよ。ここにいたら、毎日、おいしい卵と梨を食べさせてもらえるので、とても気に入っているのだ」
九官鳥が満ち足りたような声で、そう言った。
「そうか。では外に連れていく前に、ぜったいに逃げないと、ぼくに固く約束してほしい」
「いいよ。約束する」
九官鳥がそう答えた。
ぼくはシャオパイに九官鳥が言ったことを伝えた。
シャオパイはそれでもまだ警戒の糸を緩めないでいた。口では何とでも言えると思ったからだ。
「ぼくも一緒についていく。九官鳥が逃げないかどうか、しっかり見張っておく」
きぜんとした声で、シャオパイがそう言った。
「もし逃げたら、ぼくの責任ではないからね。笑い猫のあんちゃんのせいだからね」
シャオパイがそう言った。
「分かったよ。責任を取るよ」
ぼくは、そう答えた。
それからまもなく、ぼくたちは別荘を出て、翠湖公園へ向かって走っていった。ぼくとアーヤーとシャオパイは地上を走り、九官鳥はぼくたちの上を飛びながらついてきた。
「おまえたちは、走るのが、どうしてそんなに遅いのか」
九官鳥が上から、ぶつぶつ言っていた。
走るのが遅いのは、ぼくとアーヤーのせいではない。シャオパイのせいだ。シャオパイは、前をほとんど見ないで、上ばかり見て、九官鳥の動きを警戒していたからだ。前をほとんど見ないシャオパイは、まっすぐ走れないで、よろめくように走っていた。シャオパイのスピードに合わせるために、ぼくとアーヤーは走る速さを緩めざるを得なかったのだ。ぼくは、このことを九官鳥に告げた。
「おれは約束は必ず守る鳥だ。おまえと約束した通り、おれはぜったいに逃げたりしない。シャオパイにそう言ってくれ」
「分かった。すぐ伝える」
ぼくは九官鳥が言ったことをシャオパイに話した。
シャオパイはそれでもまだまっすぐ前を見ないで、頭を上げて九官鳥の動きをじっと見張っていた。
「信用することはいいことだよ。おまえは、ぼくの言っていることを信用しないのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「信用する」
即座に、シャオパイがそう答えた。
「そうだろう。だったら、九官鳥はぜったいに逃げないと、ぼくが保証しているのだから、ぼくの言うことを信用しなさいよ」
「分かった」
シャオパイがうなずいた。
それからまもなくシャオパイはようやく、前をしっかり見ながら走り始めた。もう九官鳥の動きをじっと見ることはなく前だけを見ながら走っていた。そのために、ぼくたちの走る速さがぐんぐん上がった。
ほどなく、ぼくたちは翠湖公園に着いた。東門に向かっていくと、東門の前に新聞売りのお年寄りがいて、新聞を売っている姿が見えてきた。
「人民日報、ローカル新聞、ビジネス新聞」
「人民日報、ローカル新聞、ビジネス新聞」
威勢のいい売り声が遠くまでよく響いていて、それにつられるように、たくさんの人たちが新聞売りのお年寄りの近くに寄ってきて、新聞を買い求める姿が目に映った。
「ほら、聞こえるでしょう。うちのアーヤーが学びたいと思っている言葉は、あの
売り声なのです」
ぼくは九官鳥にそう言った。
新聞を売っているお年寄りの近くに、木があったので、九官鳥は、木の枝に留まって、お年寄りの売り声を聞いていた。
「人民日報、ローカル新聞、ビジネス新聞」
「人民日報、ローカル新聞、ビジネス新聞」
お年寄りは声に抑揚をつけながら、弾むようなリズムに乗って楽しそうに売っていた。道を行く人たちは、その売り声に引きつけられるように、お年寄りの近くに次から次に寄ってきて、新聞が飛ぶように売れていた。お年寄りは、ほくほくしながら、新聞を渡したり、代金を受け取ったり、おつりを出したりしていた。とてもせわしなく見えたが、幸福感にあふれているように見えた。
ぼくとアーヤーとシャオパイも、お年寄りの売り声に引きつけられるようにして、お年寄りに近づいていった。ぼくたちは新聞は買えないけど、新聞がたくさん売れて気分がよさそうにしているお年寄りの近くにいたら、ぼくたちも幸せな気分になれるような気がしたからだ。
ところが実際はちがっていた。お年寄りは、ぼくたちを見ると、ひどく不愉快そうな顔をして、
「しっ、しっ、しっ、あっちいけ」
と言って、ぼくたちを追い払おうとした。目ざわりだったようだ。お年寄りはシャオパイを何と足げにした。
「ワン、ワン、ワン」
シャオパイが怒って、大きな声でほえたてた。シャオパイは小型犬なので、体は小さいが、ほえ声は大型犬に勝るとも劣らないほど大きい。新聞を買おうとしていた人たちが、びっくりして買わないで、逃げるようにして、その場を去っていった。
思わぬ事態になりそうだったので、ここは逃げるのが得策だと思って、ぼくはシャオパイとアーヤーに声をかけて、いっしょにその場をさっと離れていった。
「人民日報、ローカル新聞、ビジネス新聞」
お年寄りの抑揚のある売り声が、遠くからまた聞こえてきた。
ぼくとシャオパイとアーヤーが、お年寄りのいる売り場から逃げていくのを見て、九官鳥も、一緒についてきた。
「あの売り声を覚えましたか」
ぼくは上を向いて、九官鳥に聞いた。
「いや、まだだ。何十回も聞かなければ覚えることができない」
九官鳥がそう答えた。九官鳥はそれから、いぶかしそうな目でぼくを見た。
「おまえの子どもはどうして、あの売り声を覚えたいと思っているのか」
「すぐに分かるから、ついてきて」
ぼくは、そう答えて、九官鳥を今度は公園の西門に誘導した。
西門の前に着くと、言葉が話せない障害者のお年寄りがいて、新聞を売ろうとしていた。今日もまた全然売ることができなくて、お年寄りの前には、新聞が山積みされたままだった。
風が吹いていて、風に巻きあげられた落ち葉が、お年寄りの頭の上や、山積みされた新聞の上に、ひらひらと落ちていた。お年寄りは、手で落ち葉を払いながら、すぐ前を急ぎ足で、そそくさと通り過ぎていく人たちを、うつろな目で見ていた。やるせない悲しさが目のなかにあふれていた。
「分かっただろ」
ぼくは九官鳥に聞いた。
「うん、分かった」
九官鳥がうなずいた。
「おれはこれからすぐうちへ帰って練習する」
九官鳥が力強い声で、そう言ってくれた。
「お父さん、私も行く」
アーヤーも気合が入っていた。
(アーヤーがもし、あの売り声を早く習得できたら、言葉が話せない障害者のお年寄りが幸せになる日が早くやってくるにちがいない)
ぼくはそう思った。
朝早く、ぼくとアーヤーは予定より早く、シャオパイが住んでいる別荘に出かけていった。今日からアーヤーは正式に九官鳥に弟子入りをして、人の声の出し方を学ぶことにしたからだ。九官鳥にはアーヤーの気持ちをまだ伝えていなかった。伝えたら、たぶん馬鹿にされて、取り合ってもらえないと思ったからだ。
シャオパイが住んでいる別荘に着いて、ドアをノックすると、シャオパイが出てきた。
アーヤーが青い野菊の花を口にくわえているのを見て、シャオパイが
「アーヤー、おまえはどうして、ぼくが青い花が好きなのを知っていたの」
と、聞いていた。シャオパイは、てっきり、アーヤーが自分へのプレゼントを持ってきてくれたのだと思ったようだった。
「違う、違う、これはおまえへのプレゼントではない。九官鳥にあげるために持ってきたのだ」
ぼくはアーヤーに代わって、そう言った。するとシャオパイが不満そうな顔をした。「どうしてぼくではなくて、九官鳥にあげるの」
「アーヤーが今日から九官鳥に弟子入りして、人の声を学ぶことになったからだ」
ぼくはそう答えた。
「ああ、そうだったね。うまく学ぶことができたらいいね」
シャオパイがそう言った。
「ありがとう」
ぼくはシャオパイにそう言うと、応接室に行った。アーヤーもついてきた。
応接室の上にある止まり木に九官鳥が留まっていた。九官鳥は、ぼくとアーヤーを見ると
「やあ、おまえたちか」
と、止まり木の上から、ぼくたちに声をかけた。
九官鳥は、それからまもなく、ぼくたちの前に降りてきた。
アーヤーは九官鳥に青い野菊をあげた。そして九官鳥に大きく一礼をした。
「これは……どういうことなのだ」
九官鳥がぼくに聞いた。
「うちのアーヤーは、あなたのことをとても崇拝しています。あなたに弟子入りをして、人の声が話せるようになりたいと思っています」
ぼくが、わけを話した。
「ばかな」
九官鳥が高慢ちきな声でそう言った。
「この世の中に人の声が話せる猫がいるわけがない。おまえ、見たことがあるのか」
猫を見下したような言いぐさに、ぼくはかちんときた。でも、ここは気持ちをぐっと抑えた。
「ではお聞きしますが、ぼくと会う前に、笑える猫を見たことがありますか」
「……」
返事はなかった。答えに窮している九官鳥を見て、ぼくはさらに問い詰めた。
「ではもう一つ、お聞きしますが、ぼくと会う前に、動物の言葉をいろいろ話せたり、人の言葉が分る猫を見たことがありますか」
「……」
今度も答は返ってこなかった。
「多分、どちらもないだろうと思います」
九官鳥の心を読んで、ぼくはそう言った。
「そうだ、そのとおりだ」
九官鳥が、つぶやくように言った。
「世の中に不可能なことはないのです。どんなに不可能に思えることであっても、実際にやってみないと分からないのです」
ぼくの話を、九官鳥はうなずきながら聞いていた。
「見たところ、あなたも普通の鳥とはちがって、大きなことをやってやろうという気概にあふれていて、異彩を放っているように見えます」
ぼくはそう言って、九官鳥の歓心を買おうとした。
「そうか。そう見えるか。お前の目は節穴ではないな」
九官鳥は、まんざらでもないような顔をしていた。
「あなたの大きな志が何なのか、ぼくには分かります」
ぼくがそう言うと、
「そうか。何だと思うか」
と、九官鳥が聞いた。
「この世に奇跡を起こすことです」
ぼくは、そう答えた。
九官鳥は、それを聞いて
「よく分かったな。まあ、そういうところだ」
と、答えた。
「でしたら、今、あなたにチャンスが訪れているのです。アーヤーに人の言葉が話せるように指導できたら、奇跡を起こすことができるではないですか」
ぼくはそう言った。九官鳥が首をかしげた。
「確かに、そうかもしれないが、猫に人の言葉を習得させるのは奇跡のレベルをはるかに超えている。万に一つの可能性もない」
九官鳥がそう言った。
「おっしゃることはよく分かります。でも、それでもぼくはアーヤーの純粋な願いの実現に向けて、できるだけのことをしてあげたいのです。だめで、もともとだと、ぼくもアーヤーも思っていますから」
ぼくはそう言って、九官鳥にこびた。
「そうか。無駄だと百パーセント分かっていることをするのは、おれはあまり気乗りがしないのだがな」
九官鳥が渋い顔をしていた。
「人の言葉を習得するためには、大変な労力と時間を要する。物真似が得意なおれでも、毎日、血のにじむような練習を、何十回も何百回も繰り返しおこなってきた。あげくの果てには、飼い主さんが、うるさがって、おれを家から追い出してしまった。飼い主さんが、おれに何と言ったか分かるか」
九官鳥がそう言った。
「もう、おまえとは話したくない」
ぼくは、とっさにそう答えた。以前、九官鳥がそう言うのを何度も聞いたことがあったからだ。九官鳥が、けげんそうな顔をしていた。
「えっ、どうして分かるのだ」
「だって、あなたが一番よく話している人の言葉が、これだから」
ぼくは、そう答えて、くすくすっと笑った。
九官鳥は合点がいったような顔をしていた。
「物真似の習得は本当に大変だ。練習、練習の繰り返しで、のどを痛めて、口のなかが燃えるように熱くなるし、のどから血が出てくる」
九官鳥が苦渋の色を浮かべながら、そう言った。
九官鳥が言ったことを、ぼくはアーヤーに伝えた。
「お父さん、心配しないで。どんなに大変でもめげないわ。のどから血が出てもこわくないわ」
アーヤーは、けなげに、そう答えた。
ぼくはそれを聞いて、九官鳥に太鼓判を押した。
「どんなに大変でもめげないとアーヤーは言っています。アーヤーの一番よいところは、苦しさを恐れないところです。いったんやると自分で決めたことは、たとえ雨が降ろうが槍が降ろうが、けっして最後まであきらめない子どもです」
ぼくは誇らしげに、アーヤーのことを推賞した。
「そうか。それなら教えがいのある猫かもしれないな。しかし、おれはこれまで猫に教えたことはないし、猫にどうやって教えたらいいのかも分からない」
九官鳥は困惑げな顔をしていた。
「大丈夫です。あなたが今、教えることができる言葉を、何度も何度も繰り返して言って聞かせるだけでいいのです」
ぼくは九官鳥に助言した。
「そうか。それだったら、おれにもできないことがないかもしれないな」
九官鳥がそう答えた。
「でも、おまえはいったい、この子にどんな言葉を学ばせたいと思っているのだ」
九官鳥が聞いた。
「新聞の売り声です」
ぼくはそう答えた。
「新聞の売り声か。おれにはそんな言葉は話せないよ」
九官鳥が首を横に振った。
「大丈夫です。ぼくはこれから、あなたを連れて翠湖公園に行きます。公園の東門の前に新聞売りのお年寄りがいて、毎日、威勢のいい声で新聞を売っています。その売り声を覚えて、うちのアーヤーに教えてほしいのです」
ぼくはそう言った。
「分かった。新聞の売り声がどんなものか分からないが、新しい言葉を覚えるのも面白そうだな」
九官鳥がそう答えた。
九官鳥を外に連れ出すためには、シャオパイの許可を得なければならない。飼い主さんが留守の間、シャオパイがこの家の管理を任されているからだ。九官鳥の世話もシャオパイが任されている。
「シャオパイ、九官鳥を公園に連れていきたいと思っているが、いいかな」
ぼくがそう聞くと、シャオパイは顔の色を変えた。
「だめだよ。九官鳥が逃げていったら、ぼくはとても困るわ」
シャオパイの言っていることが、分からないでもなかった。シャオパイは九官鳥のことがあまり好きではなかったから、逃げたら逃げたで、それも悪くはないと思っているはずである。しかし飼い主さんが九官鳥をとても好きなことをシャオパイは知っていたので、逃げたら困ると思っていたのだ。シャオパイにとって、飼い主さんがすべてなので、飼い主さんに嫌われたら、ここにいられなくなる。シャオパイはそのことを心配していたのだ。
ぼくはシャオパイの気持ちを九官鳥に伝えた。
「そうか。おれはぜったい逃げないけどな」
九官鳥がそう言った。
「おれは、このうちが大好きだし、飼い主さんも優しい人だから、ぜったい逃げないよ。ここにいたら、毎日、おいしい卵と梨を食べさせてもらえるので、とても気に入っているのだ」
九官鳥が満ち足りたような声で、そう言った。
「そうか。では外に連れていく前に、ぜったいに逃げないと、ぼくに固く約束してほしい」
「いいよ。約束する」
九官鳥がそう答えた。
ぼくはシャオパイに九官鳥が言ったことを伝えた。
シャオパイはそれでもまだ警戒の糸を緩めないでいた。口では何とでも言えると思ったからだ。
「ぼくも一緒についていく。九官鳥が逃げないかどうか、しっかり見張っておく」
きぜんとした声で、シャオパイがそう言った。
「もし逃げたら、ぼくの責任ではないからね。笑い猫のあんちゃんのせいだからね」
シャオパイがそう言った。
「分かったよ。責任を取るよ」
ぼくは、そう答えた。
それからまもなく、ぼくたちは別荘を出て、翠湖公園へ向かって走っていった。ぼくとアーヤーとシャオパイは地上を走り、九官鳥はぼくたちの上を飛びながらついてきた。
「おまえたちは、走るのが、どうしてそんなに遅いのか」
九官鳥が上から、ぶつぶつ言っていた。
走るのが遅いのは、ぼくとアーヤーのせいではない。シャオパイのせいだ。シャオパイは、前をほとんど見ないで、上ばかり見て、九官鳥の動きを警戒していたからだ。前をほとんど見ないシャオパイは、まっすぐ走れないで、よろめくように走っていた。シャオパイのスピードに合わせるために、ぼくとアーヤーは走る速さを緩めざるを得なかったのだ。ぼくは、このことを九官鳥に告げた。
「おれは約束は必ず守る鳥だ。おまえと約束した通り、おれはぜったいに逃げたりしない。シャオパイにそう言ってくれ」
「分かった。すぐ伝える」
ぼくは九官鳥が言ったことをシャオパイに話した。
シャオパイはそれでもまだまっすぐ前を見ないで、頭を上げて九官鳥の動きをじっと見張っていた。
「信用することはいいことだよ。おまえは、ぼくの言っていることを信用しないのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「信用する」
即座に、シャオパイがそう答えた。
「そうだろう。だったら、九官鳥はぜったいに逃げないと、ぼくが保証しているのだから、ぼくの言うことを信用しなさいよ」
「分かった」
シャオパイがうなずいた。
それからまもなくシャオパイはようやく、前をしっかり見ながら走り始めた。もう九官鳥の動きをじっと見ることはなく前だけを見ながら走っていた。そのために、ぼくたちの走る速さがぐんぐん上がった。
ほどなく、ぼくたちは翠湖公園に着いた。東門に向かっていくと、東門の前に新聞売りのお年寄りがいて、新聞を売っている姿が見えてきた。
「人民日報、ローカル新聞、ビジネス新聞」
「人民日報、ローカル新聞、ビジネス新聞」
威勢のいい売り声が遠くまでよく響いていて、それにつられるように、たくさんの人たちが新聞売りのお年寄りの近くに寄ってきて、新聞を買い求める姿が目に映った。
「ほら、聞こえるでしょう。うちのアーヤーが学びたいと思っている言葉は、あの
売り声なのです」
ぼくは九官鳥にそう言った。
新聞を売っているお年寄りの近くに、木があったので、九官鳥は、木の枝に留まって、お年寄りの売り声を聞いていた。
「人民日報、ローカル新聞、ビジネス新聞」
「人民日報、ローカル新聞、ビジネス新聞」
お年寄りは声に抑揚をつけながら、弾むようなリズムに乗って楽しそうに売っていた。道を行く人たちは、その売り声に引きつけられるように、お年寄りの近くに次から次に寄ってきて、新聞が飛ぶように売れていた。お年寄りは、ほくほくしながら、新聞を渡したり、代金を受け取ったり、おつりを出したりしていた。とてもせわしなく見えたが、幸福感にあふれているように見えた。
ぼくとアーヤーとシャオパイも、お年寄りの売り声に引きつけられるようにして、お年寄りに近づいていった。ぼくたちは新聞は買えないけど、新聞がたくさん売れて気分がよさそうにしているお年寄りの近くにいたら、ぼくたちも幸せな気分になれるような気がしたからだ。
ところが実際はちがっていた。お年寄りは、ぼくたちを見ると、ひどく不愉快そうな顔をして、
「しっ、しっ、しっ、あっちいけ」
と言って、ぼくたちを追い払おうとした。目ざわりだったようだ。お年寄りはシャオパイを何と足げにした。
「ワン、ワン、ワン」
シャオパイが怒って、大きな声でほえたてた。シャオパイは小型犬なので、体は小さいが、ほえ声は大型犬に勝るとも劣らないほど大きい。新聞を買おうとしていた人たちが、びっくりして買わないで、逃げるようにして、その場を去っていった。
思わぬ事態になりそうだったので、ここは逃げるのが得策だと思って、ぼくはシャオパイとアーヤーに声をかけて、いっしょにその場をさっと離れていった。
「人民日報、ローカル新聞、ビジネス新聞」
お年寄りの抑揚のある売り声が、遠くからまた聞こえてきた。
ぼくとシャオパイとアーヤーが、お年寄りのいる売り場から逃げていくのを見て、九官鳥も、一緒についてきた。
「あの売り声を覚えましたか」
ぼくは上を向いて、九官鳥に聞いた。
「いや、まだだ。何十回も聞かなければ覚えることができない」
九官鳥がそう答えた。九官鳥はそれから、いぶかしそうな目でぼくを見た。
「おまえの子どもはどうして、あの売り声を覚えたいと思っているのか」
「すぐに分かるから、ついてきて」
ぼくは、そう答えて、九官鳥を今度は公園の西門に誘導した。
西門の前に着くと、言葉が話せない障害者のお年寄りがいて、新聞を売ろうとしていた。今日もまた全然売ることができなくて、お年寄りの前には、新聞が山積みされたままだった。
風が吹いていて、風に巻きあげられた落ち葉が、お年寄りの頭の上や、山積みされた新聞の上に、ひらひらと落ちていた。お年寄りは、手で落ち葉を払いながら、すぐ前を急ぎ足で、そそくさと通り過ぎていく人たちを、うつろな目で見ていた。やるせない悲しさが目のなかにあふれていた。
「分かっただろ」
ぼくは九官鳥に聞いた。
「うん、分かった」
九官鳥がうなずいた。
「おれはこれからすぐうちへ帰って練習する」
九官鳥が力強い声で、そう言ってくれた。
「お父さん、私も行く」
アーヤーも気合が入っていた。
(アーヤーがもし、あの売り声を早く習得できたら、言葉が話せない障害者のお年寄りが幸せになる日が早くやってくるにちがいない)
ぼくはそう思った。