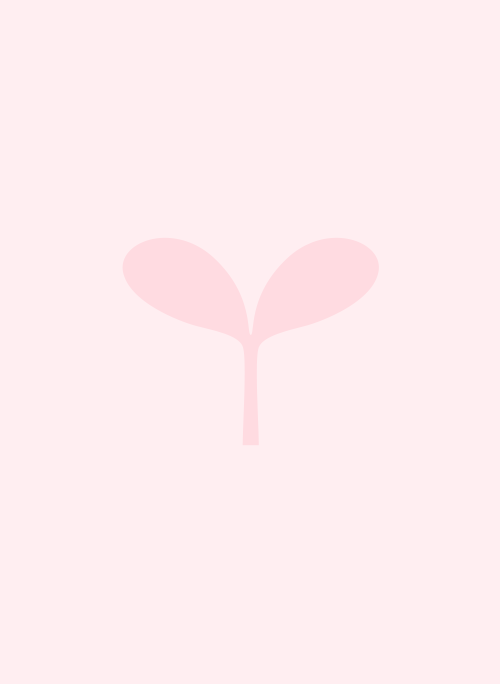天気……秋風が強く吹いて、黄金色に色づいたイチョウの木の葉はすっかり散ってしまった。いよいよ冬の到来だ。
アーヤーが二つ目の願いをかなえるために、シャオパイが住んでいる別荘に行って、九官鳥に教えを乞うことができるかどうかは、こちらの意思だけでは決めることができない。九官鳥がアーヤーに教えてくれるかや、飼い主さんが許可してくれるかや、アーヤーがシャオパイと、うまくやっていけるかどうかによって決まる。シャオパイには、もうすでにアーヤーの願いを伝えていた。飼い主さんは今、不在なので、飼い主さんが帰ってくる前に、アーヤーを毎日、別荘に行かせて環境に慣れさせたり、シャオパイとうまくやっていけるかどうか見てみることにした。
昨日、ぼくはシャオパイに
「アーヤーのことをどう思う」
と、聞いた。するとシャオパイは
「とてもいいよ。来たばかりなのに、花壇にいたネズミが一匹もいなくなった」
と、答えてくれた。
「アーヤーはお母さんにそっくりだね。ネズミのつかまえ方もとても品があって」
シャオパイがそう言って、アーヤーのことを、しきりにほめてくれた。
「アーヤーの性格についてはどう思う。おまえと、気が合いそうか」
ぼくが心配そうに聞くと、
「うん、もちろん、合うよ」
と、シャオパイが答えてくれた。
「笑い猫のあんちゃんと、奥さんが猫のなかで最高の猫だけど、アーヤーは、どちらからも、いいところを受け継いでいる。あんちゃんの知恵と、奥さんの善良さをね」
シャオパイがそう言ってくれたので、ぼくはなんだか照れくさくなった。
ともあれ、シャオパイがアーヤーのことを気に入ってくれて、よかった。でもそうは言っても、やはりまだ心のなかに、少し気がかりなことがある。シャオパイの飼い主さんがアーヤーのことをどう思ってくれるか分からなかったからだ。ぼくのそういった気持ちを察して、シャオパイが
「大丈夫よ。心配いらないよ」
と、言ってくれた。
「ぼくの飼い主さんが、ぼくをとても好きなのは、あんちゃんも知っているでしょ」
シャオパイが聞いた。ぼくはうなずいた。
「ぼくが好きなものは飼い主さんも好きだから、ぼくがアーヤーを好きなら、飼い主さんもアーヤーをきっと好きになるよ」
シャオパイがそう言った。それを聞いて、ぼくは、ひとまず、ほっとした。
今朝早く、アーヤーが突然、びっくりするくらい感情を高ぶらせながら、ぼくと妻猫に
「私には夢があるの」
と言った。
「分かっているわ。お父さんのように人の話が分かる猫になりたいのでしょ」
妻猫がそう言った。
するとアーヤーが首を横に振った。
「それは、これまで思っていた夢。今、私はもう一つ夢があるの」
アーヤーの目が輝いていた。
「何だい、それは」
ぼくは興味をそそられていた。
「何でしょう。お父さん、お母さん、ちょっと考えてみて」
アーヤーは、ぼくと妻猫の顔を交互に見ながら、分かるかどうか、うかがおうとしていた。ぼくとお母さんは顔を見合わせて、しばらく考えをめぐらせた。でもぼくにも、お母さんにも、さっぱり見当がつかなかった。
「分からないよ」
「何でしょうね」
ぼくと妻猫は、そう答えるしかなかった。
「もったいぶらないで早く言えよ。いったい、何を考えているのだ、おまえは」
ぼくはアーヤーにせかすように言った。アーヤーはうなずいた。
「人の声が話せる猫になりたいの」
アーヤーが、えりを正して、そう言った。
「えっ、何だって。本当か」
ぼくは、開いた口がふさがらなかった。そして思わず、はははと笑わずにはいられなかった。妻猫もびっくりして、顔を軽く横に揺らしながら、そんなことできるわけがないという仕草をした。
「アーヤー、本当にそんなことを考えているの」
妻猫が聞き返した。アーヤーはうなずいた。
「アーヤー、それはあまりにも現実離れしすぎているわ」
妻猫がさとすようにアーヤーに言った。それを聞いて、アーヤーが口をとがらせた。
「人の話が分かるだけでは物足りないの。人の声も出せる猫になりたいの」
アーヤーがそう言った。妻猫がそれを聞いて
「人の話が分かるようになるだけでも、大変なことだよ。人の声が出せるのは、もっと大変なことだよ」
と言った。
「分かっているわ。でも、できるかどうか、やってみたいの」
アーヤーが、そう言った。
「でも、どうやって人の声の出し方を学ぶの」
妻猫がけげんそうな顔をしていた。
「お父さんが人の話が分かるのは、人のうちに住んでいたからだよ。お父さんに毎日、話しかけてくれる人がいて、何度も話を聞いているうちに、お父さんはだんだん人の話が分かるようになってきたのよ。でも、お父さんにも人の声は出せないわ。どうやって、誰に学ぶのよ」
妻猫が理路整然と話した。
「そうだよ。お母さんのいうとおりだよ」
ぼくもそう言った。
それでもアーヤーはまだひるまなかった。
「お父さんやお母さんの言うことはよく分かるわ。でも学ぶ方法は、ほかにもあると思うわ。周りに人がいなくても、お父さんが教えることができなくても、人の声の出し方を学ぶ方法はあると思うわ」
アーヤーがそう言って反論した。
「どうやって?」
妻猫が、いぶかしそうな顔をしていた。
「シャオパイが住んでいる別荘に人の言葉が話せる九官鳥がいるわ。あの鳥に声の出し方を習いたいと思っているの」
アーヤーがそう言った。
「あっ、そうか。そういう方法もあるか」
ぼくは、そう思った。アーヤーの奇知に感心した。
「それにしても、おまえはどうして、そんな、とてつもないことを急に考えるようになったのだ」
ぼくにはどうしても合点がいかなかった。
アーヤーが、わけを話してくれた。
「翠湖公園には出入口が二つあるよね。東門と西門。どちらの門の前にも新聞売りのお年寄りがいて、新聞を売っている。東門の前で売っているお年寄りは元気がよくて、威勢のいい声で売っている。そのため新聞が毎日飛ぶように売れている。それに対して西門の前で新聞を売っているお年寄りは、言葉が話せない障害者。威勢のいい声が出せないから、新聞がほとんど売れない。売れ残った新聞をたくさん三輪自転車の荷台に積んで、重そうにペダルをこぎながら寂しそうに帰っていく後ろ姿を見るたびに心が痛んでたまらないの。あの人を手伝って大きな声で新聞を売ってあげられたらいいのになあと、いつも思っているの。でも私には無理だと思って、やりきれない気持ちで毎日過ごしていた。ところがシャオパイの家にいる九官鳥に初めて会って、私の夢に希望の光がともった。九官鳥が、人の声そっくりに話せるのだから、わたしにもできないことはないのではないかと思ったの」
アーヤーがそう話した。ぼくはそれを聞いて思わず心を打たれた。アーヤーがまさかそんなことを考えているとは思ってもいなかったからだ。生まれてからまだまもない、幼いアーヤーの心のなかに、もうすでに、かわいそうな人を思いやる優しさが生まれていたとはまったく想像もしていなかった。でもとてもうれしかった。感動して、ぼくは胸が熱くなって、涙が出そうになった。それと同時に、自分で自分のことが恥ずかしくなった。翠湖公園のなかを毎日、東門から西門まで散歩しているのに、西門にいる新聞売りのお年寄りが言葉が話せない障害者だとはまったく気がつかないでいたからだ。
ぼくはこれからすぐ翠湖公園の西門に行って、言葉が話せない新聞売りの障害者がどんな人なのか見てみることにした。
翠湖の上にかけられているアーチ橋を渡って東のほうへ行くと東門があり、西のほうへ行くと西門がある。アーチ橋を渡り終えたばかりのとき、老いらくさんがお年寄りらしい渋い声で
「やあ、笑い猫」
と、声をかけてくれた。
ぼくは老いらくさんに会ったときはいつも、あいさつは抜きにして、単刀直入に聞きたいことを聞くようにしている。
「公園の西門の前に言葉が話せない新聞売りの障害者がいるのを、ご存じですか」
「それとおまえと、どう関係があるのか」
老いらくさんが逆に、聞き返してきた。
「ぼくとは直接、関係ないです。アーヤーの夢と関係があるのです」
ぼくはそう答えた。
「そうか、確か、アーヤーの夢は……」
老いらくさんは、そう言って、しばらく考えていた。
「あー、思い出した。おまえはわしに以前、話してくれたことがある。アーヤーの夢はおまえと同じように人の話が聞いて分かる猫になることだったな」
ぼくはうなずいた。
「でも……」
老いらくさんが合点がいかない顔をした。
「でも何ですか」
ぼくは聞き返した。
「あのお年寄りは話ができないではないか。あの人とアーヤーの夢がどう関係があるのか」
老いらくさんが首をひねっていた。
「今、アーヤーには、新しい夢が芽生えたのです。それは人の話ができる猫になりたいという夢です」
ぼくはそう答えた。それを聞いて老いらくさんは、あきれたような顔をした。
「ふん、それのどこが夢か。奇想天外で馬鹿げた話ではないか。あきれて、ものも言えない」
老いらくさんがさげすむような目で、ぼくを見た。
「おまえは父親としてアーヤーに言って聞かせなければならない。子どもはみな、夢を見てもいいが、妄想だけは絶対にするなって」
老いらくさんが厳しい声で、そう言った。
ぼくはもうこれ以上、老いらくさんと話したくなかったので、西門に行って言葉が話せない新聞売りの障害者を見て、それからアーヤーの夢について再び老いらくさんと話すことにした。老いらくさんもついてきた。
ぼくと老いらくさんが公園の西門の前に着くと、新聞売りのお年寄りが腰かけに寂しそうに座っているのが見えた。お年寄りの前にはいろいろな新聞が、うず高く積まれていた。お年寄りの前をたくさんの人たちが、ひっきりなしに通り過ぎていたが、誰一人、足をとめて、新聞を買っていく人はいなかった。
「この人が言葉が話せない新聞売りのお年寄りですよ。アーヤーが手伝いたいと思っている」
ぼくは老いらくさんに、そう言った。
「そうか。この人か」
老いらくさんが、うなずいた。
「老いらくさんは、これでもまだアーヤーが考えていることは馬鹿げていると思っているのですか。この人を助けて新聞を売ってあげるために、売り声を出せるようになりたいというアーヤーの願いは馬鹿げていると思っているのですか」
ぼくがそう言うと、老いらくさんは返答に詰まっていた。
「確かにこの人は、とてもかわいそうな人だな。新聞が全然売れていない」
老いらくさんが、なまりのように重いため息をついた。
言葉が話せないお年寄りは、近くを通り過ぎていく人に、目で、新聞を買ってくださいという気持ちを送っていた。でも通行人は誰も、お年寄りと目を合わせようとはしないで、汚いものを避けるように、そそくさと去っていた。お年寄りの目のなかには、新聞を買ってくれる人を待ち望む期待感と、誰も買ってくれない虚しさがあふれていた。ぼくはもう見ていられなくなった。誰かが足をとめて、たとえ一部でもいいから、このお年寄りの新聞を買ってくれることを、ぼくは心から望んでいた。
そのとき、ある人が、お年寄りの前を急いで通り過ぎようとして、うっかりして、カバンのなかから、携帯電話を落としてしまった。落としたことに気がつかないで、その人はそのまま、さっさと行ってしまおうとした。それを見て、お年寄りはびっくりして、すぐに腰かけから立ち上がって携帯電話を拾い上げた。老いらくさんが、それを見て
「新聞を買ってもらえるチャンスだ。急いで」
と、声を上げた。むろん、老いらくさんの声がお年寄りに聞こえるはずがないが、お年寄りは携帯電話を落とした人のあとを追いかけて走り出した。二十メートルぐらい追いかけて、お年寄りは落とした人に追いつくことができた。後ろから背中をたたいて振り向かせて、携帯電話を落としたことに気づかせた。落とした人は、お年寄りに感謝の気持ちを述べてから、お礼のお金を渡そうとしていた。でもお年寄りは首を横に振って受け取ることを固辞していた。それからまもなく、お年寄りは売り場に戻ってきた。携帯電話を落とした人も、お年寄りの売り場に戻ってきた。お年寄りは、その人を見て、新聞の束を指差しながら、(お礼のお金は要りませんから、新聞を一部買ってください。お礼はそれで十分です)と、目で伝えていた。携帯電話を落とした人は、うんうんと、うなずいてから、一部ではなくて、すべての新聞を一部ずつ買ってお金を払っていた。そのあと紙幣を一枚、お年寄りに無理やり渡してから、逃げるような速足で、その場を去っていった。
お年寄りはそのあと何もなかったかのように、再び腰かけに座って、新聞を買ってくれる人をじっと待っていた。買ってくれる人は誰もいなかったが、お年寄りは、それでも、どこか満たされたような顔をしていた。
「わしは今、あのお年寄りの気持ちを推測している。『小人の心をもって君子の心を推し量る』といったところかな」
老いらくさんが、そう言った。
「そうですか。げすの勘ぐりですか」
「そうだよ。さもしい考えであのお年寄りの心のなかを邪推するのはどうかと思うが、新聞が数部売れただけで、あんなにうれしそうな顔をしている。心がとても純粋なのだろうな。わしだったら、あれくらいの売り上げでは、とても満足できない」
老いらくさんが自分の愚かさを深く恥じているような顔をしていた。
「そうですね。あのお年寄りの純粋さを、ぼくたちは見習わなければならないですね」
「そうだな。わしも、そう思う」
老いらくさんが、そう答えた。
「純粋さと言えば、うちのアーヤーの純粋さも、小ばかにしないで、夢の実現に向けて、できるだけ力を貸してあげなければならないと、ぼくは思っています」
ぼくがそう言うと、老いらくさんはうなずいた。
「『志あるところに道は開ける』と言うではありませんか」
ぼくがそう言うと、老いらくさんが
「うん、わしもそう思っている」
と、答えた。
ぼくと老いらくさんは、ようやく意見が合った。
アーヤーが二つ目の願いをかなえるために、シャオパイが住んでいる別荘に行って、九官鳥に教えを乞うことができるかどうかは、こちらの意思だけでは決めることができない。九官鳥がアーヤーに教えてくれるかや、飼い主さんが許可してくれるかや、アーヤーがシャオパイと、うまくやっていけるかどうかによって決まる。シャオパイには、もうすでにアーヤーの願いを伝えていた。飼い主さんは今、不在なので、飼い主さんが帰ってくる前に、アーヤーを毎日、別荘に行かせて環境に慣れさせたり、シャオパイとうまくやっていけるかどうか見てみることにした。
昨日、ぼくはシャオパイに
「アーヤーのことをどう思う」
と、聞いた。するとシャオパイは
「とてもいいよ。来たばかりなのに、花壇にいたネズミが一匹もいなくなった」
と、答えてくれた。
「アーヤーはお母さんにそっくりだね。ネズミのつかまえ方もとても品があって」
シャオパイがそう言って、アーヤーのことを、しきりにほめてくれた。
「アーヤーの性格についてはどう思う。おまえと、気が合いそうか」
ぼくが心配そうに聞くと、
「うん、もちろん、合うよ」
と、シャオパイが答えてくれた。
「笑い猫のあんちゃんと、奥さんが猫のなかで最高の猫だけど、アーヤーは、どちらからも、いいところを受け継いでいる。あんちゃんの知恵と、奥さんの善良さをね」
シャオパイがそう言ってくれたので、ぼくはなんだか照れくさくなった。
ともあれ、シャオパイがアーヤーのことを気に入ってくれて、よかった。でもそうは言っても、やはりまだ心のなかに、少し気がかりなことがある。シャオパイの飼い主さんがアーヤーのことをどう思ってくれるか分からなかったからだ。ぼくのそういった気持ちを察して、シャオパイが
「大丈夫よ。心配いらないよ」
と、言ってくれた。
「ぼくの飼い主さんが、ぼくをとても好きなのは、あんちゃんも知っているでしょ」
シャオパイが聞いた。ぼくはうなずいた。
「ぼくが好きなものは飼い主さんも好きだから、ぼくがアーヤーを好きなら、飼い主さんもアーヤーをきっと好きになるよ」
シャオパイがそう言った。それを聞いて、ぼくは、ひとまず、ほっとした。
今朝早く、アーヤーが突然、びっくりするくらい感情を高ぶらせながら、ぼくと妻猫に
「私には夢があるの」
と言った。
「分かっているわ。お父さんのように人の話が分かる猫になりたいのでしょ」
妻猫がそう言った。
するとアーヤーが首を横に振った。
「それは、これまで思っていた夢。今、私はもう一つ夢があるの」
アーヤーの目が輝いていた。
「何だい、それは」
ぼくは興味をそそられていた。
「何でしょう。お父さん、お母さん、ちょっと考えてみて」
アーヤーは、ぼくと妻猫の顔を交互に見ながら、分かるかどうか、うかがおうとしていた。ぼくとお母さんは顔を見合わせて、しばらく考えをめぐらせた。でもぼくにも、お母さんにも、さっぱり見当がつかなかった。
「分からないよ」
「何でしょうね」
ぼくと妻猫は、そう答えるしかなかった。
「もったいぶらないで早く言えよ。いったい、何を考えているのだ、おまえは」
ぼくはアーヤーにせかすように言った。アーヤーはうなずいた。
「人の声が話せる猫になりたいの」
アーヤーが、えりを正して、そう言った。
「えっ、何だって。本当か」
ぼくは、開いた口がふさがらなかった。そして思わず、はははと笑わずにはいられなかった。妻猫もびっくりして、顔を軽く横に揺らしながら、そんなことできるわけがないという仕草をした。
「アーヤー、本当にそんなことを考えているの」
妻猫が聞き返した。アーヤーはうなずいた。
「アーヤー、それはあまりにも現実離れしすぎているわ」
妻猫がさとすようにアーヤーに言った。それを聞いて、アーヤーが口をとがらせた。
「人の話が分かるだけでは物足りないの。人の声も出せる猫になりたいの」
アーヤーがそう言った。妻猫がそれを聞いて
「人の話が分かるようになるだけでも、大変なことだよ。人の声が出せるのは、もっと大変なことだよ」
と言った。
「分かっているわ。でも、できるかどうか、やってみたいの」
アーヤーが、そう言った。
「でも、どうやって人の声の出し方を学ぶの」
妻猫がけげんそうな顔をしていた。
「お父さんが人の話が分かるのは、人のうちに住んでいたからだよ。お父さんに毎日、話しかけてくれる人がいて、何度も話を聞いているうちに、お父さんはだんだん人の話が分かるようになってきたのよ。でも、お父さんにも人の声は出せないわ。どうやって、誰に学ぶのよ」
妻猫が理路整然と話した。
「そうだよ。お母さんのいうとおりだよ」
ぼくもそう言った。
それでもアーヤーはまだひるまなかった。
「お父さんやお母さんの言うことはよく分かるわ。でも学ぶ方法は、ほかにもあると思うわ。周りに人がいなくても、お父さんが教えることができなくても、人の声の出し方を学ぶ方法はあると思うわ」
アーヤーがそう言って反論した。
「どうやって?」
妻猫が、いぶかしそうな顔をしていた。
「シャオパイが住んでいる別荘に人の言葉が話せる九官鳥がいるわ。あの鳥に声の出し方を習いたいと思っているの」
アーヤーがそう言った。
「あっ、そうか。そういう方法もあるか」
ぼくは、そう思った。アーヤーの奇知に感心した。
「それにしても、おまえはどうして、そんな、とてつもないことを急に考えるようになったのだ」
ぼくにはどうしても合点がいかなかった。
アーヤーが、わけを話してくれた。
「翠湖公園には出入口が二つあるよね。東門と西門。どちらの門の前にも新聞売りのお年寄りがいて、新聞を売っている。東門の前で売っているお年寄りは元気がよくて、威勢のいい声で売っている。そのため新聞が毎日飛ぶように売れている。それに対して西門の前で新聞を売っているお年寄りは、言葉が話せない障害者。威勢のいい声が出せないから、新聞がほとんど売れない。売れ残った新聞をたくさん三輪自転車の荷台に積んで、重そうにペダルをこぎながら寂しそうに帰っていく後ろ姿を見るたびに心が痛んでたまらないの。あの人を手伝って大きな声で新聞を売ってあげられたらいいのになあと、いつも思っているの。でも私には無理だと思って、やりきれない気持ちで毎日過ごしていた。ところがシャオパイの家にいる九官鳥に初めて会って、私の夢に希望の光がともった。九官鳥が、人の声そっくりに話せるのだから、わたしにもできないことはないのではないかと思ったの」
アーヤーがそう話した。ぼくはそれを聞いて思わず心を打たれた。アーヤーがまさかそんなことを考えているとは思ってもいなかったからだ。生まれてからまだまもない、幼いアーヤーの心のなかに、もうすでに、かわいそうな人を思いやる優しさが生まれていたとはまったく想像もしていなかった。でもとてもうれしかった。感動して、ぼくは胸が熱くなって、涙が出そうになった。それと同時に、自分で自分のことが恥ずかしくなった。翠湖公園のなかを毎日、東門から西門まで散歩しているのに、西門にいる新聞売りのお年寄りが言葉が話せない障害者だとはまったく気がつかないでいたからだ。
ぼくはこれからすぐ翠湖公園の西門に行って、言葉が話せない新聞売りの障害者がどんな人なのか見てみることにした。
翠湖の上にかけられているアーチ橋を渡って東のほうへ行くと東門があり、西のほうへ行くと西門がある。アーチ橋を渡り終えたばかりのとき、老いらくさんがお年寄りらしい渋い声で
「やあ、笑い猫」
と、声をかけてくれた。
ぼくは老いらくさんに会ったときはいつも、あいさつは抜きにして、単刀直入に聞きたいことを聞くようにしている。
「公園の西門の前に言葉が話せない新聞売りの障害者がいるのを、ご存じですか」
「それとおまえと、どう関係があるのか」
老いらくさんが逆に、聞き返してきた。
「ぼくとは直接、関係ないです。アーヤーの夢と関係があるのです」
ぼくはそう答えた。
「そうか、確か、アーヤーの夢は……」
老いらくさんは、そう言って、しばらく考えていた。
「あー、思い出した。おまえはわしに以前、話してくれたことがある。アーヤーの夢はおまえと同じように人の話が聞いて分かる猫になることだったな」
ぼくはうなずいた。
「でも……」
老いらくさんが合点がいかない顔をした。
「でも何ですか」
ぼくは聞き返した。
「あのお年寄りは話ができないではないか。あの人とアーヤーの夢がどう関係があるのか」
老いらくさんが首をひねっていた。
「今、アーヤーには、新しい夢が芽生えたのです。それは人の話ができる猫になりたいという夢です」
ぼくはそう答えた。それを聞いて老いらくさんは、あきれたような顔をした。
「ふん、それのどこが夢か。奇想天外で馬鹿げた話ではないか。あきれて、ものも言えない」
老いらくさんがさげすむような目で、ぼくを見た。
「おまえは父親としてアーヤーに言って聞かせなければならない。子どもはみな、夢を見てもいいが、妄想だけは絶対にするなって」
老いらくさんが厳しい声で、そう言った。
ぼくはもうこれ以上、老いらくさんと話したくなかったので、西門に行って言葉が話せない新聞売りの障害者を見て、それからアーヤーの夢について再び老いらくさんと話すことにした。老いらくさんもついてきた。
ぼくと老いらくさんが公園の西門の前に着くと、新聞売りのお年寄りが腰かけに寂しそうに座っているのが見えた。お年寄りの前にはいろいろな新聞が、うず高く積まれていた。お年寄りの前をたくさんの人たちが、ひっきりなしに通り過ぎていたが、誰一人、足をとめて、新聞を買っていく人はいなかった。
「この人が言葉が話せない新聞売りのお年寄りですよ。アーヤーが手伝いたいと思っている」
ぼくは老いらくさんに、そう言った。
「そうか。この人か」
老いらくさんが、うなずいた。
「老いらくさんは、これでもまだアーヤーが考えていることは馬鹿げていると思っているのですか。この人を助けて新聞を売ってあげるために、売り声を出せるようになりたいというアーヤーの願いは馬鹿げていると思っているのですか」
ぼくがそう言うと、老いらくさんは返答に詰まっていた。
「確かにこの人は、とてもかわいそうな人だな。新聞が全然売れていない」
老いらくさんが、なまりのように重いため息をついた。
言葉が話せないお年寄りは、近くを通り過ぎていく人に、目で、新聞を買ってくださいという気持ちを送っていた。でも通行人は誰も、お年寄りと目を合わせようとはしないで、汚いものを避けるように、そそくさと去っていた。お年寄りの目のなかには、新聞を買ってくれる人を待ち望む期待感と、誰も買ってくれない虚しさがあふれていた。ぼくはもう見ていられなくなった。誰かが足をとめて、たとえ一部でもいいから、このお年寄りの新聞を買ってくれることを、ぼくは心から望んでいた。
そのとき、ある人が、お年寄りの前を急いで通り過ぎようとして、うっかりして、カバンのなかから、携帯電話を落としてしまった。落としたことに気がつかないで、その人はそのまま、さっさと行ってしまおうとした。それを見て、お年寄りはびっくりして、すぐに腰かけから立ち上がって携帯電話を拾い上げた。老いらくさんが、それを見て
「新聞を買ってもらえるチャンスだ。急いで」
と、声を上げた。むろん、老いらくさんの声がお年寄りに聞こえるはずがないが、お年寄りは携帯電話を落とした人のあとを追いかけて走り出した。二十メートルぐらい追いかけて、お年寄りは落とした人に追いつくことができた。後ろから背中をたたいて振り向かせて、携帯電話を落としたことに気づかせた。落とした人は、お年寄りに感謝の気持ちを述べてから、お礼のお金を渡そうとしていた。でもお年寄りは首を横に振って受け取ることを固辞していた。それからまもなく、お年寄りは売り場に戻ってきた。携帯電話を落とした人も、お年寄りの売り場に戻ってきた。お年寄りは、その人を見て、新聞の束を指差しながら、(お礼のお金は要りませんから、新聞を一部買ってください。お礼はそれで十分です)と、目で伝えていた。携帯電話を落とした人は、うんうんと、うなずいてから、一部ではなくて、すべての新聞を一部ずつ買ってお金を払っていた。そのあと紙幣を一枚、お年寄りに無理やり渡してから、逃げるような速足で、その場を去っていった。
お年寄りはそのあと何もなかったかのように、再び腰かけに座って、新聞を買ってくれる人をじっと待っていた。買ってくれる人は誰もいなかったが、お年寄りは、それでも、どこか満たされたような顔をしていた。
「わしは今、あのお年寄りの気持ちを推測している。『小人の心をもって君子の心を推し量る』といったところかな」
老いらくさんが、そう言った。
「そうですか。げすの勘ぐりですか」
「そうだよ。さもしい考えであのお年寄りの心のなかを邪推するのはどうかと思うが、新聞が数部売れただけで、あんなにうれしそうな顔をしている。心がとても純粋なのだろうな。わしだったら、あれくらいの売り上げでは、とても満足できない」
老いらくさんが自分の愚かさを深く恥じているような顔をしていた。
「そうですね。あのお年寄りの純粋さを、ぼくたちは見習わなければならないですね」
「そうだな。わしも、そう思う」
老いらくさんが、そう答えた。
「純粋さと言えば、うちのアーヤーの純粋さも、小ばかにしないで、夢の実現に向けて、できるだけ力を貸してあげなければならないと、ぼくは思っています」
ぼくがそう言うと、老いらくさんはうなずいた。
「『志あるところに道は開ける』と言うではありませんか」
ぼくがそう言うと、老いらくさんが
「うん、わしもそう思っている」
と、答えた。
ぼくと老いらくさんは、ようやく意見が合った。