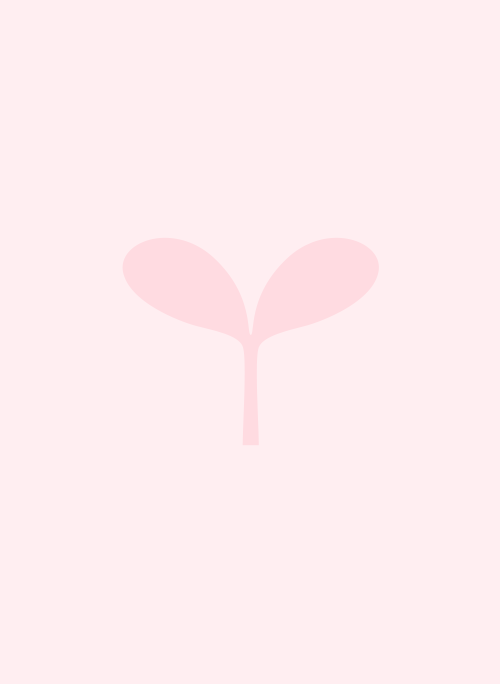天気……翠湖公園のなかに咲いていた菊は、ほとんど枯れてしまったが、道端に生えている野菊はいまが見ごろを迎えている。夕方になると、空に眉のような三日月が出ていた。
「あの家には、シャオパイと飼い主さんだけしか住んでいないのでしょ」
アーヤーがいぶかしそうな顔をしていた。
「そうだよ」
ぼくは、そう答えた。
「だったら、あの話し声は誰だったの。誰か、お客さんでも来ていたの」
「うーん、どうだろう。お父さんも、初めはそう思ったが、飼い主さんが、お客さんをうちに残したまま、どこかに旅行に出かけるわけがないから、とても不思議に思っている」
ぼくにも合点がいかなかった。でも昨日は確かに留守の家から電話が鳴る音と人の話し声が聞こえてきた。あれはいったい、誰だったのだ。
この謎を解くために、ぼくとアーヤーは夜が明けるとすぐに家を出て、シャオパイの別荘をめざして、すっ飛んでいった。
別荘に着くとすぐに、前庭の花壇の前をそそくさと通り抜けて、裏庭にある花壇のほうへ回った。裏庭の花壇の先には池がある。翠湖ほど大きくはないが、とても静寂できれいな池だ。池のなかには、つがいのオシドリが一組泳いでいて、気持ちよさそうに行ったり来たりしていた。
シャオパイが家のなかから出てくるまで、ぼくたちは庭の樹木の茂みのなかに姿を隠すことにした。家のなかにまだ誰か人がいて、その人に見つかってはいけないからだ。
ずいぶん待ってから、ようやくシャオパイが家のなかから出てくるのが見えた。ゴミ袋を口にくわえていた。
「シャオパイ、こっちへ来い」
ぼくは声を低く抑えながら、茂みのなかからシャオパイに呼びかけた。
ぼくに気がついたシャオパイはゴミ袋をゴミ箱に入れると、急いでぼくたちの前に来た。
「笑い猫、どうして、なかに入ってこなかったの」
シャオパイが、けげんそうな顔をしていた。無理もない。ぼくはこれまで、来るときはいつも、遠慮しないで、うちのなかにそのまま入っていたからだ。飼い主さんがいるときでも、家のなかに、すーっと入っていた。飼い主さんは、ぼくとシャオパイが友だちであることを知っていたから、ぼくを見ても追い出したりしなかったからだ。
ぼくはそれでもまだ警戒の糸をゆるめないで声を低く抑えたままシャオパイに聞いた。
「うちに誰か来ているのか」
シャオパイは首を横に振った。
「誰もいない」
「本当に」
「本当だよ。だって飼い主さんは長い旅に出たから。昨日、ぼくは飼い主さんを見送りに空港まで行ってきたばかりだから」
シャオパイがそう答えた。
「知っているよ。出かけていくところを見たから。でも、それにしてはおかしなことがあったのだ」
ぼくがそう言うと、シャオパイが小首をかしげていた。ぼくは、きのうのことを話した。
「おまえと飼い主さんが出ていったあと、この家の応接室から声が聞こえてきたのだ。耳をすまして聞いていると、電話が鳴る音と、人の話し声だった」
「えっ、本当?」
シャオパイは丸い目をますます丸くしていた。
「いつごろですか」
「おまえと飼い主さんが出て行ったすぐあとだ」
ぼくはそう答えた。
「まず初めに電話が鳴る音がして、そのあと女の人と男の人の話し声が聞こえてきた」
「えっ、本当に。そんなことぜったいにありえない」
シャオパイは確信にあふれた声で,そう言った。
「ここには、ぼくと、ぼくの飼い主さんしかいない。ほかの人は誰もいない。うそだと思うのなら、なかに入ってみて」
シャオパイがそう言った。
ぼくとアーヤーは、言われるままに、恐る恐る、なかに入っていった。確かに誰もいなかった。応接室にも行ったが、人がいた気配はまったくなかった。シャオパイは応接室の隅々までにおいをかぎまわっていた。ソファーの下にも入っていって、くんくんと注意深く、においをかいでいた。
「異質なにおいは、何もしない。飼い主さんのにおいしかしない。ほかの人のにおいなど、まったくしない」
シャオパイがそう言った。
「じゃあ、二階にも行ってみよう」
ぼくはそう言って、疑惑の念をまだ緩めなかった。
二階には飼い主さんの書斎があった。窓に面して大きな文机が置かれていた。文机の周りには大きな本箱が壁にぴったりとくっつけるように置かれていた。書斎のなかは整然としていて、ここにも人が入った形跡はまったくなかった。
「じゃあ、三階にも行ってみよう」
ぼくはまだ疑惑の念を解かなかった。
三階は飼い主さんの寝室だった。ぼくはシャオパイのあとについて、大きなベッドの下に入っていった。カーテンの後ろや、トイレやクローゼットのなかも調べた。それでもまだ誰かがこの家に入った形跡を見つけることはできなかった。
「この家に、赤の他人が入れるわけがない」
シャオパイがそう言った。ちょうどそのとき、一階の応接室のなかから電話の鳴る音が聞こえてきた。電話の音に続いて男の人と女の人の話し声も聞こえてきた。
「もう、おまえとは話したくない」
「もう、あなたとは話したくない」
どちらも声がとがっていて、かりかりしているような声の響きだった。
「ほら、聞こえるだろう。男の人と女の人が話しているじゃないか」
ぼくがそう言うと、シャオパイが
「あれは違うよ。あれは人が話している声ではないよ。うちで飼っている鳥が鳴いている声だよ」
と、答えた。
(えっ)と、ぼくは思った。
シャオパイは人の言葉が分からないが、ぼくは分かる。応接室から聞こえている声は間違いなく人の声だ。どうして鳥があのような声で鳴くことができるだろうか。
ぼくたちは三階から急いで下におりて、一階にある応接室に戻った。窓の上のほうを見ると、天井から鳥の止まり木がつり下げてあって、体が黒くて、くちばしと足が、オレンジ色をしている鳥が留まっているのが見えた。おしゃれで、とてもかっこよい鳥だった。
ぼくはこの鳥を見たことがある。九官鳥という名前の鳥だ。馬小跳のおばあちゃんのうちにこの鳥がいて、人の声真似ができた。でもあの九官鳥は人の声真似があまり上手ではなかったので、声を聞いたら鳥の声だとすぐに分かった。女の人の声と男の人の声を使い分けることもできなかった。
ほくとアーヤーは頭をあげて、九官鳥を見ていた。九官鳥は下を見て、頭をきょろきょろさせながら、ぼくたちを探るような目で、じろじろ見ていた。
ぼくはいろいろな動物の言葉が話せるので、鳥の言葉で話しかけた。
「こんにちは」
ぼくの声を聞いて、九官鳥は、ぎくっとしたようだった。まさか、ぼくが鳥の言葉を話せるとは思ってもいなかったのだろう。
「こんにちは」
ぼくはもう一度、鳥の言葉であいさつをした。
「こんにちは」
九官鳥が不思議そうな顔をしながら、ぼくにあいさつを返してくれた。
「こんにちは。ぼくは笑い猫と言います」
ぼくは微笑みを浮かべながら、あいさつをした。
「そうか。笑い猫か。確かに笑える猫だな」
九官鳥がそう答えた。
「ぼくとシャオパイは仲のいい友だちなのです」
ぼくがそう言うと、九官鳥がうなずいた。
「見たら分かる」
九官鳥はそれでもまだ合点がいかないような顔をしていた。
「おまえは猫なのに、どうして鳥の言葉が話せるのか」
九官鳥は首をひねりながら、まだじろじろした目で、ぼくのほうを見ていた。
「ぼくはいろいろな動物の言葉が話せるのです」
ぼくはそう答えた。
「人の言葉も話せるのか」
九官鳥がさらに聞いてきた。
「聞くことはできますが、話すことはできません」
ぼくは、ほほほと笑いながら、そう答えた。
「さっき、人の声で話をしていたのは、あなたですか」
気になっていたことを、ぼくは聞いた。
「そうだ」
九官鳥がうなずいた。
「男の人の声と女の人の声が聞こえてきたけど、どちらの声真似もできるのですか」
ぼくはさらに聞いた。
「そうだ。信じられないというのなら、おまえに聞かせてやろう」
九官鳥はそう言うと、首を縮めて男の人の低い声で
「もう、おまえとは話したくない」
と言った。そのあと今度は首を伸ばして
「もう、あなたとは話したくない」
と、女の人の高い声で言った。
声を聞いた途端、ぼくは、がくぜんとした。間違いなく、さっき三階にいたときに聞こえてきた声そのものだったからだ。なんと、この九官鳥は人の声そっくりの声が出せるのだ。しかも男の人の声真似も女の人の声真似もできるのだ。
「電話が鳴る音も、あなたが……」
ぼくが聞くと、九官鳥がうなずいた。
「おれが一番得意としているのは、電話が鳴る音だ。オフィスにある電話が鳴る音も、家庭にある電話が鳴る音も、本物そっくりに真似できる。年配者のガラケーが鳴る音も、若者のスマートフォンが鳴る音も、そっくりに真似できる」
九官鳥が自慢そうに言った。
九官鳥はそれからまもなく、いろいろな電話の音を真似してみせた。どれもみな、まるで本物の電話が鳴っているように聞こえた。
あっけにとられたぼくは、しばらく、ぼうぜんとして、口をぽかんと開けたまま、その場に立ちすくんでいるよりほかなかった。
しばらくしてから、ほくとアーヤーは応接室を出た。
「九官鳥はいつこのうちに来たのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「つい最近。一週間ほど前」
シャオパイがそう答えた。
「誰が連れてきたのか」
「飼い主さんの友だちが連れてきた」
「そうか」
ぼくにはようやく納得がいった。
「それにしても、あの九官鳥の才能はたいしたものだ。ぼくはこれまで九官鳥を見たことがあるが、あそこまでそっくりに真似できなかった」
感心しきりの声で、ぼくはそう言った。
「そうですか。九官鳥と飼い主さんはいつも一緒にいて、何度も何度も繰り返して練習していたから、九官鳥は人の声真似が上手にできるようになったのだと思う」
シャオパイがそう答えた。
「楽しくていいだろう」
ぼくがそう聞くと、シャオパイが首を横に振った。
「どうしてだ。にぎやかでいいだろう」
と、ぼくはシャオパイにもう一度聞いた。
「うるさくて、たまらないわ。それに九官鳥がうちに来てから、飼い主さんが、ぼくと一緒に過ごす時間が以前に比べて、ずっと少なくなった」
シャオパイがそう答えた。
「焼きもちを焼いているのではないか。九官鳥が、おまえに代わって、飼い主さんの愛を独り占めしてしまうのではないかと思って、それで、おまえは焼きもちを焼いているのだろう」
ぼくはシャオパイの心のなかを推察した。
「違うよ。そうじゃないよ」
シャオパイが強く否定した。
「じゃあ、どうしてだい」
ぼくは、けげんに思って聞き返した。
「ぼくが気に入らないのは、九官鳥は自己顕示欲が強いからだよ。それに、うぬぼれで、ほかのものを見下すところがある」
シャオパイが、そう答えた。
「そうか、自分の才能に自信を持ちすぎているのだろうな」
ぼくは、そう答えた。
ぼくとアーヤーは、それからまもなく、うちへ帰ることにした。
うちへ帰る途中、アーヤーが聞いた。
「お父さん、あの九官鳥が人の声を話す才能はたいしたものだと言ったけど、本当にそうなの」
「うん」
ぼくはうなずいた。
「そんなに素晴らしいの」
「そうだよ。人の声とまったく見分けがつかないほど素晴らしい。目をつむって聞いたら、九官鳥が話している声とはとても思えないほどだ」
「そうなの。そんなに素晴らしいの。だったら、もしかしたら私の願いがかなうかもしれないわ」
限りなく遠くを見つめるような目で、アーヤーがふいにそう言った。
ぼくはそれを聞いて、合点がいかなかった。
「おまえの願いはお母さんのようにきれいで、品のある猫になることだろう」
ぼくがそう言うと、アーヤーは首を横に振った。
「それは一つ目の願い。もう一つ、願いがあるの」
アーヤーの目が、きらきら輝いていた。
「なんだい、それは」
ぼくは、気もそぞろに聞き返した。
「お父さんのように、人の話を聞いて分かる猫になること」
アーヤーがそう答えた。
「えっ、本当か。本当にそんなことを思っているのか」
ぼくは、びっくりして、聞き返した。アーヤーがうなずいた。
アーヤーの二つ目の願いを、ぼくは今、初めて知った。
「そうか。それはうれしいな」
ぼくはそう答えた。
ぼくが人の言葉を聞いて分かるようになったのは、以前ぼくは、人に飼われていたからだ。飼い主である杜真子がぼくに話しかけてくれる言葉を何度も聞いているうちに、少しずつ言葉の意味が分かるようになってきた。でも今の生活のなかで、アーヤーに話しかけてくれる人は誰もいないので、アーヤーが人の言葉を聞いて分からないのは当たり前だ。
「これまで、わたしの二つ目の願いは無理だと思っていたけど、人の言葉が上手に話せる九官鳥に会ったから、その言葉を何度も聞いたら、もしかしたら、意味が分かるようになるかもしれないと思うようになったの」
アーヤーはうれしくてたまらないといった顔をしながら、そう言った。それからまもなくアーヤーは、弾むような足取りで、うちへ帰っていった。
「あの家には、シャオパイと飼い主さんだけしか住んでいないのでしょ」
アーヤーがいぶかしそうな顔をしていた。
「そうだよ」
ぼくは、そう答えた。
「だったら、あの話し声は誰だったの。誰か、お客さんでも来ていたの」
「うーん、どうだろう。お父さんも、初めはそう思ったが、飼い主さんが、お客さんをうちに残したまま、どこかに旅行に出かけるわけがないから、とても不思議に思っている」
ぼくにも合点がいかなかった。でも昨日は確かに留守の家から電話が鳴る音と人の話し声が聞こえてきた。あれはいったい、誰だったのだ。
この謎を解くために、ぼくとアーヤーは夜が明けるとすぐに家を出て、シャオパイの別荘をめざして、すっ飛んでいった。
別荘に着くとすぐに、前庭の花壇の前をそそくさと通り抜けて、裏庭にある花壇のほうへ回った。裏庭の花壇の先には池がある。翠湖ほど大きくはないが、とても静寂できれいな池だ。池のなかには、つがいのオシドリが一組泳いでいて、気持ちよさそうに行ったり来たりしていた。
シャオパイが家のなかから出てくるまで、ぼくたちは庭の樹木の茂みのなかに姿を隠すことにした。家のなかにまだ誰か人がいて、その人に見つかってはいけないからだ。
ずいぶん待ってから、ようやくシャオパイが家のなかから出てくるのが見えた。ゴミ袋を口にくわえていた。
「シャオパイ、こっちへ来い」
ぼくは声を低く抑えながら、茂みのなかからシャオパイに呼びかけた。
ぼくに気がついたシャオパイはゴミ袋をゴミ箱に入れると、急いでぼくたちの前に来た。
「笑い猫、どうして、なかに入ってこなかったの」
シャオパイが、けげんそうな顔をしていた。無理もない。ぼくはこれまで、来るときはいつも、遠慮しないで、うちのなかにそのまま入っていたからだ。飼い主さんがいるときでも、家のなかに、すーっと入っていた。飼い主さんは、ぼくとシャオパイが友だちであることを知っていたから、ぼくを見ても追い出したりしなかったからだ。
ぼくはそれでもまだ警戒の糸をゆるめないで声を低く抑えたままシャオパイに聞いた。
「うちに誰か来ているのか」
シャオパイは首を横に振った。
「誰もいない」
「本当に」
「本当だよ。だって飼い主さんは長い旅に出たから。昨日、ぼくは飼い主さんを見送りに空港まで行ってきたばかりだから」
シャオパイがそう答えた。
「知っているよ。出かけていくところを見たから。でも、それにしてはおかしなことがあったのだ」
ぼくがそう言うと、シャオパイが小首をかしげていた。ぼくは、きのうのことを話した。
「おまえと飼い主さんが出ていったあと、この家の応接室から声が聞こえてきたのだ。耳をすまして聞いていると、電話が鳴る音と、人の話し声だった」
「えっ、本当?」
シャオパイは丸い目をますます丸くしていた。
「いつごろですか」
「おまえと飼い主さんが出て行ったすぐあとだ」
ぼくはそう答えた。
「まず初めに電話が鳴る音がして、そのあと女の人と男の人の話し声が聞こえてきた」
「えっ、本当に。そんなことぜったいにありえない」
シャオパイは確信にあふれた声で,そう言った。
「ここには、ぼくと、ぼくの飼い主さんしかいない。ほかの人は誰もいない。うそだと思うのなら、なかに入ってみて」
シャオパイがそう言った。
ぼくとアーヤーは、言われるままに、恐る恐る、なかに入っていった。確かに誰もいなかった。応接室にも行ったが、人がいた気配はまったくなかった。シャオパイは応接室の隅々までにおいをかぎまわっていた。ソファーの下にも入っていって、くんくんと注意深く、においをかいでいた。
「異質なにおいは、何もしない。飼い主さんのにおいしかしない。ほかの人のにおいなど、まったくしない」
シャオパイがそう言った。
「じゃあ、二階にも行ってみよう」
ぼくはそう言って、疑惑の念をまだ緩めなかった。
二階には飼い主さんの書斎があった。窓に面して大きな文机が置かれていた。文机の周りには大きな本箱が壁にぴったりとくっつけるように置かれていた。書斎のなかは整然としていて、ここにも人が入った形跡はまったくなかった。
「じゃあ、三階にも行ってみよう」
ぼくはまだ疑惑の念を解かなかった。
三階は飼い主さんの寝室だった。ぼくはシャオパイのあとについて、大きなベッドの下に入っていった。カーテンの後ろや、トイレやクローゼットのなかも調べた。それでもまだ誰かがこの家に入った形跡を見つけることはできなかった。
「この家に、赤の他人が入れるわけがない」
シャオパイがそう言った。ちょうどそのとき、一階の応接室のなかから電話の鳴る音が聞こえてきた。電話の音に続いて男の人と女の人の話し声も聞こえてきた。
「もう、おまえとは話したくない」
「もう、あなたとは話したくない」
どちらも声がとがっていて、かりかりしているような声の響きだった。
「ほら、聞こえるだろう。男の人と女の人が話しているじゃないか」
ぼくがそう言うと、シャオパイが
「あれは違うよ。あれは人が話している声ではないよ。うちで飼っている鳥が鳴いている声だよ」
と、答えた。
(えっ)と、ぼくは思った。
シャオパイは人の言葉が分からないが、ぼくは分かる。応接室から聞こえている声は間違いなく人の声だ。どうして鳥があのような声で鳴くことができるだろうか。
ぼくたちは三階から急いで下におりて、一階にある応接室に戻った。窓の上のほうを見ると、天井から鳥の止まり木がつり下げてあって、体が黒くて、くちばしと足が、オレンジ色をしている鳥が留まっているのが見えた。おしゃれで、とてもかっこよい鳥だった。
ぼくはこの鳥を見たことがある。九官鳥という名前の鳥だ。馬小跳のおばあちゃんのうちにこの鳥がいて、人の声真似ができた。でもあの九官鳥は人の声真似があまり上手ではなかったので、声を聞いたら鳥の声だとすぐに分かった。女の人の声と男の人の声を使い分けることもできなかった。
ほくとアーヤーは頭をあげて、九官鳥を見ていた。九官鳥は下を見て、頭をきょろきょろさせながら、ぼくたちを探るような目で、じろじろ見ていた。
ぼくはいろいろな動物の言葉が話せるので、鳥の言葉で話しかけた。
「こんにちは」
ぼくの声を聞いて、九官鳥は、ぎくっとしたようだった。まさか、ぼくが鳥の言葉を話せるとは思ってもいなかったのだろう。
「こんにちは」
ぼくはもう一度、鳥の言葉であいさつをした。
「こんにちは」
九官鳥が不思議そうな顔をしながら、ぼくにあいさつを返してくれた。
「こんにちは。ぼくは笑い猫と言います」
ぼくは微笑みを浮かべながら、あいさつをした。
「そうか。笑い猫か。確かに笑える猫だな」
九官鳥がそう答えた。
「ぼくとシャオパイは仲のいい友だちなのです」
ぼくがそう言うと、九官鳥がうなずいた。
「見たら分かる」
九官鳥はそれでもまだ合点がいかないような顔をしていた。
「おまえは猫なのに、どうして鳥の言葉が話せるのか」
九官鳥は首をひねりながら、まだじろじろした目で、ぼくのほうを見ていた。
「ぼくはいろいろな動物の言葉が話せるのです」
ぼくはそう答えた。
「人の言葉も話せるのか」
九官鳥がさらに聞いてきた。
「聞くことはできますが、話すことはできません」
ぼくは、ほほほと笑いながら、そう答えた。
「さっき、人の声で話をしていたのは、あなたですか」
気になっていたことを、ぼくは聞いた。
「そうだ」
九官鳥がうなずいた。
「男の人の声と女の人の声が聞こえてきたけど、どちらの声真似もできるのですか」
ぼくはさらに聞いた。
「そうだ。信じられないというのなら、おまえに聞かせてやろう」
九官鳥はそう言うと、首を縮めて男の人の低い声で
「もう、おまえとは話したくない」
と言った。そのあと今度は首を伸ばして
「もう、あなたとは話したくない」
と、女の人の高い声で言った。
声を聞いた途端、ぼくは、がくぜんとした。間違いなく、さっき三階にいたときに聞こえてきた声そのものだったからだ。なんと、この九官鳥は人の声そっくりの声が出せるのだ。しかも男の人の声真似も女の人の声真似もできるのだ。
「電話が鳴る音も、あなたが……」
ぼくが聞くと、九官鳥がうなずいた。
「おれが一番得意としているのは、電話が鳴る音だ。オフィスにある電話が鳴る音も、家庭にある電話が鳴る音も、本物そっくりに真似できる。年配者のガラケーが鳴る音も、若者のスマートフォンが鳴る音も、そっくりに真似できる」
九官鳥が自慢そうに言った。
九官鳥はそれからまもなく、いろいろな電話の音を真似してみせた。どれもみな、まるで本物の電話が鳴っているように聞こえた。
あっけにとられたぼくは、しばらく、ぼうぜんとして、口をぽかんと開けたまま、その場に立ちすくんでいるよりほかなかった。
しばらくしてから、ほくとアーヤーは応接室を出た。
「九官鳥はいつこのうちに来たのか」
ぼくはシャオパイに聞いた。
「つい最近。一週間ほど前」
シャオパイがそう答えた。
「誰が連れてきたのか」
「飼い主さんの友だちが連れてきた」
「そうか」
ぼくにはようやく納得がいった。
「それにしても、あの九官鳥の才能はたいしたものだ。ぼくはこれまで九官鳥を見たことがあるが、あそこまでそっくりに真似できなかった」
感心しきりの声で、ぼくはそう言った。
「そうですか。九官鳥と飼い主さんはいつも一緒にいて、何度も何度も繰り返して練習していたから、九官鳥は人の声真似が上手にできるようになったのだと思う」
シャオパイがそう答えた。
「楽しくていいだろう」
ぼくがそう聞くと、シャオパイが首を横に振った。
「どうしてだ。にぎやかでいいだろう」
と、ぼくはシャオパイにもう一度聞いた。
「うるさくて、たまらないわ。それに九官鳥がうちに来てから、飼い主さんが、ぼくと一緒に過ごす時間が以前に比べて、ずっと少なくなった」
シャオパイがそう答えた。
「焼きもちを焼いているのではないか。九官鳥が、おまえに代わって、飼い主さんの愛を独り占めしてしまうのではないかと思って、それで、おまえは焼きもちを焼いているのだろう」
ぼくはシャオパイの心のなかを推察した。
「違うよ。そうじゃないよ」
シャオパイが強く否定した。
「じゃあ、どうしてだい」
ぼくは、けげんに思って聞き返した。
「ぼくが気に入らないのは、九官鳥は自己顕示欲が強いからだよ。それに、うぬぼれで、ほかのものを見下すところがある」
シャオパイが、そう答えた。
「そうか、自分の才能に自信を持ちすぎているのだろうな」
ぼくは、そう答えた。
ぼくとアーヤーは、それからまもなく、うちへ帰ることにした。
うちへ帰る途中、アーヤーが聞いた。
「お父さん、あの九官鳥が人の声を話す才能はたいしたものだと言ったけど、本当にそうなの」
「うん」
ぼくはうなずいた。
「そんなに素晴らしいの」
「そうだよ。人の声とまったく見分けがつかないほど素晴らしい。目をつむって聞いたら、九官鳥が話している声とはとても思えないほどだ」
「そうなの。そんなに素晴らしいの。だったら、もしかしたら私の願いがかなうかもしれないわ」
限りなく遠くを見つめるような目で、アーヤーがふいにそう言った。
ぼくはそれを聞いて、合点がいかなかった。
「おまえの願いはお母さんのようにきれいで、品のある猫になることだろう」
ぼくがそう言うと、アーヤーは首を横に振った。
「それは一つ目の願い。もう一つ、願いがあるの」
アーヤーの目が、きらきら輝いていた。
「なんだい、それは」
ぼくは、気もそぞろに聞き返した。
「お父さんのように、人の話を聞いて分かる猫になること」
アーヤーがそう答えた。
「えっ、本当か。本当にそんなことを思っているのか」
ぼくは、びっくりして、聞き返した。アーヤーがうなずいた。
アーヤーの二つ目の願いを、ぼくは今、初めて知った。
「そうか。それはうれしいな」
ぼくはそう答えた。
ぼくが人の言葉を聞いて分かるようになったのは、以前ぼくは、人に飼われていたからだ。飼い主である杜真子がぼくに話しかけてくれる言葉を何度も聞いているうちに、少しずつ言葉の意味が分かるようになってきた。でも今の生活のなかで、アーヤーに話しかけてくれる人は誰もいないので、アーヤーが人の言葉を聞いて分からないのは当たり前だ。
「これまで、わたしの二つ目の願いは無理だと思っていたけど、人の言葉が上手に話せる九官鳥に会ったから、その言葉を何度も聞いたら、もしかしたら、意味が分かるようになるかもしれないと思うようになったの」
アーヤーはうれしくてたまらないといった顔をしながら、そう言った。それからまもなくアーヤーは、弾むような足取りで、うちへ帰っていった。