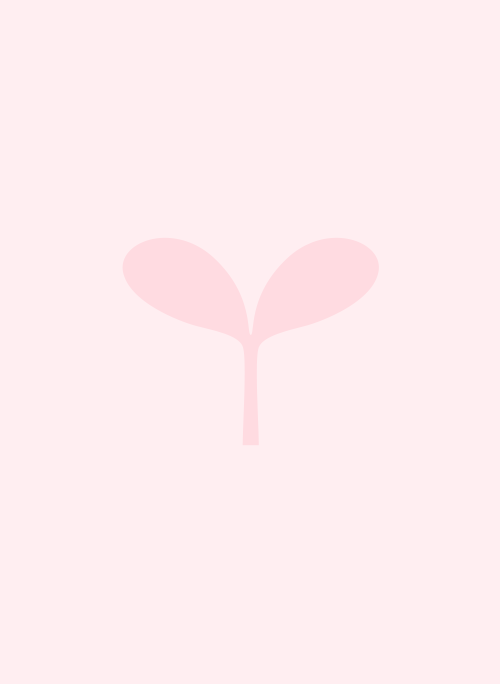天気……心地よい秋風が、さわさわと吹いている。空に広がっている雲は風に吹き散らされるように、ぱらぱらと流れている。翠湖の湖面には風にそよぐようにさざ波が立っている。イチョウの葉は散ってしまい、秋の気配が色濃く感じられるようになってきた。
ぼくは翠湖公園の秋景色がとても好きだ。黄金色に色づいたイチョウの葉が、秋風にそよそよと、そよいでいるときの美しさといったら、言葉ではとても表現できないほどだ。イチョウの葉の一枚一枚に、繊細な模様が施されていて、まるで小さな舞扇のようにきれいだ。風がそよそよと、そよぐたびに、小さな黄金色のイチョウの葉は、ひらひらと舞いながら地面の上に落ちていく。地面にうっすらと散り敷いたあと、時間とともに、だんだん重なっていく。そして一夜のうちに厚く積もる。ふかふかと積もったイチョウの葉の上を歩くと、かさかさと音がして、とても気持ちがいい。イチョウの葉が、はらはらと散っている時季は、ぼくは毎日、夜が明ける前にイチョウ林にやってくる。夜が明けると、清掃作業員がやってきて落ち葉を片付けてしまうからだ。
ぼくの友だちである老いらくさんも毎日、夜が明ける前にイチョウ林にやってくる。いつもはぼくのほうが早いが、今朝は老いらくさんのほうが早かった。
「笑い猫、今朝は遅かったな」
老いらくさんが言った。
「ぼくが遅かったのではないですよ。老いらくさんが早かっただけです」
ぼくはそう答えた。
「そうか、そうだったか。わしは最近よく眠れないので、早く出てきたのだ」
老いらくさんは物憂げな顔をしていた。
「どうしたのですか。何かあったのですか」
心配になって、ぼくは聞き返した。
「おまえのうちのサンパオがラブラドル犬を探すために、うちを出ていってから、サンパオのことがずっと気になって眠れないのだ」
老いらくさんがそう答えた。
「そうだったのですか。ご心配ありがとうございます」
ラブラドル犬に教えを請いに行ったサンパオのことを気遣ってくれる老いらくさんに、ぼくは感謝した。
「でもどうしてですか。ぼくと妻猫はサンパオの親だから、ぼくたちがサンパオのことを心配するのは当然ですが、老いらくさんがどうして……」
ぼくは、ふに落ちないでいた。
「以前、おまえはわしをサンパオに近づけさせてくれなかった。そのために離れたところからサンパオを見ているしかなかった。もうずいぶん長くサンパオに会っていない。この寂しさといったら、心のなかに、ぽっかりと穴が空いたようで……」
老いらくさんはわびしそうな顔をしていた。
「そうだったのですか。でも時がたったので、あの子たちは今は、もう赤ん坊ではないのです。もうみんな大きくなったので、自立して生きていかなければならないときになっているのです」
ぼくはそう答えた。
「ということは、サンパオだけでなく、パントーもアーヤーも、うちを離れていかなければならないときにさしかかっているということか」
老いらくさんがそう聞いた。
「そのとおりです。子どもたちは大きくなったら、両親のもとを離れて自立した生活を始めなければならないのです」
ぼくは、きっぱりとそう言った。
「そうか……。でもお母さんは離れがたく思っているのではないか」
老いらくさんが妻猫の心に思いをはせていた。
「確かにそうかもしれません。でも両親が子どもと離れがたく思って、子どもをいつまでもそばに引き留めておくことは、子どもを愛していることにはなりません。子どもを害していることであり、度を過ぎた利己心と言ってもいいかもしれません。そうは思いませんか」
ぼくは老いらくさんに問いかけた。
「そうだ、そのとおりだ」
老いらくさんが感心したような声でうなずいた。
「笑い猫、わしにはたくさんの子孫がいるが、これまできちんと生き方の哲理を教えたことがなかった。そのため、わしには将来性にあふれた優れた子孫が輩出しなかった。将来の見通しも理想もなく、ただ漫然とその日暮らしをしているだけの子孫。それにひきかえ、パントーやアーヤーやサンパオは違う。彼らはみな将来性にあふれている。もしかしたらパントーとアーヤーも家を出て自立したあとの生活場所をもう見つけているのではないか」
老いらくが聞いてきた。
「そんなことありません。まだです」
ぼくはそう答えた。
「老いらくさんは経験豊かで知識が広いから、どこかよい場所をご存じだったらお薦めしていただけないでしょうか」
ぼくはお願いした。
「そうだなあ……」
老いらくさんはそう言いながら、地面に積もった落ち葉の上を、ゆっくりとした速さで、ころころ転がりながら、行ったり来たりしていた。考えを巡らすときの老いらくさんのくせだ。
「遠すぎるところはだめだな。遠すぎたら、おまえとお母さんが会いに行きにくくなるからな。かといって近すぎるところもよくないな。近すぎたら、パントーとアーヤーはしょっちゅう、うちへ帰ってくるかもしれないからな。そうなったら、彼らを独り立ちさせるという目的が達せられないことになる」
老いらくさんがそう言った。さすが老いらくさん。考えることが理にかなっていて行き届いている。立派だと感心せざるを得ない。
「じゃあ、いちばんよいところは遠すぎもせず、近すぎもせず、その中間あたりのところですね」
ぼくは老いらくさんの意見に賛同した。
ぼくと老いらくさんはしばらくの間、話をやめた。ぼくの耳には老いらくさんが落ち葉の上を転がっているときに出る、かさかさいう音だけが聞こえていた。
「あっ、いいところがある。アーヤーにぴったりのところだ」
老いらくさんが突然、大きな声で、そう言った。
「どこですか」
ぼくは間髪を入れずに聞いた。
「シャオパイが住んでいる、あの別荘だよ」
老いらくさんがそう答えた。
プードル犬のシャオパイはこの町の郊外にある別荘に住んでいる。飼い主さんはきれいな女の人だ。ぼくと老いらくさんはその別荘に何度か行ったことがある。ぼくは飼い主さんと一緒に午後、お茶を飲んだこともある。ぼくの記憶によれば、飼い主さんはおいしい花餅を食べたり、香りのよいロウバイ茶を飲むことが好きなようだ。
「あそこはいいところですね」
老いらくさんが薦める別荘に親しみを感じていたぼくは、老いらくさんの提案に心から賛同した。
「この前、シャオパイのうちに行ったとき、花壇のなかにネズミがいるのを見つけた。アーヤーがあのうちに行ったらすぐにネズミをつかまえて技量を発揮することができるね」
ぼくがそう言うと、老いらくさんが不快そうな顔をした。
「そんな意味ではない。アーヤーにネズミをつかまえに行かせるのでは役不足というものだ」
ぼくは異を唱えた。
「猫がネズミをつかまえるのは理の当然。どうして役不足なの」
「わしが言いたいのは、ネズミをつかまえることができる猫は、どこにでもいるが、品格のある猫はめったにいないということだ。アーヤーがあの別荘に行って、シャオパイの飼い主さんの優美な雰囲気を毎日見ていたら、自然と感化されてアーヤーも品格のある猫になりうる可能性が出てくる。わしはそのことを言いたいのだ」
老いらくさんの話にうなずけるところもあったが、それでもまだ異を唱えたいところもあった。でもそのとき清掃作業員が大きなほうきを持って落ち葉掃きに来るのが見えたので、ぼくと老いらくさんはそそくさとイチョウ林を出て、アーチ橋のたもとで別れた。
家へ帰ってから、老いらくさんがさっき言っていたことを、ぼくは思い返した。それからアーヤーの性格の特徴についても綿密に分析してみた。すると思わず、ふふふと笑みがこぼれずにはいられなかった。
朝ご飯を食べ終わったばかりのアーヤーが、ぼくの前にやってきた。ぼくの顔をじろじろと見ながら、
「お父さん、どうして笑っているの」
と、けげんそうな顔で聞いた。
「笑っていないよ」
ぼくはそう答えて、顔に出ていた笑みを、さっと抑えた。
「アーヤー、お父さんは今日、お前をあるところへ連れていきたいと思っている」
えりを正してから、ぼくはアーヤーにそう言った。
「どこへ」
アーヤーは、きょとんとした顔をしていた。
「シャオパイが住んでいる別荘だよ。行ってみたいだろう」
ぼくが誘いかけると、アーヤーは、なんとも言えない表情をした。
「あまり興味がないわ。でもシャオパイの飼い主さんにはとても興味があるけど」
アーヤーがそう答えた。
「へえ、そうなのか。でもどうしてだい」
ぼくには合点がいかなかった。
「だって、お父さんがいつも飼い主さんは、とてもきれいで上品な人だと言っているから、どんな人だろうと思って、思いをはせているの。まだ会ったことがないから」
アーヤーが顔を少し赤らめながら、そう言った。
「そうか、そうだったのか。それなら行ってみようよ。どんな人か分かるから」
ぼくがそう言うと、アーヤーはうなずいた。
それからまもなく、ぼくはアーヤーを連れて、この町の郊外にあるシャオパイの別荘をめざして飛ぶように速く走っていった。別荘が立ち並んでいるところに来ると、ぼくの目に、シャオパイが住んでいる別荘がすぐに飛び込んできた。屋根のてっぺんはとがっていて、白い格子窓が部屋の外についているすてきなうちだ。
「ほら、あそこがシャオパイのうちだ」
心をときめかせながら、ぼくはアーヤーに教えた。
「きれいなうちですね」
アーヤーが、うっとりしたような顔をしていた。
ぼくとアーヤーがシャオパイのうちの前に着くと、玄関の前に車が一台停まっていた。運転手が後ろのトランクを開けて、荷物を入れているところだった。
「飼い主さんはこれからどこかへ出かけるようだ」
ぼくはアーヤーに、ひそひそと耳打ちした。
それからまもなく玄関のドアが開いて、シャオパイが出てきた。シャオパイは体にぴったりしたベージュ色のダスターコートをまとっていた。飼い主さんも出てきた。飼い主さんもベージュ色のダスターコートをまとっていて、目には黒いサングラスをかけていた。長い縮れ髪に秋風が当たって、しなやかに揺れていた。
「なんてきれいな人でしょう。お父さんが話していたとおりの人だわ」
アーヤーは思わず感心して、つぶやいていた。
それからまもなく飼い主さんはシャオパイを手に抱えながら、車に乗った。
車のドアが閉まって、車が出ていった。
「シャオパイも飼い主さんといっしょに、どこか遠いところに出かけていくの」
アーヤーが聞いた。
「いや、違うよ。シャオパイは留守番をしなければならないから、うちへ戻ってくるはずだよ」
ぼくはそう答えた。
「でもシャオパイも一緒に車に乗ったじゃない」
アーヤーは合点がいかないような顔をしていた。
「シャオパイは飛行場まで飼い主さんを見送りに行っただけだと思うよ。しばらくしたらまた戻ってくる」
ぼくはそう答えた。
「へえ、そうなの」
「たぶんそうだよ。この前、シャオパイに会ったときに、そう言ったのだ。飼い主さんがいつも飛行場までシャオパイを連れていくので、ロビーで飼い主さんを見送り、そのあと、運転手がシャオパイを別荘まで連れて帰るって」
ぼくがそう言うと、シャオパイは、うなずいていた。
「シャオパイは空港へ行ったことがおそらく一番多い犬じゃないかと思う。多すぎて、これまで何回行ったのか、自分でもはっきり覚えていないのではないかな」
ぼくがそう言うと、アーヤーがうらやましそうな顔をした。
「シャオパイの生活はいいなあ」
「どうしてだい」
「だって飛行機を間近で何回も見ることができるなんて、いいに決まっているじゃない」
アーヤーがそう答えた。
「確かにそうだな。空を飛べないぼくたちにとって、飛行機はあこがれの対象だし、飛行機を見るとロマンを感じるからな」
ぼくはそう答えた。
それからまもなく、ぼくはシャオパイのうちの庭を案内することにした。アーヤーをこのうちに初めて連れてきたから、ここがどんなうちなのか教えてあげなければと思ったからだ。まず花壇を案内することにした。前庭にも裏庭にも花壇があるので、まず前庭にある花壇を見せて、それから裏庭に連れて行った。裏庭にある花壇には、大きなモクセイの木が植えられていた。ぼくとアーヤーは木から落ちないように気をつけながら、木を登っていった。白い格子窓の内側に薄いレースのカーテンが引いてあって、カーテン越しに水晶灯がつるしてある明るい応接室が透けてみえた。
「お父さん、応接室から何か聞こえてきませんか」
アーヤーがそう言った。
「えっ、そうか」
ぼくは耳をぴんと立てた。すると確かに応接室のなかから音が鳴っているのが聞こえてきた。電話の音だった。そのあとすぐ人が話している声も聞こえてきた。
「こんにちは、お元気ですか」
女の人の高い声だった。
「うん、元気だよ」
今度は男の人の低い声がした。
(あれっ、部屋のなかに誰かいる。お客さんでも来ているのだろうか)
ぼくとアーヤーはびっくりして、急いで木から降りた。知らない人がいるのは落ち着かなかったので、ぼくとアーヤーは、そのあとすぐ、この家を出て、一目散にうちまで駆けて帰った。
ぼくは翠湖公園の秋景色がとても好きだ。黄金色に色づいたイチョウの葉が、秋風にそよそよと、そよいでいるときの美しさといったら、言葉ではとても表現できないほどだ。イチョウの葉の一枚一枚に、繊細な模様が施されていて、まるで小さな舞扇のようにきれいだ。風がそよそよと、そよぐたびに、小さな黄金色のイチョウの葉は、ひらひらと舞いながら地面の上に落ちていく。地面にうっすらと散り敷いたあと、時間とともに、だんだん重なっていく。そして一夜のうちに厚く積もる。ふかふかと積もったイチョウの葉の上を歩くと、かさかさと音がして、とても気持ちがいい。イチョウの葉が、はらはらと散っている時季は、ぼくは毎日、夜が明ける前にイチョウ林にやってくる。夜が明けると、清掃作業員がやってきて落ち葉を片付けてしまうからだ。
ぼくの友だちである老いらくさんも毎日、夜が明ける前にイチョウ林にやってくる。いつもはぼくのほうが早いが、今朝は老いらくさんのほうが早かった。
「笑い猫、今朝は遅かったな」
老いらくさんが言った。
「ぼくが遅かったのではないですよ。老いらくさんが早かっただけです」
ぼくはそう答えた。
「そうか、そうだったか。わしは最近よく眠れないので、早く出てきたのだ」
老いらくさんは物憂げな顔をしていた。
「どうしたのですか。何かあったのですか」
心配になって、ぼくは聞き返した。
「おまえのうちのサンパオがラブラドル犬を探すために、うちを出ていってから、サンパオのことがずっと気になって眠れないのだ」
老いらくさんがそう答えた。
「そうだったのですか。ご心配ありがとうございます」
ラブラドル犬に教えを請いに行ったサンパオのことを気遣ってくれる老いらくさんに、ぼくは感謝した。
「でもどうしてですか。ぼくと妻猫はサンパオの親だから、ぼくたちがサンパオのことを心配するのは当然ですが、老いらくさんがどうして……」
ぼくは、ふに落ちないでいた。
「以前、おまえはわしをサンパオに近づけさせてくれなかった。そのために離れたところからサンパオを見ているしかなかった。もうずいぶん長くサンパオに会っていない。この寂しさといったら、心のなかに、ぽっかりと穴が空いたようで……」
老いらくさんはわびしそうな顔をしていた。
「そうだったのですか。でも時がたったので、あの子たちは今は、もう赤ん坊ではないのです。もうみんな大きくなったので、自立して生きていかなければならないときになっているのです」
ぼくはそう答えた。
「ということは、サンパオだけでなく、パントーもアーヤーも、うちを離れていかなければならないときにさしかかっているということか」
老いらくさんがそう聞いた。
「そのとおりです。子どもたちは大きくなったら、両親のもとを離れて自立した生活を始めなければならないのです」
ぼくは、きっぱりとそう言った。
「そうか……。でもお母さんは離れがたく思っているのではないか」
老いらくさんが妻猫の心に思いをはせていた。
「確かにそうかもしれません。でも両親が子どもと離れがたく思って、子どもをいつまでもそばに引き留めておくことは、子どもを愛していることにはなりません。子どもを害していることであり、度を過ぎた利己心と言ってもいいかもしれません。そうは思いませんか」
ぼくは老いらくさんに問いかけた。
「そうだ、そのとおりだ」
老いらくさんが感心したような声でうなずいた。
「笑い猫、わしにはたくさんの子孫がいるが、これまできちんと生き方の哲理を教えたことがなかった。そのため、わしには将来性にあふれた優れた子孫が輩出しなかった。将来の見通しも理想もなく、ただ漫然とその日暮らしをしているだけの子孫。それにひきかえ、パントーやアーヤーやサンパオは違う。彼らはみな将来性にあふれている。もしかしたらパントーとアーヤーも家を出て自立したあとの生活場所をもう見つけているのではないか」
老いらくが聞いてきた。
「そんなことありません。まだです」
ぼくはそう答えた。
「老いらくさんは経験豊かで知識が広いから、どこかよい場所をご存じだったらお薦めしていただけないでしょうか」
ぼくはお願いした。
「そうだなあ……」
老いらくさんはそう言いながら、地面に積もった落ち葉の上を、ゆっくりとした速さで、ころころ転がりながら、行ったり来たりしていた。考えを巡らすときの老いらくさんのくせだ。
「遠すぎるところはだめだな。遠すぎたら、おまえとお母さんが会いに行きにくくなるからな。かといって近すぎるところもよくないな。近すぎたら、パントーとアーヤーはしょっちゅう、うちへ帰ってくるかもしれないからな。そうなったら、彼らを独り立ちさせるという目的が達せられないことになる」
老いらくさんがそう言った。さすが老いらくさん。考えることが理にかなっていて行き届いている。立派だと感心せざるを得ない。
「じゃあ、いちばんよいところは遠すぎもせず、近すぎもせず、その中間あたりのところですね」
ぼくは老いらくさんの意見に賛同した。
ぼくと老いらくさんはしばらくの間、話をやめた。ぼくの耳には老いらくさんが落ち葉の上を転がっているときに出る、かさかさいう音だけが聞こえていた。
「あっ、いいところがある。アーヤーにぴったりのところだ」
老いらくさんが突然、大きな声で、そう言った。
「どこですか」
ぼくは間髪を入れずに聞いた。
「シャオパイが住んでいる、あの別荘だよ」
老いらくさんがそう答えた。
プードル犬のシャオパイはこの町の郊外にある別荘に住んでいる。飼い主さんはきれいな女の人だ。ぼくと老いらくさんはその別荘に何度か行ったことがある。ぼくは飼い主さんと一緒に午後、お茶を飲んだこともある。ぼくの記憶によれば、飼い主さんはおいしい花餅を食べたり、香りのよいロウバイ茶を飲むことが好きなようだ。
「あそこはいいところですね」
老いらくさんが薦める別荘に親しみを感じていたぼくは、老いらくさんの提案に心から賛同した。
「この前、シャオパイのうちに行ったとき、花壇のなかにネズミがいるのを見つけた。アーヤーがあのうちに行ったらすぐにネズミをつかまえて技量を発揮することができるね」
ぼくがそう言うと、老いらくさんが不快そうな顔をした。
「そんな意味ではない。アーヤーにネズミをつかまえに行かせるのでは役不足というものだ」
ぼくは異を唱えた。
「猫がネズミをつかまえるのは理の当然。どうして役不足なの」
「わしが言いたいのは、ネズミをつかまえることができる猫は、どこにでもいるが、品格のある猫はめったにいないということだ。アーヤーがあの別荘に行って、シャオパイの飼い主さんの優美な雰囲気を毎日見ていたら、自然と感化されてアーヤーも品格のある猫になりうる可能性が出てくる。わしはそのことを言いたいのだ」
老いらくさんの話にうなずけるところもあったが、それでもまだ異を唱えたいところもあった。でもそのとき清掃作業員が大きなほうきを持って落ち葉掃きに来るのが見えたので、ぼくと老いらくさんはそそくさとイチョウ林を出て、アーチ橋のたもとで別れた。
家へ帰ってから、老いらくさんがさっき言っていたことを、ぼくは思い返した。それからアーヤーの性格の特徴についても綿密に分析してみた。すると思わず、ふふふと笑みがこぼれずにはいられなかった。
朝ご飯を食べ終わったばかりのアーヤーが、ぼくの前にやってきた。ぼくの顔をじろじろと見ながら、
「お父さん、どうして笑っているの」
と、けげんそうな顔で聞いた。
「笑っていないよ」
ぼくはそう答えて、顔に出ていた笑みを、さっと抑えた。
「アーヤー、お父さんは今日、お前をあるところへ連れていきたいと思っている」
えりを正してから、ぼくはアーヤーにそう言った。
「どこへ」
アーヤーは、きょとんとした顔をしていた。
「シャオパイが住んでいる別荘だよ。行ってみたいだろう」
ぼくが誘いかけると、アーヤーは、なんとも言えない表情をした。
「あまり興味がないわ。でもシャオパイの飼い主さんにはとても興味があるけど」
アーヤーがそう答えた。
「へえ、そうなのか。でもどうしてだい」
ぼくには合点がいかなかった。
「だって、お父さんがいつも飼い主さんは、とてもきれいで上品な人だと言っているから、どんな人だろうと思って、思いをはせているの。まだ会ったことがないから」
アーヤーが顔を少し赤らめながら、そう言った。
「そうか、そうだったのか。それなら行ってみようよ。どんな人か分かるから」
ぼくがそう言うと、アーヤーはうなずいた。
それからまもなく、ぼくはアーヤーを連れて、この町の郊外にあるシャオパイの別荘をめざして飛ぶように速く走っていった。別荘が立ち並んでいるところに来ると、ぼくの目に、シャオパイが住んでいる別荘がすぐに飛び込んできた。屋根のてっぺんはとがっていて、白い格子窓が部屋の外についているすてきなうちだ。
「ほら、あそこがシャオパイのうちだ」
心をときめかせながら、ぼくはアーヤーに教えた。
「きれいなうちですね」
アーヤーが、うっとりしたような顔をしていた。
ぼくとアーヤーがシャオパイのうちの前に着くと、玄関の前に車が一台停まっていた。運転手が後ろのトランクを開けて、荷物を入れているところだった。
「飼い主さんはこれからどこかへ出かけるようだ」
ぼくはアーヤーに、ひそひそと耳打ちした。
それからまもなく玄関のドアが開いて、シャオパイが出てきた。シャオパイは体にぴったりしたベージュ色のダスターコートをまとっていた。飼い主さんも出てきた。飼い主さんもベージュ色のダスターコートをまとっていて、目には黒いサングラスをかけていた。長い縮れ髪に秋風が当たって、しなやかに揺れていた。
「なんてきれいな人でしょう。お父さんが話していたとおりの人だわ」
アーヤーは思わず感心して、つぶやいていた。
それからまもなく飼い主さんはシャオパイを手に抱えながら、車に乗った。
車のドアが閉まって、車が出ていった。
「シャオパイも飼い主さんといっしょに、どこか遠いところに出かけていくの」
アーヤーが聞いた。
「いや、違うよ。シャオパイは留守番をしなければならないから、うちへ戻ってくるはずだよ」
ぼくはそう答えた。
「でもシャオパイも一緒に車に乗ったじゃない」
アーヤーは合点がいかないような顔をしていた。
「シャオパイは飛行場まで飼い主さんを見送りに行っただけだと思うよ。しばらくしたらまた戻ってくる」
ぼくはそう答えた。
「へえ、そうなの」
「たぶんそうだよ。この前、シャオパイに会ったときに、そう言ったのだ。飼い主さんがいつも飛行場までシャオパイを連れていくので、ロビーで飼い主さんを見送り、そのあと、運転手がシャオパイを別荘まで連れて帰るって」
ぼくがそう言うと、シャオパイは、うなずいていた。
「シャオパイは空港へ行ったことがおそらく一番多い犬じゃないかと思う。多すぎて、これまで何回行ったのか、自分でもはっきり覚えていないのではないかな」
ぼくがそう言うと、アーヤーがうらやましそうな顔をした。
「シャオパイの生活はいいなあ」
「どうしてだい」
「だって飛行機を間近で何回も見ることができるなんて、いいに決まっているじゃない」
アーヤーがそう答えた。
「確かにそうだな。空を飛べないぼくたちにとって、飛行機はあこがれの対象だし、飛行機を見るとロマンを感じるからな」
ぼくはそう答えた。
それからまもなく、ぼくはシャオパイのうちの庭を案内することにした。アーヤーをこのうちに初めて連れてきたから、ここがどんなうちなのか教えてあげなければと思ったからだ。まず花壇を案内することにした。前庭にも裏庭にも花壇があるので、まず前庭にある花壇を見せて、それから裏庭に連れて行った。裏庭にある花壇には、大きなモクセイの木が植えられていた。ぼくとアーヤーは木から落ちないように気をつけながら、木を登っていった。白い格子窓の内側に薄いレースのカーテンが引いてあって、カーテン越しに水晶灯がつるしてある明るい応接室が透けてみえた。
「お父さん、応接室から何か聞こえてきませんか」
アーヤーがそう言った。
「えっ、そうか」
ぼくは耳をぴんと立てた。すると確かに応接室のなかから音が鳴っているのが聞こえてきた。電話の音だった。そのあとすぐ人が話している声も聞こえてきた。
「こんにちは、お元気ですか」
女の人の高い声だった。
「うん、元気だよ」
今度は男の人の低い声がした。
(あれっ、部屋のなかに誰かいる。お客さんでも来ているのだろうか)
ぼくとアーヤーはびっくりして、急いで木から降りた。知らない人がいるのは落ち着かなかったので、ぼくとアーヤーは、そのあとすぐ、この家を出て、一目散にうちまで駆けて帰った。