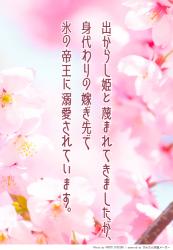一方で、翔は二十九歳だと語った。
「専門店営業本部の参加は初だそうですね? プロジェクトに抜擢されて驚いたでしょう……って、ああ、もう面倒だな」
口調がふと軽いものになる。
「すみません。外だけでいいので、タメ口でもいいですか? ですますだとどうも調子が狂ってしまって」
「は、はい。構いませんが……」
「じゃあ、入江さんもタメ口で頼む」
「えっ」
「対等じゃないと話しにくいだろう」
口調がくだけたものになると、十年前のあの頃に戻った気分になる。
(……何を考えているの。身の程知らずよ)
美波はぐっと気持ちを押し殺した。
病院で翔と過ごした数ヶ月は、今となっては一時の夢のようなものだ。
一方、当時の翔は失明しており、ずっと暗闇の中にいたのだから、むしろ悪夢の日々だったかもしれない。
すっかり立ち直ってエリート社員として生きている今、思い出したくもない忌々しい記憶になっている可能性もある。
そう考えると胸の奥がチクリと痛んだ、
美波にとってはあの夏の日々の記憶だけは、何年経ってもキラキラして輝いていて、宝物のように大切な思い出だったから。
だからこそ、その輝きを失わないためにも、自分の正体を明かすことはできなかった。
(翔君にだけは嫌われたくないし、失望されたくない……)
「――入江さん」
不意に翔が背中を向けたまま立ち止まる。
「聞きたいことがある」
「専門店営業本部の参加は初だそうですね? プロジェクトに抜擢されて驚いたでしょう……って、ああ、もう面倒だな」
口調がふと軽いものになる。
「すみません。外だけでいいので、タメ口でもいいですか? ですますだとどうも調子が狂ってしまって」
「は、はい。構いませんが……」
「じゃあ、入江さんもタメ口で頼む」
「えっ」
「対等じゃないと話しにくいだろう」
口調がくだけたものになると、十年前のあの頃に戻った気分になる。
(……何を考えているの。身の程知らずよ)
美波はぐっと気持ちを押し殺した。
病院で翔と過ごした数ヶ月は、今となっては一時の夢のようなものだ。
一方、当時の翔は失明しており、ずっと暗闇の中にいたのだから、むしろ悪夢の日々だったかもしれない。
すっかり立ち直ってエリート社員として生きている今、思い出したくもない忌々しい記憶になっている可能性もある。
そう考えると胸の奥がチクリと痛んだ、
美波にとってはあの夏の日々の記憶だけは、何年経ってもキラキラして輝いていて、宝物のように大切な思い出だったから。
だからこそ、その輝きを失わないためにも、自分の正体を明かすことはできなかった。
(翔君にだけは嫌われたくないし、失望されたくない……)
「――入江さん」
不意に翔が背中を向けたまま立ち止まる。
「聞きたいことがある」