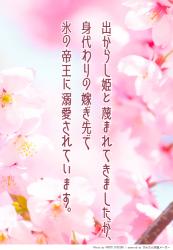座布団に腰を下ろし、一人俯く母の姿を見た美波は、
(お母さん、こんなに老けていた?)
、と首を傾げた。
緑がゆっくりと顔を上げ、美波の顔を見て目を見開く。
「えっ……。美波……なの?」
「そうだよ」
十年前大学進学で一人暮らしを始めて以降、実家に帰ったことは数えるほどしかない。それも親族の冠婚葬祭のためで、用事が終わるとすぐに帰ってきた。ほとんど無視されていたからだ。
両親からの連絡もなかったし、そうなると自分からするのも躊躇われる。
両親――特に母の緑に必要な娘は姉の茉莉だけだ。ずっと出来のいい茉莉ばかりを溺愛し、期待をかけ、優先してきた。
八年前、父が降格になって家計が苦しいからと、美波に進学を諦めるように言ったのも、茉莉の高額な私大の学費だけは確保するためだ。
――高校三年生になったばかりの頃だったか。ある夜母にダイニングに呼び出され、大学を卒業したら就職しろと迫られた。
『どうして? 私、模試でやっとK大が合格圏に入るようになったのに』
K大は茉莉が進学した私大だった。当時まだ父に、母に愛してほしい。認められたい。関心を持ってほしいと切望していたので、茉莉と同じように勉強ができるようになれば、自分を見てくれるのではないかと期待していたのだ。
なのに、なぜと絶句していると、緑は「ちょっと色々あって、お父さんのお給料が下がったのよ」と苦々しげに呟いた。
『姉さんは……』
『そんな、せっかく頑張ってK大に入学したのに、退学なんて茉莉が可哀想じゃない』
なら、進学もできない私は可哀想ではないのか――。
そう訴えたかったが言葉が出てこなかった。
長年自分の気持ちを押し殺してきたので、どう意思表示をすればよいのかがわからなくなっていたのだ。
美波の沈黙を承知したと受け取ったのか、緑は『あなたはいい子ねえ』と猫撫で声を出した。
『大丈夫よ。先生には私が言っておくから』
(お母さん、こんなに老けていた?)
、と首を傾げた。
緑がゆっくりと顔を上げ、美波の顔を見て目を見開く。
「えっ……。美波……なの?」
「そうだよ」
十年前大学進学で一人暮らしを始めて以降、実家に帰ったことは数えるほどしかない。それも親族の冠婚葬祭のためで、用事が終わるとすぐに帰ってきた。ほとんど無視されていたからだ。
両親からの連絡もなかったし、そうなると自分からするのも躊躇われる。
両親――特に母の緑に必要な娘は姉の茉莉だけだ。ずっと出来のいい茉莉ばかりを溺愛し、期待をかけ、優先してきた。
八年前、父が降格になって家計が苦しいからと、美波に進学を諦めるように言ったのも、茉莉の高額な私大の学費だけは確保するためだ。
――高校三年生になったばかりの頃だったか。ある夜母にダイニングに呼び出され、大学を卒業したら就職しろと迫られた。
『どうして? 私、模試でやっとK大が合格圏に入るようになったのに』
K大は茉莉が進学した私大だった。当時まだ父に、母に愛してほしい。認められたい。関心を持ってほしいと切望していたので、茉莉と同じように勉強ができるようになれば、自分を見てくれるのではないかと期待していたのだ。
なのに、なぜと絶句していると、緑は「ちょっと色々あって、お父さんのお給料が下がったのよ」と苦々しげに呟いた。
『姉さんは……』
『そんな、せっかく頑張ってK大に入学したのに、退学なんて茉莉が可哀想じゃない』
なら、進学もできない私は可哀想ではないのか――。
そう訴えたかったが言葉が出てこなかった。
長年自分の気持ちを押し殺してきたので、どう意思表示をすればよいのかがわからなくなっていたのだ。
美波の沈黙を承知したと受け取ったのか、緑は『あなたはいい子ねえ』と猫撫で声を出した。
『大丈夫よ。先生には私が言っておくから』