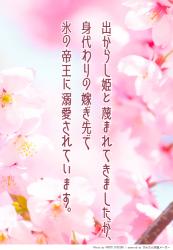――美波の母、緑の実家は東京都の隣県K県K市にあり、現在は伯母薫が婿を取って後を継いでいる。祖母の面倒も彼女が同居して見ていた。
亡くなった祖母の通夜と通夜、及び告別式は、同市内のメモリアルホールで開催されることになり、美波が到着すると喪主である薫が出迎えてくれた。
「伯母さん、お久しぶりです」
「あら、茉莉ちゃん来るの明日じゃ……って、えっ、美波ちゃん? ええっ」
薫は目を瞬かせた。
「びっくりした……。ごめんなさいね。髪が伸びたから? それともお化粧のせいかしら。こうして見るとあなたたち、顔立ちもよく似ていたのね。どうして気付かなかったのかしら」
美波もまた驚いた。薫にまで茉莉に似ている、更に見間違えたとまでと言われるとは思わなかったからだ。声はともかくとして、今まで容姿を言及されたことなどなかったのに。
伯母の薫は十年前の翔のように目が見えないわけでない。自分たち姉妹のことをよく知っているのに。
「そうでしょうか。あの、両親と姉は……」
「緑は来たけど衛さんは欠席だそうよ。今海外に出張中で帰ってこれないんですって。茉莉ちゃんは仕事で明日の告別式だけ来るって」
衛とは父の名前である。義母の葬儀に出ない夫など聞いたことがないし、第一衛は海外など関係ない部署に所属していたはずだ。何か嘘を吐かねばならない理由があるのだろうか。
「母はどこですか」
「控室よ。他の皆もいるわ」
「じゃあ、もう来ている人に挨拶して来ます」
美波は薫に礼を言ってそこに向かった
――伯母だけではない。美波が足を踏み入れるなり、茶を飲んでいた年配の親族は皆、「ええっ、美波ちゃんなのかい?」と目を見開いた。
「見違えたよ。一瞬茉莉ちゃんかと。何年ぶりだい? 今いくつなの」
「二十五です」
「早いなあ。最後に会ったのは高校生くらいだったっけ。いやあ、本当に綺麗になったなあ」
薫の一人息子であり、一回り上の従兄が感心したように頷く。続いてその妻が興味津々と言ったように聞いてきた。
「今どこに勤めているの」
「イダテンって言うスポーツ用品メーカーです」
「ええっ、前テレビのCMで見たよ」
「上場企業じゃなかったか? たいしたものだ」
「でも、美波ちゃん、頭よかったものね。確か国立のK大でしょ」
親族の中では一番若いからだろうか。すっかり話題の中心になってしまう。皆に取り囲まれてしまったために、奥の席に母がいるのにまったく気付かなかった。
「緑さん、水くさいじゃないか。美波ちゃんがこんなに美人になって、おまけに出世していたなんて知らなかったよ」
親族の一人が視線を向け、話を振ったので、ようやくはっとする。
「お母さん……」
亡くなった祖母の通夜と通夜、及び告別式は、同市内のメモリアルホールで開催されることになり、美波が到着すると喪主である薫が出迎えてくれた。
「伯母さん、お久しぶりです」
「あら、茉莉ちゃん来るの明日じゃ……って、えっ、美波ちゃん? ええっ」
薫は目を瞬かせた。
「びっくりした……。ごめんなさいね。髪が伸びたから? それともお化粧のせいかしら。こうして見るとあなたたち、顔立ちもよく似ていたのね。どうして気付かなかったのかしら」
美波もまた驚いた。薫にまで茉莉に似ている、更に見間違えたとまでと言われるとは思わなかったからだ。声はともかくとして、今まで容姿を言及されたことなどなかったのに。
伯母の薫は十年前の翔のように目が見えないわけでない。自分たち姉妹のことをよく知っているのに。
「そうでしょうか。あの、両親と姉は……」
「緑は来たけど衛さんは欠席だそうよ。今海外に出張中で帰ってこれないんですって。茉莉ちゃんは仕事で明日の告別式だけ来るって」
衛とは父の名前である。義母の葬儀に出ない夫など聞いたことがないし、第一衛は海外など関係ない部署に所属していたはずだ。何か嘘を吐かねばならない理由があるのだろうか。
「母はどこですか」
「控室よ。他の皆もいるわ」
「じゃあ、もう来ている人に挨拶して来ます」
美波は薫に礼を言ってそこに向かった
――伯母だけではない。美波が足を踏み入れるなり、茶を飲んでいた年配の親族は皆、「ええっ、美波ちゃんなのかい?」と目を見開いた。
「見違えたよ。一瞬茉莉ちゃんかと。何年ぶりだい? 今いくつなの」
「二十五です」
「早いなあ。最後に会ったのは高校生くらいだったっけ。いやあ、本当に綺麗になったなあ」
薫の一人息子であり、一回り上の従兄が感心したように頷く。続いてその妻が興味津々と言ったように聞いてきた。
「今どこに勤めているの」
「イダテンって言うスポーツ用品メーカーです」
「ええっ、前テレビのCMで見たよ」
「上場企業じゃなかったか? たいしたものだ」
「でも、美波ちゃん、頭よかったものね。確か国立のK大でしょ」
親族の中では一番若いからだろうか。すっかり話題の中心になってしまう。皆に取り囲まれてしまったために、奥の席に母がいるのにまったく気付かなかった。
「緑さん、水くさいじゃないか。美波ちゃんがこんなに美人になって、おまけに出世していたなんて知らなかったよ」
親族の一人が視線を向け、話を振ったので、ようやくはっとする。
「お母さん……」