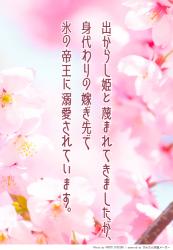「それは……」
「やっぱり女性に対しては可愛いでしょう」と言おうとして、自分に「何を言っているんだ」とツッコむ。同時に、会話の内容に既視感を覚えた。いつかどこかで似たような遣り取りをしたような――。
(確か、ずっと昔――)
しかし、思い出しかけた記憶は、不意にオフィスのドアが開けられたことで、一瞬で四散してしまった。
「失礼します。警備の者ですが」
「あっ、申し訳ございません。まだ仕事が残ってて……」
「システムの点検の都合で、今夜はもうすぐ消灯するんですよ。後一時間で終わらせてもらえますか」
「えっ、そうなんですか。わかりました」
「私も当分そちらの作業にかかりきりなので、消灯はしっかりして帰ってくださいね」
「はーい」
慌ててパソコンに向き直る。
「……ということは、帰るまでは俺たちだけってことか」
なぜか嬉しそうな翔とは対照的に、美波は困り果てて頭を抱えた。
「あああ、どうしよう。全然思い浮かばない……。高橋さんはどんな風にアイデアを出したの?」
「俺はやっぱり自分が履きたい靴はどんなものかってところからスタートしているな。今回はウォーキングシューズ中心だけど、前昔サッカーやってたって言っただろう」
「うん……」
翔のサッカーへの思いは、痛いほどよく知っていた。
「でも、足と目をやられてできなくなって……それからずっとどうすればもう一度ピッチに立てるかって考え続けていた」
「……」
美波は翔が何を言っているのかわからなかった。サッカーができない体なのにどうやってサッカーをやるというのか。
「だから、スポーツ用品メーカーに就職したんだ」
将来サッカーシューズの商品企画や製造に関わるつもりだと翔は語った。
キラキラ光る目を美波に向ける。
「いつか俺の夢を乗せたシューズを日本代表に履かせてやる。夢も俺の一部だ。俺の夢が選手と一緒になってピッチを駆け抜ける」
夢も俺の一部――その一言は美波の胸をも熱くした。
「まあ、夢はもう一つあるんだけどな。今回はそっちをコンセプトにしたアイデアを出した」
「そうなんだ……」
「あくまで参考な」
美波は涙が出そうになるのをなんとか堪えながら、翔のしなやかな強さに改めて惹き付けられるのを感じていた。
(翔君……諦めていなかったんだ)
一度壊れそうになった翔の心は、傷付いたからこそより輝きを増して、輝かしい未来に向かって歩き続けている。
(……私は?)
自分はどうなのかと心に問い掛ける。
(……私は立ち止まったままでいいの?)
「やっぱり女性に対しては可愛いでしょう」と言おうとして、自分に「何を言っているんだ」とツッコむ。同時に、会話の内容に既視感を覚えた。いつかどこかで似たような遣り取りをしたような――。
(確か、ずっと昔――)
しかし、思い出しかけた記憶は、不意にオフィスのドアが開けられたことで、一瞬で四散してしまった。
「失礼します。警備の者ですが」
「あっ、申し訳ございません。まだ仕事が残ってて……」
「システムの点検の都合で、今夜はもうすぐ消灯するんですよ。後一時間で終わらせてもらえますか」
「えっ、そうなんですか。わかりました」
「私も当分そちらの作業にかかりきりなので、消灯はしっかりして帰ってくださいね」
「はーい」
慌ててパソコンに向き直る。
「……ということは、帰るまでは俺たちだけってことか」
なぜか嬉しそうな翔とは対照的に、美波は困り果てて頭を抱えた。
「あああ、どうしよう。全然思い浮かばない……。高橋さんはどんな風にアイデアを出したの?」
「俺はやっぱり自分が履きたい靴はどんなものかってところからスタートしているな。今回はウォーキングシューズ中心だけど、前昔サッカーやってたって言っただろう」
「うん……」
翔のサッカーへの思いは、痛いほどよく知っていた。
「でも、足と目をやられてできなくなって……それからずっとどうすればもう一度ピッチに立てるかって考え続けていた」
「……」
美波は翔が何を言っているのかわからなかった。サッカーができない体なのにどうやってサッカーをやるというのか。
「だから、スポーツ用品メーカーに就職したんだ」
将来サッカーシューズの商品企画や製造に関わるつもりだと翔は語った。
キラキラ光る目を美波に向ける。
「いつか俺の夢を乗せたシューズを日本代表に履かせてやる。夢も俺の一部だ。俺の夢が選手と一緒になってピッチを駆け抜ける」
夢も俺の一部――その一言は美波の胸をも熱くした。
「まあ、夢はもう一つあるんだけどな。今回はそっちをコンセプトにしたアイデアを出した」
「そうなんだ……」
「あくまで参考な」
美波は涙が出そうになるのをなんとか堪えながら、翔のしなやかな強さに改めて惹き付けられるのを感じていた。
(翔君……諦めていなかったんだ)
一度壊れそうになった翔の心は、傷付いたからこそより輝きを増して、輝かしい未来に向かって歩き続けている。
(……私は?)
自分はどうなのかと心に問い掛ける。
(……私は立ち止まったままでいいの?)