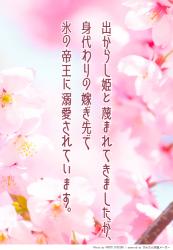翔は仁王立ちになって腕を組んでいた。切れ長の目に真っ直ぐに見据えられ、ドキリとしてその場で固まってしまう。
「もう十時だぞ」
「い、いや、どうして翔く……高橋さんが」
美波はしまったと視線を落とした。
(私さっきも無意識のうちに翔君って呼んじゃった?)
いつも心の中で呼んでいた、昔の呼び名を口にしてしまった。
しかし、翔が意識した様子はない。
(……よかった。気付いていないみたい)
それにしてもなぜ翔が専門店営業本部のオフィスにいるのか。
翔はドアに目をやり、「電気付いてたから」と答えた。
「もう十一時だぞ。というか、この一週間入江さん、残業だらけじゃなかったか。過労で倒れるぞ。いい加減帰れ」
そういうわけにもいかない。
「まだ企画書をまとめていないから。私の家ってパソコンがないから、オフィスで終わらせなくちゃいけないの。あっ、タイムカードはもう押してあるから、これは残業の中に入っていないので安心して」
「馬鹿。それは残業にしていいんだよ」
「でも、定時で仕上げられなかったのは私の力不足の問題だもの」
翔は「関係ない」とバッサリと切り捨てた。
「企業はそういう力不足も考慮しているから遠慮は必要ない。できなかったらできなかったと報告すればいいだけだ。ほら、帰るぞ」
翔が無理矢理パソコンの電源を落とそうとする。
「待って!」
美波は慌てて翔の腕を掴んだ。
「心配してくれてありがとう。でも……大丈夫。営業事務では繁忙期の残業なんて当然だし、もう慣れているから」
「でもな」
「私……」
出会って初めて翔の目を真っ直ぐに見返した気がした。
何に驚いたのか、翔がわずかに目を見開く。
「任された仕事はきちんとやりたいの」
それくらいしかできることがないからこそ、それだけは譲れなかった。
翔や茉莉のようにキラキラ輝けない、路傍の石ころのような自分が持つ、たった一つのプライドなのだ。
「もう少ししたら帰るから」
「……」
翔は美波を見下ろしたまま口を噤んでいたが、やがて何を思ったのか隣の席の椅子を引き、どかりと腰を下ろして長い足を組んだ。
「た、高橋さん?」
「あんた、頑固そうだからな。放っておいたら明日の朝まで居座ってそうだ」
「頑固って……」
「でも、それがあんたのいいところなんだろうな」
「もう十時だぞ」
「い、いや、どうして翔く……高橋さんが」
美波はしまったと視線を落とした。
(私さっきも無意識のうちに翔君って呼んじゃった?)
いつも心の中で呼んでいた、昔の呼び名を口にしてしまった。
しかし、翔が意識した様子はない。
(……よかった。気付いていないみたい)
それにしてもなぜ翔が専門店営業本部のオフィスにいるのか。
翔はドアに目をやり、「電気付いてたから」と答えた。
「もう十一時だぞ。というか、この一週間入江さん、残業だらけじゃなかったか。過労で倒れるぞ。いい加減帰れ」
そういうわけにもいかない。
「まだ企画書をまとめていないから。私の家ってパソコンがないから、オフィスで終わらせなくちゃいけないの。あっ、タイムカードはもう押してあるから、これは残業の中に入っていないので安心して」
「馬鹿。それは残業にしていいんだよ」
「でも、定時で仕上げられなかったのは私の力不足の問題だもの」
翔は「関係ない」とバッサリと切り捨てた。
「企業はそういう力不足も考慮しているから遠慮は必要ない。できなかったらできなかったと報告すればいいだけだ。ほら、帰るぞ」
翔が無理矢理パソコンの電源を落とそうとする。
「待って!」
美波は慌てて翔の腕を掴んだ。
「心配してくれてありがとう。でも……大丈夫。営業事務では繁忙期の残業なんて当然だし、もう慣れているから」
「でもな」
「私……」
出会って初めて翔の目を真っ直ぐに見返した気がした。
何に驚いたのか、翔がわずかに目を見開く。
「任された仕事はきちんとやりたいの」
それくらいしかできることがないからこそ、それだけは譲れなかった。
翔や茉莉のようにキラキラ輝けない、路傍の石ころのような自分が持つ、たった一つのプライドなのだ。
「もう少ししたら帰るから」
「……」
翔は美波を見下ろしたまま口を噤んでいたが、やがて何を思ったのか隣の席の椅子を引き、どかりと腰を下ろして長い足を組んだ。
「た、高橋さん?」
「あんた、頑固そうだからな。放っておいたら明日の朝まで居座ってそうだ」
「頑固って……」
「でも、それがあんたのいいところなんだろうな」