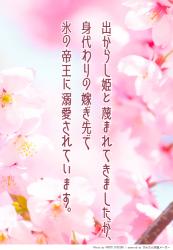――こうした美波の硬直した心境とは真逆に、プロジェクトは順調に進んでいった。
市場調査とターゲティングを終え、商品企画の段階まで進んでいる。
今回は新技術を採用した新シリーズの展開だ。ある程度専門知識が求められるために、いつもならマーケティング部内の企画部門に任せる。
しかし、今回はやはり社長の提案で、プロジェクトに直に関わった社員、全員が企画書を提出するよう求められたのだという。
美波はその連絡を三井から受けた時、思わず「私もですか!?」と自分を指差してしまった。
「そうそう。入江さんだけではなく全員ね。当然僕もやるよ」
「でも、私は素人ですし……」
「素人だから自由に考えられるって調書もあるよ。それに、今回は企画といってもブレインストーミング的なものだし、採用されることの方が少ないから。されてもちゃんとプロが手直しするし、そんなに構えて書かなくても大丈夫」
一ヶ月後までに三案出してほしいのだという。
はっきり言ってまったく自信がない。しかし、仕事ならばやるしかなかった。
「……わかりました」
なお、美波は現在プロジェクトに関わる業務だけではなく、専門店営業本部の営業事務も担っている。つい先週一人急に退職してしまったためだ。そんな中で更に一つ仕事が増えたので、まさにてんてこ舞いの状況だった。
美波の心境を察したのか、三井が「入江さんが忙しいのはわかっているからね」と頷く。
「まあ、僕らなんてテキトーでいいんだよ、テキトーで」
「そうですね……」
だが、いくら適当にと言われても、適当にできないのが美波である。
締め切り前日の夜遅く、営業事務で残業が発生したのもあって、うんうん唸りつつPCに向かっていた。なお、すでに他の社員は全員帰宅している。
美波はこのプロジェクトのメンバーとなるまではただの営業事務で、営業のサポート業務が仕事。自分で考えて何かをやる機会がなかった。
それだけに自由にどうぞと言われても難しい。なんとか二案はまとめたものの、あと一案がまったく思い浮かばなかった。
パソコンに表示された時計が午後十一時を指し示す。同時に、ロイヤルミルクティーの缶がデスクにとんと置かれた。美波が一番好きなソフトドリンクだった。
「えっ……」
驚いて思わず顔を上げる。
「翔……君?」
市場調査とターゲティングを終え、商品企画の段階まで進んでいる。
今回は新技術を採用した新シリーズの展開だ。ある程度専門知識が求められるために、いつもならマーケティング部内の企画部門に任せる。
しかし、今回はやはり社長の提案で、プロジェクトに直に関わった社員、全員が企画書を提出するよう求められたのだという。
美波はその連絡を三井から受けた時、思わず「私もですか!?」と自分を指差してしまった。
「そうそう。入江さんだけではなく全員ね。当然僕もやるよ」
「でも、私は素人ですし……」
「素人だから自由に考えられるって調書もあるよ。それに、今回は企画といってもブレインストーミング的なものだし、採用されることの方が少ないから。されてもちゃんとプロが手直しするし、そんなに構えて書かなくても大丈夫」
一ヶ月後までに三案出してほしいのだという。
はっきり言ってまったく自信がない。しかし、仕事ならばやるしかなかった。
「……わかりました」
なお、美波は現在プロジェクトに関わる業務だけではなく、専門店営業本部の営業事務も担っている。つい先週一人急に退職してしまったためだ。そんな中で更に一つ仕事が増えたので、まさにてんてこ舞いの状況だった。
美波の心境を察したのか、三井が「入江さんが忙しいのはわかっているからね」と頷く。
「まあ、僕らなんてテキトーでいいんだよ、テキトーで」
「そうですね……」
だが、いくら適当にと言われても、適当にできないのが美波である。
締め切り前日の夜遅く、営業事務で残業が発生したのもあって、うんうん唸りつつPCに向かっていた。なお、すでに他の社員は全員帰宅している。
美波はこのプロジェクトのメンバーとなるまではただの営業事務で、営業のサポート業務が仕事。自分で考えて何かをやる機会がなかった。
それだけに自由にどうぞと言われても難しい。なんとか二案はまとめたものの、あと一案がまったく思い浮かばなかった。
パソコンに表示された時計が午後十一時を指し示す。同時に、ロイヤルミルクティーの缶がデスクにとんと置かれた。美波が一番好きなソフトドリンクだった。
「えっ……」
驚いて思わず顔を上げる。
「翔……君?」