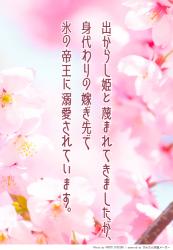――目が見えないとその他の感覚――特に聴覚が敏感になる。
翔はもともと耳がよかったのもあり、「ナツ」の感情の波を声から敏感に感じ取っていた。「ナツ」は一見明るく元気な面白い女の子だった。
だが、付き合いが長くなると、優しく思いやりがあるのは間違いないが、本当の彼女は大人しく、不器用で、寂しがり屋なのではないかと感じるようになった。
――「ナツ」との何気ないお喋りはいつも楽しかったが、時折ふっと会話が途切れることがあった。
そんなことは男友だちとでもいくらでもあるし、それで大して気まずくなることもない。
だが、「ナツ」はそのたびに「あっ、ごめんね」と謝って、必死に別の話題を探そうとする。謝る必要など何もないのに。
嘘を吐くのも苦手だった。
あれはいつのことだったか、「ナツ」がケーキを差し入れてくれたことがある。あいにく、好物のチョコレートケーキは一つしかなかった。
翔は「ナツ」がチョコレートケーキを好きなら、迷わず彼女に譲るつもりだった。自分が美味しいと思うより彼女に喜んでほしかったから。「ナツ」が好きだったから。
なのに、「ナツ」は「チーズケーキが好き」と答えたのだ。
『翔君はチョコレート好きだったよね? はい、どうぞ』
翔は「ナツ」はチーズが苦手だと知っていた。以前、サンドイッチに挟まっていたスライススチーズを、どうしても食べられないと嘆いていたことがあった。翔はそれを「じゃあ、勿体ないから俺がもらう」と食べたのだ。
だが、「ナツ」はすっかりその遣り取りを忘れていた。
「ナツ」はいつもこうだった。与えようとするばかりで何もほしがらない。
翔は「ナツ」にもっと欲深くなってほしかった。チョコレートケーキも、自分との未来も――何よりあなたがほしいのだと言ってほしかった。
だから、「ナツ」にもやりたいことがあると知った時には嬉しかった。
『知っていた? 翔君の病室からも海が見えるの。青灰色の静かな海……。あの海を翔君と一緒に見に行ってみたい。砂浜を歩いて、波の音を聞いて……』
彼女からそう聞いた時、夏の砂浜を「ナツ」と一緒に歩く光景が、脳裏に色鮮やかに浮かんだ。
その時サッカーだけではない、もう一つの夢ができたのだ。
『彼女と一緒に青灰色の本物の海を見たい』
翔はもともと耳がよかったのもあり、「ナツ」の感情の波を声から敏感に感じ取っていた。「ナツ」は一見明るく元気な面白い女の子だった。
だが、付き合いが長くなると、優しく思いやりがあるのは間違いないが、本当の彼女は大人しく、不器用で、寂しがり屋なのではないかと感じるようになった。
――「ナツ」との何気ないお喋りはいつも楽しかったが、時折ふっと会話が途切れることがあった。
そんなことは男友だちとでもいくらでもあるし、それで大して気まずくなることもない。
だが、「ナツ」はそのたびに「あっ、ごめんね」と謝って、必死に別の話題を探そうとする。謝る必要など何もないのに。
嘘を吐くのも苦手だった。
あれはいつのことだったか、「ナツ」がケーキを差し入れてくれたことがある。あいにく、好物のチョコレートケーキは一つしかなかった。
翔は「ナツ」がチョコレートケーキを好きなら、迷わず彼女に譲るつもりだった。自分が美味しいと思うより彼女に喜んでほしかったから。「ナツ」が好きだったから。
なのに、「ナツ」は「チーズケーキが好き」と答えたのだ。
『翔君はチョコレート好きだったよね? はい、どうぞ』
翔は「ナツ」はチーズが苦手だと知っていた。以前、サンドイッチに挟まっていたスライススチーズを、どうしても食べられないと嘆いていたことがあった。翔はそれを「じゃあ、勿体ないから俺がもらう」と食べたのだ。
だが、「ナツ」はすっかりその遣り取りを忘れていた。
「ナツ」はいつもこうだった。与えようとするばかりで何もほしがらない。
翔は「ナツ」にもっと欲深くなってほしかった。チョコレートケーキも、自分との未来も――何よりあなたがほしいのだと言ってほしかった。
だから、「ナツ」にもやりたいことがあると知った時には嬉しかった。
『知っていた? 翔君の病室からも海が見えるの。青灰色の静かな海……。あの海を翔君と一緒に見に行ってみたい。砂浜を歩いて、波の音を聞いて……』
彼女からそう聞いた時、夏の砂浜を「ナツ」と一緒に歩く光景が、脳裏に色鮮やかに浮かんだ。
その時サッカーだけではない、もう一つの夢ができたのだ。
『彼女と一緒に青灰色の本物の海を見たい』