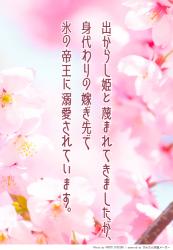「そんな、バカだなんて……」
(……どうしよう)
まさか、そんなに長く翔を縛り付けていたなんて――喜びよりも罪悪感を覚える。
「悪い。こんな話をして困らせて」
「いえ……」
「仕方ない。また一から探すしかないか」
ナツの件はこれで終わったはずだった。翔は彼女を諦めざるを得ず、いい思い出でのままで終わるはずだった。
それから半月後、プロジェクトに協力する広告代理店の担当として、姉の茉莉がイダテンにやって来なければ――。
――翔はわけがわからず目を瞬かせた。
「ごめんなさい。ナツさんって誰?」
他でもない美波にナツではないと否定されたからだ。そんなはずがない。彼女は嘘を吐いている。
(なぜだ? 入江さん、どうして自分がナツだと言ってくれないんだ)
翔は彼女こそが「ナツ」だと確信していた。こんなに綺麗な声の持ち主は彼女しかいない。
学生時代は自分の足で、社会人になってからは悪友の経営する探偵事務所に依頼してまで、「ナツ」を探し続けてきた。
そして昨年、ようやく「ナツ」と思われる女性を突き止めた。当時入院していた病院で、看護師をしていた女性とのコンタクトが取れたのだ。
彼女は十年前自分と同じ病棟、同じ階の入院患者の世話をしており、その中に一人印象的な少女がいたと語った。
『とても綺麗な声の子だったわ。物静かだけどよく見ると結構可愛い顔をしていたからよく覚えてる。どうしていつもあんなに寂しそうなんだろうって不思議だった』
彼女の名前は入江美波と言い、当時高校一年生になったばかり。
『盲腸で入院して、予定通り一週間くらいで退院したはずよ。でも、時々病院の庭で顔を見るようになって、今度は家族か友だちのお見舞いに来たのかと思っていたの。そう、あなたに会いにきていたのね』
そこで今度は入江美波という女性を調べたところ、なんと転職先の会社で営業事務をしているのだと判明した。更に、同じプロジェクトに参加すると知って、自分たちはどこかで繋がっていたのだと感じて嬉しくなった。
ところが、やっと会えた美波は「ナツ」なんて知らないという。嘘だろう。俺にはわかるんだとと問い詰めたかったが、理性でぐっと自分を押し留めた。
たった数ヶ月の交流だったが、翔はナツも自分を好いてくれているという確信があった。そして、ナツにとっても自分は忘れられない男であるはずだとも。
だが、それは自惚れだったのかもしれない。何せもう十年も前の話なのだ。新しく男がいるので、自分を面倒に感じ、忘れた振りをしても不思議ではない。
女は新しい恋人ができると、たちまち気持ちが上書きされ、過去の男など忘れてしまうと聞いたことがある。
手術が成功したあと黙って姿を消したのも、他に好きな相手ができてフェードアウトしただけなのかもしれない。
だが、心が「ナツは――美波はそんな子ではない」と叫ぶのだ。
とはいえ、美波本人に否定されてはどうしようもない。しかし、諦めるつもりはまったくなかった。例え恋人がいようと関係ない。
こうなれば、振り向いてくれるまで接触を続け、口説くしかないかと考えていたその時、目を伏せていた彼女の細い肩が、カタカタと小刻みに震えているのが目に入った。
(……怯えてる?)
一体何に怯えているのか。
(もしかして、何か事情があるのか?)
声が似ているという姉について追及してみると、顔色がもっと悪くなってしまった。
ナツだと認めると何か都合の悪いことが起こるのか。
それはどんな事情なのか。その姉とやらが関係しているのか――。
(……どうしよう)
まさか、そんなに長く翔を縛り付けていたなんて――喜びよりも罪悪感を覚える。
「悪い。こんな話をして困らせて」
「いえ……」
「仕方ない。また一から探すしかないか」
ナツの件はこれで終わったはずだった。翔は彼女を諦めざるを得ず、いい思い出でのままで終わるはずだった。
それから半月後、プロジェクトに協力する広告代理店の担当として、姉の茉莉がイダテンにやって来なければ――。
――翔はわけがわからず目を瞬かせた。
「ごめんなさい。ナツさんって誰?」
他でもない美波にナツではないと否定されたからだ。そんなはずがない。彼女は嘘を吐いている。
(なぜだ? 入江さん、どうして自分がナツだと言ってくれないんだ)
翔は彼女こそが「ナツ」だと確信していた。こんなに綺麗な声の持ち主は彼女しかいない。
学生時代は自分の足で、社会人になってからは悪友の経営する探偵事務所に依頼してまで、「ナツ」を探し続けてきた。
そして昨年、ようやく「ナツ」と思われる女性を突き止めた。当時入院していた病院で、看護師をしていた女性とのコンタクトが取れたのだ。
彼女は十年前自分と同じ病棟、同じ階の入院患者の世話をしており、その中に一人印象的な少女がいたと語った。
『とても綺麗な声の子だったわ。物静かだけどよく見ると結構可愛い顔をしていたからよく覚えてる。どうしていつもあんなに寂しそうなんだろうって不思議だった』
彼女の名前は入江美波と言い、当時高校一年生になったばかり。
『盲腸で入院して、予定通り一週間くらいで退院したはずよ。でも、時々病院の庭で顔を見るようになって、今度は家族か友だちのお見舞いに来たのかと思っていたの。そう、あなたに会いにきていたのね』
そこで今度は入江美波という女性を調べたところ、なんと転職先の会社で営業事務をしているのだと判明した。更に、同じプロジェクトに参加すると知って、自分たちはどこかで繋がっていたのだと感じて嬉しくなった。
ところが、やっと会えた美波は「ナツ」なんて知らないという。嘘だろう。俺にはわかるんだとと問い詰めたかったが、理性でぐっと自分を押し留めた。
たった数ヶ月の交流だったが、翔はナツも自分を好いてくれているという確信があった。そして、ナツにとっても自分は忘れられない男であるはずだとも。
だが、それは自惚れだったのかもしれない。何せもう十年も前の話なのだ。新しく男がいるので、自分を面倒に感じ、忘れた振りをしても不思議ではない。
女は新しい恋人ができると、たちまち気持ちが上書きされ、過去の男など忘れてしまうと聞いたことがある。
手術が成功したあと黙って姿を消したのも、他に好きな相手ができてフェードアウトしただけなのかもしれない。
だが、心が「ナツは――美波はそんな子ではない」と叫ぶのだ。
とはいえ、美波本人に否定されてはどうしようもない。しかし、諦めるつもりはまったくなかった。例え恋人がいようと関係ない。
こうなれば、振り向いてくれるまで接触を続け、口説くしかないかと考えていたその時、目を伏せていた彼女の細い肩が、カタカタと小刻みに震えているのが目に入った。
(……怯えてる?)
一体何に怯えているのか。
(もしかして、何か事情があるのか?)
声が似ているという姉について追及してみると、顔色がもっと悪くなってしまった。
ナツだと認めると何か都合の悪いことが起こるのか。
それはどんな事情なのか。その姉とやらが関係しているのか――。