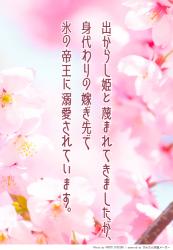――視界がぐらぐら揺れている。
「俺はナツをずっと探していた……あんたはナツなのか?」
目の前にいるスーツ姿の翔の顔もだ。
一瞬地震かと思ったがそうではない。動揺しているからだとすぐに気付いた。
(駄目よ。落ち着いて)
必死に自分に言い聞かせる。
まさか、翔が自分を覚えていたどころか、ずっと行方を探していたなんて。
「ごめんなさい。ナツさんって誰?」
出した声が震えていなかったのでほっとした。
(絶対にバレたくない。どうして今になって)
あれから十年、自分なりに努力はしてきたが、相変わらず暗くて冴えない地味子のままだ。自信がなくて異性と付き合った経験もない。こんな女になったのだと知られたくない。
というよりは、翔が愛した「ナツ」は一夜の夏の夢。幻のような存在で現実にはいなかった女の子だ。どれだけ捜したところでどこにもいない。どれだけ望まれても会わせてあげられないのだ。
とにかくなんのことだかわからないと言った顔をして見せる。
「心当たりがなくて……」
翔は苛立たしげに美波の肩を掴んだ。
「今説明したはずだ。あんたはナツなんだろう?」
その顔が怒って見えるのはなぜなのか。
(私が明るくて、元気で、面白い、翔君が思い描いていたような女じゃないから?)
なら、決して認めてはならなかった。
「えっと、私の声と似た人?」
あくまで白を切る。すると、翔も自信がなくなってきたのだろうか。
「違うのか……?」
、と首を傾げた。
「自分じゃ実感できないんだけど、私の声って有名な声優さんに似ているみたい。だから、時々驚かれることがあるの。結構似た人はいるんじゃかいかな」
「……」
翔はまだじっと美波を見つめている。
「……入江さん、あんたの声に似た人は他に知っているか?」
「姉が声だけはそっくりだって言るけど」
「そうか。お姉さんが……」
ようやく「悪かった」と溜め息を吐く。
「……俺の勘違いだったみたいだな。君のお姉さんと会うことはできるだろうか」
「ごめんなさい。それは難しいかと……」
美波は大学進学と同時に、母の反対を押し切って家を出ている。原因は家庭の問題と姉の茉莉、自分との間に生まれた確執からだ。以降、時々しか連絡を取っていない。
「高橋さん、どうしてそのナツさんを捜しているの? 昔お世話になったお礼を言いたいとか?」
「いや、違う」
翔は身を翻して前を見つめた。
「まだ好きだって伝えたい」
「……っ」
「十年も前のガキだった頃のことで、顔を見たこともないのに、バカみたいだって思うだろ? でも、どうしても忘れられないんだ。あんな風に純粋に誰かを好きになれることって……もう二度とない気がする」
「俺はナツをずっと探していた……あんたはナツなのか?」
目の前にいるスーツ姿の翔の顔もだ。
一瞬地震かと思ったがそうではない。動揺しているからだとすぐに気付いた。
(駄目よ。落ち着いて)
必死に自分に言い聞かせる。
まさか、翔が自分を覚えていたどころか、ずっと行方を探していたなんて。
「ごめんなさい。ナツさんって誰?」
出した声が震えていなかったのでほっとした。
(絶対にバレたくない。どうして今になって)
あれから十年、自分なりに努力はしてきたが、相変わらず暗くて冴えない地味子のままだ。自信がなくて異性と付き合った経験もない。こんな女になったのだと知られたくない。
というよりは、翔が愛した「ナツ」は一夜の夏の夢。幻のような存在で現実にはいなかった女の子だ。どれだけ捜したところでどこにもいない。どれだけ望まれても会わせてあげられないのだ。
とにかくなんのことだかわからないと言った顔をして見せる。
「心当たりがなくて……」
翔は苛立たしげに美波の肩を掴んだ。
「今説明したはずだ。あんたはナツなんだろう?」
その顔が怒って見えるのはなぜなのか。
(私が明るくて、元気で、面白い、翔君が思い描いていたような女じゃないから?)
なら、決して認めてはならなかった。
「えっと、私の声と似た人?」
あくまで白を切る。すると、翔も自信がなくなってきたのだろうか。
「違うのか……?」
、と首を傾げた。
「自分じゃ実感できないんだけど、私の声って有名な声優さんに似ているみたい。だから、時々驚かれることがあるの。結構似た人はいるんじゃかいかな」
「……」
翔はまだじっと美波を見つめている。
「……入江さん、あんたの声に似た人は他に知っているか?」
「姉が声だけはそっくりだって言るけど」
「そうか。お姉さんが……」
ようやく「悪かった」と溜め息を吐く。
「……俺の勘違いだったみたいだな。君のお姉さんと会うことはできるだろうか」
「ごめんなさい。それは難しいかと……」
美波は大学進学と同時に、母の反対を押し切って家を出ている。原因は家庭の問題と姉の茉莉、自分との間に生まれた確執からだ。以降、時々しか連絡を取っていない。
「高橋さん、どうしてそのナツさんを捜しているの? 昔お世話になったお礼を言いたいとか?」
「いや、違う」
翔は身を翻して前を見つめた。
「まだ好きだって伝えたい」
「……っ」
「十年も前のガキだった頃のことで、顔を見たこともないのに、バカみたいだって思うだろ? でも、どうしても忘れられないんだ。あんな風に純粋に誰かを好きになれることって……もう二度とない気がする」