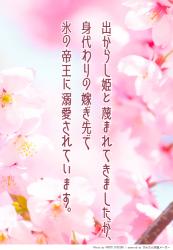その後は美波持参のアイスロイヤルミルクティーを飲みながら、二人で他愛ないお喋りを楽しんだ。
「へえ、お前の制服って学校セーラー服なんだ」
「翔君が通ってた高校はどうだった?」
「男も女もブレザーだったな」
(翔君と知り合ってもう二ヶ月。まさか、こんなに仲良くなれるなんて思わなかった)
美波にとってこうした翔との一時が、かけがえのないものになっていた。
(ずっとこうしていられたらいいのに……)
そう感じるのはいずれ終わりが来るとわかっているからだ。だが、その時はまだ先だと思っていた。いや、そう思いたかった。
だから、不意に話が途切れて同時に翔も黙り込み、やがて口を開いて話を切り出した時には、一瞬にして全身が凍り付いたような気がした、
「俺、角膜の移植手術受けようと思うんだ」
「えっ……」
「なかなか決心できなかったんだけど、やっと踏ん切りが付いた。最初にお前に言いたかったんだ」
翔は今まで口にしたことのなかった、まったく見えない世界について語った。
「目が見えなくなるって視界が真っ暗になるってわけじゃないんだ」
正確には真っ暗になる患者もいるが、グレーや真っ白、ピンク一色など人によって違うらしい。
「俺の場合は……ブルーとグレーの中間。青灰色? ブルーグレー? ずっと海の中にいるみたいだった」
それも、深く冷たい冬の海だ。
「もうサッカー選手になれないって聞いて、自棄になっていたからかもな。俺には絶望の色に見えた」
たとえ目が治ってもサッカー選手になれないなら、結局心はその海の中に沈んだままだ。なら、手術を受けたところで同じだと感じた。
「生きている限り、この冷たい海の底にいるしかないのかって苦しかった。だけど――」
眼帯越しの見えない目を美波に向ける。
「だけどあの日……お前に初めて会ったあの日、波の音が聞こえた気がしたんだ」
寄せては引く心落ち着かせる波の音。あまりに優しく綺麗で泣きたくなるような――。
「……お前の声だった」
「へえ、お前の制服って学校セーラー服なんだ」
「翔君が通ってた高校はどうだった?」
「男も女もブレザーだったな」
(翔君と知り合ってもう二ヶ月。まさか、こんなに仲良くなれるなんて思わなかった)
美波にとってこうした翔との一時が、かけがえのないものになっていた。
(ずっとこうしていられたらいいのに……)
そう感じるのはいずれ終わりが来るとわかっているからだ。だが、その時はまだ先だと思っていた。いや、そう思いたかった。
だから、不意に話が途切れて同時に翔も黙り込み、やがて口を開いて話を切り出した時には、一瞬にして全身が凍り付いたような気がした、
「俺、角膜の移植手術受けようと思うんだ」
「えっ……」
「なかなか決心できなかったんだけど、やっと踏ん切りが付いた。最初にお前に言いたかったんだ」
翔は今まで口にしたことのなかった、まったく見えない世界について語った。
「目が見えなくなるって視界が真っ暗になるってわけじゃないんだ」
正確には真っ暗になる患者もいるが、グレーや真っ白、ピンク一色など人によって違うらしい。
「俺の場合は……ブルーとグレーの中間。青灰色? ブルーグレー? ずっと海の中にいるみたいだった」
それも、深く冷たい冬の海だ。
「もうサッカー選手になれないって聞いて、自棄になっていたからかもな。俺には絶望の色に見えた」
たとえ目が治ってもサッカー選手になれないなら、結局心はその海の中に沈んだままだ。なら、手術を受けたところで同じだと感じた。
「生きている限り、この冷たい海の底にいるしかないのかって苦しかった。だけど――」
眼帯越しの見えない目を美波に向ける。
「だけどあの日……お前に初めて会ったあの日、波の音が聞こえた気がしたんだ」
寄せては引く心落ち着かせる波の音。あまりに優しく綺麗で泣きたくなるような――。
「……お前の声だった」