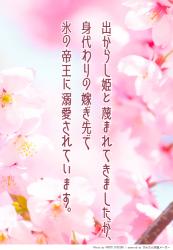翔は時々こうした笑い方をする。きっと癖なのだろう。美波は最近こうした翔の一つ一つの仕草を知り、心のアルバムに仕舞うのがすっかり楽しみになっていた。
「ある方法って?」
「”学校帰りの彼女と喋りたいから、数時間だけでいいから二人きりにしてくれ“って言ったら向こうだってそんなにうるさく言わないさ」
「えっ……」
心臓がドキリと跳ねた。
「だから、方便だって、方便。……嫌だったか?」
「う、ううん」
方便でも翔が彼女だと言ってくれたことが嬉しかった。
「お前が普通に見舞いに来れればいんだけど、難しいんだろ?」
「ごめんね。うち、親が厳しめで、男の人に会いに行くなんて絶対に許可してくれないから。万が一病院から連絡が来て、バレたら二度と来れなくなると思う」
美波はこれも方便だと心の中で言い訳をする。
それに、全くの嘘ではない。両親が厳しいのは本当だった。父は「家に恥を掻かせるんじゃない」、母は「あんまり迷惑掛けないでね」が、自分に対してだけの口癖になっているくらいだ。
翔は「大変だな」と頷いた。
「俺のおふくろは犯罪以外はなんでも好きにやれって感じだよ。と言っても、俺が男だからってのもあるだろうな。女の子だからお前の親も心配なんだろ。まだ十七歳だもんな」
「そう……だね」
美波は本当は高校一年生で十五歳だが、二年生の十七歳だと嘘をついている。正体を誤魔化すためと、まだ十五歳だと知られると、さすがに引かれそうだと思ったからだ。
曖昧な笑みで誤魔化してケーキの箱の一つを開ける。
「それよりほら、ケーキ食べようよ。種類は……」
「ちょっと待て。匂いで当てる。チョコレートケーキと、チーズケーキと、シュークリームだろ」
「すごい! 正解! どれがいい?」
「じゃあ、チョコレ――」
翔は「……いや」と口を噤んだ。
「お前は何が好きなんだ」
美波もチョコレートケーキが一番好きだ。だが、翔が好きなら翔に食べてほしい。
「私はチーズケーキ」
とっさにそう答えた。しかし、実は美波はチーズ自体が苦手だ。
「ある方法って?」
「”学校帰りの彼女と喋りたいから、数時間だけでいいから二人きりにしてくれ“って言ったら向こうだってそんなにうるさく言わないさ」
「えっ……」
心臓がドキリと跳ねた。
「だから、方便だって、方便。……嫌だったか?」
「う、ううん」
方便でも翔が彼女だと言ってくれたことが嬉しかった。
「お前が普通に見舞いに来れればいんだけど、難しいんだろ?」
「ごめんね。うち、親が厳しめで、男の人に会いに行くなんて絶対に許可してくれないから。万が一病院から連絡が来て、バレたら二度と来れなくなると思う」
美波はこれも方便だと心の中で言い訳をする。
それに、全くの嘘ではない。両親が厳しいのは本当だった。父は「家に恥を掻かせるんじゃない」、母は「あんまり迷惑掛けないでね」が、自分に対してだけの口癖になっているくらいだ。
翔は「大変だな」と頷いた。
「俺のおふくろは犯罪以外はなんでも好きにやれって感じだよ。と言っても、俺が男だからってのもあるだろうな。女の子だからお前の親も心配なんだろ。まだ十七歳だもんな」
「そう……だね」
美波は本当は高校一年生で十五歳だが、二年生の十七歳だと嘘をついている。正体を誤魔化すためと、まだ十五歳だと知られると、さすがに引かれそうだと思ったからだ。
曖昧な笑みで誤魔化してケーキの箱の一つを開ける。
「それよりほら、ケーキ食べようよ。種類は……」
「ちょっと待て。匂いで当てる。チョコレートケーキと、チーズケーキと、シュークリームだろ」
「すごい! 正解! どれがいい?」
「じゃあ、チョコレ――」
翔は「……いや」と口を噤んだ。
「お前は何が好きなんだ」
美波もチョコレートケーキが一番好きだ。だが、翔が好きなら翔に食べてほしい。
「私はチーズケーキ」
とっさにそう答えた。しかし、実は美波はチーズ自体が苦手だ。