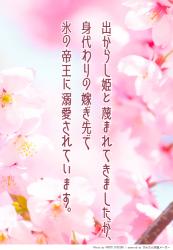病状が落ち着くまで一ヶ月も待ってくれたのだから、気遣いのある対応だとは理解している。だが、長年の夢をついに失った事実を、受け入れることができなかったと。
「事故に遭った日を毎日思い出すんだ。あの日バスじゃなく電車にしていれば、タクシーだってあったのにって何度も後悔して……自分に腹が立って悔しくて」
翔の声が激情に震える。
「いっそサッカーなんて嫌いになれたらいいのに……。夢の中ではいつもピッチを駆け回っていて……」
朝起きて、現実を思い知って死んでしまいたくなる。なぜ俺は生きているんだと翔は吐き出した。
美波は何も言えなかった。何を言っても安っぽい慰めにしかならない気がしたからだ。
「……二度と治らないの?」
「いいや。足の骨折はそのうち治るし、角膜移植をすれば目も見えるようになるそうだ。だけど激しい運動はできなくなるから、やっぱりプロとしてやって行くのは無理だと言われた」
そう告知されると手術を受ける気にもなれず、医師に説得されても頑として首を横に振っているのだと。
「サッカーのことしか考えてこなかったのに、そのサッカーを奪われるなんて……。どうして俺だったんだ?」
何十億人も人間がいるのに、なぜよりによって自分がと。
翔の苦悩と絶望が痛いほど伝わってきて、美波は思わず膝の上の両の拳を、爪が食い込むほど固く握り締めた。
(……私だったらよかったのに)
特別なところなどなにもない、味噌っかすの自分だったらよかったのに。両親は姉の茉莉さえいればよいと思っているから。
翔は視線を落として大きく息を吐いた。
「こんなこと通りすがりのあんたに聞かせて悪いな」
女手一つで自分を育ててくれた母親は、命だけでも助かってよかったと口にするばかりなので、こんな愚痴を言えるはずもない。
もちろん元チームメイトたちにも無理だ。どうしても複雑な感情を抱いてしまう。
「彼女とは音信不通になったしな。……サッカー選手じゃない俺には用はないってことか」
美波はさすがにこの一言には絶句した。
辛い時にこそ寄り添おうとするのが恋人や伴侶ではないのか。
「事故に遭った日を毎日思い出すんだ。あの日バスじゃなく電車にしていれば、タクシーだってあったのにって何度も後悔して……自分に腹が立って悔しくて」
翔の声が激情に震える。
「いっそサッカーなんて嫌いになれたらいいのに……。夢の中ではいつもピッチを駆け回っていて……」
朝起きて、現実を思い知って死んでしまいたくなる。なぜ俺は生きているんだと翔は吐き出した。
美波は何も言えなかった。何を言っても安っぽい慰めにしかならない気がしたからだ。
「……二度と治らないの?」
「いいや。足の骨折はそのうち治るし、角膜移植をすれば目も見えるようになるそうだ。だけど激しい運動はできなくなるから、やっぱりプロとしてやって行くのは無理だと言われた」
そう告知されると手術を受ける気にもなれず、医師に説得されても頑として首を横に振っているのだと。
「サッカーのことしか考えてこなかったのに、そのサッカーを奪われるなんて……。どうして俺だったんだ?」
何十億人も人間がいるのに、なぜよりによって自分がと。
翔の苦悩と絶望が痛いほど伝わってきて、美波は思わず膝の上の両の拳を、爪が食い込むほど固く握り締めた。
(……私だったらよかったのに)
特別なところなどなにもない、味噌っかすの自分だったらよかったのに。両親は姉の茉莉さえいればよいと思っているから。
翔は視線を落として大きく息を吐いた。
「こんなこと通りすがりのあんたに聞かせて悪いな」
女手一つで自分を育ててくれた母親は、命だけでも助かってよかったと口にするばかりなので、こんな愚痴を言えるはずもない。
もちろん元チームメイトたちにも無理だ。どうしても複雑な感情を抱いてしまう。
「彼女とは音信不通になったしな。……サッカー選手じゃない俺には用はないってことか」
美波はさすがにこの一言には絶句した。
辛い時にこそ寄り添おうとするのが恋人や伴侶ではないのか。