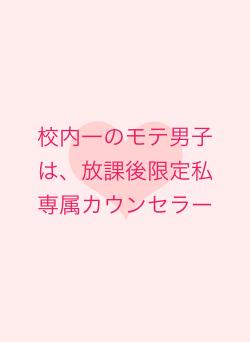「万桜が優しいからだよ」
壮矢ははっきりとそう言い切った。優しいとは無縁で、最低という言葉が良く似合う私にそう言い切ったのだ。
「万桜は優しいんだよ、絶対に」
「そんなわけないでしょ」
「いつか分かるよ」
壮矢はそれだけ言って立ち上がった。
「じゃあ、そろそろ帰ろうかな」
「あ、待って。英語の教科書……!」
私は慌ててスクールバッグから壮矢の名前が書かれたスクールバッグを取り出した。
壮矢は教科書を受け取り、楽しそうに笑っている。
「そうだった。今日、僕は英語の教科書を返して貰うために来たんだったね」
私が壮矢に会いやすくするために自分が言った理由を一瞬忘れていたようだった。
壮矢ははっきりとそう言い切った。優しいとは無縁で、最低という言葉が良く似合う私にそう言い切ったのだ。
「万桜は優しいんだよ、絶対に」
「そんなわけないでしょ」
「いつか分かるよ」
壮矢はそれだけ言って立ち上がった。
「じゃあ、そろそろ帰ろうかな」
「あ、待って。英語の教科書……!」
私は慌ててスクールバッグから壮矢の名前が書かれたスクールバッグを取り出した。
壮矢は教科書を受け取り、楽しそうに笑っている。
「そうだった。今日、僕は英語の教科書を返して貰うために来たんだったね」
私が壮矢に会いやすくするために自分が言った理由を一瞬忘れていたようだった。