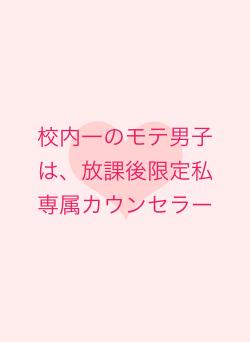壮矢が見つめている海は、もう真っ赤な夕日に変わっている。壮矢の横顔すらも赤く照らされている。
「壮矢」
私は無意識に名前を呼んでしまっていた。
「ん?」
私の方に顔を向けた壮矢になんと声をかけるつもりだったのだろう。
自分の本心は明かさないくせに、壮矢にだけ寄り添うような言葉をかける方が残酷なんじゃないの?
それでも、一つだけ言いたいことがあった。
「私、壮矢からもう逃げない……と思う。ううん、逃げない。隠しごととか嘘とかあるかもしれない。でも、もう勝手に離れようとしない。それくらい壮矢の『嘘をついても良いから、離れないで』は私にとって救いだったの」
美しい理由じゃない。どこまでも私は最低なままだけれど。
「多分ずっと本心を見せずに相手と繋がりを持つことにどこか罪悪感があった。それでも、私は変われない。ううん、変わりたくない。このままの繋がり方で良いと思ってしまっている。それでも、そんな自分が世間一般では最低だってことも分かっているから……壮矢から逃げていた。でも、壮矢は私が逃げる方が嫌だってよく分かったから」
「うん。僕は万桜が逃げたり、離れたりする方がずっと嫌」
「でも、本当に良いの? きっと私は壮矢に一生本心も考えていることも明かさないかもしれない。日常会話しかしなくて、上部だけの繋がりのままかもしれない」
「良いよ。万桜と話せるなら、会話の中身なんてどんな内容でも良い」
「どうしてそんなに……」
「どうしてそんなに出会って間もない私のことを受け入れてくれるの?」と言いたかったが、最後まで言葉を紡ぐことは出来なかった。しかし、壮矢は私に優しく微笑んだ。
私の言いたかったことはバレバレだったらしい。
「壮矢」
私は無意識に名前を呼んでしまっていた。
「ん?」
私の方に顔を向けた壮矢になんと声をかけるつもりだったのだろう。
自分の本心は明かさないくせに、壮矢にだけ寄り添うような言葉をかける方が残酷なんじゃないの?
それでも、一つだけ言いたいことがあった。
「私、壮矢からもう逃げない……と思う。ううん、逃げない。隠しごととか嘘とかあるかもしれない。でも、もう勝手に離れようとしない。それくらい壮矢の『嘘をついても良いから、離れないで』は私にとって救いだったの」
美しい理由じゃない。どこまでも私は最低なままだけれど。
「多分ずっと本心を見せずに相手と繋がりを持つことにどこか罪悪感があった。それでも、私は変われない。ううん、変わりたくない。このままの繋がり方で良いと思ってしまっている。それでも、そんな自分が世間一般では最低だってことも分かっているから……壮矢から逃げていた。でも、壮矢は私が逃げる方が嫌だってよく分かったから」
「うん。僕は万桜が逃げたり、離れたりする方がずっと嫌」
「でも、本当に良いの? きっと私は壮矢に一生本心も考えていることも明かさないかもしれない。日常会話しかしなくて、上部だけの繋がりのままかもしれない」
「良いよ。万桜と話せるなら、会話の中身なんてどんな内容でも良い」
「どうしてそんなに……」
「どうしてそんなに出会って間もない私のことを受け入れてくれるの?」と言いたかったが、最後まで言葉を紡ぐことは出来なかった。しかし、壮矢は私に優しく微笑んだ。
私の言いたかったことはバレバレだったらしい。