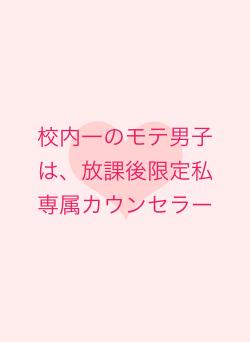壮矢に初めて会った時の光景が目に浮かぶ。
水平線に浮かぶ夕日に向かって、壮矢はなにかを願っていた。涙を流しながら。
壮矢にだって何か事情があるのだろう。
それに私と壮矢の関係は不思議で、友達ということも出来ないし。
そんな思考を遮るように授業開始を告げるチャイムが鳴る。
私は壮矢の英語の教科書をスクールバッグに戻して、教壇に視線を向けた。
水平線に浮かぶ夕日に向かって、壮矢はなにかを願っていた。涙を流しながら。
壮矢にだって何か事情があるのだろう。
それに私と壮矢の関係は不思議で、友達ということも出来ないし。
そんな思考を遮るように授業開始を告げるチャイムが鳴る。
私は壮矢の英語の教科書をスクールバッグに戻して、教壇に視線を向けた。