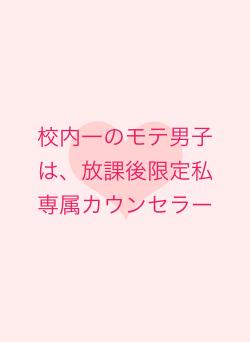拓人くんが私と青年の会話を理解したのか、私に駆け寄ってくる。
「お姉ちゃん、やっぱり冷たいの?」
その言葉に私は私は慌てて、「寒くないよ!」と腕を上げて元気に見えるようにポーズする。
そして、すぐに青年と視線を合わせた。
これ以上は拓人くんが気を使ってしまう。
そう伝えた私の視線はどうやら伝わったらしい。
「拓人。お姉ちゃんは大丈夫だって。でも家に帰ったら、お兄ちゃんにマフラーを渡してくれる? お兄ちゃんがお姉ちゃんに返しに行くから」
「うん!」
どうやら青年に私にマフラーを返さないという選択肢はなかったらしい。
でも、本当にもう要らない。
というより、もう一度この青年に会いたくない。
わざわざ会うのも面倒くさいし、先ほどの夕日に照らされた光景が頭から離れていない自分自身が気持ち悪く感じる。
なんて言おうか。
ここで断ったら変な人だと思われるだろうか。
変な人という単語が頭の中に浮かんで、「どうせもう二度と会わない人だしどうでも良いや」が勝つ。
「お姉ちゃん、やっぱり冷たいの?」
その言葉に私は私は慌てて、「寒くないよ!」と腕を上げて元気に見えるようにポーズする。
そして、すぐに青年と視線を合わせた。
これ以上は拓人くんが気を使ってしまう。
そう伝えた私の視線はどうやら伝わったらしい。
「拓人。お姉ちゃんは大丈夫だって。でも家に帰ったら、お兄ちゃんにマフラーを渡してくれる? お兄ちゃんがお姉ちゃんに返しに行くから」
「うん!」
どうやら青年に私にマフラーを返さないという選択肢はなかったらしい。
でも、本当にもう要らない。
というより、もう一度この青年に会いたくない。
わざわざ会うのも面倒くさいし、先ほどの夕日に照らされた光景が頭から離れていない自分自身が気持ち悪く感じる。
なんて言おうか。
ここで断ったら変な人だと思われるだろうか。
変な人という単語が頭の中に浮かんで、「どうせもう二度と会わない人だしどうでも良いや」が勝つ。