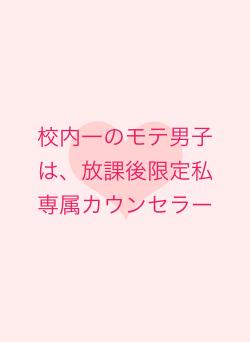何も答えてくれない。
声を殺して泣き続ける珀人に私はどうすれば良いか分からない。
「ねぇ、珀人。何が苦しいのか教えて、絶対に力になるから。私は絶対に珀人から離れないから」
珀人の力になりたい、それは紛れもない本心だった。
だから珀人も頼ってくれると思っていた。
思い込んでいた。
「伶菜、じゃあ一つだけ頼みがある」
「なに?」
「絶対に俺の力になろうなんて思うな」
突然の突き放された言葉に、私は泣きそうになる。
珀人が泣いているから、余計に泣いてしまいそうで。
「なんで珀人の力になりたいって思ったら駄目なの。私じゃ頼りないってこと?」
否定して欲しかった。それだけを願っていたのに。
「そうだよ」
短くそう答えた珀人に私は絶望して、珀人を置いて教室を飛び出した。
高校から離れたくて、靴を履き替えて校舎から逃げるように出ていく。
涙が止まらなくて、悔しくて堪らなかった。
珀人の力になりたかっただけなのに、珀人はそれを拒否した。
私じゃ力になれないとはっきりそう言った。
涙を拭う気すら起きなくて、ボロボロと地面に涙を落としていく。
その日はどうやって家に帰ったのか自分でも分からなかった。
気づいたら自宅に着いていた自分を見て、「馬鹿みたい」と自分を嘲笑った。
声を殺して泣き続ける珀人に私はどうすれば良いか分からない。
「ねぇ、珀人。何が苦しいのか教えて、絶対に力になるから。私は絶対に珀人から離れないから」
珀人の力になりたい、それは紛れもない本心だった。
だから珀人も頼ってくれると思っていた。
思い込んでいた。
「伶菜、じゃあ一つだけ頼みがある」
「なに?」
「絶対に俺の力になろうなんて思うな」
突然の突き放された言葉に、私は泣きそうになる。
珀人が泣いているから、余計に泣いてしまいそうで。
「なんで珀人の力になりたいって思ったら駄目なの。私じゃ頼りないってこと?」
否定して欲しかった。それだけを願っていたのに。
「そうだよ」
短くそう答えた珀人に私は絶望して、珀人を置いて教室を飛び出した。
高校から離れたくて、靴を履き替えて校舎から逃げるように出ていく。
涙が止まらなくて、悔しくて堪らなかった。
珀人の力になりたかっただけなのに、珀人はそれを拒否した。
私じゃ力になれないとはっきりそう言った。
涙を拭う気すら起きなくて、ボロボロと地面に涙を落としていく。
その日はどうやって家に帰ったのか自分でも分からなかった。
気づいたら自宅に着いていた自分を見て、「馬鹿みたい」と自分を嘲笑った。