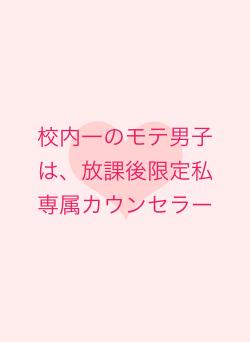「伶菜がどれだけ嫌がっても、俺は付きまとうからな!」
「ストーカーじゃん。ていうか怨霊じゃん!」
教室に響き渡る好きな人と私の会話。
他の人からは私の独り言に聞こえているのだろうけれど。
「でも丹野くんにすぐに近づいたり、告白したりするのはやめる。私が死ぬとして、丹野くんを巻き込む可能性があるなんて絶対に嫌だから」
そう話した私の顔を珀人が慈しむような目で見ている。
悲しさを秘めているような、どこか暗さを秘めている瞳だった。
教室の暑さすら忘れそうになる。それでも、風の音だけは耳に入ってくる感じが気持ち悪かった。
「珀人?」
「いやー、伶菜は眩しいなぁって。アホなだけかもだけれど」
「ちょっと!?」
珀人の雰囲気はもう普通に戻っていた。
夏の風が通り過ぎていく。
冬の冷たさとは全く違う暖かさを含んだ風は、私の頬に擦れていく。
そんな風すら幽霊の珀人はもう感じられないと思うと、どこか心がキュッと締ったのが分かった。
「ストーカーじゃん。ていうか怨霊じゃん!」
教室に響き渡る好きな人と私の会話。
他の人からは私の独り言に聞こえているのだろうけれど。
「でも丹野くんにすぐに近づいたり、告白したりするのはやめる。私が死ぬとして、丹野くんを巻き込む可能性があるなんて絶対に嫌だから」
そう話した私の顔を珀人が慈しむような目で見ている。
悲しさを秘めているような、どこか暗さを秘めている瞳だった。
教室の暑さすら忘れそうになる。それでも、風の音だけは耳に入ってくる感じが気持ち悪かった。
「珀人?」
「いやー、伶菜は眩しいなぁって。アホなだけかもだけれど」
「ちょっと!?」
珀人の雰囲気はもう普通に戻っていた。
夏の風が通り過ぎていく。
冬の冷たさとは全く違う暖かさを含んだ風は、私の頬に擦れていく。
そんな風すら幽霊の珀人はもう感じられないと思うと、どこか心がキュッと締ったのが分かった。