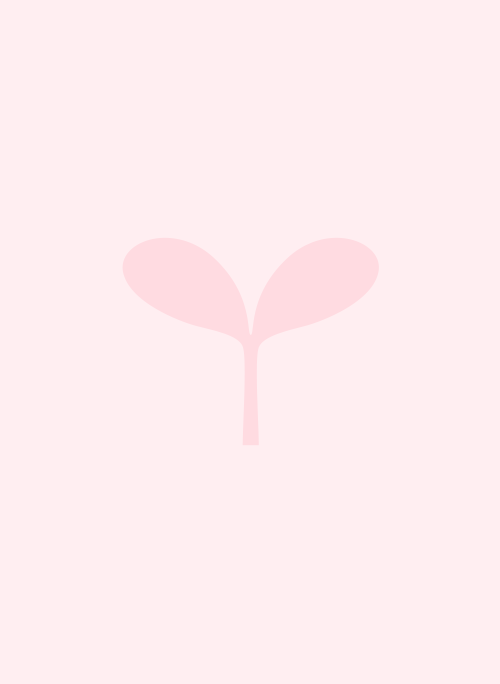天気……ぎらぎら照りつける暑い陽ざしにさらされて、人も動物も植物も生気を失ってぐったりしていた。でも神様はとても慈悲深いおかたなので、耐えられないほどの暑さに地球上の生物をさらすのはかわいそうだと思って、時折、空からシャワーのような恵みの雨を降らしてくださる。今日も三度、晴れわたった空から、急ににわか雨が降ってきて、そのたびに気温が少し下がって、ほっと一息つくことができた。
団長の奥さんが戻ってこなかったので、団長の心配はいかばかりだろうと思って、ぼくは昨夜は一睡もできなかった。今朝早く、夜が明けるか明けないかのうちに、ぼくはうちを出て、湖畔にそって歩きながら、寂寞とした気持ちで団長のことを思っていた。翠湖の中ではスイレンの白い花があちこちに咲いていた。湖畔から少し離れたところにあるスイレンの上に団長がいるのが見えた。じっとして物思いにふけりながら、空を見上げていた。ぼくが声をかけると気がついて、湖畔に泳いできた。団長の目がとろんとしているのを見て
「昨夜は眠れなかったのではないですか」
と、ぼくは心配そうに聞いた。団長はうなずいた。
「目を閉じようとしても、すぐにオンプーのことが脳裏に浮かんできて眠れなかった」
団長がそう言った。
「奥さんのことをとても愛しておられたのですね」
ぼくは団長の気持ちを察して、心がとても沈んでいた。
「おれとオンプーはオタマジャクシのころから、大の仲良しだった。いつもいっしょにいて、子どものころから、お互いに深く愛し合っていた。オンプーがいない生活なんて考えられない。オンプーはおれにとって、かけがえのない存在だった。生きがいだったのだ」
団長が、そう言った。それを聞いて、ぼくは心の中が切なくてきゅんとなった。
「まだあきらめてはいけません。これからみんなで再びグルメ街に行って、オンプーを探して、連れて帰りましょう」
ぼくは団長に、そう言った。すると団長は意外にも首を横に振った。
「いや、それはできない。おれたちの仕事は町全体の害虫を駆除することだから、仕事を棚上げにして、団員全部をグルメ街に探しに行かせることはできない。リーダーである以上、私欲を優先させるわけにはいかない」
団長が、きっぱりと、そう言った。それを聞いて、ぼくは団長のリーダーシップに感動した。
「ではぼくは今日、高音部のパートだけを連れてグルメ街に行きます。昨夜行った時、グルメ街はハエやカがとても多かったです。グルメ街は中音部のパートが受け持っていますが、オンプーは高音部のパートだから、今日は中音部と高音部のパートを入れ替えて、高音部のパートをグルメ街に行かせます」
ぼくは団長に、そう言った。すると団長が
「分かった。そうしよう」
と言って、ぼくの提案に同意してくれた。
それからまもなく、団長が団員たちに呼びかけて、パートごとに分かれて眼鏡橋の上に集合させた。
「今日もみんな元気で、害虫の駆除をしてから、夕方になったら全員無事でここに帰ってくること。駆除の途中で捕らえられているカエルを発見したら、すぐにおれに連絡すること。高音部と中音部のパートは今日は担当地域が異なるので注意すること」
団長は、そう言って、団員たちに訓示を垂れていた。その時、老いらくさんが息せききってやってきた。ぼくは老いらくさんに、中音部のパートをA地域へ連れていくように言った。老いらくさんは快く引き受けてくれた。ぼくは高音部のパートをB地域へ連れていくことにした。団長も、ぼくといっしょについてきた。
B地域の中心部にあるグルメ街に、ぼくや団長や高音部の団員たちが着いた時は、朝の十時ごろだったので、どのレストランもまだ開店前で、人通りは少なくて、ひっそりしていた。団長の指図を受けて、カエルたちは、数匹ずつに分かれて、それぞれのレストランの裏口から入っていって、ハエやカの駆除を始めた。カエルたちに気がついた人もいたが、捕まえたり、追い出したりする人はいなかった。テレビや新聞で、福の神のように報道されていたから、カエルたちを虐待するのはよくないと思っていたからかもしれない。ぼくはそう思った。駆除に行ったカエルたちは、駆除の傍ら目を厨房の隅々にまで凝らして、捕らえられて、もがいているカエルがいないかどうか調べていた。ぼくと団長も手分けして、グルメ街全体を回りながら、どこかにオンプーがいないか、血眼になって探していた。するとその時、突然、思いがけないことに、向こうから馬小跳と、彼の親友である唐飛と張達と毛超が、ひょっこりやってくるのが見えた。まさか、彼らがここへやってくるとは、ぼくは思ってもいなかった。
(何をしに来たのだろうか。もしかしたら、カエルたちが昨夜、ここに来たというニュースを見て、わざわざやってきたのだろうか)
ぼくは、そう思った。ぼくは急いで馬小跳たちのほうへかけていった。すると馬小跳たちも、ぼくを見て、びっくりしていた。
「あれっ、笑い猫。どうして、ここにいるのだ?」
馬小跳はそう言って、けげんそうな顔をしながらぼくを抱きかかえた。
「おれは昨日、カエルを捕まえた男に飛び掛かっていった猫をテレビで見た。あれはお前だったのか」
馬小跳がそう言った。ぼくは、にっこりと笑みを浮かべた。
「やはり、そうだったのか」
馬小跳がうなずいていた。
「あの映像を見て、みんなお前のことを『スーパーキャット』と呼んでいるぞ」
毛超がそう言った。
唐飛は、食いしん坊なので、ポケットの中に、いつも何か食べ物を持っているが、ぼくを見て、ポケットの中から、ビスケットを取り出して
「これはおれからのほうびだ」
と言って、二枚くれた。馬小跳は唐飛のことをけちと呼んでいるが、唐飛はぼくに対しては、けちどころか気前がよくて、食べ物をよくくれる。
張達は、ぼくに対して一定の距離を置いている。ぼくの立派な行為を見て、表面的には敬っているような態度をとるが、実際には、ぼくを怖がっている。子どものころ、猫にひっかかれたことがあって、それがトラウマとなっているように思える。でも張達も根は優しいので、いつも小遣いから煮干しを買ってきて、うちまでもってきてくれる。張達も心の中では、ぼくのことをとても愛してくれていることを、ぼくは知っている。
彼らの話を聞いて、やはりぼくが思っていた通りに、カエルたちがグルメ街にやってきたというニュースを見て、ここにやってきたことが明らかになった。馬小跳も、彼の友だちもみんな優しい男の子たちなので、レストランの厨房に閉じ込められているカエルたちを解放してあげようと思って、ここへ来たのかもしれない。ぼくはそう思った。たくさんのカエルたちが、レストランの中へ、せわしげに出たり入ったりして、ハエやカに飛びついているのを見て、馬小跳たちはびっくりしていた。
「テレビの中で見たカエルたちはみんな歌を歌っていたけど、今はどうして歌っていないのかなあ」
毛超がけげんそうな顔をしていた。
「カエルたちは昼間は仕事をして、夕方になってから歌うのだ」
馬小跳がそう答えていた。
「仕事をするのには危険がともなうし、ここは危険が多すぎる」
唐飛がそう言った。
「だから、おれたちが守ってあげなければならないのだ」
馬小跳がそう答えていた。
張達は吃音障害があるので、言葉がスムーズに出てこないで、どもることがよくある。うんうんと、うなずきながら、
「絶対に……守って……危険を……」
と、ぶつぶつ言っていた。
いずれにせよ、馬小跳と、彼の親友たちは、ぼくと同じように、カエルたちを守ってあげなければという気概にあふれているのが、言葉の端々から、伝わってきたので、ぼくはとても心強く思った。
ぼくと馬小跳たちがカエルたちをしっかり守ってあげたので、店がオープンするまでの間、何も問題は起こらなかった。そのために、カエルたちはハエやカの駆除に専念することができた。カエルたちが頑張ったので、店がオープンする前に、グルメ街にいた害虫を、ほとんど一掃することができた。カエルの団長はそれを確認してから、団員たちを別の地域へ駆除に向かわせることにした。
団長の奥さんであるオンプーの姿は、見つけることができなかったので、団長はうつろな顔をしていた。
「心配しないでください。ぼくは、引き続き、グルメ街に留まって、オンプーの捜索を続けることにします」
ぼくは団長にそう答えた。
「団長はどうされますか」
ぼくは団長に聞いた。
「おれも、ここに残りたいのはやまやまだが、仕事が大事なので、団員たちといっしょに別の地域へ駆除に行くことにする」
団長がそう言った。それを聞いて、ぼくは感動した。愛する奥さんのことよりも、仕事を優先させる団長の考え方に、ぼくは敬服してやまなかった。団長はそれからまもなく高音部の団員たちを引き連れて、別の地域へ害虫の駆除に出かけて行った。グルメ街に残ったのはぼくだけではなかった。馬小跳たちも、グルメ街に残っていた。馬小跳たちは、ショーウィンドーに陳列してあるサンプルをじっと見ていたので
(お昼なので、ご飯を食べて帰ることにしたのかな)
と、ぼくは思った。馬小跳たちはいくつかの店を回ってから、中華料理のレストランに入っていった。ぼくもついていった。馬小跳たちは空いている四人掛けの席に座った。ぼくはテーブルの下に座った。唐飛が
「すみません、メニューを見せてください」
と言っていた。その声を聞いて若いウェートレスがすぐにメニューを持ってきてくれた。
馬小跳たちは、頭を突き合わせながら、細かにメニューを見ていた。
「この店にはカエル料理はないのかな」
唐飛がそう言った。
「メニューには載っていないけども、もしかしたら、あるかもしれないよ」
馬小跳がそう答えていた。その声を耳にして、ウェートレスが
「以前はありましたが、今はありません」
と、答えていた。
「どうしてですか?」
唐飛が聞き返していた。
「カエルたちがマスコミで取り上げられてから、カエル料理を食べることに抵抗を感じる人が多くなったからです」
ウェートレスが、そう答えていた。
「そうですか。分かりました。では、ほかの店に行ってみます」
唐飛がそう答えていた。馬小跳たちはそのあとすぐ席を立って、店を出ていった。ぼくもあとからついていった。馬小跳たちは、ほかの店にもいくつか行ってみたが、どの店も同じだった。カエル料理を注文して食べる人がいなくなったのは、カエルたちにとって何よりの朗報なので、このことを早く団長に伝えなければと、ぼくは思った。
グルメ街の中で一番有名なレストランは、高級料理が名物だし、値段も高かったので、馬小跳たちは入るか入らないか店の前でしばらく迷っていた。でも思い切って入ることにして、店のドアを開けた。ぼくも中に入っていった。馬小跳たちの姿を見て、店長がけげんそうな顔をしながら
「子どもだけで来たのか?」
と聞いた。
「そうです。子どもだけではいけませんか?」
馬小跳が言葉を返した。
「いけないということではないが、ここは大人のお客さんがほとんどだ。高級料理が多いので、値段が高い。子どもはもう少し安いところで食べたほうがいい」
店長がそう答えていた。
「分かりました。ではここでは食べないことにします」
馬小跳がそう答えていた。
「ここで食べない代わりに、一つ、お尋ねしたいことがあります」
馬小跳がそう言った。
「何か?」
店長が聞き返していた。
「カエル料理はありますか?」
馬小跳がそう聞いていた。
「ない」
店長がそう答えた。
「そうですか。分かりました」
馬小跳がそう答えた。馬小跳はそのあとみんなで、その店を出ようとした。ぼくもすぐあとに続いた。その時、店の外に怪しい人影がちらっと見えた。ぼくは不審に思ったので、急いで店の外に出て、その人影を追っていった。でも人込みにまぎれて、その姿を見失ってしまった。馬小跳がぼくの異変に気がついて息せききって走ってきた。
「笑い猫、どうしたのだ?」
馬小跳がそう言った。ぼくは人の話を聞いて分かるが、人の言葉は話すことができないので、とてももどかしく思った。
団長の奥さんが戻ってこなかったので、団長の心配はいかばかりだろうと思って、ぼくは昨夜は一睡もできなかった。今朝早く、夜が明けるか明けないかのうちに、ぼくはうちを出て、湖畔にそって歩きながら、寂寞とした気持ちで団長のことを思っていた。翠湖の中ではスイレンの白い花があちこちに咲いていた。湖畔から少し離れたところにあるスイレンの上に団長がいるのが見えた。じっとして物思いにふけりながら、空を見上げていた。ぼくが声をかけると気がついて、湖畔に泳いできた。団長の目がとろんとしているのを見て
「昨夜は眠れなかったのではないですか」
と、ぼくは心配そうに聞いた。団長はうなずいた。
「目を閉じようとしても、すぐにオンプーのことが脳裏に浮かんできて眠れなかった」
団長がそう言った。
「奥さんのことをとても愛しておられたのですね」
ぼくは団長の気持ちを察して、心がとても沈んでいた。
「おれとオンプーはオタマジャクシのころから、大の仲良しだった。いつもいっしょにいて、子どものころから、お互いに深く愛し合っていた。オンプーがいない生活なんて考えられない。オンプーはおれにとって、かけがえのない存在だった。生きがいだったのだ」
団長が、そう言った。それを聞いて、ぼくは心の中が切なくてきゅんとなった。
「まだあきらめてはいけません。これからみんなで再びグルメ街に行って、オンプーを探して、連れて帰りましょう」
ぼくは団長に、そう言った。すると団長は意外にも首を横に振った。
「いや、それはできない。おれたちの仕事は町全体の害虫を駆除することだから、仕事を棚上げにして、団員全部をグルメ街に探しに行かせることはできない。リーダーである以上、私欲を優先させるわけにはいかない」
団長が、きっぱりと、そう言った。それを聞いて、ぼくは団長のリーダーシップに感動した。
「ではぼくは今日、高音部のパートだけを連れてグルメ街に行きます。昨夜行った時、グルメ街はハエやカがとても多かったです。グルメ街は中音部のパートが受け持っていますが、オンプーは高音部のパートだから、今日は中音部と高音部のパートを入れ替えて、高音部のパートをグルメ街に行かせます」
ぼくは団長に、そう言った。すると団長が
「分かった。そうしよう」
と言って、ぼくの提案に同意してくれた。
それからまもなく、団長が団員たちに呼びかけて、パートごとに分かれて眼鏡橋の上に集合させた。
「今日もみんな元気で、害虫の駆除をしてから、夕方になったら全員無事でここに帰ってくること。駆除の途中で捕らえられているカエルを発見したら、すぐにおれに連絡すること。高音部と中音部のパートは今日は担当地域が異なるので注意すること」
団長は、そう言って、団員たちに訓示を垂れていた。その時、老いらくさんが息せききってやってきた。ぼくは老いらくさんに、中音部のパートをA地域へ連れていくように言った。老いらくさんは快く引き受けてくれた。ぼくは高音部のパートをB地域へ連れていくことにした。団長も、ぼくといっしょについてきた。
B地域の中心部にあるグルメ街に、ぼくや団長や高音部の団員たちが着いた時は、朝の十時ごろだったので、どのレストランもまだ開店前で、人通りは少なくて、ひっそりしていた。団長の指図を受けて、カエルたちは、数匹ずつに分かれて、それぞれのレストランの裏口から入っていって、ハエやカの駆除を始めた。カエルたちに気がついた人もいたが、捕まえたり、追い出したりする人はいなかった。テレビや新聞で、福の神のように報道されていたから、カエルたちを虐待するのはよくないと思っていたからかもしれない。ぼくはそう思った。駆除に行ったカエルたちは、駆除の傍ら目を厨房の隅々にまで凝らして、捕らえられて、もがいているカエルがいないかどうか調べていた。ぼくと団長も手分けして、グルメ街全体を回りながら、どこかにオンプーがいないか、血眼になって探していた。するとその時、突然、思いがけないことに、向こうから馬小跳と、彼の親友である唐飛と張達と毛超が、ひょっこりやってくるのが見えた。まさか、彼らがここへやってくるとは、ぼくは思ってもいなかった。
(何をしに来たのだろうか。もしかしたら、カエルたちが昨夜、ここに来たというニュースを見て、わざわざやってきたのだろうか)
ぼくは、そう思った。ぼくは急いで馬小跳たちのほうへかけていった。すると馬小跳たちも、ぼくを見て、びっくりしていた。
「あれっ、笑い猫。どうして、ここにいるのだ?」
馬小跳はそう言って、けげんそうな顔をしながらぼくを抱きかかえた。
「おれは昨日、カエルを捕まえた男に飛び掛かっていった猫をテレビで見た。あれはお前だったのか」
馬小跳がそう言った。ぼくは、にっこりと笑みを浮かべた。
「やはり、そうだったのか」
馬小跳がうなずいていた。
「あの映像を見て、みんなお前のことを『スーパーキャット』と呼んでいるぞ」
毛超がそう言った。
唐飛は、食いしん坊なので、ポケットの中に、いつも何か食べ物を持っているが、ぼくを見て、ポケットの中から、ビスケットを取り出して
「これはおれからのほうびだ」
と言って、二枚くれた。馬小跳は唐飛のことをけちと呼んでいるが、唐飛はぼくに対しては、けちどころか気前がよくて、食べ物をよくくれる。
張達は、ぼくに対して一定の距離を置いている。ぼくの立派な行為を見て、表面的には敬っているような態度をとるが、実際には、ぼくを怖がっている。子どものころ、猫にひっかかれたことがあって、それがトラウマとなっているように思える。でも張達も根は優しいので、いつも小遣いから煮干しを買ってきて、うちまでもってきてくれる。張達も心の中では、ぼくのことをとても愛してくれていることを、ぼくは知っている。
彼らの話を聞いて、やはりぼくが思っていた通りに、カエルたちがグルメ街にやってきたというニュースを見て、ここにやってきたことが明らかになった。馬小跳も、彼の友だちもみんな優しい男の子たちなので、レストランの厨房に閉じ込められているカエルたちを解放してあげようと思って、ここへ来たのかもしれない。ぼくはそう思った。たくさんのカエルたちが、レストランの中へ、せわしげに出たり入ったりして、ハエやカに飛びついているのを見て、馬小跳たちはびっくりしていた。
「テレビの中で見たカエルたちはみんな歌を歌っていたけど、今はどうして歌っていないのかなあ」
毛超がけげんそうな顔をしていた。
「カエルたちは昼間は仕事をして、夕方になってから歌うのだ」
馬小跳がそう答えていた。
「仕事をするのには危険がともなうし、ここは危険が多すぎる」
唐飛がそう言った。
「だから、おれたちが守ってあげなければならないのだ」
馬小跳がそう答えていた。
張達は吃音障害があるので、言葉がスムーズに出てこないで、どもることがよくある。うんうんと、うなずきながら、
「絶対に……守って……危険を……」
と、ぶつぶつ言っていた。
いずれにせよ、馬小跳と、彼の親友たちは、ぼくと同じように、カエルたちを守ってあげなければという気概にあふれているのが、言葉の端々から、伝わってきたので、ぼくはとても心強く思った。
ぼくと馬小跳たちがカエルたちをしっかり守ってあげたので、店がオープンするまでの間、何も問題は起こらなかった。そのために、カエルたちはハエやカの駆除に専念することができた。カエルたちが頑張ったので、店がオープンする前に、グルメ街にいた害虫を、ほとんど一掃することができた。カエルの団長はそれを確認してから、団員たちを別の地域へ駆除に向かわせることにした。
団長の奥さんであるオンプーの姿は、見つけることができなかったので、団長はうつろな顔をしていた。
「心配しないでください。ぼくは、引き続き、グルメ街に留まって、オンプーの捜索を続けることにします」
ぼくは団長にそう答えた。
「団長はどうされますか」
ぼくは団長に聞いた。
「おれも、ここに残りたいのはやまやまだが、仕事が大事なので、団員たちといっしょに別の地域へ駆除に行くことにする」
団長がそう言った。それを聞いて、ぼくは感動した。愛する奥さんのことよりも、仕事を優先させる団長の考え方に、ぼくは敬服してやまなかった。団長はそれからまもなく高音部の団員たちを引き連れて、別の地域へ害虫の駆除に出かけて行った。グルメ街に残ったのはぼくだけではなかった。馬小跳たちも、グルメ街に残っていた。馬小跳たちは、ショーウィンドーに陳列してあるサンプルをじっと見ていたので
(お昼なので、ご飯を食べて帰ることにしたのかな)
と、ぼくは思った。馬小跳たちはいくつかの店を回ってから、中華料理のレストランに入っていった。ぼくもついていった。馬小跳たちは空いている四人掛けの席に座った。ぼくはテーブルの下に座った。唐飛が
「すみません、メニューを見せてください」
と言っていた。その声を聞いて若いウェートレスがすぐにメニューを持ってきてくれた。
馬小跳たちは、頭を突き合わせながら、細かにメニューを見ていた。
「この店にはカエル料理はないのかな」
唐飛がそう言った。
「メニューには載っていないけども、もしかしたら、あるかもしれないよ」
馬小跳がそう答えていた。その声を耳にして、ウェートレスが
「以前はありましたが、今はありません」
と、答えていた。
「どうしてですか?」
唐飛が聞き返していた。
「カエルたちがマスコミで取り上げられてから、カエル料理を食べることに抵抗を感じる人が多くなったからです」
ウェートレスが、そう答えていた。
「そうですか。分かりました。では、ほかの店に行ってみます」
唐飛がそう答えていた。馬小跳たちはそのあとすぐ席を立って、店を出ていった。ぼくもあとからついていった。馬小跳たちは、ほかの店にもいくつか行ってみたが、どの店も同じだった。カエル料理を注文して食べる人がいなくなったのは、カエルたちにとって何よりの朗報なので、このことを早く団長に伝えなければと、ぼくは思った。
グルメ街の中で一番有名なレストランは、高級料理が名物だし、値段も高かったので、馬小跳たちは入るか入らないか店の前でしばらく迷っていた。でも思い切って入ることにして、店のドアを開けた。ぼくも中に入っていった。馬小跳たちの姿を見て、店長がけげんそうな顔をしながら
「子どもだけで来たのか?」
と聞いた。
「そうです。子どもだけではいけませんか?」
馬小跳が言葉を返した。
「いけないということではないが、ここは大人のお客さんがほとんどだ。高級料理が多いので、値段が高い。子どもはもう少し安いところで食べたほうがいい」
店長がそう答えていた。
「分かりました。ではここでは食べないことにします」
馬小跳がそう答えていた。
「ここで食べない代わりに、一つ、お尋ねしたいことがあります」
馬小跳がそう言った。
「何か?」
店長が聞き返していた。
「カエル料理はありますか?」
馬小跳がそう聞いていた。
「ない」
店長がそう答えた。
「そうですか。分かりました」
馬小跳がそう答えた。馬小跳はそのあとみんなで、その店を出ようとした。ぼくもすぐあとに続いた。その時、店の外に怪しい人影がちらっと見えた。ぼくは不審に思ったので、急いで店の外に出て、その人影を追っていった。でも人込みにまぎれて、その姿を見失ってしまった。馬小跳がぼくの異変に気がついて息せききって走ってきた。
「笑い猫、どうしたのだ?」
馬小跳がそう言った。ぼくは人の話を聞いて分かるが、人の言葉は話すことができないので、とてももどかしく思った。