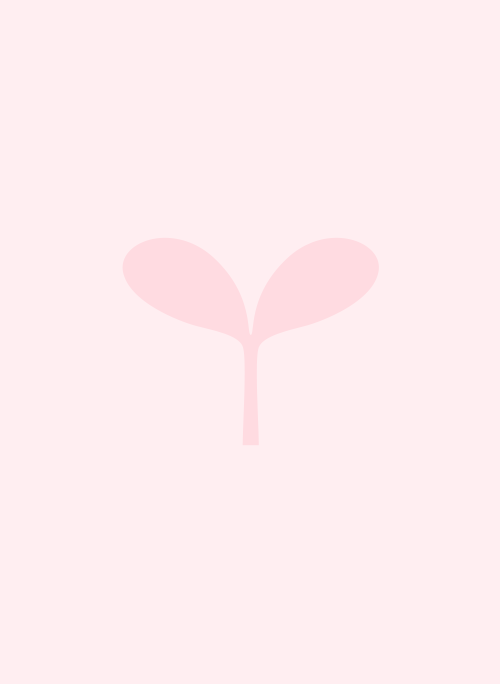中国の大学や高校は7月から8月にかけて夏休み期間なので、かおりは、その間、実家で、新しい学校で働くための書類の準備をしていました。
8月の下旬に学校からの招聘状や、学校を管轄する治安局から労働ビザや入国許可証が届いたので、かおりはそれらの書類を持って、福岡にある領事館に行って出国のための手続きをしました。
病院で健康診断書を作ってもらったり、警察署で無犯罪証明書を出してもらったり、スマートフォンで航空券の予約もしました。
9月の初めにすべての書類ができあがったので、かおりは学校に飛行機の到着日時と搭乗する便名をメールで伝えました。
9月7日に、かおりは長崎から再び船に乗って上海へ向けて出国しました。長崎を出てから2日後に船が上海の港に着きました。その日はちょうどかおりの43歳の誕生日だったので、かおりは上海の中心街にあるレストランに行って、おいしい上海料理を食べたり、ジュースで祝ってから地下鉄で飛行場まで行きました。
飛行場に着くとすぐにチェックインカウンターで搭乗手続きをしてから、ハルピン行きの直行便に乗り込みました。上海とハルピンは距離にして約1,650キロ離れています。飛行機が離陸してから約2時間55分の時間を要して、飛行機はようやくハルピンの太平国際空港に着きました。
ハルピンは中国の最も北にある黒竜江省の省都で、人口は一千万人あまり。気候は寒冷で、夏は短くて夏の1日の平均気温は22.8℃くらい。冬は長くて冬の1日の平均気温は-18.6℃くらい。11月の初めから3月の下旬までが冬で、町のあちこちが厚い氷で覆われるので「氷の町」と呼ばれています。寒さが最も厳しい1月から2月にかけては、夜間は-40℃近くまで冷え込みます。気候が乾燥しているので、雪の量はそれほど多くはありませんが、それでも冬の期間を通して雪が降ります。
春と秋は短くて、どちらも2か月くらいしかありません。ハルピンを代表する有名なものといえば、ビールと、『氷雪大世界』があげられます。ハルピンビールは日本でいえばサッポロビールのようなものだし、『氷雪大世界』は日本でいえば札幌の雪まつりのようなものです。
かおりはビールは飲まないし、札幌の雪まつりを見に行ったこともありませんが、ハルピンと札幌は似たような町だなあと思いました。ハルピンは気候の上では、札幌よりもずっと寒いところなので、長崎で生まれ育ったかおりにとって、ハルピンの冬の寒さに耐えられるだろうかという不安がなかったわけではありません。
しかしそれよりも未知の世界に身を置くことで得られる期待感のほうが大きかったので、飛行機がハルピンの太平国際空港に着いたとき、かおりの心はわくわくしていて、ゴムまりのようにはずんでいました。
空港で検疫や入国審査を受けてから、機内に預けた荷物を受け取り、税関での申告も終えて到着ロビーに出たときに、外で待っていた人たちのなかから、
「あのー、佐倉先生ですか」
と、声をかけられました。
「はい、そうです。佐倉です」
かおりは、にっこりと答えました。
「私は黒竜江大学の外事局で働いております陳麗紅と申します。先生をお迎えにまいりました。これからどうぞよろしくお願いいたします」
陳さんが上手な日本語でそうおっしゃいました。陳さんはかおりよりも7つぐらい年下に見える髪が長くてきれいな女性でした。
「こちらこそ、どうぞよろしくお願いします」
かおりは丁寧に頭をさげて、お辞儀をしました。
「上海からの長旅でお疲れになられたでしょう。お荷物、私がお持ちいたします」
陳さんが気を遣ってくださいました。
「いえいえ、大丈夫です。荷物は自分で持ちます」
かおりはそう答えました。
「ご遠慮なさらないでください。これ、私がお持ちいたします」
陳さんがそうおっしゃって、かおりが手に持っていたハープケースを指でさされたので、「じゃあ、遠慮なくお願いします。ありがとうございます」
と、答えて、陳さんに持ってもらいました。
空港の正面玄関から二、三分歩いたところに学校の車が待たせてあったので、ドライバーにあいさつをしてから、かおりは陳さんといっしょに大学へ向かいました。空港を出てから三十分ほどで、車は市内の中心部に入り、やがて正面に立派で大きな建物が見えてきました。
「あれが私たちの大学です」
陳さんが、そうおっしゃいました。大学というよりも、日本の国会議事堂を思わせるような、威風堂々とした外観に、かおりは圧倒されていました。
学校の車はやがて、黒竜江大学の正門の前で止まりました。
「さあ、着きましたよ」
陳さんにうながされて、かおりは車を降りました。
「ここが私たちの黒竜江大学です。黒大(ヘイター)と呼ばれています」
陳さんが、そうおっしゃいました。近くで見る建物の壮観さは、あまりにも立派すぎて、言葉を失ってしまうほどでした。かおりは、思わず、おじけづいて、二、三歩、後ずさりしました。
(私のような、取るに足らない小さい人間が、こんなに大きくて立派な建物のなかで授業などをしてもいいのだろうか。なんだか場違いのところにきたように見えるし、身の程知らずも、はなはだしい)
かおりは、そう思いました。でも仕事を引き受けて、ここに来た以上、今さら引き返すわけにもいかないので、覚悟を決めて、(なるようになるさ)と、思うことにしました。
立派なのは大学の外観だけではなくて、内部の教室棟も立派でした。どの教室にも最新のコンピューターが備えてあって、大型のスクリーンを通して、効果的な授業ができるように教育環境が整えられていたからです。
宿舎のなかも立派でした。かおりに与えられた宿舎は3LDKのマンションで、居間にも台所にも寝室にもバスルームにも、暖房用のスチーム菅が何本も設置されていました。お風呂も、今までの学校とは違って、シャワーだけでなく、湯船につかることができるようになっていたので、冬の寒さ対策が十分になされていることを感じて、かおりはうれしく思いました。
宿舎のなかには新しく購入されたばかりの冷蔵庫や洗濯機や電子レンジやダブルベッドが備えつけてありました。部屋代や電気代やガス代やインターネットの接続料はすべて学校負担。食堂も学校の食堂が安く利用できるし、近くにスーパーもあるので買い物に便利だし自炊もできます。至れり尽くせりのもてなしをされているように思えて、「外教(外国人教師)」を心から歓迎している大学の姿勢をつくづくと感じたり、気遣いに応えるだけの貢献をしなければと、意をあらたにしていました。
荷物の整理もそこそこにして、かおりは就任早々から、心構えを十分にして、持っているすべての能力を出し切って授業の準備をしたり、日々の授業をおこなっていました。かおりが担当するクラスは、二年生、三年生、四年生、大学院生と、多岐にわたっていました。教える内容も、作文、新聞精読、古典文学、ビジネス日本語と、多岐にわたっていました。授業のほかに、卒論やスピーチコンテストの指導もあります。一年生は入学してから三か月間は軍事訓練が朝から晩まであるので、授業はありませんが、12月からは初級日本語の文法の授業を、かおりは任されていました。毎日とても忙しくて、休日も返上して、かおりは懸命に頑張っていました。
かおりがこの学校に来てから三週間ほどたった10月1日から、国慶節(中国の建国記念日)の休暇期間に入りました。休みが一週間あるので、かおりは休みを利用して、父が以前住んでいた長春の町へ行くことにしました。ハルピンから長春まで高速鉄道で一時間ほどで行けます。かおりの父親が拾われて、養父母に育てられて、高校を卒業するまで住んでいた家が今もあるので、ハルピンに来たのを機に、いつかぜひその家を訪ねてみたいと、かおりはずっと思っていました。
父親が日本に帰国してからも、かおりは、養父母の孫娘にあたる王艶さんと、子どものころから手紙やメールで連絡を取り合っていました。お会いしたことはこれまでなかったのですが、今回、初めて会えるので、それも楽しみでした。王艶さんとかおりは年も近かったし、王艶さんも高校で日本語教師をしておられたので、話も弾むのではないかと、かおりは思っていました。王艶さんにはあらかじめ連絡を入れておいたので、電車が長春の駅に着いたら、待っていてくださるはずです。
朝の十時過ぎに長春の駅に電車が着いたので、携帯電話で王艶さんに連絡を入れました。するとすぐに手を振りながら、王艶さんが近づいてこられました。
「いらっしゃい、待ってたわ」
王艶さんが笑顔で迎えてくださいました。
「お出迎え、ありがとうございます」
かおりは恭しく、王艶さんにあいさつをしました。それからまもなく、かおりと王艶さんは、駅前から出ている53番のバスに乗りました。バスは30分ほどで市街地を抜けて、あたり一面に、のどかな田園風景が広がっている静かな農村地帯に入っていきました。バスに50分ほど乗ったところで、バスを降りて、そこから歩いて10分ほど行ったところに小さな集落があり、そのなかの一軒に、かおりは案内されました。
「さあ、着いたわよ。このうちで、あなたのお父様は育てられたのよ」
王艶さんがそう、おっしゃいました。父が育ったうちを初めて実際に目にしたかおりは、感慨深いものを感じていました。
「このうちの前に、ごみのように捨てられていたお父様を、私の祖父母が見つけたときは、お父様はまだ生まれたばかりだったそうですよ」
王艶さんの説明を聞いて、かおりは七十年近い前の遠い昔へ心をタイムスリップさせていました。
うちのなかに入ると、王艶さんのご両親と、王艶さんのご主人が温かく迎えてくださいました。王艶さんの一人娘である小静ちゃんも笑顔で迎えてくれました。
「お父さん、この方が正さんの娘さんよ」
王艶さんがそうおっしゃると、
「おう、そうか。この人がねぇ……」
王艶さんのお父様は、感慨深そうな顔をしながら、かおりの顔を見ていました。
「正は私より2つ年下で、実の弟のようにかわいがっていたよ。小さいころは、いっしょによく遊んだなぁ……。冬は池でスケート、夏は川で魚とり、春は野原でサッカー、秋は山で木の実拾い。懐かしいなぁ」
王艶さんのお父様が、そうおっしゃいました。
「正は、高校を卒業するまでこの家で過ごしていたよ。利発な子で、学校の成績がとてもよかった。国立大学の医学部に進学して、このうちを離れていったが、休みの日にはよくうちへ帰ってきたよ。バイオリンが上手で、うちでよく弾いてくれたよ」
王艶さんのお父様にとって、かおりの父親の思い出は尽きないようでした。王艶さんのお母様は手作りの料理を作って、かおりをもてなしてくださいました。
「さぁ、どうぞ、たくさんお召し上がりください」
お母様がそうおっしゃったので、かおりは舌鼓を打ちながら、料理の味を堪能していました。
そのあと、かおりは王艶さんや、王艶さんのご両親といっしょに、父親を育ててくださった養父母が眠っていらっしゃる小高い丘の上にお墓参りに行きました。墓石の前に花と水と線香を供えて、手を合わせながら
(父を大切に育ててくださってありがとうございます。こ恩は一生忘れません)
と、心をこめて感謝の気持ちを述べました。養父母のお墓参りをすることは、かおりの長年の念願だったので、お墓参りを終えたあと、かおりは、ほっとしていました。
それからまもなく、かおりは王艶さんたちと別れて、ハルピンへ帰っていきました。
8月の下旬に学校からの招聘状や、学校を管轄する治安局から労働ビザや入国許可証が届いたので、かおりはそれらの書類を持って、福岡にある領事館に行って出国のための手続きをしました。
病院で健康診断書を作ってもらったり、警察署で無犯罪証明書を出してもらったり、スマートフォンで航空券の予約もしました。
9月の初めにすべての書類ができあがったので、かおりは学校に飛行機の到着日時と搭乗する便名をメールで伝えました。
9月7日に、かおりは長崎から再び船に乗って上海へ向けて出国しました。長崎を出てから2日後に船が上海の港に着きました。その日はちょうどかおりの43歳の誕生日だったので、かおりは上海の中心街にあるレストランに行って、おいしい上海料理を食べたり、ジュースで祝ってから地下鉄で飛行場まで行きました。
飛行場に着くとすぐにチェックインカウンターで搭乗手続きをしてから、ハルピン行きの直行便に乗り込みました。上海とハルピンは距離にして約1,650キロ離れています。飛行機が離陸してから約2時間55分の時間を要して、飛行機はようやくハルピンの太平国際空港に着きました。
ハルピンは中国の最も北にある黒竜江省の省都で、人口は一千万人あまり。気候は寒冷で、夏は短くて夏の1日の平均気温は22.8℃くらい。冬は長くて冬の1日の平均気温は-18.6℃くらい。11月の初めから3月の下旬までが冬で、町のあちこちが厚い氷で覆われるので「氷の町」と呼ばれています。寒さが最も厳しい1月から2月にかけては、夜間は-40℃近くまで冷え込みます。気候が乾燥しているので、雪の量はそれほど多くはありませんが、それでも冬の期間を通して雪が降ります。
春と秋は短くて、どちらも2か月くらいしかありません。ハルピンを代表する有名なものといえば、ビールと、『氷雪大世界』があげられます。ハルピンビールは日本でいえばサッポロビールのようなものだし、『氷雪大世界』は日本でいえば札幌の雪まつりのようなものです。
かおりはビールは飲まないし、札幌の雪まつりを見に行ったこともありませんが、ハルピンと札幌は似たような町だなあと思いました。ハルピンは気候の上では、札幌よりもずっと寒いところなので、長崎で生まれ育ったかおりにとって、ハルピンの冬の寒さに耐えられるだろうかという不安がなかったわけではありません。
しかしそれよりも未知の世界に身を置くことで得られる期待感のほうが大きかったので、飛行機がハルピンの太平国際空港に着いたとき、かおりの心はわくわくしていて、ゴムまりのようにはずんでいました。
空港で検疫や入国審査を受けてから、機内に預けた荷物を受け取り、税関での申告も終えて到着ロビーに出たときに、外で待っていた人たちのなかから、
「あのー、佐倉先生ですか」
と、声をかけられました。
「はい、そうです。佐倉です」
かおりは、にっこりと答えました。
「私は黒竜江大学の外事局で働いております陳麗紅と申します。先生をお迎えにまいりました。これからどうぞよろしくお願いいたします」
陳さんが上手な日本語でそうおっしゃいました。陳さんはかおりよりも7つぐらい年下に見える髪が長くてきれいな女性でした。
「こちらこそ、どうぞよろしくお願いします」
かおりは丁寧に頭をさげて、お辞儀をしました。
「上海からの長旅でお疲れになられたでしょう。お荷物、私がお持ちいたします」
陳さんが気を遣ってくださいました。
「いえいえ、大丈夫です。荷物は自分で持ちます」
かおりはそう答えました。
「ご遠慮なさらないでください。これ、私がお持ちいたします」
陳さんがそうおっしゃって、かおりが手に持っていたハープケースを指でさされたので、「じゃあ、遠慮なくお願いします。ありがとうございます」
と、答えて、陳さんに持ってもらいました。
空港の正面玄関から二、三分歩いたところに学校の車が待たせてあったので、ドライバーにあいさつをしてから、かおりは陳さんといっしょに大学へ向かいました。空港を出てから三十分ほどで、車は市内の中心部に入り、やがて正面に立派で大きな建物が見えてきました。
「あれが私たちの大学です」
陳さんが、そうおっしゃいました。大学というよりも、日本の国会議事堂を思わせるような、威風堂々とした外観に、かおりは圧倒されていました。
学校の車はやがて、黒竜江大学の正門の前で止まりました。
「さあ、着きましたよ」
陳さんにうながされて、かおりは車を降りました。
「ここが私たちの黒竜江大学です。黒大(ヘイター)と呼ばれています」
陳さんが、そうおっしゃいました。近くで見る建物の壮観さは、あまりにも立派すぎて、言葉を失ってしまうほどでした。かおりは、思わず、おじけづいて、二、三歩、後ずさりしました。
(私のような、取るに足らない小さい人間が、こんなに大きくて立派な建物のなかで授業などをしてもいいのだろうか。なんだか場違いのところにきたように見えるし、身の程知らずも、はなはだしい)
かおりは、そう思いました。でも仕事を引き受けて、ここに来た以上、今さら引き返すわけにもいかないので、覚悟を決めて、(なるようになるさ)と、思うことにしました。
立派なのは大学の外観だけではなくて、内部の教室棟も立派でした。どの教室にも最新のコンピューターが備えてあって、大型のスクリーンを通して、効果的な授業ができるように教育環境が整えられていたからです。
宿舎のなかも立派でした。かおりに与えられた宿舎は3LDKのマンションで、居間にも台所にも寝室にもバスルームにも、暖房用のスチーム菅が何本も設置されていました。お風呂も、今までの学校とは違って、シャワーだけでなく、湯船につかることができるようになっていたので、冬の寒さ対策が十分になされていることを感じて、かおりはうれしく思いました。
宿舎のなかには新しく購入されたばかりの冷蔵庫や洗濯機や電子レンジやダブルベッドが備えつけてありました。部屋代や電気代やガス代やインターネットの接続料はすべて学校負担。食堂も学校の食堂が安く利用できるし、近くにスーパーもあるので買い物に便利だし自炊もできます。至れり尽くせりのもてなしをされているように思えて、「外教(外国人教師)」を心から歓迎している大学の姿勢をつくづくと感じたり、気遣いに応えるだけの貢献をしなければと、意をあらたにしていました。
荷物の整理もそこそこにして、かおりは就任早々から、心構えを十分にして、持っているすべての能力を出し切って授業の準備をしたり、日々の授業をおこなっていました。かおりが担当するクラスは、二年生、三年生、四年生、大学院生と、多岐にわたっていました。教える内容も、作文、新聞精読、古典文学、ビジネス日本語と、多岐にわたっていました。授業のほかに、卒論やスピーチコンテストの指導もあります。一年生は入学してから三か月間は軍事訓練が朝から晩まであるので、授業はありませんが、12月からは初級日本語の文法の授業を、かおりは任されていました。毎日とても忙しくて、休日も返上して、かおりは懸命に頑張っていました。
かおりがこの学校に来てから三週間ほどたった10月1日から、国慶節(中国の建国記念日)の休暇期間に入りました。休みが一週間あるので、かおりは休みを利用して、父が以前住んでいた長春の町へ行くことにしました。ハルピンから長春まで高速鉄道で一時間ほどで行けます。かおりの父親が拾われて、養父母に育てられて、高校を卒業するまで住んでいた家が今もあるので、ハルピンに来たのを機に、いつかぜひその家を訪ねてみたいと、かおりはずっと思っていました。
父親が日本に帰国してからも、かおりは、養父母の孫娘にあたる王艶さんと、子どものころから手紙やメールで連絡を取り合っていました。お会いしたことはこれまでなかったのですが、今回、初めて会えるので、それも楽しみでした。王艶さんとかおりは年も近かったし、王艶さんも高校で日本語教師をしておられたので、話も弾むのではないかと、かおりは思っていました。王艶さんにはあらかじめ連絡を入れておいたので、電車が長春の駅に着いたら、待っていてくださるはずです。
朝の十時過ぎに長春の駅に電車が着いたので、携帯電話で王艶さんに連絡を入れました。するとすぐに手を振りながら、王艶さんが近づいてこられました。
「いらっしゃい、待ってたわ」
王艶さんが笑顔で迎えてくださいました。
「お出迎え、ありがとうございます」
かおりは恭しく、王艶さんにあいさつをしました。それからまもなく、かおりと王艶さんは、駅前から出ている53番のバスに乗りました。バスは30分ほどで市街地を抜けて、あたり一面に、のどかな田園風景が広がっている静かな農村地帯に入っていきました。バスに50分ほど乗ったところで、バスを降りて、そこから歩いて10分ほど行ったところに小さな集落があり、そのなかの一軒に、かおりは案内されました。
「さあ、着いたわよ。このうちで、あなたのお父様は育てられたのよ」
王艶さんがそう、おっしゃいました。父が育ったうちを初めて実際に目にしたかおりは、感慨深いものを感じていました。
「このうちの前に、ごみのように捨てられていたお父様を、私の祖父母が見つけたときは、お父様はまだ生まれたばかりだったそうですよ」
王艶さんの説明を聞いて、かおりは七十年近い前の遠い昔へ心をタイムスリップさせていました。
うちのなかに入ると、王艶さんのご両親と、王艶さんのご主人が温かく迎えてくださいました。王艶さんの一人娘である小静ちゃんも笑顔で迎えてくれました。
「お父さん、この方が正さんの娘さんよ」
王艶さんがそうおっしゃると、
「おう、そうか。この人がねぇ……」
王艶さんのお父様は、感慨深そうな顔をしながら、かおりの顔を見ていました。
「正は私より2つ年下で、実の弟のようにかわいがっていたよ。小さいころは、いっしょによく遊んだなぁ……。冬は池でスケート、夏は川で魚とり、春は野原でサッカー、秋は山で木の実拾い。懐かしいなぁ」
王艶さんのお父様が、そうおっしゃいました。
「正は、高校を卒業するまでこの家で過ごしていたよ。利発な子で、学校の成績がとてもよかった。国立大学の医学部に進学して、このうちを離れていったが、休みの日にはよくうちへ帰ってきたよ。バイオリンが上手で、うちでよく弾いてくれたよ」
王艶さんのお父様にとって、かおりの父親の思い出は尽きないようでした。王艶さんのお母様は手作りの料理を作って、かおりをもてなしてくださいました。
「さぁ、どうぞ、たくさんお召し上がりください」
お母様がそうおっしゃったので、かおりは舌鼓を打ちながら、料理の味を堪能していました。
そのあと、かおりは王艶さんや、王艶さんのご両親といっしょに、父親を育ててくださった養父母が眠っていらっしゃる小高い丘の上にお墓参りに行きました。墓石の前に花と水と線香を供えて、手を合わせながら
(父を大切に育ててくださってありがとうございます。こ恩は一生忘れません)
と、心をこめて感謝の気持ちを述べました。養父母のお墓参りをすることは、かおりの長年の念願だったので、お墓参りを終えたあと、かおりは、ほっとしていました。
それからまもなく、かおりは王艶さんたちと別れて、ハルピンへ帰っていきました。