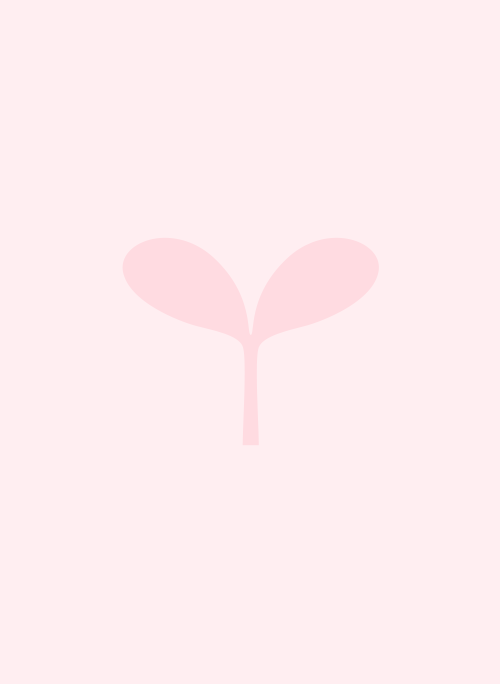2013年の9月から、かおりは江蘇省の南京にある田家炳高級中学という高校で教鞭を執ることになりました。南京と言えば、今から76年前に「南京大虐殺」という、日本の軍部が引き起こした歴史的な汚点が今でも色濃く残っている町です。日本側の報告によると約20万人、中国側の報告によると約43万人もの中国人が虐殺されたと言われています。戦後70年以上がたった今日でも、けっして過去の出来事として歴史のかなたに無造作に葬り去ることができない事件であり、中学や高校の教科書にも掲載されています。当時のことを知っておられる生き証人の方や、いとしい親族のかけがえのない命を無慈悲に奪われた方や、あのときの残酷な様子を祖父母や両親から伝え聞いて心を痛めている方も、南京にはたくさんいらっしゃるはずです。南京大虐殺紀念館には無数の遺骨が今でも展示されていると聞いたことがあります。
そのことを思うと、南京の高校に次の就職先が決まったとき、かおりの心は少し複雑な気持ちにとらわれていました。辞退してほかの町で、あらたな就職先を探すという選択肢もないことはありませんでした。しかし一番最初に声をかけてくださった学校が南京にある田家炳高級中学だったので、かおりは恩を感じて引き受けることにしました。
(日本人がかつて人道的に絶対に許されない残酷な行為をおこなった町、南京。それだけに、今の私が中国の方たちに愛情をもって接して、せめてもの償いをしていかなければならない)
かおりは心からそう思いました。
9月の1日に南京の禄口国際空港へ降り立ったかおりを、学校の先生方が三人温かく出迎えてくださいました。
「佐倉先生いらっしゃいませ」
「ようこそ南京へ」
「心から歓迎いたします」
三人の先生方は、それぞれサインボードを胸に抱えて、かおりの到着を笑顔で待っていてくださいました。
空港から学校のマイクロバスに乗って、赴任先の田家炳高級中学まで行き、まず最初に宿舎を案内されました。3LDKの立派な宿舎で、かおりを迎え入れるために新しく購入されたばかりの家具や冷蔵庫や電子レンジや洗濯機など、生活必需品がすべて備えてありました。部屋代や光熱費や水道代はすべて学校側の負担。部屋の窓から見える景色はきれいで、初秋の日差しを浴びて、木々の緑がきらきらと輝いていました。
翌朝の9時ごろ、日本語主任の欧先生が宿舎にお見えになって、校内を案内してくださいました。まず最初に職員室へ連れていってくださったので、かおりは先生方に赴任のあいさつをしました。校長先生をはじめ、どの先生方もみんな、とても真面目そうな方ばかりで、心のなかに深い教育愛を抱いておられて、熱く燃えていらっしゃるのが、ひしひしと伝わってきました。欧先生はそのあと、かおりを教室棟へ連れて行ってくださいました。授業を受けている学生たちの姿を廊下の窓ごしに眺めたり、教室棟の管理人のおじさんや、掃除のおばさんにも、かおりは笑顔であいさつをしました。
「日本語を学んでいる学生は、この学校に現在、200人ほどいます。卒業後は、ほぼ全員、日本の大学に進学します。よい成績を取らないと、日本のいい大学に進学できないので、どの学生も日本語を学ぶモチベーションがとても高いです。いい大学を出て、いい会社に就職するために、みんな真剣に学んでいます。学生のなかには、両親や祖父母から猛反対されながら、日本語を学んでいる学生もいます。戦争中に日本軍がおこなった残虐な行為は、みんな知っています。でも気にしないでください。日本語を学んでいる学生のなかに反日的な感情を持っている人は一人もいませんから」
欧先生がそうおっしゃいました。
この学校へ来てから一週間ほどたった九月九日から、かおりは、いよいよ授業を始めることになりました。この日は、ちょうどかおりの42歳の誕生日でもありました。初めての授業をするために、少し緊張した面持ちでかおりは二年一組の教室に入っていきました。すると教室のホワイトボードにマーカーで「佐倉先生、お誕生日おめでとうございます」と、書かれていたので、かおりはびっくりしました。
(えっ、どうして学生は私の誕生日が今日だということを知っていたのだろう)
かおりは、けげんそうな顔で、一番前の席に座っていた学生に聞きました。
「昨日、欧先生から伺いました」
学生がそう答えました。
そのあと、学生の一人が立ち上がって教卓のところへ近づいてきました。
「私はこのクラスの学級委員の鄭芙蓉です。これ、私たちからのプレゼントです。これから一年間、ご指導よろしくお願いいたします」
鄭さんがそう言って、赤いリボンでラッピングされた箱をかおりに手渡しました。
「これ、私たちからのプレゼントです」
鄭さんが、うやうやしい声でそう言って、一礼しました。
「こちらこそ、よろしくお願いします」
かおりも一礼してから、笑顔でそう答えました。
そのあとクラスのみんなが声をそろえて、「ハッピーバースデーツーユー」と歌ってくれました。思ってもいなかったうれしいハプニングに、初めての授業を前に緊張していたかおりの心がほぐれました。歌が終わったあと、かおりは学生に
「この箱、開けてもいい」
と、聞きました。学生がにっこり、うなずきました。
箱のなかには、精緻なデザインが施された赤いスカーフが入っていました。
「わあ、きれい。細かくて手の込んだ刺繍が施されたシルクのスカーフですね。ありがとう。大切にするわ」
かおりは、にっこり答えました。
「お気に召していただけて、よかったです。このスカーフは蘇州で作られたものです」
鄭さんがそう答えました。
「そうですか。蘇州のシルクは有名ですよね。本当にありがとう。これまで四十年あまり生きてきたけど、こんなにうれしかった誕生日は初めてだわ」
高級感にあふれるシルクのスカーフを手にとって、かおりの心は喜びで満たされていました。目はうるうるして、思わず涙が出そうになりました。
「佐倉先生、今日の夕方、お時間がおありになりますか」
鄭さんが聞きました。
「もしおありになるようでしたら、佐倉先生のために歓迎パーティーをしようと思っているのです」
「ありがとう。ぜひ参加させていただくわ」
かおりは、にっこり、うなずきました。
その日の夕方、学校の近くのレストランを会場にして、二年一組のクラス全員と日本語担当の先生が集まって、かおりのために盛大なパーティーが開かれました。
「佐倉先生、お誕生日おめでとうございます」
「佐倉先生、ようこそ私たちの学校へいらっしゃいました」
先生方も学生たちも、かおりのことを心から歓迎してくれたので、かおりの心は高揚感にあふれていました。
「私は日本の歌を知っているわ」
学生の一人がそう言って、テレサ・テンの『時の流れに身をまかせ』を、日本語と中国語で歌ってくれました。かおりも歌のお返しをしなければと思って、中国人なら誰でもよく知っている『月亮代表我的心(月は私の心を表す)』を歌って、みんなの拍手喝采を浴びました。
日がたつにつれて、この学校での授業や生活にもだんだん慣れてきて、かおりは毎日、充実した日々を過ごしていました。先生方や学生たちの誕生日をノートに書いてもらったので、誕生日にはお祝いのメッセージを添えて、プレゼントを贈ったりしていました。男の先生にはネクタイ、女の先生にはブラウス、学生たちにはチョコレートをプレゼントしていました。みんなとても喜んでくれました。贈られるよりも贈るほうがずっとうれしい気持ちになれるので、贈るたびに、かおり自身が誰よりも幸せな気持ちになっていました。
11月の半ばに開かれた学園祭のときには、かおりは日本から持ってきたアイリッシュハープを弾いて、先生方や学生たちの前で披露しました。同僚の男性教師の周先生がクラシックギターを弾かれるので、いっしょに合奏したりもしました。『浜辺の歌』や、『蘇州夜曲』や、『時の流れに身をまかせ』といった日本の曲をハープのソロで弾いたり、周先生といっしょに作った『南京情歌』という曲を弾き語りで歌ったりしました。かおりが日本語で詞を書いて、周先生が曲とコードをつけて、二人でデュエットして、みんなの拍手喝采を浴びました。
学園祭の翌日は休みだったので、かおりは周先生に誘われて、二人で玄武湖公園へ行って、湖にボートを浮かべて、楽しいひとときを過ごしました。
「佐倉先生はまだお一人でしたよね」
オールをこぎながら、周先生がそうおっしゃいました。かおりはうなずきました。
「あのー、もしよかったら、これからの人生を、ぼくといっしょに歩んでいきませんか」
思ってもいなかったことを、周先生が急におっしゃったので、かおりはびっくりしました。おっしゃる意味を取り違えたのかもしれないと思ったので、かおりは探るような目で周先生を見ました。
「それって、もしかしたら、私と結婚……」
周先生がうなずきました。
「いやですか。ぼくのこと、嫌いですか」
「……」
かおりには答えようがありませんでした。それよりも何よりも、周先生がまだ独身でいらっしゃるとは、かおりはまったく思ってもいませんでした。
「ぼくはこれまで39年間生きてきましたが、結婚したことはまだ一度もありません。女性と深いお付き合いしたこともありません。ぼくは愛のすべてを教育に捧げてきました。40歳を前にして、今やっと恋愛に対する関心が少しだけ芽生えてきました。佐倉先生にお会いして初めて恋愛感情が芽生えたと言っても過言ではありません」
周先生が真剣な目で、そうおっしゃいました。
「ぼくには佐倉先生が必要なんです。どうかぼくと……」
周先生が哀願するような目で、かおりを見続けていました。
「そんなことを急におっしゃられても困ります。お気持ちはありがたいですが、私はもう四十路を過ぎている女性です。周先生はまだ三十代でいらっしゃるから、もっとお若くて魅力のある女性がふさわしいと思います」
かおりは、そう答えました。それを聞いて、周先生は首を横に振りました。
「三十代といっても、ぎりぎりです。けっして若くはありません」
「でも私よりは三歳お若いです。私より、もっとお若い方といっしょになられたほうが、お子さんもできるだろうし、家のなかに子どもの声が楽しく響いて、幸せな家庭が築かれると思います」
かおりはそう答えました。
「子どもはどうでもいいです。私には学校の子どもがたくさんいます。休みの日には、学校の子どもがよくうちへ遊びにくるので、うちのなかで、にぎやかな声が響いていますよ。それで十分です。学校を卒業した教え子も時々、うちへ遊びに来ます。その子たちが、ぼくにとって、かけがえのない大切な子どもなのです」
周先生が、そうおっしゃいました。それを聞いてかおりは、周先生は本当にあふれんばかりの教育愛に燃えていらっしゃる方だなあと思って、心から敬服しました。
「佐倉先生も、ぼくも音楽が大好きだから、『歌』という子どもを、二人でたくさん作ることができます。佐倉先生が詞を書いて、私が曲をつけて、歌ができたら、その歌を歌って聞かせたり、合奏したりして聴く人の心を和ませることができます。それが、ぼくの理想の人生なのです」
周先生がそうおっしゃいました。
周先生の言葉に、かおりは心が少し傾きかけました。でもやはり冷静に考えると、家庭のなかに自分たちの子どもがいて楽しくて明るい生活をしていくことが、人が幸せになるためには絶対に必要なことだと思っていたので、周先生との関係を友愛以上に発展させてはいけないと思いました。周先生のことは、とても好きなので、周先生のお気持ちを傷つけないように言葉を慎重に選びながら、かおりは周先生に思いを伝えました。
「そうですか。それはとても残念です。これまで39年間生きてきて、初めて恋愛感情を抱かせてくれた佐倉先生と、いっしょになれないのは本当に残念でたまりません。このまま、この湖に落ちて死んでしまいたいくらいです」
それを聞いて、かおりは思わず、おかしくなって、くすくす笑いました。
「オーバーなこと、おっしゃらないでくださいよ。周先生がいなくなったら、周先生の教育愛も終わってしまうではありませんか。周先生にとっては、恋愛よりも教育愛のほうがずっと大切なんでしょう」
「……」
周先生には返す言葉が見つからないでいるようでした。
「大丈夫ですよ。周先生には、そのうちきっと、私よりもはるかに素敵な女性が現れますから」
かおりはそう言って、周先生の気持ちをなだめました。周先生は首をまた横にふりました。
「ぼくは絶対にあきらめません。たとえ5年でも10年でも待ちます」
周先生がそうおっしゃいました。
「困った先生ですね。ふふふ……」
かおりは、おかしくなって、含み笑いを浮かべました。周先生も照れくさそうに笑みを浮かべておられました。
ボートを降りたあと、湖の近くにある喫茶店でコーヒーを飲みながら、家族のことについての話に話題が及びました。
「ぼくの祖父の兄弟は3人いましたが、みんな日本人に殺されました。祖父からその話を聞いたとき、日本人はなんて残虐非道なのだろうと思いました。子ども心に日本人に対 して激しい怒りと強い敵愾心(てきがいしん)を感じたりもしていました。でも今は考え方 が少し変わりました。悪道極まりないことをしたのは、日本の軍人であって、一般の日本 人ではないと思うようになったからです」
「……」
重い話だったので、かおりには、どう答えてよいか分からないでいました。
「先の戦争のときに日本人が中国の方々にとても残忍なことをしたことは私も、もちろん知っています。日本人の一人として本当に申し訳なく思っております」
一呼吸、間を置いてから、かおりは胸の奥深くに抱いていた謝罪の念を、絞りだすような声で吐露しました。
「戦争と言えば、私の父も大変苦労しました。終戦間際に中国の長春で生まれて、中国人に育てられた戦争孤児だからです。路頭にごみのように捨てられていた父をかわいそうに思って中国人が助けてくれなかったなら、父は幼いまま死んでいただろうと思います」
かおりがそう言うと、今度は周先生が答に詰まっておられました。
「戦争は本当に後世まで深いしこりを残しますね」
「そうですね。戦勝国にも敗戦国にも関係なく、今でも深い遺恨が残っていて、後世に永遠に受け継がれていくものだと思います」
かおりと周先生はそう言って、うなずきあっていました。
それからまもなく、かおりと周先生は喫茶店を出て、玄武公園の前にあるバス停から62番のバスに乗って、それぞれの宿舎へ帰っていきました。
それから二週間ほどたった12月の初め、日本語主任の欧先生が授業が終わったあと、
「日本の高校では、どれくらいの学校で中国語が教えられていますか」
と、おたずねになりました。すぐには答えられなかったので、スマートフォンで調べてから
「10校に1校ぐらいの割合です」
と、かおりは答えました。
「数はどれくらいですか。どんな学校で教えられていますか」
欧先生は日本の教育事情に興味がおありのようでした。
「全国で500校ぐらいの高校で教えられています。一流の進学校ではなくて、レベルがそれほど高くない進学校か、商業高校で教えられています」
スマートフォンで得られた情報をもとに、かおりはそう答えました。
「そうですか。卒業後は中国の大学に進学したり、中国で働いたりする学生が多いのでしょうか」
欧先生は興味深そうな顔をして、かおりにききました。
「いえ、そうとばかりも限りません。共通一次試験の問題が英語よりも中国語のほうが簡単に作られているので、英語に自信がない学生が共通一次試験で高得点を取るために勉強していることもあります。大学に進学しない学生が趣味として勉強していることもあります」
かおりはそう答えました。
「そうですか。中国でも似たようなところがあります。田舎の学校では農民の子どもが多いので、学力はあまり高くありません。そのために英語の難しい問題を解くのは苦手だから、中学のときから日本語を勉強して、高校でさらに勉強して、大学入学試験を日本語で受ける学生がたくさんいます」
欧先生が、そうおっしゃいました。
「そうですか。日本では中学校のときに中国語を勉強する学生は、ほとんどいません」
かおりは、そう答えました。
「日本の中学や高校で教えられている外国語と言ったら、英語がほとんどです。これではますます親米派を増やすだけで、アジア諸国への親近感を生む土壌が築かれないのではないかと思って、私はとても危惧しています。日本はアジアの一員ですから、アメリカよりも中国や韓国といった近隣諸国との友好関係や相互理解を今以上に深めていって、揺るぎないものにすることがまず大切ではないかと、私は思っています。そのためにはモノを売ったり買ったりするだけでなく、相互にコミュニケーションが取れるように相手国の言葉や文化を学び合う必要があると思います。これまで日本では明治以後、欧米志向が強まり、中学や高校で教えられる外国語といったら、英語がほとんどでした。しかしそれでも日本人の英語は上手ではありません。日本で生活しているかぎり、英語を話せなくても生活に全然支障はありません。日本では最近、小学校でも英語が教えられるようになりました。しかし私個人の考えとしては、それよりも中学や高校で第二外国語として中国語や韓国語を学ばせるほうがいいと思っています。授業が無理ならクラブ活動でもいいと思っています。中国語は漢字を使う言語だから、英語よりもやさしいと思ったり、親近感を持てる学生もいるはずです」
かおりは熱弁をふるって、思いのすべてを一気にまくしたてました。
「そうですね。私も同感です」
欧先生が、うんうんと、うなずかれました。 かおりは語学が好きだったから、大学で英語を専攻しました。卒業後は高校で英語教師にもなりました。しかし子どものころ、祖母から、曽祖父の妹が長崎に落とされた原子爆弾で、生まれたばかりの赤ちゃんを胸に抱いたまま亡くなっていたことを聞いていたので、原爆を落としたアメリカの言葉である英語が本当はあまり好きではありませんでした。それよりも終戦直後の混乱のなかで、中国に取り残された父を孤児として大切に育ててくれた養父母の言葉である中国語に興味を抱いていました。そのためにかおりは、母の介護をするために高校の教師を辞めたあと、独学で中国語の勉強を始めて、今、こうして中国で働いていたのです。 2014年の7月の初めまで、かおりは南京の田家炳高級中学で働きました。次の新しい赴任校は東北地方のハルピンにある黒竜江大学に決まりました。南京を離れる日が近づくにつれて、かおりは先生方や学生たちとの別れに後ろ髪を引かれるような辛い思いを感じることが多くなりました。最後の日には、先生方がパーティーを開いてくださいました。パーティーの席でかおりは、アイリッシュハープでショパンの『別れの曲』を弾きました。これまで一年間親切にしていただいた先生方への哀別の気持ちをこめて、切々と弾きました。琴線に触れるようなかおりの演奏に、先生方はしんみりした顔をして静かに聞き入っていらっしゃいました。なかでも一番寂しそうな顔をしておられたのは周先生でした。周先生からは、玄武公園でのデート以来、何度もお誘いを受けたので、いっしょに楽器を持ち寄って、静かな公園の片隅で合奏したり、二人で詞と曲を書いて新しい歌を作ったりしていました。いっしょに蘇州や杭州に日帰りの旅行に出かけたこともありました。でも結局、最後まで周先生が待ち望んでおられたような言葉が、かおりの口から聞けなかったので、周先生は思うようにならないもどかしさを感じておられたようでした。 「ハルピンはここから遠いですが、いつか佐倉先生に会いに行きます。ぼくはまだ佐倉先生のことをあきらめたわけではありません」 翌日の朝、高速鉄道の駅まで迎えに来てくださった周先生が、別れ間際に、そうおっしゃいました。
それを聞いて、かおりは、くすっと笑いました。
南京から上海まで高速鉄道で1時間20分かかり、そのあと路線バスでフェリーの乗り場まで行きました。上海と長崎の間を行き来している『オーシャンローズ号』という客船に乗って帰国するためです。長崎まで26時間の長旅でしたが、揺れることはほとんどなく、まるで海上ホテルに泊まっているかのような快適な旅でした。船のなかには大浴場やカラオケ室や卓球台などもあったし、映画の上映やコンサートなどもあっていました。かおりはデッキで海を眺めながらハープを弾いたり、船のなかで知り合った人たちと話をしたり、トランプをしたりして、豪華客船の楽しい旅に酔いしれていました。
そのことを思うと、南京の高校に次の就職先が決まったとき、かおりの心は少し複雑な気持ちにとらわれていました。辞退してほかの町で、あらたな就職先を探すという選択肢もないことはありませんでした。しかし一番最初に声をかけてくださった学校が南京にある田家炳高級中学だったので、かおりは恩を感じて引き受けることにしました。
(日本人がかつて人道的に絶対に許されない残酷な行為をおこなった町、南京。それだけに、今の私が中国の方たちに愛情をもって接して、せめてもの償いをしていかなければならない)
かおりは心からそう思いました。
9月の1日に南京の禄口国際空港へ降り立ったかおりを、学校の先生方が三人温かく出迎えてくださいました。
「佐倉先生いらっしゃいませ」
「ようこそ南京へ」
「心から歓迎いたします」
三人の先生方は、それぞれサインボードを胸に抱えて、かおりの到着を笑顔で待っていてくださいました。
空港から学校のマイクロバスに乗って、赴任先の田家炳高級中学まで行き、まず最初に宿舎を案内されました。3LDKの立派な宿舎で、かおりを迎え入れるために新しく購入されたばかりの家具や冷蔵庫や電子レンジや洗濯機など、生活必需品がすべて備えてありました。部屋代や光熱費や水道代はすべて学校側の負担。部屋の窓から見える景色はきれいで、初秋の日差しを浴びて、木々の緑がきらきらと輝いていました。
翌朝の9時ごろ、日本語主任の欧先生が宿舎にお見えになって、校内を案内してくださいました。まず最初に職員室へ連れていってくださったので、かおりは先生方に赴任のあいさつをしました。校長先生をはじめ、どの先生方もみんな、とても真面目そうな方ばかりで、心のなかに深い教育愛を抱いておられて、熱く燃えていらっしゃるのが、ひしひしと伝わってきました。欧先生はそのあと、かおりを教室棟へ連れて行ってくださいました。授業を受けている学生たちの姿を廊下の窓ごしに眺めたり、教室棟の管理人のおじさんや、掃除のおばさんにも、かおりは笑顔であいさつをしました。
「日本語を学んでいる学生は、この学校に現在、200人ほどいます。卒業後は、ほぼ全員、日本の大学に進学します。よい成績を取らないと、日本のいい大学に進学できないので、どの学生も日本語を学ぶモチベーションがとても高いです。いい大学を出て、いい会社に就職するために、みんな真剣に学んでいます。学生のなかには、両親や祖父母から猛反対されながら、日本語を学んでいる学生もいます。戦争中に日本軍がおこなった残虐な行為は、みんな知っています。でも気にしないでください。日本語を学んでいる学生のなかに反日的な感情を持っている人は一人もいませんから」
欧先生がそうおっしゃいました。
この学校へ来てから一週間ほどたった九月九日から、かおりは、いよいよ授業を始めることになりました。この日は、ちょうどかおりの42歳の誕生日でもありました。初めての授業をするために、少し緊張した面持ちでかおりは二年一組の教室に入っていきました。すると教室のホワイトボードにマーカーで「佐倉先生、お誕生日おめでとうございます」と、書かれていたので、かおりはびっくりしました。
(えっ、どうして学生は私の誕生日が今日だということを知っていたのだろう)
かおりは、けげんそうな顔で、一番前の席に座っていた学生に聞きました。
「昨日、欧先生から伺いました」
学生がそう答えました。
そのあと、学生の一人が立ち上がって教卓のところへ近づいてきました。
「私はこのクラスの学級委員の鄭芙蓉です。これ、私たちからのプレゼントです。これから一年間、ご指導よろしくお願いいたします」
鄭さんがそう言って、赤いリボンでラッピングされた箱をかおりに手渡しました。
「これ、私たちからのプレゼントです」
鄭さんが、うやうやしい声でそう言って、一礼しました。
「こちらこそ、よろしくお願いします」
かおりも一礼してから、笑顔でそう答えました。
そのあとクラスのみんなが声をそろえて、「ハッピーバースデーツーユー」と歌ってくれました。思ってもいなかったうれしいハプニングに、初めての授業を前に緊張していたかおりの心がほぐれました。歌が終わったあと、かおりは学生に
「この箱、開けてもいい」
と、聞きました。学生がにっこり、うなずきました。
箱のなかには、精緻なデザインが施された赤いスカーフが入っていました。
「わあ、きれい。細かくて手の込んだ刺繍が施されたシルクのスカーフですね。ありがとう。大切にするわ」
かおりは、にっこり答えました。
「お気に召していただけて、よかったです。このスカーフは蘇州で作られたものです」
鄭さんがそう答えました。
「そうですか。蘇州のシルクは有名ですよね。本当にありがとう。これまで四十年あまり生きてきたけど、こんなにうれしかった誕生日は初めてだわ」
高級感にあふれるシルクのスカーフを手にとって、かおりの心は喜びで満たされていました。目はうるうるして、思わず涙が出そうになりました。
「佐倉先生、今日の夕方、お時間がおありになりますか」
鄭さんが聞きました。
「もしおありになるようでしたら、佐倉先生のために歓迎パーティーをしようと思っているのです」
「ありがとう。ぜひ参加させていただくわ」
かおりは、にっこり、うなずきました。
その日の夕方、学校の近くのレストランを会場にして、二年一組のクラス全員と日本語担当の先生が集まって、かおりのために盛大なパーティーが開かれました。
「佐倉先生、お誕生日おめでとうございます」
「佐倉先生、ようこそ私たちの学校へいらっしゃいました」
先生方も学生たちも、かおりのことを心から歓迎してくれたので、かおりの心は高揚感にあふれていました。
「私は日本の歌を知っているわ」
学生の一人がそう言って、テレサ・テンの『時の流れに身をまかせ』を、日本語と中国語で歌ってくれました。かおりも歌のお返しをしなければと思って、中国人なら誰でもよく知っている『月亮代表我的心(月は私の心を表す)』を歌って、みんなの拍手喝采を浴びました。
日がたつにつれて、この学校での授業や生活にもだんだん慣れてきて、かおりは毎日、充実した日々を過ごしていました。先生方や学生たちの誕生日をノートに書いてもらったので、誕生日にはお祝いのメッセージを添えて、プレゼントを贈ったりしていました。男の先生にはネクタイ、女の先生にはブラウス、学生たちにはチョコレートをプレゼントしていました。みんなとても喜んでくれました。贈られるよりも贈るほうがずっとうれしい気持ちになれるので、贈るたびに、かおり自身が誰よりも幸せな気持ちになっていました。
11月の半ばに開かれた学園祭のときには、かおりは日本から持ってきたアイリッシュハープを弾いて、先生方や学生たちの前で披露しました。同僚の男性教師の周先生がクラシックギターを弾かれるので、いっしょに合奏したりもしました。『浜辺の歌』や、『蘇州夜曲』や、『時の流れに身をまかせ』といった日本の曲をハープのソロで弾いたり、周先生といっしょに作った『南京情歌』という曲を弾き語りで歌ったりしました。かおりが日本語で詞を書いて、周先生が曲とコードをつけて、二人でデュエットして、みんなの拍手喝采を浴びました。
学園祭の翌日は休みだったので、かおりは周先生に誘われて、二人で玄武湖公園へ行って、湖にボートを浮かべて、楽しいひとときを過ごしました。
「佐倉先生はまだお一人でしたよね」
オールをこぎながら、周先生がそうおっしゃいました。かおりはうなずきました。
「あのー、もしよかったら、これからの人生を、ぼくといっしょに歩んでいきませんか」
思ってもいなかったことを、周先生が急におっしゃったので、かおりはびっくりしました。おっしゃる意味を取り違えたのかもしれないと思ったので、かおりは探るような目で周先生を見ました。
「それって、もしかしたら、私と結婚……」
周先生がうなずきました。
「いやですか。ぼくのこと、嫌いですか」
「……」
かおりには答えようがありませんでした。それよりも何よりも、周先生がまだ独身でいらっしゃるとは、かおりはまったく思ってもいませんでした。
「ぼくはこれまで39年間生きてきましたが、結婚したことはまだ一度もありません。女性と深いお付き合いしたこともありません。ぼくは愛のすべてを教育に捧げてきました。40歳を前にして、今やっと恋愛に対する関心が少しだけ芽生えてきました。佐倉先生にお会いして初めて恋愛感情が芽生えたと言っても過言ではありません」
周先生が真剣な目で、そうおっしゃいました。
「ぼくには佐倉先生が必要なんです。どうかぼくと……」
周先生が哀願するような目で、かおりを見続けていました。
「そんなことを急におっしゃられても困ります。お気持ちはありがたいですが、私はもう四十路を過ぎている女性です。周先生はまだ三十代でいらっしゃるから、もっとお若くて魅力のある女性がふさわしいと思います」
かおりは、そう答えました。それを聞いて、周先生は首を横に振りました。
「三十代といっても、ぎりぎりです。けっして若くはありません」
「でも私よりは三歳お若いです。私より、もっとお若い方といっしょになられたほうが、お子さんもできるだろうし、家のなかに子どもの声が楽しく響いて、幸せな家庭が築かれると思います」
かおりはそう答えました。
「子どもはどうでもいいです。私には学校の子どもがたくさんいます。休みの日には、学校の子どもがよくうちへ遊びにくるので、うちのなかで、にぎやかな声が響いていますよ。それで十分です。学校を卒業した教え子も時々、うちへ遊びに来ます。その子たちが、ぼくにとって、かけがえのない大切な子どもなのです」
周先生が、そうおっしゃいました。それを聞いてかおりは、周先生は本当にあふれんばかりの教育愛に燃えていらっしゃる方だなあと思って、心から敬服しました。
「佐倉先生も、ぼくも音楽が大好きだから、『歌』という子どもを、二人でたくさん作ることができます。佐倉先生が詞を書いて、私が曲をつけて、歌ができたら、その歌を歌って聞かせたり、合奏したりして聴く人の心を和ませることができます。それが、ぼくの理想の人生なのです」
周先生がそうおっしゃいました。
周先生の言葉に、かおりは心が少し傾きかけました。でもやはり冷静に考えると、家庭のなかに自分たちの子どもがいて楽しくて明るい生活をしていくことが、人が幸せになるためには絶対に必要なことだと思っていたので、周先生との関係を友愛以上に発展させてはいけないと思いました。周先生のことは、とても好きなので、周先生のお気持ちを傷つけないように言葉を慎重に選びながら、かおりは周先生に思いを伝えました。
「そうですか。それはとても残念です。これまで39年間生きてきて、初めて恋愛感情を抱かせてくれた佐倉先生と、いっしょになれないのは本当に残念でたまりません。このまま、この湖に落ちて死んでしまいたいくらいです」
それを聞いて、かおりは思わず、おかしくなって、くすくす笑いました。
「オーバーなこと、おっしゃらないでくださいよ。周先生がいなくなったら、周先生の教育愛も終わってしまうではありませんか。周先生にとっては、恋愛よりも教育愛のほうがずっと大切なんでしょう」
「……」
周先生には返す言葉が見つからないでいるようでした。
「大丈夫ですよ。周先生には、そのうちきっと、私よりもはるかに素敵な女性が現れますから」
かおりはそう言って、周先生の気持ちをなだめました。周先生は首をまた横にふりました。
「ぼくは絶対にあきらめません。たとえ5年でも10年でも待ちます」
周先生がそうおっしゃいました。
「困った先生ですね。ふふふ……」
かおりは、おかしくなって、含み笑いを浮かべました。周先生も照れくさそうに笑みを浮かべておられました。
ボートを降りたあと、湖の近くにある喫茶店でコーヒーを飲みながら、家族のことについての話に話題が及びました。
「ぼくの祖父の兄弟は3人いましたが、みんな日本人に殺されました。祖父からその話を聞いたとき、日本人はなんて残虐非道なのだろうと思いました。子ども心に日本人に対 して激しい怒りと強い敵愾心(てきがいしん)を感じたりもしていました。でも今は考え方 が少し変わりました。悪道極まりないことをしたのは、日本の軍人であって、一般の日本 人ではないと思うようになったからです」
「……」
重い話だったので、かおりには、どう答えてよいか分からないでいました。
「先の戦争のときに日本人が中国の方々にとても残忍なことをしたことは私も、もちろん知っています。日本人の一人として本当に申し訳なく思っております」
一呼吸、間を置いてから、かおりは胸の奥深くに抱いていた謝罪の念を、絞りだすような声で吐露しました。
「戦争と言えば、私の父も大変苦労しました。終戦間際に中国の長春で生まれて、中国人に育てられた戦争孤児だからです。路頭にごみのように捨てられていた父をかわいそうに思って中国人が助けてくれなかったなら、父は幼いまま死んでいただろうと思います」
かおりがそう言うと、今度は周先生が答に詰まっておられました。
「戦争は本当に後世まで深いしこりを残しますね」
「そうですね。戦勝国にも敗戦国にも関係なく、今でも深い遺恨が残っていて、後世に永遠に受け継がれていくものだと思います」
かおりと周先生はそう言って、うなずきあっていました。
それからまもなく、かおりと周先生は喫茶店を出て、玄武公園の前にあるバス停から62番のバスに乗って、それぞれの宿舎へ帰っていきました。
それから二週間ほどたった12月の初め、日本語主任の欧先生が授業が終わったあと、
「日本の高校では、どれくらいの学校で中国語が教えられていますか」
と、おたずねになりました。すぐには答えられなかったので、スマートフォンで調べてから
「10校に1校ぐらいの割合です」
と、かおりは答えました。
「数はどれくらいですか。どんな学校で教えられていますか」
欧先生は日本の教育事情に興味がおありのようでした。
「全国で500校ぐらいの高校で教えられています。一流の進学校ではなくて、レベルがそれほど高くない進学校か、商業高校で教えられています」
スマートフォンで得られた情報をもとに、かおりはそう答えました。
「そうですか。卒業後は中国の大学に進学したり、中国で働いたりする学生が多いのでしょうか」
欧先生は興味深そうな顔をして、かおりにききました。
「いえ、そうとばかりも限りません。共通一次試験の問題が英語よりも中国語のほうが簡単に作られているので、英語に自信がない学生が共通一次試験で高得点を取るために勉強していることもあります。大学に進学しない学生が趣味として勉強していることもあります」
かおりはそう答えました。
「そうですか。中国でも似たようなところがあります。田舎の学校では農民の子どもが多いので、学力はあまり高くありません。そのために英語の難しい問題を解くのは苦手だから、中学のときから日本語を勉強して、高校でさらに勉強して、大学入学試験を日本語で受ける学生がたくさんいます」
欧先生が、そうおっしゃいました。
「そうですか。日本では中学校のときに中国語を勉強する学生は、ほとんどいません」
かおりは、そう答えました。
「日本の中学や高校で教えられている外国語と言ったら、英語がほとんどです。これではますます親米派を増やすだけで、アジア諸国への親近感を生む土壌が築かれないのではないかと思って、私はとても危惧しています。日本はアジアの一員ですから、アメリカよりも中国や韓国といった近隣諸国との友好関係や相互理解を今以上に深めていって、揺るぎないものにすることがまず大切ではないかと、私は思っています。そのためにはモノを売ったり買ったりするだけでなく、相互にコミュニケーションが取れるように相手国の言葉や文化を学び合う必要があると思います。これまで日本では明治以後、欧米志向が強まり、中学や高校で教えられる外国語といったら、英語がほとんどでした。しかしそれでも日本人の英語は上手ではありません。日本で生活しているかぎり、英語を話せなくても生活に全然支障はありません。日本では最近、小学校でも英語が教えられるようになりました。しかし私個人の考えとしては、それよりも中学や高校で第二外国語として中国語や韓国語を学ばせるほうがいいと思っています。授業が無理ならクラブ活動でもいいと思っています。中国語は漢字を使う言語だから、英語よりもやさしいと思ったり、親近感を持てる学生もいるはずです」
かおりは熱弁をふるって、思いのすべてを一気にまくしたてました。
「そうですね。私も同感です」
欧先生が、うんうんと、うなずかれました。 かおりは語学が好きだったから、大学で英語を専攻しました。卒業後は高校で英語教師にもなりました。しかし子どものころ、祖母から、曽祖父の妹が長崎に落とされた原子爆弾で、生まれたばかりの赤ちゃんを胸に抱いたまま亡くなっていたことを聞いていたので、原爆を落としたアメリカの言葉である英語が本当はあまり好きではありませんでした。それよりも終戦直後の混乱のなかで、中国に取り残された父を孤児として大切に育ててくれた養父母の言葉である中国語に興味を抱いていました。そのためにかおりは、母の介護をするために高校の教師を辞めたあと、独学で中国語の勉強を始めて、今、こうして中国で働いていたのです。 2014年の7月の初めまで、かおりは南京の田家炳高級中学で働きました。次の新しい赴任校は東北地方のハルピンにある黒竜江大学に決まりました。南京を離れる日が近づくにつれて、かおりは先生方や学生たちとの別れに後ろ髪を引かれるような辛い思いを感じることが多くなりました。最後の日には、先生方がパーティーを開いてくださいました。パーティーの席でかおりは、アイリッシュハープでショパンの『別れの曲』を弾きました。これまで一年間親切にしていただいた先生方への哀別の気持ちをこめて、切々と弾きました。琴線に触れるようなかおりの演奏に、先生方はしんみりした顔をして静かに聞き入っていらっしゃいました。なかでも一番寂しそうな顔をしておられたのは周先生でした。周先生からは、玄武公園でのデート以来、何度もお誘いを受けたので、いっしょに楽器を持ち寄って、静かな公園の片隅で合奏したり、二人で詞と曲を書いて新しい歌を作ったりしていました。いっしょに蘇州や杭州に日帰りの旅行に出かけたこともありました。でも結局、最後まで周先生が待ち望んでおられたような言葉が、かおりの口から聞けなかったので、周先生は思うようにならないもどかしさを感じておられたようでした。 「ハルピンはここから遠いですが、いつか佐倉先生に会いに行きます。ぼくはまだ佐倉先生のことをあきらめたわけではありません」 翌日の朝、高速鉄道の駅まで迎えに来てくださった周先生が、別れ間際に、そうおっしゃいました。
それを聞いて、かおりは、くすっと笑いました。
南京から上海まで高速鉄道で1時間20分かかり、そのあと路線バスでフェリーの乗り場まで行きました。上海と長崎の間を行き来している『オーシャンローズ号』という客船に乗って帰国するためです。長崎まで26時間の長旅でしたが、揺れることはほとんどなく、まるで海上ホテルに泊まっているかのような快適な旅でした。船のなかには大浴場やカラオケ室や卓球台などもあったし、映画の上映やコンサートなどもあっていました。かおりはデッキで海を眺めながらハープを弾いたり、船のなかで知り合った人たちと話をしたり、トランプをしたりして、豪華客船の楽しい旅に酔いしれていました。