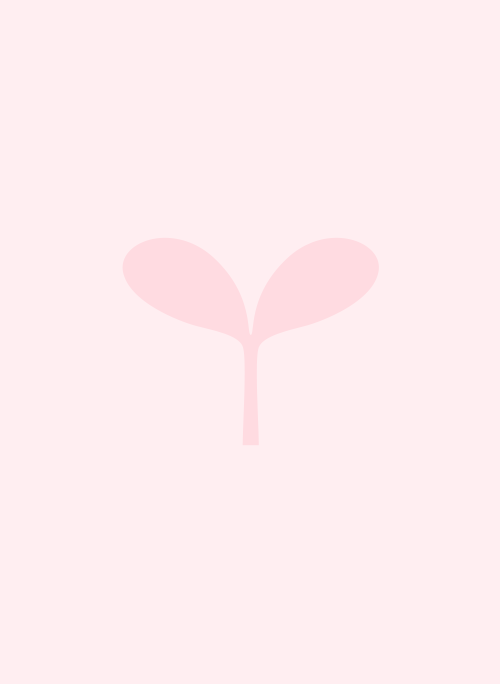佐倉かおりが、中国の湖南省の長沙市にある湖南外国語大学に日本語教師として赴任することが決まったのは、2012年の2月のことでした。40歳のときです。かおりは、それまで長崎の実家で、15年近くパラサイトシングルをしていました。と言っても、働くのが嫌いで、家でぶらぶらしていたわけではありません。地元の国立大学を卒業してから高校の英語教師として福岡の県立高校で働いていましたが、一人暮らしの母親が脳卒中で倒れて介護が必要な身体となったので、仕事を辞めて25歳のときに長崎へ帰ってきて母の介護をしていました。
「本当に申し訳ないねえ。私のために、おまえの大切な青春や仕事を犠牲にしてしまった」
ことあるごとに、母親は、そう言って、すまなさそうな顔をしていました。
「何を言っているのですか、お母さん。私は何もそんなことを少しも気にしていませんよ。小学校のときに、お父さんが亡くなって、それ以来、お母さんは一人で私を育ててくれたし、大学まで出してくれたから、これまでの恩返しをしているだけですよ」
かおりはそう答えて、沈んでいる母親の気持ちを励ましてきました。
その母親も、かおりが39歳のときに遠いところへいってしまいました。きょうだいはなく、親しい友人もいないかおりは、寂しさを紛らわすために外国へ旅に出ることを思い立ちました。かおりはそれまで外国に行ったことは一度もありませんでした。しかし大学の教育学部で英語を専攻していたし、卒業後に英語の教師になったので、外国への興味は、それなりにありました。父親が中国で生まれた残留孤児だったので、中国への興味もありました。子どものころから長崎の中華街によく遊びに行っていたし、大学に入ってからは独学で中国語を勉強したりもしていました。
母親を失った寂しさを紛らわすために、四十九日の法要をすませたあと、かおりは中国へ旅行することにしました。父親が生まれ育った中国へ、いつか機会があったら行ってみたいと、かおりは以前からずっと思っていたからです。長崎空港から飛行機に乗って、初めて行った上海や蘇州の町で、人々の温かさに触れたかおりは、帰国する飛行機のなかで、(日本語教師の資格を取って、中国でぜひ日本語を教えたい)という思いを強く抱くようになりました。そしてそれからすぐに通信教育で日本語教師になるための資格を取るための勉強を始めました。一年後に日本語教育能力検定試験に合格したかおりは、インターネットの求人サイトに出ていた湖南外国語大学の日本語教師に応募しました。幸い採用されたかおりは不惑の年と呼ばれる40歳を迎えていたので、アラフォー女性としての、あらたな生き方を求めて、中国へ渡ることを決意しました。
湖南外国語大学への就職が決まった2012年と言えば、尖閣諸島の領有化の問題をめぐって、日中間の緊張が一番高まっていた時期でした。テレビや新聞では連日のように、中国の各地で起きていた反日デモや暴動の様子が報道されていました。かおりがこれから赴任する湖南省の長沙でも日系デパートのショーウィンドーが投石で割られたり、すし店の店長である日本人が殴られて負傷したり、デパートの前の路上に停めてあった日本製の車に火がつけられて炎上したりする事件が起きていました。
そういった反日的な事件をテレビのニュースで見たり、新聞で目にしたかおりの親戚や知人からは「今、中国へ行くのは危険すぎる。やめたほうがいい」と、忠告されました。心配してくれる気持ちは分からないでもありませんでした。しかし、今こういう情況だからこそ、かえって行くことに意義があるのではないかと思って、かおりは揺らぐ気持ちを抑えながら中国へ行くことを決心しました。
中国の上海にある浦東国際空港に着いて、そのあと飛行機を乗り継いで長沙にある黄花国際空港に到着すると、赴任先である湖南外国語大学の先生方が三人、横断幕や手づくりのプラカードを持って到着ロビーで待っていてくださいました。
「佐倉先生、いらっしゃい」
「ようこそ、佐倉先生」
横断幕やプラカードには、そう書かれていました。思ってもいなかった歓迎ぶりに、かおりは嬉しさよりも照れくささを感じていました。日中関係が緊迫した情況になっている時期にもかかわらず、日本人を温かく迎え入れてくださる中国の先生方の優しさを感じて、迷いを断ち切って、中国へ来てよかったと、かおりは思いました。
「佐倉先生、よくいらっしゃいました。職員一同、佐倉先生のご到着を心からお待ちしておりました」
「こういう時期に決心して来られるのは本当に大変だったと思います。佐倉先生の勇気あるご決断に心から感謝申し上げます」
「けっして危険な目には遭わせませんから、どうかご安心なさってください」
初めてお会いする先生方の歓迎の言葉が心にしみて、かおりの目は、うるうるしていました。涙を流さんばかりの表情で、握手の手を差し伸べてくださったり、熱くハグしてくださったり、肩に軽く手をあてて緊張をほぐしてくださった先生方にかおりは感激しました。
空港から学校の車に乗って大学に着くと、学生たちからも歓迎されました。
「何かあったらすぐにメールや電話をくださいね。いつでもすぐに先生のところへ飛んでいきます」
「絶対に先生を危ない目には遭わせませんからね」
「授業のとき以外は宿舎にじっとしていてくださいね」
「けっして一人で街の中心部には行かないでくださいね」
緊迫した情況のなかで、気遣ってくれる学生の優しさに、かおりの胸は熱くなって、涙がぽろぽろとこぼれました。
この学校で日本人は、かおり一人でした。前任者が先月までいらっしゃったようでしたが、反日デモや暴動がこの町で起きたときに、身の危険を感じて、日本に帰国されたとのことでした。同僚に日本人がいないので寂しく感じるときもありましたが、思いやりにあふれた先生方や学生たちのおかげで、かおりはそれほど不安を感じることはありませんでした。
日本語以外の外国語を学んでいる学生たちも、かおりのことを、とても気遣ってくれました。どの学生も、かおりとすれ違ったり、かおりを見かけたときには、いつも、にこやかな笑顔で「ハロー」と、声をかけてくれました。日本人の私に、どうして「ハロー」なんだろうと、最初、かおりは不思議に思いました。しばらくしてから彼らは日本語が分からないので、英語で声をかけてくれたのだと気がついて、納得がいきました。そんな学生たちに、かおりも「ハロー」と、笑顔であいさつしていました。
そんなある日のこと、かおりは一人で学校の近くの食堂に入っていって、料理を注文しました。生活に少しずつ慣れてきていたし、学校の近くであるという安心感もあって、かおりの心から緊張感が少し薄れかけていました。料理を注文するときの、たどたどしい中国語を耳にしたからでしょうか、隣のテーブルで食事をしていたグループのなかの男性の一人が、つかつかと、かおりの前にやってきました。
「あなたはどこの国の人ですか」
不審そうな顔をしながら、男性が話しかけてきました。目つきが厳しかったので、かおりは不吉な予感がしました。
厳しい目で凝視されたかおりは、ひるみました。おじけづいて、すぐには返答できなかったので、一瞬、間を置いてから、相手の目をさぐるように見ながら「日本人です」と、ぼそぼそっと答えました。するとその途端、男性が「ふん」と言って、冷ややかな視線をかおりに投げかけてきました。そのあと男性は、まるで機関銃で一斉射撃を浴びせるように、だだだだだっと、早口で、かおりにまくしたててきました。何を言っているのか、かおりにはよく分かりませんでした。でも男性が頭から湯気を立てているのが見えました。
(この人は日本や日本人に対して何か強い不満を抱いているようだ)
かおりはそう感じました。立て板に水のように、男性の早口は、すらすらとよどみなく流れ、滝のような勢いで激しく、かおりの頭の上から降ってきました。なだめるすべを持たないかおりに、男性の怒りは、エスカレートしていくばかりです。
(困ったことになった)
思いがけない事態が生じて、かおりは、どうしたらよいか分からないでいました。周りのお客さんも箸を動かす手をとめたり、話をやめて、こちらをじっと見ながら、成り行きを、うかがっていました。お店の人も、思わぬ事態に、どう対処したらよいのか分からないで仲裁に入りあぐねていました。店のなか全体に、ぴりぴりとした緊張感が走り、不穏な空気が流れていました。今、ここにいるのは自分以外は中国人ばかりのように思えたので、誰からも助け舟を出してもらえそうにありません。かおりは焦って、この場から逃げ出したいような衝動に駆られました。まだメニューを注文したばかりだから、逃げ出しても間に合います。かおりは席を立ちかけました。
するとそのとき、少し離れた席で食事をしていた若い女性が慌てた様子で立ち上がって
近づいてきました。
「ちょっと待って」
彼女が、かおりを呼び止めました。彼女はかおりのテーブルのところまで来ると、かおりに言いがかりをつけてきた男性の顔を、きりっと見てから、何か言っていました。話の内容は、かおりにはよく分かりませんでした。かろうじて聞き取れたのは、「この人は学校の先生で、とてもいい人ですよ。私たちはみんな、この先生が大好きです」という言葉だけでした。彼女の言葉を聞いたあと、男性の表情に変化が生じました。荒れ狂った海のように息巻いていた顔から、嵐がおさまったあとの海のような穏やかな顔になるのが見てとれました。男性は、しげしげと、かおりを見つめてから「すまなかった」と言って、自分の席へ戻っていきました。それと同時に、食堂全体に張りつめていた緊張感がほぐれて、お客さんたちは再び箸を動かし始めていました。騒ぎが一件落着したので、かおりもほっとして、立ちかけた席に再び戻りました。
男性の高ぶっていた気持ちを鎮めてくれた彼女は、そのあと自分のテーブルから料理をかおりのテーブルへ持ってきて、かおりと向かい合って食べ始めました。
料理を食べている彼女の顔には、どこかで見覚えがありました。
「助けてくれてありがとう。もしかしたら、あなたは日本語学科の学生さんですか」
かおりは彼女に聞きました。すると彼女は首を横に振りました。
「いいえ、違います。私は日本語学科の学生ではありません。ロシア語学科の学生です」
彼女がそう言ったので、かおりは、びっくりしました。
「えっ、だって、さっき、あなたは言っていたじゃない。『私たちはみんな、この先生が大好き』だって」
すると彼女は、いたずらっこのような笑顔を見せました。
「とっさに思いついた出まかせです」
かおりは、男の人に聞こえないように、耳打ちするように言いました。それを聞いて、かおりは口をぽかんと開けていました。
「じゃあ、さっき言った、いい人とか、みんなが大好きっていうのは、誰か友だちが言っていたの」
「学校で何度か先生を見かけたことがあったので、とっさに機転を利かせたのです」
と、彼女が答えました。
「なるほど、そうだったのか」
かおりは、うなずいていました。
「でも、実際、学校のみんなは、先生のことをいい人だと思っているはずですよ。だって、みんな毎日、笑顔で先生に挨拶しているじゃない」
言われてみれば、確かに、その通りでした。それにしても彼女の機転の良さに助けられたかおりは、感心することしきりでした。
やがて、テーブルの上に、かおりが注文した料理が運ばれてきたので、彼女といっしょにご飯を食べながら、学校の話や日本の話などをして、楽しいひとときを過ごすことができました。
食事を終えて、席を立とうとしたときに、さっき、かおりに、言いがかりをつけてきた隣の席の男性が、「すまなかった」と、もう一度、かおりに謝ってくれました。お詫びのしるしとして、かおりの食事代を払うと言ってくれましたが、かおりは気持ちだけを受け取ることにしました。
お店を出たあと、彼女は少し不安そうな表情で、かおりを見つめました。
「先生、学校を辞めて日本に帰ったりしませんよね。さっきのことで、嫌になったりしませんよね。こんな時期だから、みんな感情的になっているだけなのです」
切々と訴える彼女に、かおりは即座にうなずきました。
「もちろん、帰ったりしませんよ。私は学校やみなさんが大好きですから」
それを聞いて、彼女は、ほっとしたような顔をしました。
「今日は本当にありがとう」
「いえいえ、なんでもありませんよ。先生を助けることができて、私こそ嬉しいです」
彼女はそう言って、帰っていきました。
「本当に申し訳ないねえ。私のために、おまえの大切な青春や仕事を犠牲にしてしまった」
ことあるごとに、母親は、そう言って、すまなさそうな顔をしていました。
「何を言っているのですか、お母さん。私は何もそんなことを少しも気にしていませんよ。小学校のときに、お父さんが亡くなって、それ以来、お母さんは一人で私を育ててくれたし、大学まで出してくれたから、これまでの恩返しをしているだけですよ」
かおりはそう答えて、沈んでいる母親の気持ちを励ましてきました。
その母親も、かおりが39歳のときに遠いところへいってしまいました。きょうだいはなく、親しい友人もいないかおりは、寂しさを紛らわすために外国へ旅に出ることを思い立ちました。かおりはそれまで外国に行ったことは一度もありませんでした。しかし大学の教育学部で英語を専攻していたし、卒業後に英語の教師になったので、外国への興味は、それなりにありました。父親が中国で生まれた残留孤児だったので、中国への興味もありました。子どものころから長崎の中華街によく遊びに行っていたし、大学に入ってからは独学で中国語を勉強したりもしていました。
母親を失った寂しさを紛らわすために、四十九日の法要をすませたあと、かおりは中国へ旅行することにしました。父親が生まれ育った中国へ、いつか機会があったら行ってみたいと、かおりは以前からずっと思っていたからです。長崎空港から飛行機に乗って、初めて行った上海や蘇州の町で、人々の温かさに触れたかおりは、帰国する飛行機のなかで、(日本語教師の資格を取って、中国でぜひ日本語を教えたい)という思いを強く抱くようになりました。そしてそれからすぐに通信教育で日本語教師になるための資格を取るための勉強を始めました。一年後に日本語教育能力検定試験に合格したかおりは、インターネットの求人サイトに出ていた湖南外国語大学の日本語教師に応募しました。幸い採用されたかおりは不惑の年と呼ばれる40歳を迎えていたので、アラフォー女性としての、あらたな生き方を求めて、中国へ渡ることを決意しました。
湖南外国語大学への就職が決まった2012年と言えば、尖閣諸島の領有化の問題をめぐって、日中間の緊張が一番高まっていた時期でした。テレビや新聞では連日のように、中国の各地で起きていた反日デモや暴動の様子が報道されていました。かおりがこれから赴任する湖南省の長沙でも日系デパートのショーウィンドーが投石で割られたり、すし店の店長である日本人が殴られて負傷したり、デパートの前の路上に停めてあった日本製の車に火がつけられて炎上したりする事件が起きていました。
そういった反日的な事件をテレビのニュースで見たり、新聞で目にしたかおりの親戚や知人からは「今、中国へ行くのは危険すぎる。やめたほうがいい」と、忠告されました。心配してくれる気持ちは分からないでもありませんでした。しかし、今こういう情況だからこそ、かえって行くことに意義があるのではないかと思って、かおりは揺らぐ気持ちを抑えながら中国へ行くことを決心しました。
中国の上海にある浦東国際空港に着いて、そのあと飛行機を乗り継いで長沙にある黄花国際空港に到着すると、赴任先である湖南外国語大学の先生方が三人、横断幕や手づくりのプラカードを持って到着ロビーで待っていてくださいました。
「佐倉先生、いらっしゃい」
「ようこそ、佐倉先生」
横断幕やプラカードには、そう書かれていました。思ってもいなかった歓迎ぶりに、かおりは嬉しさよりも照れくささを感じていました。日中関係が緊迫した情況になっている時期にもかかわらず、日本人を温かく迎え入れてくださる中国の先生方の優しさを感じて、迷いを断ち切って、中国へ来てよかったと、かおりは思いました。
「佐倉先生、よくいらっしゃいました。職員一同、佐倉先生のご到着を心からお待ちしておりました」
「こういう時期に決心して来られるのは本当に大変だったと思います。佐倉先生の勇気あるご決断に心から感謝申し上げます」
「けっして危険な目には遭わせませんから、どうかご安心なさってください」
初めてお会いする先生方の歓迎の言葉が心にしみて、かおりの目は、うるうるしていました。涙を流さんばかりの表情で、握手の手を差し伸べてくださったり、熱くハグしてくださったり、肩に軽く手をあてて緊張をほぐしてくださった先生方にかおりは感激しました。
空港から学校の車に乗って大学に着くと、学生たちからも歓迎されました。
「何かあったらすぐにメールや電話をくださいね。いつでもすぐに先生のところへ飛んでいきます」
「絶対に先生を危ない目には遭わせませんからね」
「授業のとき以外は宿舎にじっとしていてくださいね」
「けっして一人で街の中心部には行かないでくださいね」
緊迫した情況のなかで、気遣ってくれる学生の優しさに、かおりの胸は熱くなって、涙がぽろぽろとこぼれました。
この学校で日本人は、かおり一人でした。前任者が先月までいらっしゃったようでしたが、反日デモや暴動がこの町で起きたときに、身の危険を感じて、日本に帰国されたとのことでした。同僚に日本人がいないので寂しく感じるときもありましたが、思いやりにあふれた先生方や学生たちのおかげで、かおりはそれほど不安を感じることはありませんでした。
日本語以外の外国語を学んでいる学生たちも、かおりのことを、とても気遣ってくれました。どの学生も、かおりとすれ違ったり、かおりを見かけたときには、いつも、にこやかな笑顔で「ハロー」と、声をかけてくれました。日本人の私に、どうして「ハロー」なんだろうと、最初、かおりは不思議に思いました。しばらくしてから彼らは日本語が分からないので、英語で声をかけてくれたのだと気がついて、納得がいきました。そんな学生たちに、かおりも「ハロー」と、笑顔であいさつしていました。
そんなある日のこと、かおりは一人で学校の近くの食堂に入っていって、料理を注文しました。生活に少しずつ慣れてきていたし、学校の近くであるという安心感もあって、かおりの心から緊張感が少し薄れかけていました。料理を注文するときの、たどたどしい中国語を耳にしたからでしょうか、隣のテーブルで食事をしていたグループのなかの男性の一人が、つかつかと、かおりの前にやってきました。
「あなたはどこの国の人ですか」
不審そうな顔をしながら、男性が話しかけてきました。目つきが厳しかったので、かおりは不吉な予感がしました。
厳しい目で凝視されたかおりは、ひるみました。おじけづいて、すぐには返答できなかったので、一瞬、間を置いてから、相手の目をさぐるように見ながら「日本人です」と、ぼそぼそっと答えました。するとその途端、男性が「ふん」と言って、冷ややかな視線をかおりに投げかけてきました。そのあと男性は、まるで機関銃で一斉射撃を浴びせるように、だだだだだっと、早口で、かおりにまくしたててきました。何を言っているのか、かおりにはよく分かりませんでした。でも男性が頭から湯気を立てているのが見えました。
(この人は日本や日本人に対して何か強い不満を抱いているようだ)
かおりはそう感じました。立て板に水のように、男性の早口は、すらすらとよどみなく流れ、滝のような勢いで激しく、かおりの頭の上から降ってきました。なだめるすべを持たないかおりに、男性の怒りは、エスカレートしていくばかりです。
(困ったことになった)
思いがけない事態が生じて、かおりは、どうしたらよいか分からないでいました。周りのお客さんも箸を動かす手をとめたり、話をやめて、こちらをじっと見ながら、成り行きを、うかがっていました。お店の人も、思わぬ事態に、どう対処したらよいのか分からないで仲裁に入りあぐねていました。店のなか全体に、ぴりぴりとした緊張感が走り、不穏な空気が流れていました。今、ここにいるのは自分以外は中国人ばかりのように思えたので、誰からも助け舟を出してもらえそうにありません。かおりは焦って、この場から逃げ出したいような衝動に駆られました。まだメニューを注文したばかりだから、逃げ出しても間に合います。かおりは席を立ちかけました。
するとそのとき、少し離れた席で食事をしていた若い女性が慌てた様子で立ち上がって
近づいてきました。
「ちょっと待って」
彼女が、かおりを呼び止めました。彼女はかおりのテーブルのところまで来ると、かおりに言いがかりをつけてきた男性の顔を、きりっと見てから、何か言っていました。話の内容は、かおりにはよく分かりませんでした。かろうじて聞き取れたのは、「この人は学校の先生で、とてもいい人ですよ。私たちはみんな、この先生が大好きです」という言葉だけでした。彼女の言葉を聞いたあと、男性の表情に変化が生じました。荒れ狂った海のように息巻いていた顔から、嵐がおさまったあとの海のような穏やかな顔になるのが見てとれました。男性は、しげしげと、かおりを見つめてから「すまなかった」と言って、自分の席へ戻っていきました。それと同時に、食堂全体に張りつめていた緊張感がほぐれて、お客さんたちは再び箸を動かし始めていました。騒ぎが一件落着したので、かおりもほっとして、立ちかけた席に再び戻りました。
男性の高ぶっていた気持ちを鎮めてくれた彼女は、そのあと自分のテーブルから料理をかおりのテーブルへ持ってきて、かおりと向かい合って食べ始めました。
料理を食べている彼女の顔には、どこかで見覚えがありました。
「助けてくれてありがとう。もしかしたら、あなたは日本語学科の学生さんですか」
かおりは彼女に聞きました。すると彼女は首を横に振りました。
「いいえ、違います。私は日本語学科の学生ではありません。ロシア語学科の学生です」
彼女がそう言ったので、かおりは、びっくりしました。
「えっ、だって、さっき、あなたは言っていたじゃない。『私たちはみんな、この先生が大好き』だって」
すると彼女は、いたずらっこのような笑顔を見せました。
「とっさに思いついた出まかせです」
かおりは、男の人に聞こえないように、耳打ちするように言いました。それを聞いて、かおりは口をぽかんと開けていました。
「じゃあ、さっき言った、いい人とか、みんなが大好きっていうのは、誰か友だちが言っていたの」
「学校で何度か先生を見かけたことがあったので、とっさに機転を利かせたのです」
と、彼女が答えました。
「なるほど、そうだったのか」
かおりは、うなずいていました。
「でも、実際、学校のみんなは、先生のことをいい人だと思っているはずですよ。だって、みんな毎日、笑顔で先生に挨拶しているじゃない」
言われてみれば、確かに、その通りでした。それにしても彼女の機転の良さに助けられたかおりは、感心することしきりでした。
やがて、テーブルの上に、かおりが注文した料理が運ばれてきたので、彼女といっしょにご飯を食べながら、学校の話や日本の話などをして、楽しいひとときを過ごすことができました。
食事を終えて、席を立とうとしたときに、さっき、かおりに、言いがかりをつけてきた隣の席の男性が、「すまなかった」と、もう一度、かおりに謝ってくれました。お詫びのしるしとして、かおりの食事代を払うと言ってくれましたが、かおりは気持ちだけを受け取ることにしました。
お店を出たあと、彼女は少し不安そうな表情で、かおりを見つめました。
「先生、学校を辞めて日本に帰ったりしませんよね。さっきのことで、嫌になったりしませんよね。こんな時期だから、みんな感情的になっているだけなのです」
切々と訴える彼女に、かおりは即座にうなずきました。
「もちろん、帰ったりしませんよ。私は学校やみなさんが大好きですから」
それを聞いて、彼女は、ほっとしたような顔をしました。
「今日は本当にありがとう」
「いえいえ、なんでもありませんよ。先生を助けることができて、私こそ嬉しいです」
彼女はそう言って、帰っていきました。