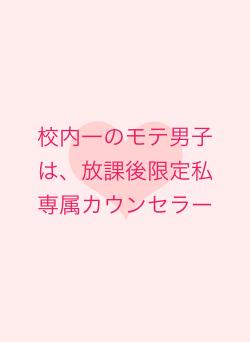「奏吾さん、私の実家についてきてくれませんか?菜々に言われたからじゃない。私ももう逃げたくないんです」
私の言葉を聞いて、奏吾さんは頷いた。
「分かった。でも……」
奏吾さんが私の頭を優しく撫でる。
「いつでも隣に俺がいることを忘れないで。それにもう昔の俺じゃないから」
「……?」
「ずっと陽月を助ける準備をしてたってこと。もう深井財閥の好きにはさせない。二度と陽月を侮辱させない」
すると、奏吾さんが私の耳元に口を近づける。
「陽月に惚れてる俺は、案外心強いよ?」
そう言って、奏吾さんはいつも通り微笑んだ。
私の言葉を聞いて、奏吾さんは頷いた。
「分かった。でも……」
奏吾さんが私の頭を優しく撫でる。
「いつでも隣に俺がいることを忘れないで。それにもう昔の俺じゃないから」
「……?」
「ずっと陽月を助ける準備をしてたってこと。もう深井財閥の好きにはさせない。二度と陽月を侮辱させない」
すると、奏吾さんが私の耳元に口を近づける。
「陽月に惚れてる俺は、案外心強いよ?」
そう言って、奏吾さんはいつも通り微笑んだ。