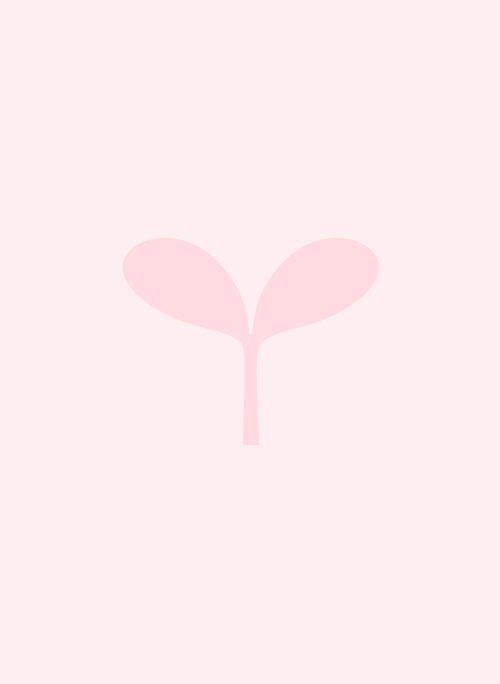第10話 放課後の図書室
その日の放課後、かおりちゃんたち、五年一組のクラスの子全員と、担任の岩山先生が、図書室でさっそくカンボジアのことを調べ始めていた。
かおりちゃんが朝の会で話したとおりに、カンボジアにはタケオという町があることが分かったので、
「本当だ ! 」
と言って、なぜか、みんな、くすくす笑っていた。
「カンボジアでは今から二十五年ぐらい前まで、二十年以上も内戦が続いていて、多くの人が亡くなったり、けがをした人がたくさんいるって、この本には書いてあるわ。内戦というのは、同じ国の人同士が戦うことよ」
岩山先生がそう言うと、悲しそうな目をしたり、なまりのようなため息をついている子がいた。
「先生、この本には、内戦が終わった今でも、カンボジアのあちこちに地雷がまだ五百万個以上も埋められたままになっていて、毎年、たくさんの人が命を落としたり、手足を吹き飛ばされているって書いてあるわ」
かおりちゃんが、顔を梅雨空のように曇らせていた。
「ほら、見て、この子。服は汚れているし、足は裸足よ」
白いセーターを着て、赤いスカートをはいた女の子が、哀れみ深い目で写真を見ていた。
「でも顔の表情は、ヒマワリのように明るくて、目がきらきらと輝いているわ」
「そうねえ、楽しそうな顔をしているわね」
「どの子もみんな、日によく焼けているね。暑い国に住んでいるのかしら」
「そうみたいよ。カンボジアには雨季と乾季があって、一年じゅう、暑いところだそうよ」
「だからみんな浅黒い顔をしているんだね」
「カンボジアには、アンコールワットといって、世界的にも有名な遺跡があって、毎年、多くの観光客が訪れているそうよ」
色が白くて、やせている男の子が、遺跡の写真に見入っていた。
「カンボジアの言葉で、『こんにちは』は、『チュムリァプ スォー』、『ありがとう』は、『オークン』と言うんだって」
髪に赤いリボンを結んだ女の子が、隣の席の、おとなしそうな男の子に教えていた。
「『ありがとう』は、『オークン』か。関西弁の『おおきに』に似ているなぁ」
男の子は、そう答えてから、くすくすと含み笑いをしていた。
「あっ、そうか、岡村君は神戸の出身だったわね」
去年の春、神戸の三宮というところから武雄に引っ越してきて、あか抜けしていた岡村君のことを、かおりちゃんは思い出していた。
「カンボジアで内戦が続いていたときには、どれくらいの人たちが戦争で亡くなったのですか ? 」
かおりちゃんの隣の席にすわっていた女の子が、岩山先生に聞いていた。
「この本によると、三百万から四百万もの人たちが殺されたと書かれているわ。特に、ポル・ポト派と呼ばれる人たちが政権を握っていた四年ぐらいの間には二百万近い人たちが殺されたそうよ。カンボジアの人口は一千二百万人ぐらいだから、わずか四年ぐらいの間に、国民の六人に一人は殺されたことになるのよね」
岩山先生の目から涙があふれそうになっていた。
「そんなにひどいことがおこなわれていたのは、いつごろのことですか ? 」
さっきの女の子が聞いていた。
「そんなに遠い昔のことではないのよ。今から四十年ぐらい前のことだから、君たちのおとうさんや、おかあさんが生まれたころのことよ」
岩山先生は子どもたちの反応を見るために、一人ひとりの顔をゆっくりと見回していた。
「どうしてそんなにひどいことがおこなわれていたのですか ? 」
かおりちゃんが聞いた。
「殺された人たちの中には、学校の先生や、お医者さんや、お寺のお坊さんなどが特に多かったそうよ。その人たちは知識をふりかざして政府にたてついたり、『政府は間違っている』と人に話す人だと思われていたからだそうよ」
「ひどいですね」
かおりちゃんが、ため息をついていた。
岩山先生は、うなずいてから、さらに話を続けた。
「内戦が始まる前には、学校の先生は二万人以上いたそうだけど、ポル・ポト派によって虐殺がおこなわれた直後には、二千八百人ぐらいにまで減ってしまったそうよ。学校や病院やお寺は壊されたから、子どもたちは学校に行けなくなったし、病気やけがをしても病院に行けなくなったって」
岩山先生の話に、図書室の中が、よどんだ空気に包まれていた。
「学校に行けなくなった子どもたちは、家で遊んでいたのですか ? 」
男の子が岩山先生に聞いていた。
「いえ、そうではないみたいよ。子どもたちは七歳になったら、親から離れ離れにさせられて、特別な施設に連れて行かれて、偏った考え方を教えこまれたみたいよ。教科書を読むと、知識や知恵がついて指導者にたてつくからだめだとして、取り上げられて燃やされたみたい」
岩山先生は本を読むのも辛そうだった。
「でも先生、今は内戦が終わってから、二十年以上たっているので、学校や病院もできてきているし、店には食料品があふれているって書いてあるよ。道路も混んでいてバイクや自転車がたくさん走っているって」
紺色のセーターを着た男の子が答えていた。
「確かにそういう状況になってきているのかもしれないわね。でもそれは大都市での光景であって、田舎のほうに行けば、今もまだ人々の暮らしは、それほど豊かではないみたいよ。それに地雷がまだ五百万個以上も埋められたままになっているので、人々が今も危険と隣り合わせの生活をしていることには変わりはないのよ」
岩山先生の説明に、子どもたちはしんみりと聞き入っていた。
「先生、この本によれば、子どもが地雷を踏んだら、百人のうちの八十五人は病院に運ばれる前に息絶えていると書かれているわ」
テーブルをはさんで岩山先生の真向かいの席にすわっていた女の子がそう言った。
「えっ、そんなに ? 」
岩山先生がびっくりしていた。
「どうしてだろう ? 子どもは体が小さくて、体力がないので、地雷を踏んで足を吹き飛ばされたら、ショックで病院に運ばれる前に亡くなってしまうのかもしれないわねぇ。かわいそう」
岩山先生がつぶやくような声で言った。
「先生、この本には、カンボジアでは今、十五歳以下の子どもの数が、全人口の半分以上を占めていると書かれているわ」
緑色のジャンパーを着た女の子が言った。
「それはすごい割合だわねぇ。子どもの数が、カンボジアではそんなに多いとは先生も知らなかったわ」
岩山先生が意外そうな顔をしていた。
「この本にはこんなことも書いてあるわ」
緑色のジャンパーを着た女の子が話を続けた。
「カンボジアでは、子どもたちの教育の問題が、地雷の撤去の問題と並んで、重要な社会問題になっているって。学校はあっても、家が貧しかったり、学校が遠かったりするために、小学校に入学しない子どもが十人中、二人ぐらいはいるらしい。入学しても卒業できる子どもは百人中、十四人ぐらいだって」
「えっ、たったそれだけしか、小学校を卒業しないの ? 」
かおりちゃんが、びっくりしたような顔をしていた。
「学校で勉強している子どものうち、教科書を持っている子どもは五人に一人ぐらいだそうよ。ノートや鉛筆も不足していて、ノートを書き終えたら、消していって書いているらしい。鉛筆も書けなくなるまで使っているそう」
女の子の話を、岩山先生もクラスのみんなも、身につまされるような思いを感じながら、静かに聞いていた。
それからまもなく、下校の時間を告げるチャイムが鳴った。校内に残っている子どもに下校をうながす放送が流れたので、岩山先生がはっとして、腕時計を見た。
「あら、もうこんな時間 ! 」
岩山先生がびっくりしたような声で、そう言った。
「じゃあ、みんな今日はこれくらいにしておこうね」
岩山先生がそう言うと、クラスのみんなは、にっこり、うなずいてから、本を元の場所へ戻し始めていた。
その日の放課後、かおりちゃんたち、五年一組のクラスの子全員と、担任の岩山先生が、図書室でさっそくカンボジアのことを調べ始めていた。
かおりちゃんが朝の会で話したとおりに、カンボジアにはタケオという町があることが分かったので、
「本当だ ! 」
と言って、なぜか、みんな、くすくす笑っていた。
「カンボジアでは今から二十五年ぐらい前まで、二十年以上も内戦が続いていて、多くの人が亡くなったり、けがをした人がたくさんいるって、この本には書いてあるわ。内戦というのは、同じ国の人同士が戦うことよ」
岩山先生がそう言うと、悲しそうな目をしたり、なまりのようなため息をついている子がいた。
「先生、この本には、内戦が終わった今でも、カンボジアのあちこちに地雷がまだ五百万個以上も埋められたままになっていて、毎年、たくさんの人が命を落としたり、手足を吹き飛ばされているって書いてあるわ」
かおりちゃんが、顔を梅雨空のように曇らせていた。
「ほら、見て、この子。服は汚れているし、足は裸足よ」
白いセーターを着て、赤いスカートをはいた女の子が、哀れみ深い目で写真を見ていた。
「でも顔の表情は、ヒマワリのように明るくて、目がきらきらと輝いているわ」
「そうねえ、楽しそうな顔をしているわね」
「どの子もみんな、日によく焼けているね。暑い国に住んでいるのかしら」
「そうみたいよ。カンボジアには雨季と乾季があって、一年じゅう、暑いところだそうよ」
「だからみんな浅黒い顔をしているんだね」
「カンボジアには、アンコールワットといって、世界的にも有名な遺跡があって、毎年、多くの観光客が訪れているそうよ」
色が白くて、やせている男の子が、遺跡の写真に見入っていた。
「カンボジアの言葉で、『こんにちは』は、『チュムリァプ スォー』、『ありがとう』は、『オークン』と言うんだって」
髪に赤いリボンを結んだ女の子が、隣の席の、おとなしそうな男の子に教えていた。
「『ありがとう』は、『オークン』か。関西弁の『おおきに』に似ているなぁ」
男の子は、そう答えてから、くすくすと含み笑いをしていた。
「あっ、そうか、岡村君は神戸の出身だったわね」
去年の春、神戸の三宮というところから武雄に引っ越してきて、あか抜けしていた岡村君のことを、かおりちゃんは思い出していた。
「カンボジアで内戦が続いていたときには、どれくらいの人たちが戦争で亡くなったのですか ? 」
かおりちゃんの隣の席にすわっていた女の子が、岩山先生に聞いていた。
「この本によると、三百万から四百万もの人たちが殺されたと書かれているわ。特に、ポル・ポト派と呼ばれる人たちが政権を握っていた四年ぐらいの間には二百万近い人たちが殺されたそうよ。カンボジアの人口は一千二百万人ぐらいだから、わずか四年ぐらいの間に、国民の六人に一人は殺されたことになるのよね」
岩山先生の目から涙があふれそうになっていた。
「そんなにひどいことがおこなわれていたのは、いつごろのことですか ? 」
さっきの女の子が聞いていた。
「そんなに遠い昔のことではないのよ。今から四十年ぐらい前のことだから、君たちのおとうさんや、おかあさんが生まれたころのことよ」
岩山先生は子どもたちの反応を見るために、一人ひとりの顔をゆっくりと見回していた。
「どうしてそんなにひどいことがおこなわれていたのですか ? 」
かおりちゃんが聞いた。
「殺された人たちの中には、学校の先生や、お医者さんや、お寺のお坊さんなどが特に多かったそうよ。その人たちは知識をふりかざして政府にたてついたり、『政府は間違っている』と人に話す人だと思われていたからだそうよ」
「ひどいですね」
かおりちゃんが、ため息をついていた。
岩山先生は、うなずいてから、さらに話を続けた。
「内戦が始まる前には、学校の先生は二万人以上いたそうだけど、ポル・ポト派によって虐殺がおこなわれた直後には、二千八百人ぐらいにまで減ってしまったそうよ。学校や病院やお寺は壊されたから、子どもたちは学校に行けなくなったし、病気やけがをしても病院に行けなくなったって」
岩山先生の話に、図書室の中が、よどんだ空気に包まれていた。
「学校に行けなくなった子どもたちは、家で遊んでいたのですか ? 」
男の子が岩山先生に聞いていた。
「いえ、そうではないみたいよ。子どもたちは七歳になったら、親から離れ離れにさせられて、特別な施設に連れて行かれて、偏った考え方を教えこまれたみたいよ。教科書を読むと、知識や知恵がついて指導者にたてつくからだめだとして、取り上げられて燃やされたみたい」
岩山先生は本を読むのも辛そうだった。
「でも先生、今は内戦が終わってから、二十年以上たっているので、学校や病院もできてきているし、店には食料品があふれているって書いてあるよ。道路も混んでいてバイクや自転車がたくさん走っているって」
紺色のセーターを着た男の子が答えていた。
「確かにそういう状況になってきているのかもしれないわね。でもそれは大都市での光景であって、田舎のほうに行けば、今もまだ人々の暮らしは、それほど豊かではないみたいよ。それに地雷がまだ五百万個以上も埋められたままになっているので、人々が今も危険と隣り合わせの生活をしていることには変わりはないのよ」
岩山先生の説明に、子どもたちはしんみりと聞き入っていた。
「先生、この本によれば、子どもが地雷を踏んだら、百人のうちの八十五人は病院に運ばれる前に息絶えていると書かれているわ」
テーブルをはさんで岩山先生の真向かいの席にすわっていた女の子がそう言った。
「えっ、そんなに ? 」
岩山先生がびっくりしていた。
「どうしてだろう ? 子どもは体が小さくて、体力がないので、地雷を踏んで足を吹き飛ばされたら、ショックで病院に運ばれる前に亡くなってしまうのかもしれないわねぇ。かわいそう」
岩山先生がつぶやくような声で言った。
「先生、この本には、カンボジアでは今、十五歳以下の子どもの数が、全人口の半分以上を占めていると書かれているわ」
緑色のジャンパーを着た女の子が言った。
「それはすごい割合だわねぇ。子どもの数が、カンボジアではそんなに多いとは先生も知らなかったわ」
岩山先生が意外そうな顔をしていた。
「この本にはこんなことも書いてあるわ」
緑色のジャンパーを着た女の子が話を続けた。
「カンボジアでは、子どもたちの教育の問題が、地雷の撤去の問題と並んで、重要な社会問題になっているって。学校はあっても、家が貧しかったり、学校が遠かったりするために、小学校に入学しない子どもが十人中、二人ぐらいはいるらしい。入学しても卒業できる子どもは百人中、十四人ぐらいだって」
「えっ、たったそれだけしか、小学校を卒業しないの ? 」
かおりちゃんが、びっくりしたような顔をしていた。
「学校で勉強している子どものうち、教科書を持っている子どもは五人に一人ぐらいだそうよ。ノートや鉛筆も不足していて、ノートを書き終えたら、消していって書いているらしい。鉛筆も書けなくなるまで使っているそう」
女の子の話を、岩山先生もクラスのみんなも、身につまされるような思いを感じながら、静かに聞いていた。
それからまもなく、下校の時間を告げるチャイムが鳴った。校内に残っている子どもに下校をうながす放送が流れたので、岩山先生がはっとして、腕時計を見た。
「あら、もうこんな時間 ! 」
岩山先生がびっくりしたような声で、そう言った。
「じゃあ、みんな今日はこれくらいにしておこうね」
岩山先生がそう言うと、クラスのみんなは、にっこり、うなずいてから、本を元の場所へ戻し始めていた。