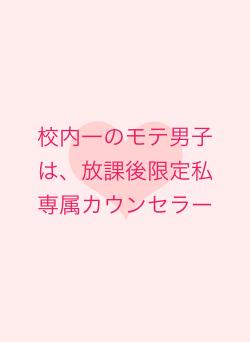「さ、そろそろ帰るか」
護くんの言葉に私は頷いて、二人で駅に向かって歩き出す。
護くんと私は路線は反対方向だけれど、駅まで行くのは同じ。
駅で解散になるのは、二人とも当たり前のように察していた。
しかし、カフェから駅の丁度中心くらいの場所で護くんが突然足を止めた。
すぐに気づいて振り返った私が見たのは、何故かどこか苦しそうな護くんの表情だった。
そんな苦しそうな表情のまま、護くんは私の名前をもう一度呼ぶ。
「想代」
「護くん……? どうかした?」
「俺は……」
その時、何かを言いかけた護くんの瞳が驚いたように大きく見開かれた。
護くんの視線は私の後ろの方向を見ていて、私も反射的に反対方向を振り返った。
「護」
護くんと顔を合わせて名前を呼ぶのは、スーツ姿がよく似合っているスタイルの良い男性。
派手すぎないのに高級感のあるスーツはその男性の雰囲気にぴったりで。
その男性は私の勤める会社の社長、本間 史桜だった。
護くんの言葉に私は頷いて、二人で駅に向かって歩き出す。
護くんと私は路線は反対方向だけれど、駅まで行くのは同じ。
駅で解散になるのは、二人とも当たり前のように察していた。
しかし、カフェから駅の丁度中心くらいの場所で護くんが突然足を止めた。
すぐに気づいて振り返った私が見たのは、何故かどこか苦しそうな護くんの表情だった。
そんな苦しそうな表情のまま、護くんは私の名前をもう一度呼ぶ。
「想代」
「護くん……? どうかした?」
「俺は……」
その時、何かを言いかけた護くんの瞳が驚いたように大きく見開かれた。
護くんの視線は私の後ろの方向を見ていて、私も反射的に反対方向を振り返った。
「護」
護くんと顔を合わせて名前を呼ぶのは、スーツ姿がよく似合っているスタイルの良い男性。
派手すぎないのに高級感のあるスーツはその男性の雰囲気にぴったりで。
その男性は私の勤める会社の社長、本間 史桜だった。