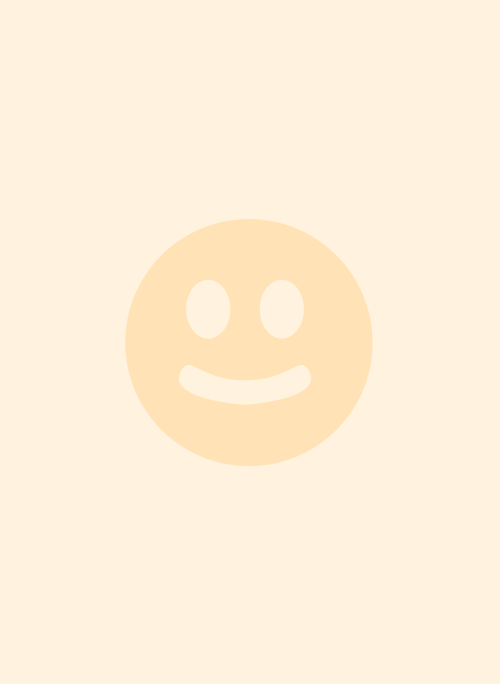診察室のドアが閉まると、外の喧騒が遠ざかり、静寂が落ちた。
成美は母と並んで椅子に座っている。目の前には、カルテを開いたままの主治医・川瀬がいる。
「検査結果は安定しています。ただ……手術は避けられません」
その声は淡々としていたが、言葉の一つ一つが重く響いた。
「予定日は九月五日です」
母が小さく息をのむ。成美は視線を落とし、手をぎゅっと握った。
「成功率は?」
「七割です」
短い答えが空気を張りつめさせた。
母は唇をかみ、涙をこらえる。
「そんなに……危険なんですか」
「大きな手術です。でも、今のままではもっと危険です」
川瀬の目は真剣だった。
診察室を出ると、母はハンカチで目を押さえた。
「ごめんね、成美。怖い思いさせて」
「……大丈夫」
そう言ったが、心臓の奥が締めつけられるように痛んだ。
病院を出ると、夕暮れの空は赤く染まっていた。
公園に寄り道した成美はベンチに座り、空を仰ぐ。
(七割……三割は失敗?)
足が震え、呼吸が浅くなる。
その時、背後から声がした。
「成美!」
振り返ると岳が立っていた。
「……どうしたの、そんな顔」
成美は首を振るが、涙があふれて止まらない。
岳はためらいもなく隣に座り、肩に手を置いた。
「泣いていいよ」
その一言に、堰を切ったように嗚咽が漏れた。
しばらく泣き続け、ようやく呼吸が整ったころ、岳がそっとハンカチを差し出した。
「ありがと……」
「聞いてもいい?」
成美は迷ったが、うなずく。
「九月に手術するの。……成功率は七割だって」
「七割……」岳は目を伏せ、しばらく沈黙した後に顔を上げた。
「三割は、怖いか?」
「怖いに決まってる……でも、やらなきゃもっと危ないんだって」
声が震え、また涙がこぼれそうになる。
岳はベンチから立ち上がり、両手を腰に当てた。
「なあ、俺さ、成功すると信じてる。だから――今は普通に過ごそう」
「普通に?」
「そう。勉強して、笑って、くだらないことでケンカして……それでいい」
成美は少し笑った。
「……ありがとう。なんか、少し楽になった」
その後、二人は並んで歩き出した。夕焼けの中で影が長く伸びる。
「なあ、手術終わったら何したい?」岳が問いかけた。
「花火、また見たいな。ちゃんと屋上で」
「決まりだな。じゃあ俺、夏休み中に準備しとく」
その言葉は、暗闇に差し込む光のように成美の心を照らした。
家に帰ると母が台所に立っていた。目はまだ赤いが、いつもどおり夕飯を作っている。
「おかえり。……大丈夫?」
「うん」
成美は笑顔を作った。
母はその顔を見て、少しだけ安堵したように微笑んだ。
夜、自室でベッドに横になると、昼間のことが頭をよぎった。
(怖い。でも……私、まだやりたいことある)
胸に手を当てると、鼓動がゆっくりと落ち着いていくのを感じた。
翌日、岳は真菜と太陽、哲平、百合子に話をした。
「成美、九月に手術するんだって」
皆、一瞬言葉を失った。
真菜が小さくつぶやく。「……だから、最近無理しなかったんだ」
「でな、手術まで普通に過ごしたいって言ってた」
岳の言葉に、太陽が手を挙げる。
「じゃあさ、何か一緒にできること考えようぜ」
「例えば?」哲平が首をかしげる。
「この前の探検も楽しかっただろ? ああいうの、もっと増やすんだよ」
百合子も頷いた。「放送委員の機材も使えるし、思い出いっぱい作ろうよ」
その日の放課後、成美の机に一枚のメモが置かれていた。
〈今日の帰り、公園集合〉
行ってみると、皆が待っていた。
「成美、これからの時間、ぜんぶ一緒に楽しもう」
岳が差し出したのは、あの「夢の計画ノート」だった。
新しいページには大きく書かれていた。
〈九月五日までの思い出リスト〉
成美は泣き笑いしながら、ペンを取った。
公園のベンチに腰掛けたまま、成美はペンを握りしめた。ページに視線を落とすと、岳が覗き込みながら微笑む。
「書きたいこと、ある?」
「うん……でも、いっぱいあるかも」
声は少し震えていたが、その目は決意を帯びていた。
まず最初に記したのは〈屋上で花火〉。前に書いた願いを、もう一度大きく書き直した。その下に、海沿い散策やみんなでの写真撮影、夏祭りでの浴衣、図書室合宿勉強会……次々と浮かんでくる願いがペンの先からあふれ出した。
「こんなにやりたいことあったんだな……」自分で驚いてつぶやくと、真菜が微笑む。
「いいじゃん。全部やろうよ。できるところまででいい」
「でも、時間が――」
「関係ないよ」太陽が腕を組んで笑う。「時間がないなら、その分楽しくすりゃいい」
百合子も手を叩いた。「放送室のスピーカーも使おうよ。音楽流して花火見たら絶対きれいだよ」
「俺は動画撮るからな」哲平がドローンの写真を指さす。「映像編集して、夏の記録にする」
岳が頷く。「ほらな。みんなもう動き出してる」
成美はその光景を見つめながら、胸が熱くなった。(この人たちと過ごせる時間が、私の宝物なんだ)
帰り道、夕焼けが街を黄金色に染めていた。成美は少しだけ歩調を緩め、肩にかかったリュックの重さを感じた。以前なら、この重ささえ負担に思っていたのに、今はなぜか心地よい。
家に着くと、母が夕飯の支度をしていた。包丁の音がリズムよく響き、味噌汁の香りが広がる。
「おかえり、今日は遅かったね」
「みんなと話してた」
母が一瞬だけ手を止めて成美の顔を見た。赤かった目はまだ完全には乾いていない。でもその表情には、少しだけ安心の色が宿っていた。
「……友達、大事にね」
「うん」
夕食の後、自室に戻った成美はノートを開き、書き加えた。
〈怖いけど、生きたい〉
その言葉を見て、胸がじんわり熱くなる。(手術が怖いのは変わらない。でも――生きたい)
夜、ベッドに潜り込むと、昼間の出来事が鮮明に蘇った。病院の白い壁、川瀬医師の真剣な顔、母の涙、岳のまっすぐな瞳。そして友達の笑顔。全部が絡まり合って、涙がまたこぼれた。でもそれは、昼間の絶望とは違う涙だった。
(泣いていいよって言われて、救われたな……)
窓の外に星がひとつ光っている。成美は胸の上で手を合わせた。
(生きたい。みんなと、もっとたくさん笑いたい)
翌日からの日々は、ほんの少しだけ色づき始めた。教室の窓から差し込む朝日がまぶしく感じられ、通学路の坂道の草花に目が向いた。病気の痛みが消えたわけではない。でも、それを抱えたまま笑う自分がいた。
放課後、岳が言った。「なあ、次は砂浜の掃除ボランティアどうだ? タイムカプセル探そうぜ」
「タイムカプセル?」成美が首をかしげる。
「ほら、小さいころ埋めたやつ。あるかもよ」
太陽が身を乗り出した。「おもしれーじゃん!」
真菜と百合子も笑顔で頷いた。
「……うん、行きたい」成美は小さく笑った。
その笑顔を見て、岳は小さく拳を握った。(よし、絶対に守る。この日常を)
成美は母と並んで椅子に座っている。目の前には、カルテを開いたままの主治医・川瀬がいる。
「検査結果は安定しています。ただ……手術は避けられません」
その声は淡々としていたが、言葉の一つ一つが重く響いた。
「予定日は九月五日です」
母が小さく息をのむ。成美は視線を落とし、手をぎゅっと握った。
「成功率は?」
「七割です」
短い答えが空気を張りつめさせた。
母は唇をかみ、涙をこらえる。
「そんなに……危険なんですか」
「大きな手術です。でも、今のままではもっと危険です」
川瀬の目は真剣だった。
診察室を出ると、母はハンカチで目を押さえた。
「ごめんね、成美。怖い思いさせて」
「……大丈夫」
そう言ったが、心臓の奥が締めつけられるように痛んだ。
病院を出ると、夕暮れの空は赤く染まっていた。
公園に寄り道した成美はベンチに座り、空を仰ぐ。
(七割……三割は失敗?)
足が震え、呼吸が浅くなる。
その時、背後から声がした。
「成美!」
振り返ると岳が立っていた。
「……どうしたの、そんな顔」
成美は首を振るが、涙があふれて止まらない。
岳はためらいもなく隣に座り、肩に手を置いた。
「泣いていいよ」
その一言に、堰を切ったように嗚咽が漏れた。
しばらく泣き続け、ようやく呼吸が整ったころ、岳がそっとハンカチを差し出した。
「ありがと……」
「聞いてもいい?」
成美は迷ったが、うなずく。
「九月に手術するの。……成功率は七割だって」
「七割……」岳は目を伏せ、しばらく沈黙した後に顔を上げた。
「三割は、怖いか?」
「怖いに決まってる……でも、やらなきゃもっと危ないんだって」
声が震え、また涙がこぼれそうになる。
岳はベンチから立ち上がり、両手を腰に当てた。
「なあ、俺さ、成功すると信じてる。だから――今は普通に過ごそう」
「普通に?」
「そう。勉強して、笑って、くだらないことでケンカして……それでいい」
成美は少し笑った。
「……ありがとう。なんか、少し楽になった」
その後、二人は並んで歩き出した。夕焼けの中で影が長く伸びる。
「なあ、手術終わったら何したい?」岳が問いかけた。
「花火、また見たいな。ちゃんと屋上で」
「決まりだな。じゃあ俺、夏休み中に準備しとく」
その言葉は、暗闇に差し込む光のように成美の心を照らした。
家に帰ると母が台所に立っていた。目はまだ赤いが、いつもどおり夕飯を作っている。
「おかえり。……大丈夫?」
「うん」
成美は笑顔を作った。
母はその顔を見て、少しだけ安堵したように微笑んだ。
夜、自室でベッドに横になると、昼間のことが頭をよぎった。
(怖い。でも……私、まだやりたいことある)
胸に手を当てると、鼓動がゆっくりと落ち着いていくのを感じた。
翌日、岳は真菜と太陽、哲平、百合子に話をした。
「成美、九月に手術するんだって」
皆、一瞬言葉を失った。
真菜が小さくつぶやく。「……だから、最近無理しなかったんだ」
「でな、手術まで普通に過ごしたいって言ってた」
岳の言葉に、太陽が手を挙げる。
「じゃあさ、何か一緒にできること考えようぜ」
「例えば?」哲平が首をかしげる。
「この前の探検も楽しかっただろ? ああいうの、もっと増やすんだよ」
百合子も頷いた。「放送委員の機材も使えるし、思い出いっぱい作ろうよ」
その日の放課後、成美の机に一枚のメモが置かれていた。
〈今日の帰り、公園集合〉
行ってみると、皆が待っていた。
「成美、これからの時間、ぜんぶ一緒に楽しもう」
岳が差し出したのは、あの「夢の計画ノート」だった。
新しいページには大きく書かれていた。
〈九月五日までの思い出リスト〉
成美は泣き笑いしながら、ペンを取った。
公園のベンチに腰掛けたまま、成美はペンを握りしめた。ページに視線を落とすと、岳が覗き込みながら微笑む。
「書きたいこと、ある?」
「うん……でも、いっぱいあるかも」
声は少し震えていたが、その目は決意を帯びていた。
まず最初に記したのは〈屋上で花火〉。前に書いた願いを、もう一度大きく書き直した。その下に、海沿い散策やみんなでの写真撮影、夏祭りでの浴衣、図書室合宿勉強会……次々と浮かんでくる願いがペンの先からあふれ出した。
「こんなにやりたいことあったんだな……」自分で驚いてつぶやくと、真菜が微笑む。
「いいじゃん。全部やろうよ。できるところまででいい」
「でも、時間が――」
「関係ないよ」太陽が腕を組んで笑う。「時間がないなら、その分楽しくすりゃいい」
百合子も手を叩いた。「放送室のスピーカーも使おうよ。音楽流して花火見たら絶対きれいだよ」
「俺は動画撮るからな」哲平がドローンの写真を指さす。「映像編集して、夏の記録にする」
岳が頷く。「ほらな。みんなもう動き出してる」
成美はその光景を見つめながら、胸が熱くなった。(この人たちと過ごせる時間が、私の宝物なんだ)
帰り道、夕焼けが街を黄金色に染めていた。成美は少しだけ歩調を緩め、肩にかかったリュックの重さを感じた。以前なら、この重ささえ負担に思っていたのに、今はなぜか心地よい。
家に着くと、母が夕飯の支度をしていた。包丁の音がリズムよく響き、味噌汁の香りが広がる。
「おかえり、今日は遅かったね」
「みんなと話してた」
母が一瞬だけ手を止めて成美の顔を見た。赤かった目はまだ完全には乾いていない。でもその表情には、少しだけ安心の色が宿っていた。
「……友達、大事にね」
「うん」
夕食の後、自室に戻った成美はノートを開き、書き加えた。
〈怖いけど、生きたい〉
その言葉を見て、胸がじんわり熱くなる。(手術が怖いのは変わらない。でも――生きたい)
夜、ベッドに潜り込むと、昼間の出来事が鮮明に蘇った。病院の白い壁、川瀬医師の真剣な顔、母の涙、岳のまっすぐな瞳。そして友達の笑顔。全部が絡まり合って、涙がまたこぼれた。でもそれは、昼間の絶望とは違う涙だった。
(泣いていいよって言われて、救われたな……)
窓の外に星がひとつ光っている。成美は胸の上で手を合わせた。
(生きたい。みんなと、もっとたくさん笑いたい)
翌日からの日々は、ほんの少しだけ色づき始めた。教室の窓から差し込む朝日がまぶしく感じられ、通学路の坂道の草花に目が向いた。病気の痛みが消えたわけではない。でも、それを抱えたまま笑う自分がいた。
放課後、岳が言った。「なあ、次は砂浜の掃除ボランティアどうだ? タイムカプセル探そうぜ」
「タイムカプセル?」成美が首をかしげる。
「ほら、小さいころ埋めたやつ。あるかもよ」
太陽が身を乗り出した。「おもしれーじゃん!」
真菜と百合子も笑顔で頷いた。
「……うん、行きたい」成美は小さく笑った。
その笑顔を見て、岳は小さく拳を握った。(よし、絶対に守る。この日常を)