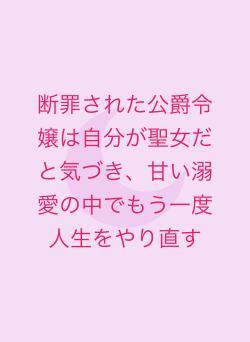「昔から両親が家にいないことが多くて、俺は自分を強く見せるためにどこか冷酷さを秘めることが正しいと思っていた。弱さを見せずに強がって、誰も信用せずに自分だけを信用する」
「それで上手くいっていたのに、ある日この屋敷に変わったメイドがやってきた」
「今まで見てきた自分を偽っているやつと同じ顔をしているのに、どこか違っていて。それでいて俺から目を逸らそうとしない、そんなメイドだった」
そのメイドが私のことだと言うことは、すぐに分かった。
蒼河様は今、私と出会った時の思い出を話してくれている。
「強がりで、意地っぱりのくせに、俺の力にはなりたいという言葉が本心から来ていることだけは良くわかった」
「そんなメイドに惹かれていく自分がいる中で……ある日、俺はそのメイドが自分で自分の両頬を叩いているところを見たんだ。ペチンという音と共に『泣いちゃだめ、夜まで我慢ね』と言っていた」
「その言葉の意味はすぐに分からなかったけれど、このメイドの弱さを見てみたいと思った。弱さを見て、受け入れて、大丈夫だと優しく言ってやりたかった。だから俺は少しでもそのメイドに近づきたくて、この勝負を提案したんだ」
蒼河様が私たちの弱点が書かれた紙が入っている箱を引き出しから取り出す。
「それで上手くいっていたのに、ある日この屋敷に変わったメイドがやってきた」
「今まで見てきた自分を偽っているやつと同じ顔をしているのに、どこか違っていて。それでいて俺から目を逸らそうとしない、そんなメイドだった」
そのメイドが私のことだと言うことは、すぐに分かった。
蒼河様は今、私と出会った時の思い出を話してくれている。
「強がりで、意地っぱりのくせに、俺の力にはなりたいという言葉が本心から来ていることだけは良くわかった」
「そんなメイドに惹かれていく自分がいる中で……ある日、俺はそのメイドが自分で自分の両頬を叩いているところを見たんだ。ペチンという音と共に『泣いちゃだめ、夜まで我慢ね』と言っていた」
「その言葉の意味はすぐに分からなかったけれど、このメイドの弱さを見てみたいと思った。弱さを見て、受け入れて、大丈夫だと優しく言ってやりたかった。だから俺は少しでもそのメイドに近づきたくて、この勝負を提案したんだ」
蒼河様が私たちの弱点が書かれた紙が入っている箱を引き出しから取り出す。