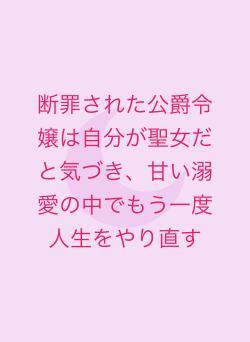「蒼河様、ちゃんとなさって下さい。あれくらいで怒っていては社交界で生きていけないことは貴方が一番分かっているでしょう?」
「……」
珍しく蒼河様は私に返事をしなかった。
「聞いていらっしゃいますか?」
私がそう聞いた瞬間、蒼河様が私を腕で囲うようにバルコニーの手すりに両手をついた。
「なぜ大人しく守られていない? メイドを守るのは主人の役目だと前に言ったはずだ」
他のご令嬢に向けられていると思っていた怒りの一部が自分に向けられていると知って、咄嗟に身構えてしまう。
蒼河様はそんな私の些細な変化を見逃す人間ではなかった。
「……」
珍しく蒼河様は私に返事をしなかった。
「聞いていらっしゃいますか?」
私がそう聞いた瞬間、蒼河様が私を腕で囲うようにバルコニーの手すりに両手をついた。
「なぜ大人しく守られていない? メイドを守るのは主人の役目だと前に言ったはずだ」
他のご令嬢に向けられていると思っていた怒りの一部が自分に向けられていると知って、咄嗟に身構えてしまう。
蒼河様はそんな私の些細な変化を見逃す人間ではなかった。