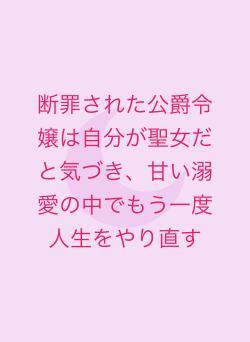「じゃあ、俺はそろそろ本当に自室に戻る。広葉もそろそろ自分の部屋に戻るだろう?」
私の気持ちが落ち着いてきていて、眠くなっていたのもお見通しらしい。
二人で月明かりに照らされた屋敷の廊下をゆっくり歩いていく。
いつも日中に歩いている屋敷の廊下であるはずなのに、まるで別世界の王城に来たような気持ちになる。
いつもは怖がってしまうような深夜の薄暗ささえ、今は美しく見えてしまう。
私の部屋に着くと、蒼河様が私の頭を軽くポンっと叩いた。
「おやすみ」
それだけ言って、蒼河様は廊下を歩いていく。
蒼河様の後ろ姿が見えなくなるまで、私は蒼河様から目が離せなかった。
「蒼河様のばか」
何も悪いことはされていないのに、どこか負けた気がして悔しくて、私は気づいたらそう呟いていた。
ドクドクとうるさいくらいに自分の心臓の音が頭にまで響いてくるように感じる。
この胸の高鳴りは深夜だけの幻だと信じたかった。
私の気持ちが落ち着いてきていて、眠くなっていたのもお見通しらしい。
二人で月明かりに照らされた屋敷の廊下をゆっくり歩いていく。
いつも日中に歩いている屋敷の廊下であるはずなのに、まるで別世界の王城に来たような気持ちになる。
いつもは怖がってしまうような深夜の薄暗ささえ、今は美しく見えてしまう。
私の部屋に着くと、蒼河様が私の頭を軽くポンっと叩いた。
「おやすみ」
それだけ言って、蒼河様は廊下を歩いていく。
蒼河様の後ろ姿が見えなくなるまで、私は蒼河様から目が離せなかった。
「蒼河様のばか」
何も悪いことはされていないのに、どこか負けた気がして悔しくて、私は気づいたらそう呟いていた。
ドクドクとうるさいくらいに自分の心臓の音が頭にまで響いてくるように感じる。
この胸の高鳴りは深夜だけの幻だと信じたかった。