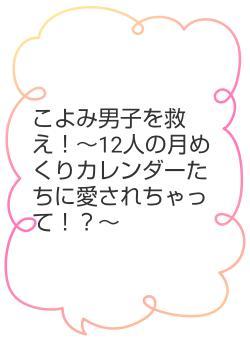そぉっと近付く、ただそれだけなのにぶわーっと手がポカポカして来た。手だけじゃない、体も緋太さんが近付いたところ全部がぶわっと熱を上げる。
電気ストーブだ、この当てた瞬間一気に熱くなるこの感覚はまぎれもなくそうだ。
「ね、温かくなってきたでしょ?」
くすっと声を漏らして、話し方も温かみを持ってる。ちょっと大人みたい。
「僕のそばにいればその赤くなった手もすぐ良くなりますよ」
「…ありがとう、ございます」
絶対もっと言うことあったはずなんだけど、緋太さんの余裕な姿勢にわたしまでおとなしくなってしまうかも。
だってじっとわたしの手を見つめて、ずっと愛しそうな瞳してるから…
な、なぜ!?
自分で言っといてわかんない!
「もう大丈夫ですよ、すっかり熱が戻って来ました」
「あ、ほんとだ!もう痛くない…」
かじかんでいた手が元に戻って赤みもなくなっていた。
「柑乃さんの手、大事にしてください」
…こ、この感じには戸惑うけど。
あの電気ストーブがこんな人とは…
どう答えたらいいのかわかんなくて、はいとしか言えなかった。
「またいつでも来て下さいね、待ってます」
電気ストーブだ、この当てた瞬間一気に熱くなるこの感覚はまぎれもなくそうだ。
「ね、温かくなってきたでしょ?」
くすっと声を漏らして、話し方も温かみを持ってる。ちょっと大人みたい。
「僕のそばにいればその赤くなった手もすぐ良くなりますよ」
「…ありがとう、ございます」
絶対もっと言うことあったはずなんだけど、緋太さんの余裕な姿勢にわたしまでおとなしくなってしまうかも。
だってじっとわたしの手を見つめて、ずっと愛しそうな瞳してるから…
な、なぜ!?
自分で言っといてわかんない!
「もう大丈夫ですよ、すっかり熱が戻って来ました」
「あ、ほんとだ!もう痛くない…」
かじかんでいた手が元に戻って赤みもなくなっていた。
「柑乃さんの手、大事にしてください」
…こ、この感じには戸惑うけど。
あの電気ストーブがこんな人とは…
どう答えたらいいのかわかんなくて、はいとしか言えなかった。
「またいつでも来て下さいね、待ってます」