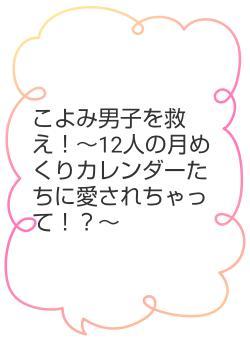制服の袖で涙を拭いて、涙で詰まって出せない声を振り絞る。
「暖が…っ」
壊れてしまった、なんて言えなかった。
そんなこと口に出したくなかった。
制服のスカートのポケットを上からぎゅっと握る。
だって暖に聞こえちゃうかもしれないもんね、聞こえてるかもしれないもん。
「柑乃さん…」
俯いて声をつまらせて泣くわたしの前に緋太さんが立った。
手をわたしの前に出そうか迷ってやめたのがわかった、グッとグーにして握りしめたから。
「僕では彼の代わりにはなれませんか?」
顔を上げることができなかった、だから緋太さんがどんな表情をしていたのかはわからない。
わからなかったけど…
保健室へ来るのは少し怖かったの。
緋太さんはやさしいから、わたしを甘えさせてくれるよね。
冷たくなった手を丁寧にあっためてくれる。
だけど今はそれが苦しい。
暖からもらう温度を忘れたくないの。
わたしは暖のことが好きだからー…
「代わり、って言ってる時点で無理ですよね」
「暖が…っ」
壊れてしまった、なんて言えなかった。
そんなこと口に出したくなかった。
制服のスカートのポケットを上からぎゅっと握る。
だって暖に聞こえちゃうかもしれないもんね、聞こえてるかもしれないもん。
「柑乃さん…」
俯いて声をつまらせて泣くわたしの前に緋太さんが立った。
手をわたしの前に出そうか迷ってやめたのがわかった、グッとグーにして握りしめたから。
「僕では彼の代わりにはなれませんか?」
顔を上げることができなかった、だから緋太さんがどんな表情をしていたのかはわからない。
わからなかったけど…
保健室へ来るのは少し怖かったの。
緋太さんはやさしいから、わたしを甘えさせてくれるよね。
冷たくなった手を丁寧にあっためてくれる。
だけど今はそれが苦しい。
暖からもらう温度を忘れたくないの。
わたしは暖のことが好きだからー…
「代わり、って言ってる時点で無理ですよね」