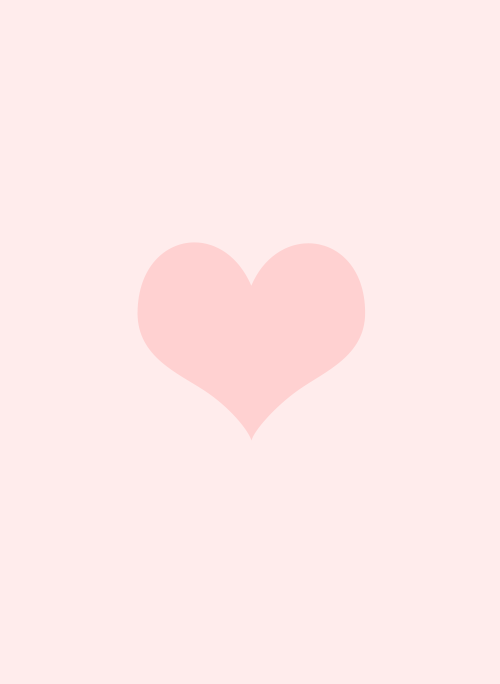第12章: 見えない鎖
夕方の学校はすでに放課後の静けさに包まれ、教室の窓からは薄紫の空が見える。風が少し強くなり、窓がカタカタと揺れる音が響く中、奏は文香を探して校内を歩いていた。心の中に湧き上がる気持ちに、もう戸惑うことはない。彼女が抱える秘密に触れた今、何もかもが繋がったように思えてならなかった。
昨日、文香が話した「鉄の伝説」。それが彼女の家族に関わることで、彼女が拒否しているその重さに気づいてしまった今、奏は彼女を放っておけないと思った。どんな過去があろうと、どんな痛みを抱えていようと、文香に寄り添いたい。その思いが、胸を熱くしている。
校庭に目を向けると、やはりあの冷たい目で一人立っている文香がいた。奏は立ち止まり、少しだけ息を整える。彼女がまた一人でいる姿を見ると、胸の奥で何かが締めつけられる。
彼女のところに歩み寄ると、文香はちらっと奏を見て、視線をそらす。その仕草が、まるで「来ないで」と言っているかのように感じられた。
「また一人か?」奏は少しだけ声をかける。その声には、これ以上彼女を一人にしておけないという強い決意が込められていた。
文香は一瞬だけ目を閉じ、すぐに無表情で答える。「あたりまえじゃない」
その冷たさに、奏は少しだけ心を痛めるが、それでも話し続けることを決めた。「君が隠してることを知りたい」彼の声は低く、真剣そのものだった。「あの伝説、君の家族が関わっているって、僕に言ったけど…君はそれを拒んでる。それがどうしてなのか、少しでもいいから教えてほしい」
文香の目がほんの一瞬、驚いたように大きく開いた。その目の中に、かすかな動揺が見えたが、すぐにまた冷たい色が戻る。
「私には関係ない」と、文香は冷静に言った。その声に、奏は一瞬だけ立ち止まった。
「君には関係あるだろ」と、奏は静かに言い返す。「君がどうして一人でいるのか、それを知りたくてたまらないんだ」
文香はその言葉に反応せず、ただ立ち尽くしている。奏は少しの間、彼女を見つめていた。何かを言おうとしたが、言葉が出なかった。沈黙が二人の間に広がる。
その時、文香がようやく口を開く。「私が拒んでいるのは、みんなが期待するような人間になりたくないから」彼女はふと顔を上げて、空を見つめる。「あの伝説の後継者なんて、誰にもなりたくない。だから私は、ずっと一人でいるんだ」
その言葉が奏の胸を深く突き刺した。文香が抱えているものが、どれほど重いのかを理解した瞬間だった。彼女が拒否する理由、孤独を選び続けた理由が、ようやく明確になった。
「君がそれを背負わなきゃならない理由はない」と、奏は少しの間黙った後、ゆっくりと答えた。「君は君でいいんだ」
文香はその言葉に少し驚いたような顔をしたが、それでもすぐに表情を戻すと、静かに言った。「私は、もう誰にも頼らない。私がやらなきゃ、誰もやらないから」
その言葉に、奏は何も言えなかった。彼女がどれほどの覚悟を持ってこの道を歩んできたのか、思い知った気がした。だが、どうしても彼女がひとりで背負うことに納得できなかった。
「でも、君が背負いきれないものは、僕が支えるから」と、奏は強く言った。その言葉が、彼女の心にどう響くのか分からないが、それでも自分の気持ちを伝えなければならなかった。
文香はその言葉を聞いて、少しだけ黙って立ち止まる。やがて、静かに顔を上げると、目を細めて言った。
「支える…?」彼女の声には、少しだけ苦笑が浮かんでいた。「私にそんなもの、求めても無駄だよ。誰にも頼るつもりはないし、支えられるほど強くないから」
その言葉に、奏の胸がさらに痛くなる。彼女がそれほどまでに傷ついているのだと、改めて思い知らされる。しかし、どうしても諦めきれない自分がいる。
「だからこそ、君には頼ってほしい。自分ひとりで全てを抱え込む必要なんてないんだ」と、奏は力強く言った。今までのように、何も言わずに見守るだけでは済まないと思った。彼女が抱えている痛みを、少しでも軽くできるなら、自分がその力になりたいと思う。
文香はしばらく静かに彼を見つめた後、やっとゆっくりと歩き出す。奏もその後ろをついていく。無言のまま歩き続ける中で、二人の間に新たな絆が生まれたような気がした。
夕方の学校はすでに放課後の静けさに包まれ、教室の窓からは薄紫の空が見える。風が少し強くなり、窓がカタカタと揺れる音が響く中、奏は文香を探して校内を歩いていた。心の中に湧き上がる気持ちに、もう戸惑うことはない。彼女が抱える秘密に触れた今、何もかもが繋がったように思えてならなかった。
昨日、文香が話した「鉄の伝説」。それが彼女の家族に関わることで、彼女が拒否しているその重さに気づいてしまった今、奏は彼女を放っておけないと思った。どんな過去があろうと、どんな痛みを抱えていようと、文香に寄り添いたい。その思いが、胸を熱くしている。
校庭に目を向けると、やはりあの冷たい目で一人立っている文香がいた。奏は立ち止まり、少しだけ息を整える。彼女がまた一人でいる姿を見ると、胸の奥で何かが締めつけられる。
彼女のところに歩み寄ると、文香はちらっと奏を見て、視線をそらす。その仕草が、まるで「来ないで」と言っているかのように感じられた。
「また一人か?」奏は少しだけ声をかける。その声には、これ以上彼女を一人にしておけないという強い決意が込められていた。
文香は一瞬だけ目を閉じ、すぐに無表情で答える。「あたりまえじゃない」
その冷たさに、奏は少しだけ心を痛めるが、それでも話し続けることを決めた。「君が隠してることを知りたい」彼の声は低く、真剣そのものだった。「あの伝説、君の家族が関わっているって、僕に言ったけど…君はそれを拒んでる。それがどうしてなのか、少しでもいいから教えてほしい」
文香の目がほんの一瞬、驚いたように大きく開いた。その目の中に、かすかな動揺が見えたが、すぐにまた冷たい色が戻る。
「私には関係ない」と、文香は冷静に言った。その声に、奏は一瞬だけ立ち止まった。
「君には関係あるだろ」と、奏は静かに言い返す。「君がどうして一人でいるのか、それを知りたくてたまらないんだ」
文香はその言葉に反応せず、ただ立ち尽くしている。奏は少しの間、彼女を見つめていた。何かを言おうとしたが、言葉が出なかった。沈黙が二人の間に広がる。
その時、文香がようやく口を開く。「私が拒んでいるのは、みんなが期待するような人間になりたくないから」彼女はふと顔を上げて、空を見つめる。「あの伝説の後継者なんて、誰にもなりたくない。だから私は、ずっと一人でいるんだ」
その言葉が奏の胸を深く突き刺した。文香が抱えているものが、どれほど重いのかを理解した瞬間だった。彼女が拒否する理由、孤独を選び続けた理由が、ようやく明確になった。
「君がそれを背負わなきゃならない理由はない」と、奏は少しの間黙った後、ゆっくりと答えた。「君は君でいいんだ」
文香はその言葉に少し驚いたような顔をしたが、それでもすぐに表情を戻すと、静かに言った。「私は、もう誰にも頼らない。私がやらなきゃ、誰もやらないから」
その言葉に、奏は何も言えなかった。彼女がどれほどの覚悟を持ってこの道を歩んできたのか、思い知った気がした。だが、どうしても彼女がひとりで背負うことに納得できなかった。
「でも、君が背負いきれないものは、僕が支えるから」と、奏は強く言った。その言葉が、彼女の心にどう響くのか分からないが、それでも自分の気持ちを伝えなければならなかった。
文香はその言葉を聞いて、少しだけ黙って立ち止まる。やがて、静かに顔を上げると、目を細めて言った。
「支える…?」彼女の声には、少しだけ苦笑が浮かんでいた。「私にそんなもの、求めても無駄だよ。誰にも頼るつもりはないし、支えられるほど強くないから」
その言葉に、奏の胸がさらに痛くなる。彼女がそれほどまでに傷ついているのだと、改めて思い知らされる。しかし、どうしても諦めきれない自分がいる。
「だからこそ、君には頼ってほしい。自分ひとりで全てを抱え込む必要なんてないんだ」と、奏は力強く言った。今までのように、何も言わずに見守るだけでは済まないと思った。彼女が抱えている痛みを、少しでも軽くできるなら、自分がその力になりたいと思う。
文香はしばらく静かに彼を見つめた後、やっとゆっくりと歩き出す。奏もその後ろをついていく。無言のまま歩き続ける中で、二人の間に新たな絆が生まれたような気がした。